
2017/12/05 - 2017/12/07
512位(同エリア1900件中)
![]()
旅人のくまさんさん
- 旅人のくまさんさんTOP
- 旅行記6398冊
- クチコミ0件
- Q&A回答0件
- 5,439,598アクセス
- フォロワー204人
大阪湾の周りの9名城巡りの締め括りです。大坂城は、上町台地の北端に位置します。かつて、この地のすぐ北の台地下には、淀川の本流が流れる天然の要害でした。また淀川を上ると京都に達する交通の要衝でもありました。
- 交通手段
- 観光バス
-
『本丸下枡形』の石垣のズームアップ光景です。その脇に見学者用通路の桟道が設けてありました。
-
『豊臣秀頼・淀殿ら自刃の地碑』への案内標識です。『豊臣秀頼(1593~1615年)は、太閤・秀吉の三男で、後継者となりました。母の淀殿は、信長に滅ぼされた浅井長政の長女です。前方に見えるのは、本丸北面の高石垣です。
-
振り返って眺めた『本丸下枡形』付近の光景です。綺麗な切込み接ぎの石垣ですが、補修されたらしい色違いの石垣が見えました。
-
イチョウ(公孫樹、銀杏、鴨脚樹)の黄葉光景です、半ば散り敷いていました。中国原産のイチョウ科イチョウ属の裸子植物です。イチョウ科の植物は中生代から新生代にかけて世界的に繁栄しましたが、氷河期にほぼ絶滅し、イチョウは唯一現存する種とされます。
-
『豊臣秀頼・淀殿ら自刃の地碑』の案内に従ってやって来た、『山里丸』です。本丸北端部の一段低くなったエリアが『山里丸』と呼ばれています。豊臣秀吉の命により、千利休が造営した茶室があった場所とされます。
-
『秀頼・淀殿ら自刃の地』のタイトルがあった説明看板の光景です。慶長20年(元和元年:1615年)、大坂夏の陣の旧暦5月8日、徳川軍に追い詰められた豊臣秀頼とその母淀殿が、山里丸で自決したと多くの記録があり、この地に大阪市により平成9年(1997年)に建てられた碑であることが紹介されていました。
-
イチオシ
『豊臣秀頼・淀殿ら自刃の地』の碑の光景です。豊臣秀頼とその母・淀殿および臣下の武将や侍女たち30余名が、大坂夏の陣で自決した場所だとされる、山里丸南東にある石碑です。ただし、自刃の地には諸説があり、その場所も徳川時代の大阪城建設で地中に埋まりましたので、正確な場所は分かりません。
-
内堀の西北側方面の光景です。こちら方面には、二の丸西北角に『伏見櫓跡』があり、その南側の『北外堀』と『東外堀』との間に、『京橋口』が設けられています。
-
内堀の東北側方面の光景です。こちら方面には、『東北堀』と『北外堀』との間に『青屋口』が設けられています。
-
『極楽橋』の袂の光景です。本丸北端の山里丸と二の丸を結ぶ全長54メートルの橋です。徳川時代の寛永3年(1626年)に創建された時は木造でしたが、明治維新の戊辰戦争によって焼け落ちたままになっていました。現在の橋は、昭和40年(1965年)に大阪城整備工事の一環として、鉄筋コンクリートで再建されたものです。上部は、『擬宝珠 高欄』の伝統的な造りです。
-
イチオシ
『極楽橋』の袂から眺めた大阪城天守の光景です。豊臣時代には、北側が大手口であったとする説もあります。絵図にも北側からの天守が描かれています。ただし現在の天守は徳川時代の天守台の上に建てられていますから、豊臣時代には、もっと東側(左側)に位置したようです。
-
『極楽橋』のタイトルがあった説明看板の光景です。徳川時代の寛永3年(1626年)に創建された時の呼び名も『極楽橋』であったことと、その名前の由来などが解説されていました。1959年(昭和34年)に行われた大阪城学術調査において、『現在の本丸は10mもの盛り土の上に建てられた』ことが分かり、徳川時代以前の石垣遺構が土中から発見されました。更に、1960年(昭和35年)、東京の中井家で発見された図には、『大坂御城小指図か不審ノ所々可相改』と上書きされた2枚の図には、お城の本丸と内堀が描かれ、建物の名前、石垣の高さや長さが書き込まれていました。その図面によれば、極楽橋は、山里曲輪の西に隣接する『芦田曲輪』から二の丸に北に架かっていました。
-
『極楽橋』の石標です。咲くほどの説明パネルには、『極楽』とは、仏教で教える楽園を指すことから、戦国時代からこの地にあった浄土真宗本願寺派の本山、大坂(石山)本願寺に因むものではないかとの解説がありました。
-
『極楽橋』の袂から眺めた天守閣のズームアップ光景です。先ほど紹介した、中井家の先祖の中井正清(なかいまさきよ)は、徳川幕府の初代京都大工頭でした。発見された図は徳川時代の大坂城を描いたものであると思われましたが、専門家が調査したところ、秀吉時代の大坂城であるとの結論になったとされます。ただし、築城後の図面ではなく、計画段階の図面との説もあるようです。その図面での天守閣の位置は、本丸の東北角でした。現在では、豊臣時代の大坂城を描いた一級史料となり、『中井家本丸図」と呼ばれています。
-
イチオシ
大阪城の内堀を巡る屋形船の光景です。『大阪城御座船(ござぶね)』と呼ばれています。左側の提灯に『大阪城』、右側に『御座船』の文字がありました。その前を過ぎる、ヒドリガモらしい鴨さん達です。屋根上に、太閤さんの瓢箪飾りもありました。
-
東側から眺めた『極楽橋』の光景です。金沢城にも極楽橋があります。金沢城築城以前に加賀一向一揆の拠点である金沢御坊があった場所です。大坂城もかつて本丸の位置に大坂(石山)本願寺の御堂がありましたので、『極楽橋』のタイトルがあった説明看板の記述も納得がいきます。
-
本丸の東北角付近の光景です。手前側の一段低くなった場所が『山里丸』、その奥の一段高くなった石垣の場所が本丸になるようです。
-
先程よりは、少し東側からの撮影です。内堀とその周りの本丸と山里丸の石垣の東面の光景です。山里丸の樹木の紅葉が鮮やかでした。
-
内堀で泳ぐ水鳥さん達です。灰色の体色に黒っぽい頭、白い嘴がオオバン(大鷭)さん、それに茶色っぽい体色のカモさんも交じっていました。ヒドリガモ(緋鳥鴨)の雌かも知れません。
-
同じく、内堀で泳ぐ水鳥さん達です。先程のオオバンさん御ほかに、頭が濃い茶色の鴨さん達の姿がありました。ヒドリガモ(緋鳥鴨)さん達でしょうか。オスの成鳥は、額から頭頂のクリーム色が特徴とされます。
-
草書体での『南無阿弥陀仏』の文字が刻まれた石碑の光景です。蓮如直筆の『蓮如六字名号碑』と呼ばれています。『蓮如上人(1415~1499年)』は、室町時代の浄土真宗の僧で、浄土真宗本願寺派第8世宗主・真宗大谷派第8代門首です。本願寺中興の祖とも呼ばれます。
-
『石山本願寺と大坂(大阪)』のタイトルがあった説明パネルの光景です。明応5年(1496年)、浄土真宗本願寺派第8世宗主の蓮如が、この地に某社を築き、6町2千軒の寺内町を開いたことから始まり、信長との11年間の石山合戦の後、京都に移ったことなどが説明されていました。大坂(石山)本願寺の遺跡は確認されていませんが、この辺りと見当が付けられています。
-
1496年に石山御坊(のちの石山本願寺)を現在の大阪城がある地に建立したとされている蓮如は、はじめて『大坂」という地名を文書に残し人物とされています。この辺りは『雁木坂』と呼ばれていますから、『大坂』の名前の名残かも知れません。『ダラダラ坂』とも呼ばれたようです。
-
離れた場所からの撮影になりましたが、低い垣根に囲われた、蓮如上人所縁の場所の光景です。先に紹介した、石碑が中央やや左奥に見えています。この碑の後ろにあった『袈裟懸けの松』は、蓮如上人が袈裟を懸けたとの言い伝えがあります。今は枯れた切り株だけが残っているようです。
-
蓮如上人所縁の場所近くから眺めた大阪城の石垣光景です。内堀の本丸側の石垣になるようでした。櫓などの姿は見えませんが、『旧・第四師団司令部』の建物がある場所付近のようでした。
-
振り返って眺めた、『玉造口跡』の光景です。大阪城搦手口の一つで、玉造方面に向かって開かれていることからの命名です。元々は大手口、京橋口と同じく多聞櫓を備えた石塁による枡形構造でした。一の門(城内側)は櫓門、二の門(城外側)は高麗門と二つの門を備えていました。戊辰戦争時(1868)の大火で、一の門と多聞櫓は焼失し、高麗門は太平洋戦争末期の空襲により焼失したようです。
-
石垣越しに眺めた天守閣の光景です。この場所からは、上階から二層部分まで見えました。撮影場所は、南外堀の外側(東側)になります。
-
これで大阪湾の周りの9名城巡りの紹介はおしまいです。最後に紹介する櫓は、『一番櫓』です。 一番櫓は南外堀に面して玉造門を側面から防御する櫓です。徳川幕府による大坂城再建工事の第三段階にあたる寛永5年(1628年)に築かれました。昭和39年(1964年)の解体修理により、万治3年(1668年)、寛文8年(1668年)、天保3年(1832年)の三回の補修があったことが判明しました。
-
南外堀の東南角付近の光景です。右端に見えているのは、『一番櫓』です。石垣の下部に白い帯があるのは、高水位の時の跡のようです。お堀の全周に亘って白い帯がありました。
-
これで大阪湾の周りの9名城巡りの紹介はおしまいです。最後に紹介する写真は、南側から眺めた南外堀です。左側に見えているのが『一番櫓』です。玉造口より北側には、『東外堀』が続きます。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
旅行記グループ
2017暮、大阪湾の名城巡り(下巻)
-

2017暮、大阪湾の名城(21/42):12月6日(5):勝瑞城(1/3):勝瑞城所縁の見性寺、本堂
2017/12/05~
板野・松茂
-

2017暮、大阪湾の名城(22/42):12月6日(6):勝瑞城(2/3):見性寺、本堂、墓所、堀
2017/12/05~
板野・松茂
-

2017暮、大阪湾の名城(23/42):12月6日(7):勝瑞城(3/3):発掘調査現場、出土品
2017/12/05~
板野・松茂
-

2017暮、大阪湾の名城(24/42):12月6日(9):徳島城(1/4):徳島城博物館、千秋閣庭園
2017/12/05~
徳島市
-

2017暮、大阪湾の名城(25/42):12月6日(10):徳島城(2/4):心字池、蜂須賀家政銅像
2017/12/05~
徳島市
-

2017暮、大阪湾の名城(26/42):12月6日(11):徳島城(3/4):城山、本丸、弓櫓
2017/12/05~
徳島市
-

2017暮、大阪湾の名城(27/42):12月6日(12):徳島城(4/4):城山、大手門、紫雲石
2017/12/05~
徳島市
-

2017暮、大阪湾の名城(28/42):12月7日(1):和歌山城(1/7):和歌山のホテル、散策
2017/12/05~
和歌山市
-

2017暮、大阪湾の名城(29/42):12月7日(2):和歌山城(2/7):和歌山城、お堀、一の門
2017/12/05~
和歌山市
-

2017暮、大阪湾の名城(30/42):12月7日(3):和歌山城(3/7):一中門、伏虎像、表坂
2017/12/05~
和歌山市
-

2017暮、大阪湾の名城(31/42):12月7日(4):和歌山城(4/7):天守、天守郭、埋門
2017/12/05~
和歌山市
-

2017暮、大阪湾の名城(32/42):12月7日(5):和歌山城(5/7):大天守、御台所展示品
2017/12/05~
和歌山市
-

2017暮、大阪湾の名城(33/42):12月7日(6):和歌山城(6/7):多門展示品、銀名水
2017/12/05~
和歌山市
-

2017暮、大阪湾の名城(34/42):12月7日(7):和歌山城(7/7):御橋廊下、二の丸
2017/12/05~
和歌山市
-

2017暮、大阪湾の名城(35/42):12月7日(8):岸和田城(1/3):二の丸、心技館、堀
2017/12/05~
岸和田・貝塚
-

2017暮、大阪湾の名城(36/42):12月7日(9):岸和田城(2/3):歴史パネル、八陣の庭園
2017/12/05~
岸和田・貝塚
-

2017暮、大阪湾の名城(37/42):12月7日(10):岸和田城(3/3):天守、八陣の庭、石庭
2017/12/05~
岸和田・貝塚
-

2017暮、大阪湾の名城(38/42):12月7日(11):大阪城(1/5):大阪城、大手門、桜門
2017/12/05~
大阪城・京橋
-

2017暮、大阪湾の名城(39/42):12月7日(12):大阪城(2/5):太鼓櫓、枡形の巨石、桜門
2017/12/05~
大阪城・京橋
-

2017暮、大阪湾の名城(40/42):12月7日(13):大阪城(3/5):西と南からの天守光景
2017/12/05~
大阪城・京橋
-

2017暮、大阪湾の名城(41/42):12月7日(14):大阪城(4/5):山里口出枡形、刻印石広場
2017/12/05~
大阪城・京橋
-

2017暮、大阪湾の名城(42/42):12月7日(15):大阪城(5/5):秀頼自刃の碑、極楽橋
2017/12/05~
大阪城・京橋
旅行記グループをもっと見る
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
大阪城・京橋(大阪) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?







































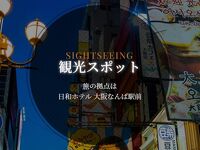







旅行記グループ 2017暮、大阪湾の名城巡り(下巻)
0
30