
2016/03/01 - 2016/06/23
1691位(同エリア7813件中)
![]()
たかちゃんティムちゃんはるおちゃん・ついでにおまけのまゆみはん。さん
第二十五章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~ふじ学徒看護隊(積徳高等女学校)の足跡を訪ねて~
最も熾烈な地上戦が行われた沖縄の地で、年端も行かない少年少女が学徒隊として動員され、多くの犠牲者を出したことはなにがしらの話で聞くことはあると思います。しかし学徒隊=ひめゆり学徒隊(部隊)という先入観があまりにも大きくなってしまっており、またその関連史跡を訪ねる時に漠然とした目的のない平和学習の結果、誤った事実が当たり前になっているのではないでしょうか?
ひめゆり学徒隊というのは沖縄師範学校女子部と沖縄県立第一高等女学校の生徒により構成された学徒看護隊のことを指し、一高女の学校広報誌の名前〝乙姫〟と沖縄師範学校女子部の学校広報誌の名前〝白百合〟を併せて〝ひめゆり〟とした戦後の命名に由来するという説からきています。その他にも学徒隊は構成され女子が15~19歳、男子が14~19歳までが学徒動員され、20もの学徒隊が作られました。しかし残念なことに生き残られた学徒の方々が非常に少なく、規模の小さな学校で構成された学徒に至っては情報が少なく、その存在すら知られていないものが多々あります。個々の史跡で追いかけるよりも学徒隊の動きでその足跡を追い掛け、少しでも検証できればと思い書き始めました。
初回は私立積徳高等女学校の生徒による学徒隊であった〝ふじ学徒看護隊(積徳学徒看護隊)〟の足跡を追ってみようと思います。
まずは私立積徳高等女学校の歴史ですが・・・。
1918(大正7)年 私立家政女学校(大典寺の庫裏を教室として始められる)本科3年、別科1年
1930(昭和5)年 高等女学校になる(四年制、生徒数200名超)
1932(昭和7)年 美栄橋に移転
1943(昭和18)年 沖縄積徳高等女学校と校名を改める
昭和19(1944)年10月10日 十・十空襲で校舎全焼。その後ほとんどの授業が停止され、全校あげて垣花、天久、識名などの高射砲陣地構築や国場での戦車壕掘り作業に従事するようになる。
昭和20(1945)年2~3月 4年生55名が看護教育を受けるようになり、東風平国民学校にあった第2野戦病院壕で実習訓練を受ける。
昭和20(1945)年3月 沖縄戦の開戦が避けられない状況となり、実習は打ち切り。生徒達は学徒看護隊として豊見城城跡にあった第24師団第二野戦病院本部壕に55人中25名が入隊し、その日から負傷兵の看護に当たった。その際卒業式は中止になっている。
昭和20(1945)年5月27日 戦況の悪化に伴い糸洲の自然壕に移動命令が出される。
昭和20(1945)年6月17日 米軍の馬乗り攻撃を受け、壕内の患者に犠牲者が出る。
昭和20(1945)年6月27日 第二野戦病院長小池勇助少佐が、野戦病院を解散させる。その際学徒隊ひとりひとりに労いの言葉をかけた。
昭和20(1945)年7月2日 米軍が掃討作戦終了を宣言する。
昭和20(1945)年9月7日 嘉手納基地内での降伏文章への調印によって沖縄戦が正式に終了する。
戦後 積徳高等女学校は復興されず廃校となる。
平成12(2000)年 積徳高等女学校関連の戦没者職員5、同窓生44人、学徒23、計72名が合祀された慰霊碑が、設立者大典寺境内に建立される。
国道331号線バイパスを空港から糸満市街へと向かう途中、左手に看板があります。糸洲の壕(ウッカーガマ)と呼ばれるこの自然壕は、豊見城城跡にあった第24師団第二野戦病院が、第32軍司令部の南部撤退命令を受けて、昭和(1945)20年5月27日にこの地に移動して来ました。第24師団第二野戦病院には私立積徳女学校生徒から構成された〝ふじ学徒看護隊〟25名が配属となっており部隊に行動をともにしています。
水が豊富に湧き出ていた場所だったため、炊事などには困らなかったものの壕内は常に湿っており、学徒隊の足袋は乾くことがなかったという証言が多くあります。しかし敗戦を免れなくなった昭和20(1945)年6月17日に最初の馬乗り攻撃を受け、学徒をはじめとする人々は壕の奥へと移動します。しかし戦況は既にどうしようもないところまで来ており、行動をともにしてきた衛生兵も斬り込み隊に任命され、夜襲をかけたものの戻ってくることはありませんでした。衛生兵が減った分の仕事は学徒隊に回ってきたという証言も残っています。
この時期になって第32軍司令部より他の学徒隊同様〝解散命令〟が出されます。砲弾が飛び交う戦地での解散命令は=死を意味するものでした。事実他の学徒隊の戦没者のほとんどがこの解散命令発令後に出ているのは周知の事実です。連絡網の状況によるものなのか、解散命令が出されている日にちは6月17~19日と記録されているものが多い中、このふじ学徒隊に出されたのは6月26日のことでした。この約1週間の解散命令の〝ずれ〟はなにを意味するのか…。それが結果的に学徒隊の犠牲者を最小限に食い止めた部隊長の判断によるものだということはあまり知られていないことです。第24師団第二野戦病院院長小池勇助軍医少佐、長野県佐久市のご出身で地元中込駅前で眼科の開業医をされておられたそうです。3回目の招集で沖縄に来られた小池隊長は他の部隊とほぼ時期を同じくして受け取った解散命令を、この状況で出すことは危険極まりないとの判断で軍命を握り潰し、壕内に残る選択肢を取ったようです。そして6月26日には第32軍の牛島司令官と長参謀長の自決の報を受け取り、日本軍の組織的抵抗の終焉を知った上で解散命令を出します。
学徒隊の前で最後の訓示をした小池隊長は、「日本は敗けました。もし負け戦になるとわかっていれば、あなた達を預かりませんでした。親御さん達に本当に申し訳ない」と深々と頭を下げられたそうです。しかし鬼畜米英の教育を受けた学徒達もそう簡単には引き下がりません。捕虜になるくらいならば自決を選ぶと最後まで隊長をはじめとする野戦病院と行動をともにしたいと食い下がります。そこで小池隊長は静かに語り掛けたそうです。
「捕虜になるのは恥ではありません。本当の恥は死ぬことです。なので決して死んではいけない。必ず生きて家族の元に帰り、この凄惨な戦争の最後を後世の国民に伝えて下さい」と。小池隊長は泣きじゃくる学徒達とひとりひとり握手をして、壕から送り出したそうです。
数人のグループで行動して逃げるように指示は出されていたものの、中には団体行動から外れる恐怖に苛まれ、壕付近に留まるものもいたそうです。まだ米軍による掃討作戦が終了していない中、ビラや拡声器による投降を促していた時期でもあるため、その生徒は米軍を通り過ごしてからばらまかれていた〝タバコ〟を拾い、小池隊長に渡そうと病院壕へと入ったところ、変わり果てた小池隊長の姿を発見します。青酸カリによる服毒自殺だったとされています。
結果としてふじ学徒25名のうち戦死者は3名(1名は戦後自死)という動員された学徒隊の中で最も少ない犠牲者だったことがわかります。戦死者数の多い少ないで語れる話ではありませんが、適切な判断がなされていれば犠牲者がこれ程多くはならなかったのではという仮説が出てきます。
「命を大切に」と言った小池隊長がなぜ死を選んだのか。本人が亡くなっているため推測の域ではあるものの、やはり小池隊長も軍人だったということだと思います。軍命とはいえ医者の本分である〝治療〟が出来ず、多くの兵士の命を救えなかった…。そして撤退に纏わる移動に於いて、重症患者を置き去りにしなければいけなかった…。それも僅かな食料と手榴弾という〝生〟とは全く逆のものを残してやらなければならなかった。沖縄戦において命の尊さを説いた数少ない軍人であった小池勇助隊長だったが故に医者としての仕事と現実の葛藤に悩んでいたことは容易に想像がつきます。非常識な言い方ですがもし学徒を含めた犠牲者が大変多かったなら、自分自身で生き長らえて後世へ伝えなければならないという〝義務感〟は持っておられたに違いないと思います。しかし近隣で多くの犠牲者を出していた学徒隊に比べると、ふじ学徒の犠牲者は少なかった…。戦争を起こした訳ではないにしろ、隊長として陸軍病院を引率した責任者には違いない…そのため最後に自分自身の進退を決められたのではないかと思います。
ふじ学徒隊の慰霊碑は戦争でなくなってしまった学び舎があった付近那覇市松山の大典寺境内にあります。小池隊長のお墓は地元野沢の本覚寺に建立されており、回忌法要には積徳高等女学校のふじ学徒隊メンバーが訪れ、命の恩人との繋がりを今なお続けておられます。
十把一絡げに軍が悪いという表現が多々見られる中、軍を構成する軍人までをも悪人と決めつけられている風潮があります。軍人とは言え一人の人間、その中には〝戦争〟という時代の流れに翻弄されながらも、必死に命の尊さを説き続けた方もおられることを忘れてはならないと思います。
もうひとつまた小池院長の部下として行動を共にされた島尾二中尉。やはり医者としての心を忘れなかった軍医の一人です。第24師団第二野戦病院の移動の時、小池院長は自力で動くことのできない重症兵の〝始末〟を命じられるものの、枕元には青酸カリではなく乾パンと手榴弾を残していったそうです。ならば命令無視か?ということにはなるものの、部下の島尾中尉のしたことに肯定も否定もしなかった小池院長の姿が、生存者の手記に記されています。立場的に命令無視を認めることはできなくても、人の気持ちを忘れない小池院長と部下の島尾中尉。その二人の心の中には通うものがあったのではと思えてなりません。最終的に小池勇助軍医中佐は自決されました。しかし島尾二中尉は生き残られふじ学徒生存者の方々とともに、豊見城城跡公園にある旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑の建立に尽力されたそうです。しかし現在豊見城城跡公園は閉鎖中で、この第二野戦病院跡を訪れることはできません。もう結構な期間閉鎖されているのでなんとか再開して欲しいとは思うのですが…。
最後に小池勇助軍医中佐辞世の詩を紹介します。
南の孤島の果てまで守りきて
御盾となりゆく吾を
沖のかもめの翼にのせて
黒潮の彼方の吾妹に告げん
【平成28(2016)年6月23日木曜日追記】
現在空手道場の建設が進む旧豊見城城址公園ですが、慰霊の碑には特例として参拝を認めているとの情報を得ました。しかし公式な情報という訳ではなく、あくまでもwebに書かれている情報のため、事前に確認することもできませんでした。ならば行って確認するしかないので、旧豊見城城址公園入口付近をよく見ながら車を進めると、どうやらそれらしき記述を発見し、表記通りに進みます。舗装路は拝所で止められていますが、広場からは進むことができ、それらしき場所まで歩いて行くと・・・、ありました。第24師団第二野戦病院患者合祀碑が。昭和57(1982)年に島尾ニ軍医やふじ学徒看護隊の生存者の手によって建立された慰霊碑です。島尾軍医はこの碑の建立を心待ちにされていたそうですが、願い叶わず亡くなられたそうです。
慰霊碑に手を合わせ、確かこの碑の下に野戦病院壕があるという記憶に従い歩いて行くと・・・、見つけました。しかし以前のように標識がある訳でもなく、ただ入口を塞ぐようにしているものが妙に違和感を感じさせるものであり、慰霊碑との位置関係をGPSで確認したところ間違いないという結論に至りました。
10年以上もの間放置されており、一見するだけでも落盤の危険性を感じるものゆえ、入口にて手を合わせ、カメラを壕内に入れてカメラに収めました。元々復元壕だったため、戦中をそのまま残している訳ではありませんが、ふじ学徒看護隊が籠ったひとつの壕として早急な対策の必要性を感じました。
第24師団第二野戦病院はこの豊見城城址の後南部へと撤退し、糸洲の壕へと向かったあとその地で学徒看護隊の解散命令を受けることになります。他の学徒看護隊に対する解散命令が、第32軍司令官自決の直前に出されていることに対し、積徳高等女学校学徒看護隊は部隊長小池勇助軍医中佐の独断で命令を先送りし、6月26日に出したことにより多くの学徒隊員の命が助かっている事実は先述した通りです。
この第24師団第二野戦病院と積徳高等女学校学徒看護隊の足取りを辿るものは、現在私が把握しているものではこれですべてです。〝第二十五章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~ふじ学徒看護隊(積徳高等女学校)の足跡を訪ねて~〟はこれにて終わります。
《平成29年6月23日追記》
本年春頃に〝糸洲の壕〟隣にある〝鎮魂之碑〟が建て替え工事中だったことを知り、確認のため訪れました。1年前には畑が広がっていたエリアは更地化され、慰霊之碑は既に新しいものに建て替えられていました。しかし壕入口には『立入禁止』と書かれた柵が建てられており、自由には中には入れなくなっています。
追記①:平成28(2016)年3月1日
追記②:平成28(2016)年4月16日
追記③:平成28(2016)年6月23日
追記④:平成29(2016)年6月23日
- 旅行の満足度
- 5.0
- 観光
- 5.0
- 交通
- 5.0
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 3万円 - 5万円
- 交通手段
- 高速・路線バス レンタカー JRローカル 自家用車 徒歩 Peach ジェットスター
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
沖縄でも珍しい浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院である大典寺です。歴史は新しく廃藩置県によって沖縄県が置かれた後明治12(1879)年に開かれました。大正4(1915)年真宗本願寺派大典寺と改名し現在に至ります。
大典寺 寺・神社・教会
-
宗教概念の違いなのでしょう。カラーリングを含めて内地のお寺とは違います。
大典寺 寺・神社・教会
-
聖徳山大典寺の碑。
大典寺 寺・神社・教会
-
近付けば近付くほどミャンマーやネパールの仏教系寺院のように見えます。
大典寺 寺・神社・教会
-
その大典寺を経営母体とした積徳高等女学校戦没者慰霊碑が敷地内に建立されています。
大典寺 寺・神社・教会
-
寺院の境内にあるため花が供えられています。
大典寺 寺・神社・教会
-
積徳高等女学校のあゆみ
1918(大正7)年 ■ 「沖縄家政実科女学校」の創立(4月22日)
那覇市松下町「大典寺」内に西本願寺南陽佛教婦人会 を中心に大典寺住職菅深明により創立される
大典寺の本堂と庫裏を教室として開校(5月1日)
職員10名 生徒22名 校長 菅 深明(すが・しんみょ う)
1926(大正15)年 ■ 大典寺隣域に校舎新築
1930(昭和5)年 ■ 「私立沖縄家政高等女学校」に改称
1932(昭和7)年 ■ 美栄橋2丁目38番地に校舎新築移転
1941(昭和16)年 ■ 寄宿舎「花園寮」を大典寺境内に設置
1943(昭和18)年 ■ 「積徳高等女学校」に改称 生徒数480名
1945(昭和20)年 ■ 7月2日米軍沖縄作戦終結宣言
沖縄戦により、28年の歴史を閉じ廃校となる
2018(平成30)年 ■ 存続していれば、創立開校から100周年を迎える
学校跡地は、モノレール美栄橋駅から徒歩4分、久茂地川の十貫瀬橋から東方向、現在の「那覇市牧志1丁目17」である。
2015(平成27)年6月23日 ふじ同窓会、大典寺共同設置大典寺 寺・神社・教会
-
私立積徳高等女学校、建物。
大典寺 寺・神社・教会
-
積徳高等女学校の生徒たち。
大典寺 寺・神社・教会
-
普段は立ち入り禁止となっている旧豊見城城跡公園ですが、慰霊の日は指定地域には入ることができるようになっているようです。(2016,06,23撮影)
-
旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑。
やっと訪ねることができました。
(2016,06,23撮影)旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑 名所・史跡
-
旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑。(2016,06,23撮影)
太平洋戦争末期の沖縄戦に於いて陸軍第24師団第二野戦病院壕が左後方の崖の中腹にありましたが、ここに配属され従軍した島尾二軍医中尉並びに積徳高等女学校学徒看護隊などの生存者より、この病院壕に於いて最後まで勝利を信じて戦い傷つき倒れた多くの英霊を供養するため、昭和57年8月に建立された合祀碑です。旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑 名所・史跡
-
島尾二軍医他積徳学徒看護隊生存者の手によって建立されました。(2016,06,23撮影)
旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑 名所・史跡
-
旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑は、第24師団第二野戦病院壕上部に建立されています。
左手にのびる道を歩いて行きます。(2016,06,23撮影)旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑 名所・史跡
-
そして下方向へと歩く道(階段)を歩いて行くと…。(2016,06,23撮影)
-
階段を降りるとなにやら人工的に作られたものを発見します。実はこれが旧陸軍第24師団第二野戦病院壕です。(2016,06,23撮影)
第24師団第二野戦病院壕 名所・史跡
-
この野戦病院壕では 沖縄戦中最激戦地と云われた首里・浦添・西原・那覇一帯から負傷兵が次々と運びこまれ、これに対応するため昼夜兼行で治療と看護が続けられました。収容能力以上600名余りの負傷兵を抱え、医療施設や医薬品も十分に間に合わず、傷口からはうじ虫がはいだしその包帯を洗っては使い、食事も満足に支給することもできず、薄暗い壕の中でうずくまって軍医さん看護婦さんと呼ぶ声や姿、そして治療の甲斐もなく戦死され埋葬された地点にまた爆撃をうけ死体や衣服が飛び散って周辺の木枝にぶらさがるなど、その惨憺たる光景は筆舌につくせなかったと伝えられております。その間戦闘はますます悪化し、昭和20年5月27日海軍記念日を期して日本海軍が総攻撃を行うという期待もむなしく逆に敵兵が目前に迫り、その晩からさらに南部の米須へと後退を開始しましたが、その際独歩患者には杖を与えて退院させ、重傷患者には水や乾パンを枕元におき「最後まで望みを捨てるな」と云いつつ置きざりにせざるをえなかったと伝えられております。この野戦病院壕に配属され従軍した軍医や積徳高等女学杖学徒看護隊などの生存者により合祀碑が建立された機会に、最後まで勝利を信じて戦い傷つき倒れた多くの英霊を供養しそして永遠の平和を祈念するため、昭和58年7月この野戦病院壕が復元されたのであります。(2016,06,23撮影)
第24師団第二野戦病院壕 名所・史跡
-
長い間手入れをされていないため、内部は荒れ放題です…。(2016,06,23撮影)
第24師団第二野戦病院壕 名所・史跡
-
いつなんどき落盤が起こっても不思議ではない状態だったため、入口から内部の様子を撮るだけにしておきます。(2016,06,23撮影)
第24師団第二野戦病院壕 名所・史跡
-
そして旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑へと戻ってきました。こんな平和一色の風景は当時は考えもつかなかったことでしょう…。(2016,06,23撮影)
旧陸軍第24師団第二野戦病院患者合祀碑 名所・史跡
-
第24師団第二野戦病院壕、糸洲の壕(ウッカーガマ)の入口です。
-
少し農道を北進すると?糸洲の壕?の看板が見えてきます。ただし国道からだとかなり見辛い…。
-
鎮魂之碑。昭和60(1980)年6月23日建立とされています。
【碑文】
此の洞窟は第二十四師団山第二野戦病院の跡である。長野富山石川県出身の将兵、現地防衛招集兵並に従軍看護婦積徳高等女学校看護隊が傷病兵を収容した壕跡である。糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
新しくなった鎮魂之碑。(2017,6,23撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
第24師団第2野戦病院長の小池勇助軍医中佐(左)と島尾二中尉(右)。
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
新しくなった鎮魂の碑。(2017,6,23撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
二基の新『チンコンノヒ』。(2017,6,23撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
ふじ学徒隊が所属していた第24師団第二野戦病院壕だった?糸洲の壕?です。別名をウッカーガマといいます。
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
階段が作られています。(2016,03,01撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
学徒の手記ではこのような容易い道のりではなかったと記述がありました。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
なのでこのようなものは当時ある訳がありません。(2016,03,01撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
さらに階段を下りていくと…。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
壕の底です。(2016,03,01撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
よく見るとガマの底部にはゴミも落ちています…。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
水が豊富な場所だけあってその水を組み上げるポンプのホースが見えています。(2016,03,01撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
ガマ底部の拝所。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
今回は装備と時間の関係でこれ以上奥へは進めません。(2016,03,01撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
水が豊富だったこのウッカーガマ、現在でも地下水を利用するためポンプのホースが巡らされています。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
ガマ底部の様子。壕内巡りに使われる足場のブロックが見えています。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
奥の方へと進みます。この先は轟の壕へと続いていたそうです。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
壕奥へと少し進み、さらに続く水脈。足場用のブロックが見えます。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
岩場を歩きながら撮った写真、その①。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
岩場を歩きながら撮った写真、その②。ズームアップしています。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
岩場を歩きながら撮った写真、その③。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
水に浸からず進める最遠端の場所。
体は入れずカメラのみ差し入れています。これが今回の限界地点です。(2016,04,16撮影)糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
水に浸からず進める最遠端の場所。
これが今回の限界地点です。体は入れずカメラのみ差し入れズームで撮影しています。ここから水路は左手に曲がっています。(2016,04,16撮影)糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
ドス黒い火炎放射器の炎の痕跡と金属が溶けた痕跡。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
こちらは逆方向です。
よく見るとブロックが水路を遮るように置いてあるようにも見えます。(2016,04,16撮影)糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
少し進んで…。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
ここが限界。こちらは足場もないので必死に岩にしがみついて写真を撮りました。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
壕内から発掘された遺物のようです。
ただ…この黄色いプラスチックは違うと思いますが…。(2016,04,16撮影)糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
最後に黙礼をして、今回の訪問は終わります。(2016,04,16撮影)
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
-
70余年前の昭和20(1945)年6月26日にこの壕を出て行ったふじ学徒(積徳学徒看護隊)達の目には、どのようにこの景色が映っていたのでしょうか…。
糸洲の壕 (ウッカーガマ) 名所・史跡
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
旅行記グループ
あみんちゅ戦争を学ぶ旅
-
前の旅行記

第二十三章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~白梅学徒隊(沖縄県立第二高等女学校)の足跡を訪ねて~
2016/03/01~
糸満・ひめゆり
-
次の旅行記

第二十二章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~糸満:マヤーガマ(マヤーアブ)~
2016/03/01~
糸満・ひめゆり
-
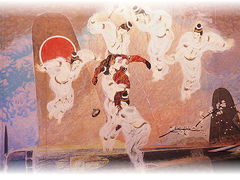
第一章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~鹿児島陸軍特攻戦跡:万世・知覧編~
2014/09/15~
知覧・南さつま・日置
-

第二章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~鹿児島海軍特攻戦跡:笠之原・串良・鹿屋編~
2014/09/15~
大隅半島(鹿屋・垂水・志布志・肝属)
-

第零章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~INDEX編~
2014/09/16~
糸満・ひめゆり
-

第四章あみんちゅ戦争を学ぶ旅沖縄~嘉数(かかず)高台公園《私見》沖縄戦解釈編~
2014/12/14~
宜野湾・北谷・中城
-

第十二章あみんちゅ戦争を学ぶ旅沖縄~対馬丸記念館・旭ヶ丘公園慰霊碑編~
2015/06/21~
那覇
-

第十一章あみんちゅ戦争を学ぶ旅沖縄~浦添大公園・嘉数高台公園編~
2015/06/21~
宜野湾・北谷・中城
-

第十七章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~西表島:宇多良(うたら)炭坑編~
2015/10/13~
西表島
-

第十八章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~南城:糸数アブチラガマ~
2016/02/28~
知念・玉城・八重瀬
-

第十九章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~ひめゆり学徒隊(沖縄師範学校女子部・沖縄県立第一高等女学校)の足跡を訪ねて~
2016/02/28~
糸満・ひめゆり
-

第二十章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~南風原(はえばる):南風原文化センター編~
2016/02/29~
知念・玉城・八重瀬
-

第二十一章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~南風原(はえばる):沖縄陸軍病院南風原壕群20号編~
2016/02/29~
知念・玉城・八重瀬
-

第二十三章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~白梅学徒隊(沖縄県立第二高等女学校)の足跡を訪ねて~
2016/03/01~
糸満・ひめゆり
-

第二十五章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~ふじ学徒看護隊(積徳高等女学校)の足跡を訪ねて~
2016/03/01~
那覇
-

第二十二章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~糸満:マヤーガマ(マヤーアブ)~
2016/03/01~
糸満・ひめゆり
-

第二十四章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~梯梧学徒隊(私立沖縄昭和高等女学校)の足跡を訪ねて~
2016/03/01~
糸満・ひめゆり
-

第二十六章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~呉・旧海軍墓地を訪ねて~
2017/04/19~
呉・海田・安浦
-

第二十八章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~なごらん学徒看護隊(沖縄県立第三高等女学校)の足跡を訪ねて~
2017/06/21~
名護
-

第二十九章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~広島原爆被害の数字と理屈~
2017/08/29~
広島市
-

第三十章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~浦上の聖人〝永井隆〟を訪ねて~
2017/09/28~
長崎市
-

第二十七章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~人間魚雷回天~
2018/05/18~
徳山・周南
-

第三十一章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~沖縄読谷村:生と死とのはざま~シムクガマ・チビチリガマ編~
2019/06/22~
恩納・読谷
-

第三十二章あみんちゅ戦争を学ぶ旅~軍都大阪編~
2020/08/19~
大阪城・京橋
旅行記グループをもっと見る
この旅行記へのコメント (3)
-
- わんぱく大将さん 2016/06/27 07:37:31
- おりしも同じ6月26日
- たかティムはるついおままゆさん
お久しぶりです。 しかし、よくまあ、こんな所を見つけましたね。おりしも同じ6月26日(日本は27日か)
大将
- たかちゃんティムちゃんはるおちゃん・ついでにおまけのまゆみはん。さん からの返信 2016/07/01 09:27:57
- RE: おりしも同じ6月26日
- 大将どん
ホンにご無沙汰しておりますn。場当たり的に発見したように見えるあの?今日だけ?の表示は、実は2ヶ月ほど調べていたんですよ。
あんまり綿密な計画はしょうに合わないのですが、この場所は学徒を語るに外せない場所だったので、市役所なんかにも問い合わせたのですが「わかりません」の一点張り。ならば現地調査や!ということで直接足を運び知った次第です(汗)。
今後ともよろしくです〜♪
たかティム。
-
- Mauricioさん 2016/06/06 09:40:01
- いつも学ばせて頂いて有難う御座います
- たかティムさん、おはようございます。
学徒看護隊の足跡を学ばせて頂きました。
詳細を南米ではどこまで正確に伝えられているのかが分かりませんが
沖縄移民の子孫の皆さんと会話の折は史実を正確に伝えなければなりません。
二世三世、今では五世六世の時代となって沖縄色が薄れています。
それでも一世である私が知っておかなければ彼らは自分たちの歴史を親から伝え聞く程度、ほんの入口くらいしか知らないのではないか、それでは笠戸丸・移民第一船からの彼らの足跡を知り得るには至らない。
沖縄こそ総力戦となったところで、何歳であろうと全員参加させられたのは容易に想像出来ます。
本土の人間として沖縄に行っても何も語られない。
しかし、南米から来たことが分かると物凄く詳しく教えて頂ける。
この差、なんですね、彼らの心がどちらに向かって開かれるか。
逆に沖縄から大阪に来た方々、彼らのクチからも何にも聞かれない。
南米に行った方々も、大阪に行った方々も、立場は同じなんだな〜。
沖縄って、本当に南米に似てる!
南米が恋しくなったら沖縄に行きたい。
心も、空気も、海も、街並みも、日本の中の南米。
ありがとう!
Mauricio
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?











































































旅行記グループ あみんちゅ戦争を学ぶ旅
3
53