
2021/12/02 - 2022/07/01
79位(同エリア220件中)
![]()
Decoさん
この旅行記のスケジュール
2022/07/01
-
三池炭山創業碑(笹林公園内)
-
宮地嶽三柱神社
-
乙宮(おとみや)神社
-
三井化学J工場
もっと見る
閉じる
この旅行記スケジュールを元に
宮浦石炭記念公園は、かつての三池炭鉱・宮浦坑跡が公園として保存・整備されたものです。
世界遺産には指定されていませんが、三池炭鉱や地域の産業の中で果たした役割は大きく、また大きな煙突も残されています。
そんな宮原石炭記念公園に加え、大牟田市役所近くの三池炭山創業碑、そして産業化遺産として重要でありながらも残念ながら取り壊しが行われている三井化学のJ工場を訪れてみました。
この旅行記は、近代化産業革命遺産の光と影・三池炭鉱のシリーズの中での順番の都合上、2022年の旅程になっていますが、2021年の夏から何度か現地に訪れて作成しています。
(2022/8/5).
- 旅行の満足度
- 4.5
- 観光
- 4.5
- 交通手段
- 自家用車 徒歩
-
今回の旅行記の始まりは大牟田駅。東口ロータリーの一画に市政100周年の記念碑がありました。世界遺産の宮原坑、三池港、三池炭鉱専用鉄道敷跡にゆるキャラのジャー坊が記されています。
大牟田駅 駅
-
大牟田といえば、草木饅頭。白あんの一口サイズの饅頭が美味しいのです。
駅前に二軒のお店があります。「総本家」の黒田屋と、「元祖」の江口栄商店。元は同じだそうですが…
ちなみに、この左の方に以前の旅行記で紹介した大牟田観光プラザがあります。総本家 黒田家 駅前店 グルメ・レストラン
-
イチオシ
JR大牟田駅前のクラシカルな建物は「大牟田市庁舎」です。
市役所の焼失の後、1936年(昭和11年)に落成したそうです。
この写真は斜め方向から撮影したので、今一つわかりにくいのですが、左右対称のバランスの取れた四階建て(写真では一階部分が写っていません)で、中央に塔屋が置かれた建物で、第二次大戦の空襲にも耐えました。
大牟田市のシンボル的建物ですが、建て替えの話も出ていて、賛否両論です。確かに横に長く、増築を繰り返しているので、段差を解消するためにスロープがあったり、複雑な構造になっています。
エレベーターも多分後付けなので、正面玄関からかなり離れた端の方にあります。
市民も職員の方たちも使いにくい建物かとは思うので、建て替えの必要性はわかりますが、この重厚な建物、どんな形でも良いから是非残してもらいたいと思います。第二次大戦前からの歴史ある市庁舎 by Decoさん大牟田市庁舎 名所・史跡
-
続いて、大牟田市役所の裏にある笹林公園へ。
この公園には「三池炭山創業碑」があります。 -
説明のプレートです。
三池炭鉱=三井のイメージがありますが、元々は藩政期に柳河藩家老・小野家と三池藩により採炭が始まりました。それが明治早々に官営化され、その後三井に払い下げられます。
この碑は三井が落札した後、官営時代の歴史を顕彰したもので、時の財務大臣・松方正義、官営時代の責任者・小林秀和、三井による落札を成功させた益田孝が当事者として記されています。
ちなみに、三池炭鉱の近代化に尽力した團琢磨は官営時代に三池炭鉱に入り、そのまま三井に移籍しました。官営時代、アメリカ帰りの技術者だった團琢磨は明治政府の藩閥官僚(長州出身)であった小林秀和とはあまりうまくいっていなかったようです。 -
碑に近づいてみます。風格があります。
-
三池炭山創業当事者として記されている、松方正義、小林秀和、益田孝。
-
碑の本体に刻まれた説明。大まかに内容を記すと…
「文明元年に石炭が発見され(稲荷山の百姓が発見したという逸話かと思われます)、三池藩・柳河藩により稲荷山・平野山・生山が開坑。
明治6年工部省管轄で官営化し大浦坑を開く(大浦坑自体は藩政期からの坑ですが、西洋技術が投入され近代的な斜坑が開かれたということかと思います)。
明治9年三井物産が石炭の販売を行うようになり海外に輸出も行う(三井グループを代表する物産は、三池炭鉱の販売からスタートしました)。
明治15年七浦坑竪坑開坑。それ以前から福岡・熊本・佐賀・長崎各県の囚人を使役しており、明治16年には三池集治監を設立して囚人労働を行う。
明治19年大蔵省の管轄に。
明治20年宮浦坑開坑。
明治22年三井家の所有に」
囚人労働の記述がみられます。三池炭鉱の初期において、労働力不足に悩む中囚人労働に大きく依存していたことを如実に物語っています。しかし多くの犠牲を出した、その過酷さを考えると、時代背景や世間の感覚が今とは異なるとはいえ、記念碑に記されていることに複雑な思いがします。
*炭鉱での囚人労働は、北海道で行われ、また長崎(高島炭鉱)、沖縄(西表炭鉱)、福岡県北部の津波山炭鉱でも行われたそうですが、ごく短期間でした。この他、炭鉱以外の鉱山でも行われていたようです。
福岡県議会は明治22年、炭鉱の囚人労働を過酷すぎるとし、県からの囚人の派遣を禁じる決議を出しています。 -
宮浦石炭記念公園へ。かつての三池炭鉱宮浦坑の一部が公園として整備されています。
世界遺産の万田坑や宮原坑が往時の姿をそのまま保存しているのに対して、宮浦坑は少し雰囲気が異なります。
宮浦石炭記念公園は1995年頃開園。三池炭鉱閉山(1997年)の少し前になります。まだ世界遺産だとか、そんな話もなかった頃のこと。大牟田市としても公園として親しんでもらい、施設の一部を残すことを考えたのでしょう。
万田坑・宮原坑のようにそのまま残した方がリアルな感じはありますが、当時の状況からして、宮浦坑を一部だけでも残してくれた大牟田市の功績は大きいと思います。三池炭鉱における重要な史跡 by Decoさん宮浦石炭記念公園 公園・植物園
-
説明板を撮影。宮浦坑は明治20年(1887)に開坑し、昭和43年(1968)まで採炭されました。実に81年稼働していたわけですね。三池炭鉱で西洋近代技術が投入されて閉山までの120年の歴史(1877~1997)の中で、最も長期間稼働していたことになります。
宮浦坑は大浦坑、七浦坑に続く三池炭鉱で西洋技術により開坑した三番目の坑ですが、掘削が始まったのは勝立坑の方が先でした。それに次いで宮浦坑の開削が始まったわけですが、この時点では宮浦坑は石炭の産出ではなく、通気坑を想定されていたそうです。しかし、勝立坑が湧水や地震のために工事が難航し、宮浦坑が揚炭の坑として本格的に整えられ、勝立坑よりも先に開坑します。
説明板には、往時の敷地図もありました。現在公園として残っているのはほんの一部、他は道路になったり、企業や工場が建っています。 -
入口から左手、道路に近い場所に第一立坑跡がありました。宮浦坑の初期に使用されたもので、今は埋め戻されて煉瓦が場所を示しています。
宮浦坑は万田坑や宮原坑より古い坑ですが、世界遺産として認定された2015年の時点では明治時代の建物や櫓は残っておらず、その点で対象外になってのかも知れません。また、公園化された1995年の時点でも明治時代の史跡はほとんどなかったのではないかと思います。それは後述のように、第一竪坑が第二次大戦後しばらくして稼働を終えていたからです。 -
第一竪坑跡の背後には、道路を隔てて工業団地が見えます。宮浦坑の使用が終わった後、工業団地として造成されました。背後に見えるのは大宝工業。その先にはヤヨイ食品があります。
-
第一竪坑跡の説明です。
かつては宮原坑や万田坑のような櫓があったようです。
この説明版、簡潔な説明とわかりやすい図面ですが、ちょっと古くなっています…
宮浦坑の第一竪坑は、明治20年(1887)から工事が始まり、翌21年に竣工。昭和22年(1947)まで使用されました。約60年の長きにわたり使用されたことになります。人員の昇降と揚炭に特化した坑で、排気は七浦坑第三斜坑から行われ、排水も七浦坑(後に宮原坑)から行われます。
大正8年(1919)には排気用の第二竪坑が設けられ、こちらは昭和26年(1951)まで使用されました。 -
第一立坑跡の前には、炭鉱で使用されていた機械が展示してありました。
後述する大斜坑跡に付帯する建物を利用しているようです。 -
煙突が見える角度から撮影。
-
中には線路が引き込まれています。
-
機械類は三点展示されていましたが、これはサイドダンプローダー。
坑道を掘るときに出た土や岩をつめ込む機械で、バケットが横に回転します。 -
フェース・ローダー。石炭の層に沿って坑道を掘るとき、ダイナマイトで砕いた石炭をかきよせコンベアーにつめ込む機械です。
-
ドリル・ジャンボ。掘削中に岩が出てきたとき、ダイナマイトをしかける穴を掘削する機械だそうです。
-
機械類の展示の奥には「材料降下坑口」がありました。
採炭のためや坑道を維持するための機械類、坑道を支える木材、採炭後の不要な空間を埋める材料などが運ばれたようです。
この坑口、斜めに地下に入るようになっていますが、これはさらに奥の坑に付設されたものだったようです。 -
材料降下坑口の右の一段高くなった場所が、大斜坑口です。
-
ここには人が入昇坑するトロッコ列車のプラットホームが残されています。
-
材料降下坑口の右の一段高くなった場所が、大斜坑口です。
ここには人が入昇坑するトロッコ列車のプラットホームが残されています。
宮浦坑が80年に及ぶ三池炭鉱再長命の坑であった理由はこの大斜坑にあります。
明治36年に宮浦坑では断層に突き当たり、ボーリングで調査した結果、その先にも炭層が広がっていることが確認され、掘り進められます。
しかし従来の第一竪坑からでは採炭に限界があり、大正12年(1923)に大斜坑の開削に着手、翌13年から揚炭が始まり、実に昭和43年(1968)まで採炭が行われました。 -
大斜坑の説明。宮浦坑は昭和43年(1968)に採炭は終了しますが、その後も1990年まで人の昇降、資材の搬入などで使用されたようです…だからこれだけ保存されていたわけですね。
-
プラットホームのあたりからは、かついての三池炭鉱専用鉄道の線路が見えます。かつてはこのあたりから石炭が積み込まれて三池港へ運ばれたいたのでしょう。
以前の旅行記でも紹介しましたが、炭鉱鉄道が使われ亡くなった後、一部は三井化学の専用線として利用され続けてきました。しかしその運行も2020年5月をもって終了しました。 -
イチオシ
線路の反対側には、三井化学の化学コンビナートがあります。
かつて、宮浦坑から産出される石炭をもとに”石炭化学コンビナート”が形成され、それが発展して現在の工場群になっています。ただ、第二次大戦後には、エネルギー革命により石油を使用するようになったとのことです。
宮浦坑が歴史的に大きな意義があるのは、長期に渡って三池炭鉱の主力坑であり続け、そしてその石炭をもとにコンビナートが形成されたことにあると思います。
三池炭鉱が閉山(1997)後でも、炭鉱から派生した化学コンビナート(三井化学、三井金属、デンカやその他の企業)は大牟田の町を支える大切な産業であり続けています。また三井系以外にも多くの企業の工場があります。 -
イチオシ
大斜坑の右側には煉瓦造りの大きな煙突があります。
宮浦坑が重要な史跡である理由には、前述のように稼働期間の長さと化学コンビナートの形成がありますが、もう一つ。この煙突の存在です。
三池炭鉱においては、世界遺産の宮原坑・万田坑荷も煙突は現存しておらず、貴重な遺構です(同じ九州の筑豊の炭鉱の跡には煙突が残されています)。 -
別角度から撮影した煙突の下の部分。
-
煙突の説明です。第一立坑の捲上機は蒸気(=石炭)が動力でしたが、その排気のために設けられたそうです。
炭坑節について書かれていて、私たちがよく耳にする歌詞も「♪三池炭鉱の上に月が出た~♪」です。が、炭鉱節のルーツは筑豊・田川市のようです…。
三池炭鉱と歌で特筆されるのは、むしろ今や沖縄民謡として知られる「十九の春」だと思います。北九州の炭鉱で流行していたラッパ節(作曲者は演歌師の添田唖蝉坊)を、炭鉱で働いていた与論島の人々が持ち帰り(=与論ラッパ節)、それが沖縄本島に伝わって「十九の春」になったたそうですから。
筑豊や長崎から与論島へ持ち帰られたともいわれますが、私は三池からの可能性が高いと思います。それは、与論島の人々が集団で移住して働いていたのは三池炭鉱であり、三池港北側にあった、新港社宅に住んでいたからです。
炭鉱節は、選炭節(石炭の選別作業中に唄われた歌)がルーツだと言われますが、ラッパ節の影響を受けていると考えられます。十九の春の元になった与論ラッパ節も、当然ラッパ節が元になっています。炭鉱節と十九の春は兄弟姉妹かいとこのような関係と考えられます。また、炭鉱節が直接与論ラッパ節に影響を与えたとも考えられています。
二つの歌の歌詞には、「男性から別れを切り出された女性が、若い頃に戻してくれれば別れる」と答える共通したテーマが見られます。 -
プラットホームと煙突の手前には、中国人殉難者の慰霊碑がありました。
-
裏面には説明がありました。
炭鉱には負の歴史があり、囚人労働や納屋制度(人集めのブローカーに支配されたタコ部屋のような制度)は酷いものだったそうです。また台風で壊滅的な被害を受けた与論島から移住した人々も差別を受け低賃金で働かざるをえませんでした。外国人労働は、そうした歴史の延長にあるように思えます。
尚、朝鮮半島からの人々よりも、中国からの人々の扱いがより酷かったそうです。当時朝鮮半島は日本領だったから、ということです。 -
公園内と外の街路樹が美しい紅葉を見せていました。メタセコイア…太古、この木が繁茂し、それが長い年月をかけて石炭になったそうです。
-
宮浦石炭記念公園の近くに小さな神社がありました。古くなっていましたが、境内はきれいに清掃されていました。
-
狛犬は独特の表情をしていました。
この神社は付近の住宅街と宮浦坑の敷地跡の工業団地との境に位置しています。この神社と狛犬、長い歴史を持つ宮浦坑をみまもってきたのでしょう。 -
【乙宮(おとみや)神社】
宮地嶽三柱神社から南の方へ。小高い台地の上に乙宮神社があります。小さな神社ですが、歴史は古いようです。宮浦という地名もこの神社に由来しているそうです。
ちなみに、三池炭鉱の明治初期の三つの坑(大浦、七浦、宮浦)には、いずれも「浦」がつき、かつては海が内陸まで深く入り込み、台地や山の麓に入江が形成されていたことを物語っています。 -
神社の境内。
-
文化財があるそうですが…
-
社はシャッターが下りていました。
-
【三井化学J工場】
この旅行記の最後に三井化学J工場を紹介したいと思います。
宮浦石炭記念公園の先に広がる化学コンビナート。その西北隅にある一際大きく存在感のある建物が三井化学のJ工場です。太平洋戦争も間近に迫った1938年に完成しましたが、当時は極秘扱い。軍事物資を生産していたからだそうです。
建物の高さは47m。7階建てですが、中は二層構造になってるので実質14階建ての高さがあります。当時としては鉄筋コンクリートの巨大建造物。原材料を最上階に引き上げ、階を下りながら製造過程を経て一階で完成品ができたそうです。
大牟田市庁舎や今は無くなってしまった松屋デパートと並んで大牟田市のシンボル的建造物でした。
そのJ工場も役目を終わり、取り壊しが始まっています。
旅行記の最後にその様子を掲載いたします。
こちらはゆめタウンのそばから撮影。この写真は2021年8月に撮影したものです。新聞にJ工場解体の記事が載っていて、今のうちにと思い撮影に行きました。このときはまだ解体の気配は感じられません。 -
イチオシ
こちらの写真は三井化学の北門付近から撮影。この写真も2021年8月に撮影
-
こちらは2022年3月撮影。取り壊しのためか、足場が組まれています。手前には古いレトロモダンな建物。こうして見ると、最近の近代的な工業団地とは一味違った魅力があります。
-
2022年5月、三井化学J工場、解体が進んでいます。さようならJ工場…。
大牟田の町のシンボルがまた一つ姿を消します。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
旅行記グループ
三池炭鉱 近代化産業革命遺産の光と影
-
前の旅行記

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(6) 勝立坑とその周辺
2021/11/30~
大牟田
-
次の旅行記

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(3) 万田坑~近代化へ向かった炭鉱~
2021/12/09~
玉名・荒尾
-

三井港倶楽部にて、春のランチ
2021/06/07~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(1) 大牟田市石炭産業科学館・三川坑
2021/11/20~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(2) 三池港(世界遺産)&「光の航路」撮影に挑む
2021/11/20~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(6) 勝立坑とその周辺
2021/11/30~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(8) 宮浦石炭記念公園と三井化学J工場
2021/12/02~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(3) 万田坑~近代化へ向かった炭鉱~
2021/12/09~
玉名・荒尾
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(5) 宮原坑周辺を歩く
2021/12/25~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(4) 宮原坑 ~旧時代の終焉~
2022/01/09~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(9) 大浦坑と化学コンビナート
2022/05/25~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(7) 文化展・炭都の暮らしと文化(大牟田市石炭産業科学館)と三池港周辺
2022/06/12~
大牟田
-

世界遺産・三池炭鉱 宮原坑 耐震工事特別公開
2022/11/03~
大牟田
-

三池港「光の航路」 2022/11/21
2022/11/21~
大牟田
-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(10) 三川坑、再び
2023/05/02~
大牟田
旅行記グループをもっと見る
この旅行記へのコメント (15)
-
- PHOPHOCHANGさん 2022/11/10 20:44:16
- ご紹介有難うございます
- まずは、PHOの旅行記をご覧いただき、有難うございました。
そのご縁で、Deco様の旅行記を拝見する機会に恵まれました。
三池炭鉱、名前は知っていても、それだけでした。
シリーズ、時間を作ってシッカリ拝見したいと思います。
公開に感謝です。
- Decoさん からの返信 2022/11/11 06:27:13
- Re: ご紹介有難うございます
- PHOPHOCHANGさん、おはようございます。
こちらこそ、拙旅行記をご覧いただきありがとうございます。
三池炭鉱、様々な悲しい出来事もあり、近くに住みながらもそれとなく避けていたテーマでした。でも、まずは事実を知ることから始めなければと思って続けています。
時々長い説明文が入ったりして、読みにくい部分もありますが、御覧いただけたら本当に嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。
Deco
-
- yamayuri2001さん 2022/08/17 09:50:36
- 三池炭鉱の事実・・・
- Decoさん、こんにちは。
囚人労働者については、網走刑務所で詳しく学びました。
その時は、同時に看守も犠牲になるとの事で
看守と言う仕事を選択する人の崇高な精神は
凄いなと思いました。
人を更生させることは一筋縄では行きませんね・・・
三池炭鉱でも、同様の事実があったんですね・・・
三池炭鉱の事実も、一人一人が心に留めておくべき史実の一つですね。
120年間も、人々の生活を支えていたのですから・・・
炭鉱節のルーツは筑豊・田川市!
そうだったんですね。
三池炭鉱と言えば、こちらとばかり思っていました。
Decoさんの旅行記は、取材に基づいて書かれる
ドキュメンタリーです。
旅行記としてここにアップするだけでは
もったいないなと感じました・・・
yamayuri2001
- Decoさん からの返信 2022/08/17 14:03:31
- Re: 三池炭鉱の事実・・・
- yamayuri2001さん、こんにちは。
炭鉱シリーズ、我ながら厳しい内容も含み、説明もわかりにくいと思いますが、読んでいただき本当に感謝しています。
以前、yamayuri2001さんが北海道を旅行されたときの網走刑務所のお話、今も強く印象に残っています。囚人労働というと、囚人の人々の境遇に関心がいきますが、考えてみれば、看守の人々も一緒なわけですね。炭鉱でも監視する立場ながら危険と隣り合わせだったことだろうと思いますし、暴動も何度か起きていて、命を落とされた方も多いと思います。
また、当地には「解脱塔」という、亡くなった囚人の人々を慰霊する碑がありますが、それも三池集治監の吏員の人々によって建立されました。監視する立場ですが、同時に人として悼む気持ちも感じられて、看守の方々も複雑な気持ちで仕事をされていたのではないかと思います。
三池炭鉱の囚人労働、明治30年代の半ば以降は縮小されます。その際、三池集治監の囚人の少なくない人々が北海道に移されたそうです。北海道の方がまだ環境としては良かった、ということのようです。私はyamayuri2001さんの旅行記を拝見して、北海道の監獄の過酷さに驚いていたのですが…三池ではもっと酷かったのかとショックを受けました。
炭鉱節、レコードで♪三池炭鉱の上に~♪と唄われたので、それが広まったようです(私も三池を唄ったものだと長い間思っていました)。筑豊の方々は残念な思いをされているかも…。
炭鉱のお話、実は私の中ではそれとなく避けていたテーマでした。詳しくは知らずとも、そこにはつらい話があるだろうということは、漠然と感じていましたから。でも、いったん知り始めると、もっと知り、自分なりにまとめなければならないと思って書いています。
この旅行記シリーズはガイドの方に教えていただいたり、展示から学んだり、本を読んだり、いろんなものがつめ込まれてまとまりがありませんが、お褒めの言葉をいただき恐縮です。ありがとうございます。
Deco
-
- ちちぼーさん 2022/08/07 23:04:29
- もったいないですね。
- Decoさん、こんにちは。
海外の中で台湾は好きな場所ですが、好きな理由の一つが古い建物を大切にしてくれること。
それが、占領中の日本の建物でも。
でも、日本は良いなあと思う建物を古いからとか危険だからとか新しい方が人気があるからとかで簡単に壊しちゃうじゃないですか。壊したら戻らないのだから、何とか残して欲しいと思うのです。
ダラダラと書きましたが、大牟田市庁舎を壊しちゃうのはもったいない。
残して欲しい建物です。見ておかなかったことに凄く後悔しています。
宮浦石炭記念公園も当時のものをもっと残して呉れたらなあと思ってしまいますが、それでも一部はのこされ、その写真を見ながらDecoさんの解説を読むと1人で回るよりはるかに学べるように思います。
炭坑節って向かい意味も知らずに盆踊りで踊るきょくでしたから、歌のルーツもとても脅威深いものでした。
捕虜の方達があっての日本の繁栄。
消せない過去ですが、そのことを決して忘れてはいけないと思います。
今回も心に響く旅行記をありがとうございました。
ちちぼー
- Decoさん からの返信 2022/08/08 18:17:12
- Re: もったいないですね。
- ちちぼーさん、こんにちは。
大牟田市庁舎は、炭鉱関係の史跡ではないけど、その時代を反映した建築物であり、またそれ自体が価値あるもの。
確かに市役所としては、バリアフリーなどで大きな欠点がありますが、どのような形であっても残してもらいたいです。
壊したら元に戻らない。そうなんですよ。ゆめタウン大牟田というショッピングモールはかつてコンビナートの端に位置しており、三井三池製作所という会社の、明治時代の煉瓦の建物がありました。製作所が移転してショッピングモールになる際、それをなんらかの形として残したいということでしたが…壊して煉瓦でトイレを作ってしまった…。残しておけば改装してカフェでもレストランでも、いかようにも活用できたのに。ちちぼーさんのコメントを拝見してこのことを思い返しています。
宮浦石炭記念公園は時代を考えれば、あの形でもよく残してくれたと思います。
息子さんもこちらにいらっしゃるし、是非またいらしてくださいね。ちちぼーさんには是非、ガイドのおじいちゃんが必死で逃げた三川坑跡を見ていただきたいと思います。
Deco
- ちちぼーさん からの返信 2022/08/08 20:43:58
- RE: Re: もったいないですね。
- 三川坑跡はぜひとも行きたいと思っています。
お恥ずかしいことに、Decoさんの掲示板なのに誤字脱字だらけで
申し訳ありません。
-
- ちゅう。さん 2022/08/07 11:57:52
- 大牟田市庁舎
- Decoさん、こんにちは~
炭鉱シリーズ、興味深く拝見しています。
さて、私が注目したのは、壮大な大牟田市庁舎。
少し調べたところ、このような近代建築の市区庁舎で残っているのは、名古屋市庁舎も含め数カ所だけとか。(県庁舎はもう少し多そうですが)
和洋折衷の帝冠様式の名古屋市庁舎より、潔くて格好いいなと思います。
地方都市でこれだけ立派な庁舎を持っているということは、往時の盛況ぶりを反映しているのでしょうか。
無責任な発言は承知ですが、
取り壊しが一旦決定しているようですが、
解体・廃棄・新築の費用=耐震・補修・館内の完全リフォーム費用であれば、
いや多少予算がかかっても、文化的な視点や、環境保全の考え方からも、
徹底的に検討して悔いのないようにしてもらいたいものですね。
暑い日が続きますが、どうぞご自愛くださいませ。
ちゅう。
- Decoさん からの返信 2022/08/07 18:45:39
- Re: 大牟田市庁舎
- ちゅう。さん、こんにちは。
大牟田市庁舎、地方都市でこれだけの建物が残っているのは、本当に希少だと思います。
おっしゃる通り、石炭産業で栄えて財政的にも豊かな時代があっての市庁舎だと思います。この旅行記で取り上げた三井化学のJ工場や、また大牟田市動物園も、石炭+派生産業で栄えたからこその建築物や施設だと思います。
市庁舎の今後について、以前は随分議論されていろんな意見もありましたが、最近はあまり聞かなくなって、ちょっと調べてみたら、「庁舎整備の今後の方向性」という文書が市役所の公式サイトにありました。
・市庁舎は近隣地に新築、令和10年頃から着工予定
・現庁舎は民間活用を検討し、令和5年までに結論を出す
ことになっているようです。
確かに現庁舎は古くて、入口も正面玄関が二階で外階段で入る形、エレベーターも端っこにあって使いにくく、スロープや回廊が入り組んでわかりにくという欠点があります。
ただ、大牟田市はかつての松屋デパートが解体され、今も三井化学J工場が解体途中です。長年親しまれ、市のアイデンティティとなっている現役の建物は市庁舎だけになってしまいました。どんな形でも残してもらいたいと思います。
現市庁舎は建築物としても大変貴重なものかと思います。九州はちょっと遠いけど、機会があったら是非いらしてくださいね。事前に申し込めば見学もできるようです。
ちゅう。さんも暑さに気を付けてお過ごしくださいね。
Deco
-
- フォートラベルユーザーさん 2022/08/06 17:18:20
- 囚人過重労働の上に、、
- こんにちは、Decoさん、
私のような
予備知識を持ち合わせない人間でも、
感じてしまうこと、
人の命の犠牲の上に成り立つものなんて、
あってはならない。持続できる訳がない。
こんな残酷な形での労働の上に
近代日本の産業発展があったという事実
これは、語り継がなければいけない。
そうしなければ、犠牲になった
魂が浮かばれませんよね。これは、戦争と
なんら変わりないと、つくづく思いましたよ…
ありがとうございました。
コトラマダム
- Decoさん からの返信 2022/08/06 18:55:30
- Re: 囚人過重労働の上に、、
- マダム、こんばんは。
三池炭鉱に限らず、日本の産業の近代化の陰には非人間的なことがあったようです。江戸時代にも、あったとは思いますが、西洋技術が投入されて生産が上がる中で、非人間的な部分も拡大していったと思います。また、明治になり、中央集権の政府ができたことも、囚人労働などにつながったと思います。
炭鉱は、江戸時代はそこそこお給料も良い仕事で、鉱夫と農家を兼業していたり、三池藩に至っては武士の内職でもあったそうで、明治に比べれば平和な時代だったのかも知れません。
囚人労働や外国人労働について、このシリーズで繰り返し書いてしまいますが、一つには自分が暮らしている地域の身近な歴史の中で、こんなにも悲しい出来事があったということが衝撃だったからだと思います。また、炭鉱の歴史を探れば、必ずと言ってよいほど悲しい出来事にぶつかることになります。悲しいことに、これが三池のみならず日本の近代化の姿です。
さて、この旅行記の煙突の所で、炭鉱節と十九の春の関係について書きました。このつながりに大きくかかわった与論島から移住してきた人々は、三池港北側の新港社宅に集まって住んでいたのですが…この社宅には三池港務所という、炭鉱鉄道や港湾に関わる部門の社宅もあったそうです。萩尾望都先生のお父様も港務所にお勤めでしたから、先生も新港社宅にお住まいだったのかも知れません。もしかしたら、与論の人々が歌うラッパ節や十九の春を聞かれたかも…。
萩尾先生のお父様は英語が得意で外国船が入ると通訳をされたりして、萩尾先生も外国人に接することがあったようです(バイオリンの名手でもあったそうです)。幼い頃から様々な文化に接していたことが、先生の漫画にも影響しているのかも知れません。
Deco
-
- チーママ散歩さん 2022/08/06 07:49:57
- おはようございます。
- 今回も深く読みました。
こういうふうに私も先日の赤谷炭鉱も仕上げたかったんです。
ところが、大雨で炭鉱跡らしきものには行けず
スノーシェード1本の旅行記に・・。
産業の発展と衰退を背景とするノスタルジアの世界をご紹介したかったのに。
ふふふふ~の真夏の怪奇現象シリーズみたいになっちゃったわ(ToT)
非人道的な労働があったことは、胸をしめつけられる思いですね。
過酷な労働の中で多くの命が失われたのですから。
このような産業遺構をめぐると
「人命を軽視し、命の価値に差をつける」
このような行為が行われていた負の遺産をも、嫌でも同時に目の当たりにします。
二度と繰り返さないことを祈るばかりですね。
それよりも、現代でもコロナ禍で労働に変化が見られましたね。
リモートで出社しなくても仕事が出来るように...と。
これまで昭和から令和までの働き方もある意味、
未来の人からは「遺構」として感じられる日がくるのかしら(^_-)
「昔は大変だったよね~
月曜から金曜まで小さな箱にぎゅうぎゅうに
押し込められて(電車)職場に移動していたんだってよ。」
ってね・・・・。
- Decoさん からの返信 2022/08/06 08:38:23
- Re: おはようございます。
- チーママ散歩さん、おはようございます。
赤谷炭鉱、天候には恵まれずとも、雰囲気は十分感じられましたよ。大雨の中、ベストの動き方をされたと思います。それに、洞門の写真、ぬらりひょんがいたくお気に入りのようで、「やっぱりチーママ散歩は同族じゃった」とご満悦です。
人命の軽視は当時「犯罪者だから、貧しいから、自分たちとは違う文化や習慣があるから→自分たちとは違う→命の重さも違う」ということだったのだと思います。
人間の世界、様々な試行錯誤を重ねながらも良い方向に向かっていっていると信じたいです。あの時代があって、その反省があって今の時代がある。近代化遺産の意義はそれを忘れず、二度と繰り返さないため、という部分も大きいと思います。働き方にしても、これから随分変わってくると思います。その根っこにあるのは、人の痛みを自分のこととして感じることだったり、自分と違う立場や個性を認めることなのかな、と思います。
私も今は田舎暮らし(!)なのですっかり忘れていますが、東京にいたころの満員電車、忘れられません。数十年後は令和の遺物になっているかも。でも当時、足腰は鍛えられました(笑)
Deco
-
- マジェッドさん 2022/08/05 23:18:09
- 今回も勉強になりました
- Deco様
マジェッドです。
今回も大牟田の炭鉱シリーズ、たいへん勉強になりました。
実は、Decoさんの旅行記に触発されて、先週の日曜日(7月31日)に大牟田で炭鉱巡りをしたところです。
大牟田市役所、笹林公園(三池炭山創業碑)、宮浦坑も電動自転車で訪れました。
その後、早鐘眼鏡橋→宮原坑と向かう予定が、どこでどう間違えたか、通町のセブンイレブンまで行ってしまうという大失態をやってしまいました。
Decoさんのような旅行記は、到底無理ですが、私も近いうちに旅行記に仕立ててみたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
マジェッド
- Decoさん からの返信 2022/08/06 08:22:18
- Re: 今回も勉強になりました
- マジェッドさん、おはようございます。
過分なお褒めお言葉をいただきありがとうございます。
7月31日炭鉱巡り…暑い中大変でしたね。でも、電動自転車はベストの選択ですね。体力の消耗を避けて小回りがききますからね。
あまりメジャーとはいえない三池炭山創業碑も廻られたとは、下調べして行かれたことと思いますが…早鐘眼鏡橋と通町セブンイレブン、方向的には…体力消耗されたことと思います。ただ、セブンから宮原坑だと、大浦町のコンビナートを通られたかもしれませんが、それはまた貴重な経験だと思います。
私もほかの方が書かれた炭鉱の旅行記、楽しませていただき、参考にさせていただいています。人それぞれ、ルートも視点も感性も違う。だからこそ面白いと感じます。マジェッドさんの旅行記、楽しみにしています。何かお役に立てることがあったら、できるだけのことはしますので、なにかあったら気軽にご連絡くださいね。
Deco
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったグルメ・レストラン
大牟田(福岡) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?































































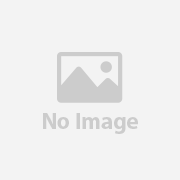













旅行記グループ 三池炭鉱 近代化産業革命遺産の光と影
15
42