
2022/04/11 - 2022/04/11
1353位(同エリア1947件中)
![]()
kojikojiさん
- kojikojiさんTOP
- 旅行記1795冊
- クチコミ1205件
- Q&A回答73件
- 3,536,350アクセス
- フォロワー172人
この旅行記スケジュールを元に
高野山と吉野山の旅が終わってすぐですが、桜を追いかけて今度もトラピックスの「高遠桜・松本城公園・上田城千本桜/春の信州 桜名所ベスト3と名湯・湯田中温泉3日間」というツアーに参加してきました。行ったことがあるのは松本城だけで信州の桜を観たことが無いのと、湯田中温泉には2連泊で2日目は終日フリーというのが選んだ理由でした。東京から志賀高原へは何度かスキーに行ったことがあり、小布施を通過するたびに一度行ってみたいと思っていました。その当時のリンゴ畑やスイスアルプスを思わせるような風景も魅力でしたが、後になって葛飾北斎が高井鴻山の家に長逗留していて肉筆の作品も残されていると知ったということもあります。今回は旅行会社のツアーではありますが、添乗員のいない交通とホテルだけが確保されたフリーツアーのスタイルで、出発日の1週間ほど前にJRの切符と最終案内書が郵送されてきました。月曜日の午前9時出発の「あずさ9号」と分かりましたが、荷物を持って新宿駅に行く方法を考えてしまいました。大江戸線か副都心線か山手線か…、どれも通勤ラッシュの時間にあたってしまいます。最近は妻の足が痛いこともあって荷物は2人分まとめて持っているので思案してしまいます。結果はタクシーで行くことになりましたが、月曜日の朝は混んでいるようで、1社には断られてしまい、タクシー配車センターで手配がつきました。当日はスムーズに自宅から新宿駅西口まで着きましたが、途中の新大久保までは母の入院や手術で何度も通った道だったので少し悲しい気分になりました。新宿駅の自由通路もすごい混雑で、電車を使わなくて良かったと思いました。ここで初めて知りましたが、「あずさ」の乗車券と特急券は自動改札に使えませんでした。10番線ホームに上がってしまうと気分はようやく旅行モードになり、売店で朝ご飯のお弁当を買って扉が開くのを待ちます。最後尾の4号車が同じツアーの方たちで、茅野駅でほぼ全員が下車しました。駅前のロータリーに向かうとバスが待っていて、ここでバス2台で総勢80人近いツアーなのだと知ります。添乗員がいないので点呼などはバスのドライバーさんが行い、松本に向けて出発します。
- 旅行の満足度
- 3.5
- 観光
- 4.0
- グルメ
- 1.0
- ショッピング
- 4.5
- 交通
- 4.5
- 同行者
- カップル・夫婦(シニア)
- 一人あたり費用
- 3万円 - 5万円
- 交通手段
- 高速・路線バス 観光バス 新幹線 私鉄 徒歩
- 旅行の手配内容
- ツアー(添乗員同行なし)
- 利用旅行会社
- 阪急交通社
-
吉野の桜を楽しんだ翌週はトラピックスの「高遠桜・松本城公園・上田城千本桜/春の信州 桜名所ベスト3と名湯・湯田中温泉3日間」というツアーに参加してきました。ツアーといっても添乗員のいない移動費とホテル代というフリーツアーです。出発の1週間ほど前に最終予定表と往復の列車のチケットが送られてきました。
-
当日は月曜日の午前9時の「あずさ9号」なので通勤ラッシュに荷物を持っての移動になってしまいます。ルートとしては大江戸線か副都心線、または山手線ですが、大きな荷物を持ってでは迷惑になるので前日にタクシーを予約しました。
新宿駅 駅
-
午前8時過ぎに新宿駅に到着しましたが、自動改札に切符を入れたら有人改札へ行くようにアナウンスされます。今まで知りませんでしたが、大きな乗車兼と特急券は自動改札に対応していないのですね。
-
妻は朝ご飯用にお弁当を物色しています。「あずさ」と「かいじ」のホームに上がるとようやく旅に出る気分になってきます。
-
10番線に列車は入線していますが、ドアが開くのは出発の15分前とアナウンスがありました。
-
高校生の頃に狩人の「あずさ2号」が流行ったので懐かしい気分になります。
-
2人分の荷物を1つの大型のキャリーバックに入れるので荷物置き場について事前に調べておきました。2019年3月のダイヤ改正以降はこの特急用新型車両「E353系」に置き換わり、荷物置き場が設置され、シートピッチも広がったと分かりました。
-
旅行会社から事前の連絡も無かったので、今回のツアーの参加人数が何人か分かりませんでしたが、いつもトラピックスのツアーで見掛けるような年齢の方ばかりが4号車を埋め尽くしていたのでバスは2台だろうなと想像しました。
-
家から持ってきた檸檬堂と氷と助六寿司の朝ご飯です。
-
久し振りに食べる大船軒の助六寿司は美味しかったです。
-
でも大船軒と言えばサンドウヰッチですね。明治32年の1899年当時は、銀座や神戸などの一部の高級洋食店でしか供されていなかったサンドウヰッチを駅弁に取り入れています。サンドウヰッチが広く世間に知られるようになり、駅弁としての一大ブームとなり、当初は輸入品を使用したハムを自家製造に変え、鎌倉ハム富岡商会を設立しています。
-
新宿を出発した「あずさ」は立川と八王子に停車していきますが、この辺りの景色はあまり面白くありません。
-
東海道新幹線などに比べると山の中を走るので面白みのない路線ではあります。
-
通過する大月駅の近くの岩殿城跡が見えました。
-
車窓の左側に富士山が見えました。東海道線に比べると手前にある山々に隠れてしまっています。
-
4号車は満席だったので進行方向右側の席から望遠レンズで撮影しましたが、何とかブレずに写っていました。
-
八ヶ岳の山々が見えてくると茅野駅も近いです。山頂の辺りにはまだ雪が残っています。
-
昭和のビーナスを中央に「縄文のビーナス」と「仮面のビーナス」の記念写真です。うまい具合に帽子が似ています。
茅野駅 駅
-
「縄文のビーナス」は昭和61年の1986年に工業団地の造成で発見された棚畑遺跡で発掘された今から約4000年から5000年前といわれる縄文時代中期土偶です。諸星大二郎の「暗黒神話」は茅野市尖石博物館から始まる物語ですが、40年以上前から行ってみたいと思いながらその願いは叶っていません。この土偶が発掘される前の1976年に少年ジャンプに掲載された作品です。
-
「仮面のビーナス」は星野之宣の「宗像教授シリーズ」の「宗像教授異考録」の「黄泉醜女(よもつしこめ)」の題材になっていることを思い出します。この仮面は人為的に醜女を作るためのものであり、仮面を押し付ける事によって作られた醜女の凄まじい醜さは悪霊や怨念を寄せ付けない効果を持ち、縄文人にとっては最強の守護神であり、死にゆく人びとを邪悪な霊から守り、安らかに旅立たせる役割を担ったのではないかとされます。
-
茅野駅前のロータリーにはバスが3台停車していましたが、そのうちの2台が同じトラピックス社のツアーバスでした。運転手さんに確認して2号車だと分かりました。
-
2台のバスはほぼ満席でしたので総勢80人に近い参加者だと分かりました。人数確認をしただけでバスはすぐに出発します。
-
茅野駅を出ると満開の桜と雪を頂いた山々が見えてきます。なんとなく美しい景色を見ることが出来る予感がありました。
-
諏訪インター―チェンジから高速に入ると諏訪湖が見えてきました。
-
諏訪大社にも参拝したことが無いのでいつか茅野と一緒に旅してみたいと思います。諏訪も諸星大二郎の「暗黒神話」や「孔子暗黒伝」の重要な場面に出てきます。
-
諏訪湖を過ぎると塩尻辺りから北アルプスの山々が見えてきます。大滝山から鍋冠山、蝶槍から常念岳の辺りのようです。
-
この辺りから北側に続く山々を登ったのは小学生の3年生から5年生にかけてなのでもう50年ほど前のことになります。
-
南岳の大キレットを越える縦走は小学生の5年生の夏休みでした。「キレット」とは漢字で「切戸」と書き、山と山をつなぐ尾根が深く切り落ちている場所のことで、長野県の方言からきた言葉と言われています。暴風雨の槍沢を下って、上高地まで濁流の梓川沿いに歩くなど小学生としては命がけのような旅の数々でした。
-
バスは「松本城大手門駐車場」に停車して、ここで2時間の自由時間になり、お昼もここで食べることになります。
-
松本城までは歩いて10分ほどの距離です。
-
トリップアドバイザーで目をつけていた「川船」という店に入ることにしました。時間が無いので少し焦っていて、妻が「他にもいい蕎麦屋さんあるよ。」という声も耳に入ってきません。妻の鼻は利くのでちゃんと従えばよかったと後悔しています。今まで数々の旅行記で悪かった店は紹介しないだけでしたが、ここは飽きれるほどひどかったのでご紹介します。
従業員もひどいが、料理もひどかった。美味しいのは冷えた瓶ビールだけ。 by kojikojiさん川船 グルメ・レストラン
-
我々の前に1組のお客さんがいましたが、通された席が気に入らなかったようで出て行かれました。その席に案内されたので一瞬躊躇しましたが、時間も無いのでそのまま座りました。おしぼりも前の方のものでしたが手を付けていないので。まずはビールを注文しましたが、冷えていて美味しかったです。「古城セット」という長野の料理らしい蕎麦のセットを注文しました。
-
最初に「手造り蕎麦の実入りそば豆腐」は蕎麦の香りなど全くしない普通の木綿豆腐のようでした。ここで「あれれ。」とおもい、次に出てきた「大ますの握り」には絶句。写真を撮るので米粒を取り除きましたが、お皿にもますの上にも米粒だらけです。これは人に出す料理じゃないなと思います。さらに酢飯が炊きたての熱々でますの切り身が煮えてしまって生臭く感じます。
-
妻が従業員のおばさんに2回席を変えられないか尋ねましたが、聞こえないふりをされ、3回目は「聞いてきます「」と言いながら厨房にも行かずに戻ってきて「ダメです。」お昼のピークを過ぎた午後1時過ぎなのでテーブルの座敷も空いていますし、後から来た2人組のお客はそちらに通されています。
-
「天然きのこおろし」に蕎麦をつけて食べるのですが、普通のスーパーで売っているようなきのこです。そばつゆも出汁の香りもしないまずさでしたが、これも美味しいわけがありません。
-
そして蕎麦が不味い。1口そのままで食べてみましたが、蕎麦よりも小麦粉の味がします。20年ほど自分でも蕎麦を打っていて、友人の勤めていた製粉会社からその年の一番良い蕎麦粉を分けてもらっています。信州にまで来てこんな不味いそばを食べなければならないのかと悲しい気持ちになりました。
-
我々が出るのと入れ違いに同じツアーの人たちが何人か店に入られました。後から入ろうとした方に「美味しかったですか?」と尋ねられたので「それ以前の問題です。やめた方がいいと思います。」とだけお伝えしました。後になって「あの時はありがとうございました。おかげで美味しいお店に出会えて楽しかったです。」といわれて嫌な思いをされずに済んでよかったなと気持ちが少し楽になりました。
-
さて済んでしまった嫌なことは忘れて松本城の見学に向かいます。妻と2人で最初に旅をしたのは松本から木曽の奈良井宿だったことを思い出しました。
中央公園 公園・植物園
-
今回のトラピックスのツアーは信州の桜の名所を3か所巡るのですが、松本城公園にはソメイヨシノ54本とヒガンサクラ25本、シダレサクラ2本の合計81本の桜しかないようです。
-
周辺のお堀には約320本の桜が咲いているようですが、2時間の自由時間では周囲まで歩いている時間はありません。
-
タイミング的には今回の松本城と上田城跡と高遠はぴったりで、どこも満開の桜で桜吹雪も美しかったです。地元の友人へのLINE連絡は妻にお願いしています。
-
松本城公園からは北アルプスの山々が美しく望めました。時期的に残雪の残るタイミングなのも良かったと思います。雪を頂いている方が美しく見えると思います。
-
常念岳から横通岳、東天井岳が見えます。これは天守に登ればさらに美しく見えるのではないかと思います。もう頭の中は桜から北アルプスの山々に変わってしまいました。
-
「黒門」から中に入るには有料ですが、天守に登るにはここにはいるしかありません。妻は最初から天守には上がらないと言っていますが、置いていくわけにはいきません。
-
公園内も空いていましたが、「黒門」の中も空いています。満開のシダレザクラと真っ黒な松本城が美しいです。
国宝松本城 名所・史跡
-
半上下(はんがみしも)を着たスタッフの方が写真を撮ってくださいました。この日の朝は7℃くらいしかなかったそうですが、昼過ぎには20℃を越えており、暑くて大変だと仰っていました。トイレに行くのも大変だそうで、熱中症にならないようにと言葉を添えてお礼を伝えます。
-
妻はこの辺りの休憩所で待っているというので1人で城内に向かいます。入り口には待ち時間10分とか書いてありましたが、他に人の姿もありません。
-
「大天守1階」
天守一階に武者走りとそれより約45センチ高い母屋部分があります。母屋部分が高くなっているのは、土台を二重に入れたためです。多くの柱に小穴が残っているのは壁があった痕跡のようです。この1間ごとの柱で天守の重みを支えているのだと感じます。 -
「鯱瓦(しゃちがわら)」
この鯱は大天守につけられていたものです。鯱は火災の際に水を吐くという想像上の魚で、口が空いているのが雄で閉じているのが雌です。松本城の鯱は南側が雄で北側が雌、雌の方が若干小さく作られています。現在据えられているものは乾小天守の鯱を模倣して製造されたものです。 -
「蕪懸魚(かぶらげぎょ)」
懸魚は本来中国では火災除けに魚の形をしていますが、日本では蕪の形を用いてきました。天守を外から見た時についている三角の破風と呼ばれる部分についています。ここに展示されているものは、昭和の修理で取り替えられたものです。 -
通常の寺院建築などと侠客の建築には違いがあるので、細かい違いはこうやって現地に足を運ばないと分からないことも多いです。
-
「大天守2階」
1階と同じ東西7間で南北に6間で、1階と同じように8室に部屋割りされていたようです。 -
大天守2階には火縄銃を主とした「松本城鉄砲蔵」の展示があります。ここには松本市出身の赤羽通重/か代子夫妻が寄贈した141挺の火縄銃と兵装品のうち、一部が展示されています。
-
「武者窓/竪格子窓(たてごうしまど)」
3連と5連の竪格子窓が見られます。格子に使われている部材は13×12センチで、ここからも火縄銃を撃ったと考えられているそうです。 -
「船載砲(せんさいほう)」
中世の末期にオランダのガレー船に船載された青銅製の船載砲です。先込めで火縄着火で鉛弾は径33ミリ。1発100グラムで、有効射程は300メートルから500メートルで、船上を引き回したり装弾の便宜を図るために車輪がついています。 -
「竪格子窓」からは掘割りに並ぶ桜の木がきれいに見えます。
-
昨年行った犬山城よりも小さな階段が設けられています。これは防御上の仕組みなのでしょうか。ここから上に登る階段は係員がいて、登りと下りの交通整理をされています。
-
窓からは「埋橋(うづみばし)」が見えます。現在は老築化のために渡れなくなっているようです。子供の頃に来た昭和40年には渡れた記憶があります。
-
やはり天守に上がると北アルプスの山並みがきれいに見えました。今回も3日間天気は最高でした。
-
大滝山から常念岳、横通岳辺りが見えるようです。
-
常念岳と横通岳は北アルプスらしい姿です。左側の常念岳の左側には槍ヶ岳も見えるようですが、この日は確認できませんでした。
-
小天守の「鯱瓦」の向こうに桜が見事です。
-
「二十六夜神」
松本城の二十六夜神は元和3年の1617年に松本に入封した戸田氏が祀ったとされています。月齢26日の月を拝む信仰で、戸田氏は毎月3石3斗3升3合3勺(約500キログラム)の米を炊いて供えたといわれています。関東地方に盛んだった月待信仰が持ちこまれたものと解されています。国宝松本城 名所・史跡
-
「作戦会議室」
この階には東西に千鳥破風と南北に唐破風が取り付けられ、室内には破風の間があり、武者窓から全方向の様子を見ることができます。戦いのときには重臣たちが作戦会議を行う場所として考えられています。 -
4階の床と天井の間は4メートル弱あり、柱と柱1つ分の間に階段をかけるので松本城では最も急な61度の階段です。大天守5階から6階への階段は、柱と柱2つ分の間に途中に踊り場を設けながら階段を架けてあります。床と天井の間は4メートル強あります。
-
本丸庭園の中に瓦を使って仕切りをしてある部分が本丸御殿の跡です。藩の正政庁で城主の居館でしたが、享保12年の1727年の閏正月朔日火事により焼失しました。この時の城主は戸田光慈で、鳥羽から入封してまもなくのことでした。その後御殿は再建されることなく、城主の政務を司る場所は二の丸御殿に移りました。
-
「御座所」
城主が天守に入ったときはここに座を構えたと考えられています。ただし客人の接待場所ではありません。戦時に城主がここに籠る場合は天守も戦闘の最終局面を迎えることになりました。3間×3間の広さで、小壁をおろし、内法長押を廻しています。 -
駆け足の見学になってしまったのは。妻を待たせているので仕方ありません。この半年で犬山城と姫路城と松本城を見ることが出来ました。これもコロナ禍で海外に行けないお陰かもしれません。
-
江戸時代以前に建設された天守が現在も保存された姿で残っている天守閣の12城の「現存天守」うち行ったことがあるのはまだ5つしかありません。
-
興味深い展示もありますが、妻は先に戻るとLINEで連絡が入りました。時間も残り少ないので先を急ぐことにします。
-
「華頭窓(かとうまど)」
禅宗寺院の建築に見られる形式で、中国から日本へは鎌倉時代に伝わります。その後城郭建築にも広がり、松本城では乾小天守4階に2か所、辰巳附櫓2階に2か所設けられています。 -
内堀の広さに驚かされます。水の上に浮かんだように見えるのはこのせいかもしれません。
-
「天守の壁と下見板」
松本城天守の壁の下部は「黒漆塗の下見板」で上部は「白漆喰」仕上げです。下見板の役割は天守の屋根で防ぎ切れない雨水をはじき天守の壁を守ることです。当時は壁全体を白漆喰で塗ると雨によって崩れるリスクが高いので、下見板が用いられました。下見板張りの天守の壁は50年の耐久性があったといいます。 -
「月見櫓」
徳川家光は寛永11年の1634年に上洛し、その帰り道に善光寺参詣を願い、宿城として松本城を宛てることになりました。中山道木曽路に落石があり、来松しなかったといいます。 -
戦いのない江戸時代初期に築造されたため、戦いに備えて造られた天守とは大きな違いがあります。「月見櫓」の北側と東側と南側の3方向が開口部になっています。月見をするときはこの舞良戸を外し、畳敷きの部屋で東から昇る月を観たのでしょう。
-
「刎ね勾欄(はねこうらん)」
月見櫓の三方を朱色の漆が塗られた刎ね勾欄を施した回縁が巡り、見るからに泰平な世の建造物であることを感じさせます。 -
駆け足で大天守の見学を終えました。
-
「石落」
石落は石垣を登る敵兵に石を落としたり、熱湯等をかけたりして天守を守る装置でした。戦いの主要武器が火縄銃となった戦国末期にはここから這い上る敵兵に火縄銃を撃ったと考えられています。 -
松本城には渡櫓・乾小天守・大天守各1階に合計11か所の石落が備えられています。石垣の両隅と中間にあり、内ぶたを開けると内部から約57度の傾斜をもつ石垣をみることができます。
-
次に来るのはいつになるのか分からないので最後に見納めしておきます。
-
初めて松本城に来たのは昭和40年の6月初旬のことでした。この後に上高地を旅したことはよく覚えています。母が弟を背負った後ろを明神池に向かって橋を渡った早朝の光景は脳裏を離れることはありません。
-
満開の桜は散り始めるギリギリの美しさで、風が吹くと散り始める桜の花びらが黒い城に映えました。
-
2時間の松本の自由時間は終わりました。急いでバスに戻ります。
-
松本を出るとバスは一般道を上田城跡に向かって出発します。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
旅行記グループ
2022松本城・上田城跡・高遠城跡の桜と湯田中温泉と小布施の旅
-

トラピックス 高遠・松本城公園・上田城千本桜 春の信州桜の名所と名湯湯田中温泉3日間(1)20年振りの松本城...
2022/04/11~
松本
-

トラピックス 高遠・松本城公園・上田城千本桜 春の信州桜の名所と名湯湯田中温泉3日間(2)上田城跡の満開の千...
2022/04/11~
上田
-

トラピックス 高遠・松本城公園・上田城千本桜 春の信州桜の名所と名湯湯田中温泉3日間(3)湯田中温泉から長野...
2022/04/12~
湯田中渋温泉郷・志賀高原
-
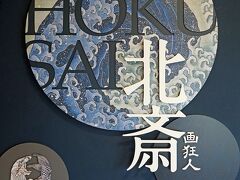
トラピックス 高遠・松本城公園・上田城千本桜 春の信州桜の名所と名湯湯田中温泉3日間(4)美しい小布施で葛飾...
2022/04/12~
湯田中渋温泉郷・志賀高原
-

トラピックス 高遠・松本城公園・上田城千本桜 春の信州桜の名所と名湯湯田中温泉3日間(5)枡一酒造でほろ酔い...
2022/04/12~
湯田中渋温泉郷・志賀高原
-

トラピックス 高遠・松本城公園・上田城千本桜 春の信州桜の名所と名湯湯田中温泉3日間(6)北アルプスの絶景を...
2022/04/13~
辰野・箕輪・高遠
旅行記グループをもっと見る
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったグルメ・レストラン
松本(長野) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?















































































































旅行記グループ 2022松本城・上田城跡・高遠城跡の桜と湯田中温泉と小布施の旅
0
84