
2019/02/10 - 2019/02/10
32位(同エリア650件中)
![]()
たびたびさん
- たびたびさんTOP
- 旅行記841冊
- クチコミ41172件
- Q&A回答431件
- 6,777,159アクセス
- フォロワー687人
この旅行記のスケジュール
2019/02/10
もっと見る
閉じる
この旅行記スケジュールを元に
近江八幡市やその周辺は近江商人の故郷。ただ、これまではその故郷の範囲は近江八幡の市街くらいなんだろうなあというぼんやりした認識だったんですが、今回、近江鉄道の沿線を歩いてみたことで、その範囲は、東近江市なども含めたかなりの地域に及ぶことがわかりました。
ただ、それは反面、近江商人というくくり方があまりにも大ざっぱすぎるということ。近江商人でも、近江八幡は八幡商人。近江鉄道沿線でも、日野の日野商人とそれ以外の湖東商人に分けられる。さらに近江商人の前身、中世に遡ると、若狭国方面へ行商を行った五箇商人。伊勢国の桑名へ行商した四本商人。その両方に属した小幡商人といった分類もあるんですね。天秤棒だけから始まって、財を成す才覚は認めますが、街道ごとに商売をする利権があった中世にあって、楽市楽座のような、現代でいうところの規制改革があって、初めてその才覚が生かされるようになるといったこともまた歴史の事実といったところでしょうか。
ちなみに、この日の「商家に伝わるひな人形めぐり」は五個荘金堂町。こちらは、五箇商人の故郷であり、後の湖東商人へとつながっていく地域。街道の結束点にある地の利を生かした歴史が背景にあるだけに、このコンパクトな市街にもその名残を見て取ることができるように思います。
市街には、外村繁邸、外村宇兵衛邸、中江準五郎邸の主要な屋敷。金堂まちなみ保存交流館も三中井百貨店の中江富十郎の邸宅。それぞれが今でも現役に近い状態。当時の優雅な暮らしぶりをそのまま体感できて本格的に楽しめます。
そこで行われるひな祭りですから、中江準五郎邸の雛匠東之湖作の「平成の創作雛」や藤井彦四郎邸の「絆雛」のシリーズなど。競い合うように飾られた自慢のひな人形は当然美しくて立派ですが、邸宅や庭園と併せてみることで楽しさは倍増します。
また、地元のボランティアの人もたくさんいてお世話してくれるし、地元の誇りや愛情も感じながら、気持ちよく拝見することができました。
-
今日のメインは、五箇荘の「商家に伝わるひな人形めぐり」なんですが、せっかくなので、近江鉄道の沿線も回ってみたい。尼子駅、豊郷駅経由で五箇荘駅に向かいます。
-
まずは、尼子駅で途中下車して、周辺散策。
-
尼子って、中国地方で覇を唱えた尼子氏のルーツなんですよね。
市街には尼子氏のルーツといったゆかりのスポットがあるので、道案内があれこれ。親切だなあと思いましたが、実はこれ。全然役に立たない。道案内は途中で途切れていて、目指してもまったくたどり着けない。近くのお寺で道を尋ねても、もしかして藤堂高虎の関係と区別がついていないようで、トンチンカンでした。 -
仕方がないので、在士高虎公園の方に急ぎます。
これはその手前の在士八幡神社。 -
江戸時代になって、藤党影盛が高虎の出身地であるここに石清水八幡宮を勧請して建立したのが始まり。
藤の花がきれいで、有名なようです。 -
在士高虎公園は、近江鉄道の尼子駅からだとそれなりにありましたが、尼子の市街を抜けた先の周囲の見晴らしがいい場所。公園の中央に騎馬姿の藤堂高虎像がすっくと立っていて、かなり目立っています。ここは高虎の出身地です。
ちなみに、高虎ははじめ浅井長政に足軽として仕え、姉川の戦いにも参戦。浅井家が滅びると豊臣政権のもとで大名へ。その後、家康に接近して、関ヶ原の戦いの後は宇和島8万石に今治12万石が加わり、20万石の大大名へ。その後、伊勢津藩22万石の初代藩主となりました。外様ではあったものの家康からは特別の信頼を得ていたように思われます。 -
そこから、続いては甲良豊後守宗廣記念館。尼子駅からだとここまでなんとかギリギリ徒歩圏内という感じです。田園地帯にポツンポツンとある集落の一つに建つ記念館は、藁ぶき屋根の建物を瓦ぶきに改装したしっかりした建物。
ところで、甲良豊後守宗廣は、江戸時代初期の幕府作事方(さくじがた)大棟梁職。宮大工の棟梁ですね。日光東照宮の仕事を最後に引退。大工道具の展示もありました。 -
甲良豊後守宗廣記念館からまた長駆して。
唯念寺は、近江鉄道尼子駅と豊郷駅のちょうど中間あたり。
中山道沿いに建つ浄土真宗大谷派の寺です。 -
始まりは、天平3年(731年)行基がこの地に建立した四十九院の一つ。周囲を豪壮な塀が囲み厳めしい真宗の寺の雰囲気がムンムン。豊郷町指定文化財の絹本着色不動明王二童子像ほかの案内板もありました。
-
その隣りには、先人を偲ぶ館。ひっそりと建つ資料館です。
豊郷町を出身とする偉大な近江商人8人を紹介する内容。木綿王といわれた薩摩治兵衛ほか。ただ、一番有名なのは伊藤忠、丸紅の元となった伊藤忠兵衛かなと思います。 -
その向かいに建つライトブルーの洋館は、旧豊郷尋常高等小学校本館。しかし、案内も何もないので、近くの人に聞いて、やっとこれが本館であることが分かりました。
至熟小学校講堂として明治期に建てられたもののようですが、復元建物なのかまだ真新しいような感じも受ける。正面中央のバルコニーがデザインのポイントでしょう。 -
ほか、豊郷小学校旧校舎群というのがこの辺りでは一つの観光スポット。というのも、これは地元出身の近江商人に因む建物なんですね。
昭和12年に丸紅の専務であった古川鉄治郎氏によって寄贈され、建築家ヴォーリズ氏の設計で建てられたもの。この建物がそれになるのかはちょっとよく分かりませんが、いずれにしても、地元への感謝の気持ちを忘れない近江商人の気概を象徴するものだと思います。 -
豊郷駅を過ぎて少し行ったところに大きな空き地があって、
-
伊藤長兵衛屋敷跡。伊藤忠兵衛じゃなくて、伊藤長兵衛??
六代目伊藤長兵衛の弟が初代伊藤忠兵衛という関係。伊藤忠兵衛とは同族ですね。かつてのお屋敷が空き地になっていて、今は石碑だけが残っています。 -
少し歩くと、今度は伊藤忠兵衛記念館。総合商社丸紅、伊藤忠商事の創始者、初代伊藤忠兵衛の本家を開放した資料館です。
-
旧道に面したお屋敷は、周囲を高い塀に囲まれていますが、大豪邸というほどの威圧感はなし。
-
むしろ、地方によくある中堅クラスの豪商といった印象です。
-
実質的な伊藤忠の創業者二代目を後継者指名した初代の妻、八重夫人の話や
-
繊維で知られる伊藤忠ですが、
-
ルーツは地元の特産品、麻布を扱う商売からだったとか。
-
リアルにいち地方商人の頃が想像されて、
-
面白く拝見しました。
-
さらに進んで。
この豊会館は、江戸時代後期、又十という商号で呉服屋から始まり、北海道にも進出、廻船業を営んだ藤野喜兵衛喜昌の旧宅。
書院や文庫倉庫に日本庭園は当時の面影をそのまま残すのが自慢です。 -
玄関を上がって、客間に続く途中には狩野永海筆による彦根屏風や井伊直弼から拝領した武具や
-
それらしい調度品の数々。
-
ここは、井伊家の飛び地領地だったそうで、井伊家のバックボーンがあったためにスケールの大きな商売が可能だったというような話も伺いました。
-
近江の地にあっても、
-
全国を見据えての展開力。
-
イチオシ
近江商人の並外れたエネルギーが
-
今でも鮮やかに実感できるような邸宅です。
-
奥には資料展示室。
-
個々の展示品は、この屋敷を買い取った地元の篤志家のコレクションなので、藤野喜兵衛喜昌とは関係なし。
ただ、地元の焼き物とかはなかなか。興味をもって拝見させてもらいました。 -
お庭の方も拝見。
-
こちらは当時の面影を残すものです。
-
続いての千樹寺は、唯念寺と同じく行基が創建した四十九院の一つ。
-
本堂は屋根が重々しくて、ちょっと頭でっかちのバランスが印象的です。
本能寺の変の後、この寺の落慶法要で、時の住職がお経に音頭の節をつけて唱い、踊ったということがあって、それが現在の江州音頭の始まりとなったとか。境内に発祥の地碑がありました。 -
豊郷駅から五箇荘駅に到着。
ここから、金堂地区ほか、ひな祭りの会場に向かいます。 -
冨来郁は、五箇荘駅から金堂町へ向かう途中の和菓子屋さん。こんなところにといった市街のはずれです。
-
とはいえ、店内は悠々とした広さがあるし、新しい建物ですが、老舗感はプンプン。
-
冨来小判という薄皮まんじゅうをいただきました。口に入れた直後はぼんやりした感じでしたが、時間が経つにつれて存在感が現れてくる。じわりと責められたような気がするおまんじゅうです。
-
ひな祭りの最初は、藤井彦四郎邸。こちらも、五個荘の近江商人屋敷を代表する邸宅の一つ。
-
敷地面積8,155㎡、建物面積710㎡の広大なお屋敷は、
-
これが玄関。
-
さっそく雛人形が出迎えてくれました。
-
小さな道具類もいいですよね。
-
奥に進むと、この邸宅の真骨頂が現れましたね。お庭の方に出てみましょうか。
-
藤井糸店を創業し財を成した彦四郎自身が構想し琵琶湖を模した
-
池泉回遊式の庭園を眺めながらの、
-
まるで迎賓館のような、明るくて優雅な佇まいです。
いいじゃないですかあ。 -
落ち着いたところで、今度はひな飾りの方です。
各部屋いっぱいにひな人形が並んでいましたが、特に目を引いたのは、この雛匠東之湖の作品。 -
現代的できらびやかな衣装は個性溢れるもの。
-
色調を統一したシリーズを感じさせる雛人形。
-
雛人形の白いお顔は、胡粉が一番だと思いますが、これはちょっと違いますね。
鋭さがなくなって、穏やかな表情。私は、胡粉に慣れているので、少し物足りないような感じもしなくはないんですが、着物とのバランスを考えるとこっちの方がいいのかもしれません。 -
萌黄色のシリーズは、
-
十二単のイメージでしょう。
-
緑になってくるとやっぱり現代的かな。
-
こっちはキラキラ。
ファンタジーの世界ですが、 -
イチオシ
なんとか雛人形の範疇には入っているでしょう。
いずれにしても、正統派の邸宅とその独特の感性のコラボもとてもいいと思いました。 -
隣の部屋からは正統派のひな飾り。
-
三人官女も、
-
イチオシ
本当に美人さんですよ~
-
古い雛人形も混じってきて、
-
ちょっと落ち着いた感じ。
-
イチオシ
ゆっくり
-
やんわり。拝見いたしました。
-
奥の応接室。というか応接場といった方がいいのかな。ちょっとした会合もできそうなスペースです。
-
日本間の一角は資料室。
-
近江商人のなんたるかを
-
生活様式の中から
-
伝えようとしています。
-
最後に敷地内の近江商人像を確認して、こちらは終了です。
-
続いては、近江商人博物館。五個荘にある巨大箱モノの一つです。
-
近江商人とは?といった総合的なテーマで解説する総合展示となっています。
ただ、その分、解説は最大公約数的なものになっているきらいがあって、敢えて言えばここじゃないと得られない情報という感じがしない。ちょっとその辺りが惜しいかなと思います。 -
さて、そこから先が金堂町地区。これは入り口です。
-
金堂馬場の五輪塔は、五個荘金堂町の入口。もう鯉通りも近い辺りです。
古びた説明板があって、それによると。。
総高197㎝の塔には、正安2年と刻まれて、これは1300年。それがほぼ完全な形で残っているのがすごいところだそう。在銘塔として、県下最古の五輪塔です。 -
中心部の寺前・鯉通りです。
-
市街を流れる小川ですが、その中にたくさんの錦鯉が優雅に泳いでいる。そして、その小川沿いには、弘誓寺を始めとする古刹が軒を並べていて、独特の景色。近江商人の屋敷が集まる金堂町ですが、ここがあることでそれだけではないよと街の厚みが出ているような気がします。
-
弘誓寺の境内に入って。こちらは、五個荘金堂町を代表する古刹。浄土真宗大谷派のお寺です。
-
開基は、なんとあの那須与一の嫡子。現在の建物は宝暦5年(1755年)に建てられたもので、国の重要文化財。特に庫裏の方は大屋根の上には煙を逃がす煙出。屋根が何層にも重なって、見応えのある建物となっています。
ちなみに、源平合戦のヒーローとなった那須与一ですが、実はむごい合戦でショックを受け、その後は精神的に病んでしまう。その子が仏門に入っていたというのは、確かにつながります。 -
金堂町は、どこからまわりましょうかね。
まずは、金堂まちなみ保存交流館かな。 -
こちらは、かつての三中井百貨店、中江4兄弟の三男、富十郎の邸宅を活用したもの。門を入るときちんとして、かつ、ゆったりと涼しげな佇まい。
-
玄関から奥座敷までがシンプルにつながっていて、これなら過ごしやすい。
-
ちょっと寛ぐには十分です。
-
反して路地庭園の方は、石組みがかなり入っていて力強い。主人の意外な好みなのかなと思いました。
-
では、この辺で昼飯です。
めんめんたなかは、うどん屋さん。藁ぶき屋根の渋い古民家で、座敷に上がっていただきます。 -
うどんは少し細めの柔らかタイプ。サイドメニューもしっかりあって、この日はバラ寿しを組み合わせたひな祭りセットとかがお勧めでした。この日はお客さんが多くてお店はちょっとパニック状態でしたが、待ち時間に座敷でゆっくり寛げると思えば問題はないでしょう。
-
さて、ここからが金堂町の本番です。
五個荘金堂町には、立派な近江商人屋敷がいくつかあって、中江準五郎邸もその一つ。 -
邸宅は、戦前に朝鮮半島、中国大陸を中心に20数店の百貨店を経営した
-
三中井商店の一族、五男の本宅です。
-
ひな飾りの圧巻は、メイン展示の雛匠東之湖の創作人形。
-
イチオシ
琵琶湖八景をイメージしたという華やかな作品で、
-
個々の人形の美しさと全体の構成力が素晴らしい。
-
毎年、少しずつキャラクターが増えてきて、
-
こうした奥行きのある作品に成長したということ。
-
イチオシ
正面にあるこの人形は今年加わったもので、羽生結弦の安倍晴明を意識したポーズです。
-
それにしても、この優雅さ。この気品。
-
見るものを釘付けにすること間違いなしの素晴らしさです。
-
先に進むと
-
一番奥は
-
蔵の展示室。
-
こちらは、土人形ですか。
-
土人形もいいですよね。
-
土人形のルーツは伏見人形なんですが、
-
全国に広まって、それぞれ地元に根付いて、発展することになりました。
素朴なだけではなくて、テーマ、表現方法など。日本人の心に響くものがあるのだと思います。 -
こちらは、二階部分。
-
落ち着いた空間に
-
かわいらしいひな飾り。
-
イチオシ
しかし、その出来栄えはさすがという感じ。
-
細かい作業が素晴らしいです。
-
すごい、すごい。だけじゃなくて、
-
子供が楽しく遊べるお人形。そんな感じかなと思います。
-
中江準五郎邸から、
-
今度は、外村宇兵衛邸。ちなみに、外村宇兵衛は、六代目、外村与左衛門の末子。分家して独立し呉服類の販売で成功。東京、横浜、京都、福井などに支店を有し、全国の長者番付にも名を連ねたという豪商です。
-
玄関を入ると広々とした土間。
-
ひな祭りの飾りつけも鮮やかな着物の展示や
-
この豪壮な御殿雛はどうですかあ。
-
特別注文のものだと思いますが、
-
細部がとってもリアル。
-
ちょっと格が違うような印象ですよね。
-
イチオシ
うーん。これもすごい。
-
人形の上質さが
-
半端ではない。
-
しびれます。
-
イチオシ
もうひとつの御殿雛。
-
内部に飾られた人形たちの
-
ちょっとした所作がいい感じ。自分がその中に入っていけるような。鮮やかなイメージが膨らみますね。
ほか、蔵の展示は、生活用品でしたが、自身で描いた扇子の絵なども見事。商売だけではない、いろんなたしなみがあったことが窺われます。最後は、庭の散策。これも豪邸を包み込む悠々とした広さがありました。 -
続いては、外村繁邸。
-
こちらは、4代目外村宇兵衛の妹みわが婿養子吉太郎を迎えて分家したのが始まり。吉太郎は、東京日本橋と高田馬場に木綿呉服問屋を開き活躍しましたが、その三男として生まれたのが外村繁。文学の道に進み、作家として活動します。
-
玄関を入るとこちらも広い土間。
-
豪壮な本宅に周囲を囲む日本庭園なども、
-
他の近江商人屋敷と比べて遜色はありません。
-
ただ、広い邸宅に対して、
-
こちらのひな飾りは、少し少な目かな。
-
ただ、ちょっと疲れてきた分。
-
これくらいの方が
-
楽かなあ。
-
邸宅を見るのと雛人形を見るのと
そのバランスはこれくらいの方が普通かもしれません。 -
ただ、ここの見どころはやはり奥の外村繁文学館。
-
上質な遺品の数々を見ているとこれも近江商人の生活を彷彿とするもの。作品のテーマも近江商人のものが多かったようで、外村繁にしか書けなかった作品も多かったのではないかと想像しました。
-
イチオシ
二階のひな飾りも
-
最後に拝見して。
-
こちらも無事に終了です。
-
ここらで、休憩もかねて、いっぺきへ。こちらもうどん屋さん。一段髙くなった場所にあって、
-
この敷地も裏手の広いスペースを眺めるとかつてのお屋敷なんだと思います。
-
うどんは、少しコシのあるもっちりタイプ。優雅なテーブル席とかはおしゃれだし、しばらくゆっくりと寛ぎたくなるような雰囲気があると思います。
-
さて、これで主要な会場はすべて見たはずなんですが、ちょっと気になる八年庵も訪ねます。
五箇荘金堂エリアからは少し外れにあって。ここは、近江商人、塚本源三郎の旧本宅です。 -
この塚本は、肌着のワコールでも知られる総合繊維商社ツカモトコーポレーションの創業家にあたります。
-
今のオーナーは地元の工務店をやっていた人だそうですが、
-
この家が二束三文で売りに出されて壊されそうになったのを見るに見かねて購入。
-
熱い思いで保存をした奇特な方。
-
そのオーナーいわく、この塚本家こそが近江商人のルーツなのだとか。
展示室には焼き物や掛け軸などがそれなりにありますが、見るべきはこの建物(撮影は禁止)だし、オーナーのお話が面白い。五個荘の商人は、佐々木六角氏の時代から庇護を受けつつ、この地では信長より先に楽市楽座のほう芽が見られたこと。六角氏の家来であった蒲生氏郷は兵を使って商人の活動を守るという先見性があったこと。三井家の祖もなまず城と呼ばれた城をもつ六角氏の家来。同じ商売のセンスを持った蒲生氏郷とは懇意な同僚の関係だったこと。江戸時代は井伊家ではなく柳沢家の飛び地となり、柳沢家の口利きで銭谷五平や紀伊国屋文左衛門らとの関係もできたとか。まだまだ研究の途上だそうですが、興味深いお話でした。普段は開いていないことも多いようですが、少なくともひな祭りの期間中は開いていますので、皆さんも時間があれば是非どうぞ。 -
ここから、五個荘駅に帰りますが、その途の中松居家住宅洋館。五個荘駅にもまあまあ近い場所です。
通りに面して建つかつての郵便局舎で、古びた洋館。中には入れないので、外観を拝見するだけです。幾何学的な文様が多用されていて、ちょっと神経質な印象もなくはないです。 -
そのそばにある五個荘中央公園。見晴らしのいい悠々とした芝生の広場を中心に、なかなかのスケール感です。ただ、まあそれだけと言えば、それだけ。ここで家族でお弁当を広げたりする光景が目に浮かびました。
-
五個荘駅から近江八幡駅に到着。今夜の宿は近江八幡です。
その前に、晩飯はこちら、近江かね安。お肉屋さんがやっている食堂で、間違えてお肉屋さんの方に入ったら食堂はあっちだよと言われて入り直し。 -
で、うーん。このお店は何かと強烈。まずは、店内の匂い。市場の解体場みたいな生肉の匂いが充満していて、これで食事をするのはかなりの肉好きじゃないと無理かなあ。そして、ご主人とその妹の強烈な個性。肉についてのこだわりが強烈。お勧めの極上焼肉丼3500円にしたら、これから食べる肉の血統書を持ち出してきてアピール。肉の方は、たっぷりサシが入っていて、肉汁がジュワっとこれも強烈。一方で、格安丼にも使うご飯だけにご飯の質はイマイチ。料理はバランスなんですが、とにかく肉、肉、肉にこだわるので全体として落ち着かない。名物店であることは間違いありませんが、それなりの覚悟をもって訪ねるお店だと思います。
-
で、宿はこちら、ビジネスホテル西ノ庄。近江八幡駅の周辺で安宿がなかったので、ここにしてみたんですが、近江八幡の駅から田んぼの脇道をトボトボと歩いた先。暗い中だったし、なんかけっこう惨めな気持ちでした。そして、やっとたどり着いたホテルも古い。常連さんらしき人もいましたが、アクセスのこと等を考えるととても一般の観光客にはお勧めできないと思います。
さて、明日は最終日。これも、近江商人のふるさと、日野ひなまつり紀行を拝見します。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (2)
-
- ミランダさん 2020/09/08 06:40:28
- ほのかに懐かしかったです
- 昔々、事情があって五個荘町に2年間住んでいました。昔のことだし、特別に興味を持って住んでいたわけではなかったのですが、ちょっと見おぼえのある建物の写真があって懐かしかったです。たびたびさんのように、興味と知識が旺盛だったら、もっと充実した暮らしになったのになあと今になって思います。(ミランダ)
- たびたびさん からの返信 2020/09/25 08:57:01
- RE: ほのかに懐かしかったです
- この辺りの観光だと近江八幡で終わってしまうのがだいたいかなと思いますが、今回、五個荘町から日野まで回って、やっぱりこの辺りを見ないと近江商人のことは分からないなという思いがこみ上げてきました。六角氏の配下だった蒲生氏郷や藤堂高虎。商人のセンスを持っていた武将であり、三井家のルーツも近江だったというのはとても面白いことだと思いました。わかっていたようでもやもやしていたことが滋賀で解決することはいくつかあって、この時もそんな思いになりました。
たびたび
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったホテル
この旅行で行ったスポット
もっと見る
湖東三山・多賀・東近江(滋賀) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?






































































































































































































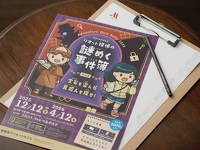





2
156