
2021/07/09 - 2021/07/12
63位(同エリア243件中)
![]()
しにあの旅人さん
- しにあの旅人さんTOP
- 旅行記251冊
- クチコミ254件
- Q&A回答18件
- 312,612アクセス
- フォロワー77人
恭仁京に遷都した聖武天皇、落ち着くかと思いきや、すぐにそわそわし始めました。「旅に出るぞ」
新しいみやこが完成していないのに、ちょっと離れた紫香楽にも宮を作ると言い出します。それだけじゃおさまらず、近くに甲賀寺を建立して、「大仏を作りたい!」
引用した参考書などは、「六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇1」に列挙しました。引用に際し、僭越ながら敬称を略させていただきます。
- 旅行の満足度
- 5.0
- 同行者
- カップル・夫婦(シニア)
- 交通手段
- 自家用車
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
恭仁京跡から紫香楽京跡までの県道307、タヌキ街道は聖武天皇が作らせたというのが前回のお話。
続日本紀天平14年(742年)2月5日、
★初めて恭仁京から東北へ行く道を造成し、近江国甲賀郡に通ずるようにした。★
地図で見るとおり、このコースはほとんど山の中で、古代も今も道路を通すコースに選択の余地がありません。難工事だったはずで、そう簡単にできるはずがない。かなり前から工事はしていたはず。
側近は、「怪しいな」と思ったでしょうね。
あたり!
8月11日、
★天皇は詔して『朕は近江国紫香楽宮に行幸しようと思う』とのべられた。そこで造営卿・正四位の智努王(ちぬの・おおきみ)、造営補・外従五位下の高岡連河内(たかおかの・むらじ・かわち)ら4人を、離宮を造る司に任じた。★
でたあ〜!
智努王は紫香楽京の造営卿、建設責任者でもあります。この道の専門家。外従五位下高岡連河内の「外」というのは、本物の貴族ではないということで、いわば技官、建築家でしょう。
22日には塩焼王などを行幸の実行責任者12人を任命。本格的です。聖武さん、気合いが入っています。 -
2020年11月16日、やって来ました紫香楽京跡。
-
といってもあるのはこれだけ。宮町公民館。
中に展示があるらしいけれど、2度とも休館中。「紫香楽京跡宮町地区」と「紫香楽京跡内裏野地区」、駐車場あり。 by しにあの旅人さん紫香楽宮跡 名所・史跡
-
小学校の運動場のような広場の一角です。
-
入口で、紫香楽らしくこの人が出迎え。なぜ網の中なんだろう。
-
タヌキ相わるいな、おまえ。
-
展示パネルがありました。これがよくできていて、インターネットにはなかった情報がいっぱいありました。以下の紫香楽宮のウンチクの出どころはここです。
一書に曰く、
山越えをして入って行きます。前方に高速道路が、空いっぱいにかかっております。不調和な感じと、ここも時代に取り残されなかった、よかった。と両方の気持ちがわいてきました。
その高速道路を右上に見ながら、さらに進むと、たんぼ。
田んぼの中に、公民館はありました。
稲の海の中の浮島のようにぽこんと、ここだけ地面の広場です。
他はみどり。稲です。
公民館は、殺風景でした。
ときにはここで、村人の集会があるのでしょう。そういう場所です。
その広場のはしっこに建物と物置?ガレージ?がありました。
中央を広く取ってあるのが、盆踊りにぴったりです。
村の運動会とかもやったのかな。
その物置の壁に、いろいろ説明があって、大変に興味深かったです。
私共のように、全国から人が訪ねてくるのでしょうね。
親切に、私みたいな素人にも分かるように説明してありました。
この公民館には、二回行ったのですが、二回とも誰もいなくて、田んぼにも誰もいなくて、こんなにいなくて大丈夫でしょうか。
ま、いない時間を選んで行っているのかもしれません。
普通の日のお昼ですから、まともな大人は働いていますね。
どこに働きに行っているんだろう?
あ、余計なことですね。
おばばは、ついつい。
By妻 -
肝心の紫香楽宮!
私たちのブログの常連さんなら驚かない。ただの田んぼであります。遺跡はこの地下に眠っています。心眼を研ぎ澄ませて田んぼを見ると、朱塗りの宮殿が沸き上がって・・・きません。田んぼは田んぼ。 -
公民館の西。
-
北東をみています。
-
東。
-
狭いですよ。南北1000m、東西1000mのいびつな円形です。
恭仁京よりさらに狭い。 -
このくらいの里山に囲まれた盆地です。
-
恭仁京は南は開いていましたが、ここは周囲全部山です。聖武天皇、引きこもる気ですね。
聖武天皇は元祖ヒッキーか! -
ドローンのスライドショーです。
狭いでしょ?
https://youtu.be/b8yLkHlhUBE -
南方向です。この先が盆地の出口。
-
盆地の南出口は400mくらいなもの。
恭仁京は狭いとはいえ、平城京の三分の一の面積はありました。しかし肝心の内裏は、西と北の里山まで数百mという端っこにわざわざもってきている。紫香楽京はみやこ自体が狭い盆地です。
聖武天皇という方は、わざわざ狭い所を好んで遷都しています。広所恐怖症というか、なにかに怯えていたような感じです。
現地に行ってきた実感。 -
一書に曰く、
この年になると、日々の過ぎ去ることが速すぎて、もう12月です。
昨年は、孫娘にクリスマスプレゼント何がいいかな?と、ママに聞きますと、「なぜか鬼滅とか言っていますよ。」ということでした。
何かと調べてみたら、え、えーっ、ヒロインが猿ぐつわしている!
鬼とはいえ、首が飛ぶ!血しぶきドバッ。
なんですか、これ。
大人気で、世を挙げて、登場人物のコスプレだそうで。
でもね、少女時代、赤毛のアン、あしながおじさんで育ったわたくしとしましては、「遊郭編」とか、のけぞりものです。
遊郭は、「たけくらべ」が、少女にはせいぜいかと。
で、今年、またもやママに聞きましたら、「すみっコぐらし」だと。
ご存知ですか?
by夫が、なにそれ?絵本?マンガ?
マンガ、絵本というほどのストーリーもなく、ただただすみっこが好きなマシュマロっぽい複数のなにかのイラストかな。
ひたすら隅っこが好きなのですね。エビフライのしっぽとかが。
そうか!聖武天皇が、ここ紫香楽宮建設を希望したのは、これだったのかも。
「鬼滅」のナントカ列車というのを見ましたが、わけのわからない得体の知れない不死身っぽい化け物との血みどろの戦い。
これって、聖武さんの住む世界だったのでは?
昨日の忠臣、今日の謀反人という生活ですからね。
その反動のすみっこ暮らし。
ホワーっと暮らしたかった。
なのに、世の中、そうそう思い通りにはいかないのだよ。
「すみっコぐらし」でも、正体不明のクレーンが、突如すみっこから、カタツムリのつもりのナメクジとかを運び出してしまいます。走って戻りますがね。
聖武天皇は、そうは行かなかったのだねー。
隅っこに戻れなかった。
かわいそ。隅っこにおいていてほしかったろうに。
ということで、ここは、聖武くんが、こころの安らぎを求めて、得られなかった土地だったのですよ。
そう思うと、ただの田んぼも、なにやらゆかしい。かな?
By妻 -
天平14年(742年)8月たぶん12日、前の日にいきなり紫香楽離宮造営卿に任命された智努王、おっとり刀でやってきました。補佐官の高岡連河内と並んで見た風景は、家と電信柱を消せばこれと同じ。茫然としたはず。
「どうしよう・・・」
恭仁宮とちがって、書紀にも続紀にも、紫香楽に離宮があったなどと書いてありません。つまりなにもないところにいきなり宮を造れというのです。
15日後には、天皇はもう来ちゃうのです。とりあえず離宮なるものを用意しなければ。
天皇の旅行のとき、仮の宿は普通「頓宮」あるいは「行宮」といいます。それがいきなり「離宮」となっている。智努王も高岡連河内も聖武天皇の癖は知っているので、離宮じゃすまないなとは思ったでしょう。
「やるっきゃない」結論はそれしかありません。
智努くん「できません、と言ったら、物理的に首が飛ぶかもね」
高岡くん「そだね〜」
突貫工事で離宮を用意したのでありましょう。
天平14年(742年)8月27日
★天皇は紫香楽宮に行幸された。(中略)その日のうちに紫香楽宮に到着した★
9月4日、
★車駕は恭仁京に還った。★
「車駕」で行ったとなっていますが、車駕は通常輿です。恭仁-紫香楽は36kmあります。
輿ではその日のうちの到着は無理じゃないかな。フツーに歩いたって、9時間。輿というのは要するにおみこしです。天皇ともなると10人以上の人間が担ぐ。時速4kmはでません。そもそもあんなものに9時間も座っていられない。
「車駕」というのは、移動する天皇の代名詞というケースもあります。乗り物は馬のこともあったでしょう。そうでなければ日付の間違いか。続日本紀の編集者菅野朝臣真道さんは、間違いなくこの道を自分で歩いていない。知っていればこんなことは書かない。
このころはまだ恭仁京の大極殿の移築も終わっていません。聖武さんはおとなしくできない人のようです。
10月には塩焼王を伊豆に配流しました。理由は書いてないのですが、現代語訳続日本紀の訳注によると、「紫香楽京の造営に反対したものであろうか」塩焼王は聖武天皇の娘、不破内親王を妻としているくらいで、側近のはず。紫香楽宮建設に反対されたのが、よほどアタマにきたようです。
12月29日から翌年1月2日までまた紫香楽に行幸。この行幸には橘諸兄が同行し、1日には先発して恭仁京に還っています。なにか、密談でもしたのか。
天平15年(743年)夏4月3日、
★天皇は紫香楽に行幸された★
16日には恭仁京に還っていますが、「行幸につき従った五位以上の28人と、六位以下の2,370人に地位に応じて禄を賜った」となっています。五位以上の貴族が100人前後のとき、28人も連れて行っている。前年暮れまでには大極殿の移築も完成しているし、もう恭仁京に飽きて、紫香楽への遷都を考え始めたのではないか。
六位以下2,370人というのはなんだろう。12泊13日とはいえ、ただの旅行にこんな人数いりません。
この2,370人、どこに泊まったんだろう。7ヶ月で2,370人分の宿舎が建設できるものかね。建築現場の仮説作業員宿舎みたいなものか。大半が宮の建設作業員とすると納得できる。「禄を賜った」ということは、やはり給料を出していたのです。
天平15年(743年)7月26日、
★天皇は紫香楽宮に行幸された。★
前回4月3日は「紫香楽」でしたが、今回は「紫香楽宮」
前年8月11日、造営卿・智努王(ちぬの・おおきみ)、造営補・高岡連河内に命じた宮ができたということです。11ヵ月で天皇の宮を造ったことになります。 -
公民館前パネルより。下記の画像も同じです。
発掘結果による紫香楽宮の想像図です。 -
2001年度発掘調査の結果です。
大安殿、東西朝堂は1辺約112mの、南に開いた方形でした。
公民館は大安殿の正面、東西朝堂のほぼ中間となります。 -
全体推定画像(CG)
公民館、つまり私たちの立ち位置は赤丸です。
背後に「御在所」というのがあります。内裏ということです。7月26日には少なくともこの部分はできていたでしょう。
光明皇后がこの日一緒かどうか、分かりません。橘諸兄は恭仁宮の留守官でしたので、この日はおりません。 -
発掘調査結果の斜めに走る道路と公民館から割り出すと、ほぼこの位置です。
田んぼの中に大安殿がありました。 -
大安殿は目の前です。
聖武天皇の後ろ姿が見えませんか。 -
紫香楽宮の夢の跡であります。
-
天平15年(743年)冬10月15日、
★天皇は次のように詔された。(中略)ここに天平15年、天を十二年で一周する木星が癸末(みずのとひつじ)に宿る十月十五日を以て、菩薩の大願を発して、盧舎那仏の金銅像一体をお造りすることとする。★
有名な「盧舎那仏造営の詔」です。長いので全文は引用しません。
これもまた日本古代史にのこる有名な詔です。これが発せられたのは、紫香楽宮でありました。私は平城宮だと思っておりました。
10月16日、
★東海・東山・北陸三道の二十五国の今年の調・庸の物資はすべて紫香楽宮に貢納させた。★
紫香楽は離宮ではなくて、天皇の正式な宮であると宣言したことになります。
パネルによれば、
「朝堂周辺には、中央官庁とみられる区画や建物跡複数見つかることから、紫香楽宮は単なる離宮にとどまらず、国家政務を担う役所群を配置する本格的な宮としての機能を有していたことがわかり、宮都の紫香楽宮がこの地にあったことが明らかになりました」
10月19日、
★天皇は紫香楽宮に行幸された。盧舎那仏の像をお造りするために、初めて甲賀寺の寺地を開いた。行基法師はここで弟子たちを率いてひろく民衆に参加を勧誘した。★
この「紫香楽宮」というのは意味不明。天皇はすでに紫香楽にいます。このあとの11月2日の記事により、4ヵ月の間ずっと紫香楽に滞在したはずです。甲賀寺近くに同じ名前の離宮が別に造られていたのかもしれません。
11月2日、
★天皇は恭仁宮に還られた。天皇の紫香楽滞在はおよそ4ヵ月であった。★ -
このあたりから聖武さんの軌道は混乱します。
11月2日に恭仁宮に還りました。
天平16年(744年)春正月1日、
★朝賀の義は取りやめた。五位以上の官人を朝堂において饗応された。★
新年は恭仁宮で迎えましたが、せっかく移築した大極殿は使わない。無理して移築したので、雨漏りでもしたか。
11日には難波宮に行幸してしまいました。
2月24日、
★紫香楽宮に行幸された。★
難波宮にいたのは1ヵ月ちょっと。
太上天皇(元正天皇)、橘諸兄は難波残留。皇后は天皇と一緒のはず。
26日には、難波宮で、難波宮を皇都とする大事な勅をだすのですが、左大臣・橘諸兄が代読しました。それをすっぽかして紫香楽宮にいっちゃたのです。
昨年11月からの4ヶ月間で、紫香楽→恭仁→難波→紫香楽と移動。
3月14日、
★金光明寺(こんこうみょうじ、東大寺)の大般若教を運んで、紫香楽宮に到着した。★
これがあるから紫香楽に来たのか。熱烈な仏教信者の聖武天皇ですから、ナンチャラの詔より大事かも。
夏4月13日、
★紫香楽宮の西北の山で火事があった。城下の男女数千余人がみな山へ行き木を切り、延焼を防いだ。天皇はこれを褒めて一人一人に麻布一端宛を与えた。★
紫香楽京の人口が「数千余人」であったことが分かります。
これから紫香楽では山火事が頻発します。
4月23日、
★紫香楽宮を造営し始めたが、百官の役所がいまだに完成しないので・・・★
「いまだに完成しない」役人どものサボタージュじゃないかな。ここに来たい役人などおりません。
11月13日、
★甲賀寺に初めて盧舎那仏の体骨柱を建てた。天皇は親しくその場に臨んで、自らの手でその綱を引かれた。★
甲賀寺の大仏については長くなりますので、別のブログにいたします。 -
天平17年(745年)春正月1日、
★朝賀の儀式が中止された。にわかに新京(紫香楽宮)に遷都して、山を伐りひらき土地を造成して、宮殿を建造したのであるが、まだ垣や塀ができあがらないので、かわりに垂れ幕などを張り巡らせた。★
天平14年(742年)8月から始めた新京つくりですが、2年以上たっても垣もできていない。あきらかに紫香楽より遅いペースです。
田舎の恭仁京よりさらに山の中の紫香楽、来たくない役人連中、てれんこてれんこ、やっております。
夏4月1日、
★紫香楽京の市の西の山で火災があった。★
4月3日、
★寺(甲賀寺か-訳注)の東の山で火災があった。★
4月8日、
★伊賀国真木山(三重県阿山町にある。紫香楽宮にも近い-訳注)で火災があり、三,四日燃え続け、数百町を延焼した。★
立て続けです。紫香楽宮をいやがる連中の放火ではないか。
極めつきは、
4月11日、
★紫香楽の宮城の東の山で火災があり、幾日も鎮火しなかった。このため都の人々は競って川辺に行き、財物をそこに埋めた。天皇も乗物を用意して、大丘野(不詳-訳注)に行幸しようとされた。★
4月13日、
★夜、小雨があり、火勢が衰え鎮火した。★
天皇自らが避難を迫られたくらいの大火事でした。
火事が収まったら、今度は地震です。
4月27日、
★この日、一晩中地震があり、それが三昼夜続いた。★
5月1日も地震。2日も地震。
聖武天皇、火事と地震で自信をなくした。
5月2日、
★この日、太政官は諸司の官人たちを招集して、どこを都とするのが良いか問うたところ、みな平城京を都にするのが良いと言上した。★
聖武天皇という方は、調子がいいときは何でも独断で決めるくせに、具合がわるくなると人の意見を聞きたがる。責任回避というのでしょう。いいリーダーではない。こういう人が社長だと、会社は潰れます。
3日も地震。 -
天平17年(745年)5月3日、
★秦公嶋麻呂を遣わして恭仁宮を掃除させた。★
もうこの段階で紫香楽を捨てる気です。
4日も地震。
四大寺の僧侶たちを集めてどこを都とするのが良いか問わせたところ、全員、平城を都とすべきだと答えました。
紫香楽を捨てるのは、ボクが決めたんじゃないからね、みんながそう言うんだからね、という言い分けです。
5日も地震。
5月5日、
★天皇は恭仁宮に還り、参議・従四位下の紀朝臣麻路を甲賀宮(紫香楽宮-訳注)の留守官に任じた。★
翌6日恭仁宮着。
あーあ、紫香楽京を捨てちゃった。
5月7日、
★平城宮の掃除をさせた。★
恭仁京も捨てる気だ。
地震は、7日、8日、9日、10日と続きます。
5月10日、
★恭仁京の市人たちが、平城京に移ってきた。早朝から夜ふけまで、先を争って行き、行列は絶えることがなかった。★
5月11日、
★甲賀宮(紫香楽宮)は空っぽで無人の地となり、盗賊が充満し、山火事の火もまだ消えなかった。それで各官司の役人や衛門府の衛士らを派遣して官物を収納させた。★
恭仁京から平城京まで続く松明の波、かたや紫香楽京の大通りを跋扈する盗賊の群、なすすべのない衛門府の衛士。大スペクタクル映画ができますね。「古代の大脱出」の一場面であります。
紫香楽京はのたれ死にです。
5月11日、
★この日天皇は恭仁京から平城京に行幸し、中宮院を御在所とした。★
聖武天皇の引っ越し癖は、こうして終わりました。
その後恭仁京、紫香楽京、甲賀寺の体骨柱だけの大仏さんがどうなったか、記録にはありません。
天平12年(740年)から天平17年(745年)までの、壮大な道楽でした。
でもまだ終わっていません、奈良の大仏さんはこれからです。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
旅行記グループ
六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇
-
前の旅行記

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇3 番外編 タヌキ街道
2021/07/09~
信楽
-
次の旅行記

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇5 甲賀寺、天皇のえんやこら
2021/07/09~
信楽
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇6 特別番組、勅令発布実況中継、難波宮より
2020/11/14~
大阪城・京橋
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇1、恭仁京はコスモスの原っぱ
2021/07/09~
木津・加茂
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇2、だれも来たがらない恭仁京
2021/07/09~
木津・加茂
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇3 番外編 タヌキ街道
2021/07/09~
信楽
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇4 紫香楽京ですみっこ暮らし
2021/07/09~
信楽
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇5 甲賀寺、天皇のえんやこら
2021/07/09~
信楽
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇7 天皇さん戻らはる
2021/07/09~
奈良市
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇8 大仏開眼の日、の朝
2021/07/09~
奈良市
旅行記グループをもっと見る
この旅行記へのコメント (4)
-
- 前日光さん 2021/12/23 22:58:02
- いやはや(@_@)
- もし側近だったなら、大変だったでしょうね(^^;)
聖武くんに振り回されて、 シッチャカメッチャカ。
落ち着かないわぁ、聖武くん。
私、典型的な農耕民族の末裔なので、どっしり腰を落ち着けてるのが好きなタイプでして。
5年間も遷都騒ぎ繰り返してくれて、いったいこの人は何なんでしょう?
こんばんは、しにあさん&by妻さん。
思うに聖武くんは猫体質ですね。
狭いところが大好きって、我が家の猫もわざわざ自分より小さな箱に入ろうとして四苦八苦しています。
なるべく狭い空間で、誰にも邪魔されたくない。
でも同じ状況にはすぐに飽きる。
次の寝床を求めて、あっちこっち。。。と。
猫なら許されるけれど、人間、しかも天下の天皇様、つらいですねぇ、聖武くん。
光明子が慰めてくれたとは思えないし、オバサマの元正様はどうだったのかな?
美人だから顔見てるだけで、気が済んだかも。
この二人確か21歳の年の差、元正様はあまりお出かけが好きではなかった様子、
「そんなに都を取っ替え引っ替えするのはおやめなさいよ」ぐらいは言われたかな?
心に闇を抱えた聖武くん、自分でもどうしたらいいのか分からず、いろいろ。。。
大仏はやはり奈良にと考えて、ひと段落。
紫香楽宮の痕跡(ほぼ田園地帯)を眺めながら、聖武くんの孤独を思いました。
恭仁京の整備がまだなのに紫香楽にお引っ越し、そこにもほんの数ヶ月、この天皇は病んでいましたねぇ。
うち続く地震、もう自分の力は及びません。
どうしたらいいの?状態、やっぱ大仏だぁ、と思ったかどうか、とにかく平城京に帰ろうとなったのか?
責任感はこの人にはありません。やりたい放題やってもなお気が晴れない。
死に至る病とは絶望である。
ああ、どうしたらいいんだぁー(*_*)
前日光
- しにあの旅人さん からの返信 2021/12/24 09:08:50
- Re: いやはや(@_@)
- 聖武くんは明らかに病気ですね。
恭仁京では、わざわざ狭いところに宮を作っている。紫香楽なんて狭すぎて一般市民住むところがない。役人たちはどこに買い物に行ったんだろう。
唐の三都制にならって、難波宮を含めて都を三つ同時に運営なんて説もあるそうですが、絶対そんな高級なものではない。難波宮はともかく、あんな狭いしょうもないものを作ったってむだですね。
絶対病気。
続日本紀はがわざわざ天皇が皇后のところに行ったなんて書いているのは、暗に2人が不仲だったと言っているのではないかと邪推しています。
するとやたらに元正太政天皇が出てくるのは、2人は怪しいと察せよ、ということかも。
続日本紀というのは日本書紀と違って、一見つまんないんですが、案外底意地の悪い代物ではないか。
純真な学者的態度より、ヨコシマな週刊誌の記者になった気分で読んだらおもしろい。
聖武くん、責任感ゼロ。なにかうまくいかないと人の意見を聞きふりをします。
こまった人です。
でも家持さんは、若い頃は聖武さんときがあっていたみたいです。
本音を知りたいところです。
我が家でも地域猫を2匹採用しております。野ネズミとモグラ退治係です。近所に、野良に不妊手術を安くやってくれる獣医さんがいて、連れて行きました。
我が家がメインのようです。テラスに猫ボックスを1匹づつ作ってやりました。狭いひとつに2匹でぎゅう詰めで寝ております。暖かくてきもちいいようです。
-
- kummingさん 2021/12/22 10:23:19
- すみっコくらし(*_*)
- しにあさん、by妻さん、こんにちは♪
ロマン派の呼び声高いお二人をもってしても、心眼を研ぎ澄ませて田んぼを見渡せば、朱塗りの宮殿が湧き上がって…、来なかった! そこから、そこらに転がる石ころ一つで千年の歴史を紡ぐby夫、by妻さんの腕の見せどころ、拝見しました♪
僅か5年間に4度のお引越し、それも庶民のお引越しとはレベルが違う、遷都ですから、費やされた労力、資材、経済的損失を想像すると、目眩が~
前回も言いましたが、振り回された官僚や政治家、人民の中にもこの被害、悲劇を未然に食い止める術はなかったのか? 「出来ません」と言ったら首がとび、反対する者は島流し(ーー;)人事権掌握する者に逆らえなかったのは、古今東西変わらずですね。
『ヒッキー』引きこもりの俗称、引きこもる人の事(コモラー、ヒキコモラー、真性・半・偽ヒキ、ともいう)、なるほど~
『すみっコぐらし』 当節流行りのキャラクターなのですね。
孫(まだ我が家にはいませんが…)に、すみっこぐらしキャラねだられたら、孫のヒッキー化心配してしまいそうな、ばあばでございます♪
聖武天皇、元祖すみっこぐらし願望者、かもしれません。
P.S. 常連さん、ばかりがカキコすると、一見さんのご訪問を遠ざけてしまうのでは?と懸念する今日この頃…、新たな読者を掘り起こし、新規投稿が待たれます^ ^
- しにあの旅人さん からの返信 2021/12/23 05:38:30
- Re: すみっコくらし(*_*)
- 一見さんもおいでになるときはおいでになるでしょう。気にせずにマイペースでやりましょう。そういうことに関わりなく気楽にやるのが4トラのいいところ。
昨日近くの本屋に行ったら、すみっコぐらしで一棚できていました。なにが面白いのか分かりませんが、おもしろい。鬼滅のナントカよりはいい。
もうすぐ7才の孫娘ですが、この3年、デズニーのアナ雪姫、鬼滅、すみっこと毎年こだわりが
変異します。アナ雪と鬼滅の間にもう一つあったかな。
クリスマスの度にそのときのトレンドを孫からおそわります。
こちとらは1年、8世紀から進歩しておりません。
鬼滅の世界からすみっこの世界への逃避というBy妻説は、聖武天皇をズバッと説明できます。
紫香楽京は本当に狭かった。盆地の半分くらいは宮殿が占めちゃうので、役人や市民はどこに住んだんだろうという感じです。
相次ぐ山火事は反紫香楽派の放火だろうという説もなっとく。
聖武天皇の頭の中、完全に破綻していたな、とつくずくおもいました。
行ってみる、というのは歴史の旅では本当に大事。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
信楽(滋賀) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?






































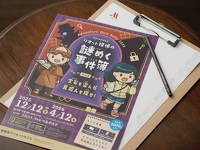





旅行記グループ 六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇
4
29