
2021/07/09 - 2021/07/12
68位(同エリア243件中)
![]()
しにあの旅人さん
- しにあの旅人さんTOP
- 旅行記251冊
- クチコミ254件
- Q&A回答18件
- 312,531アクセス
- フォロワー77人
天平15年(743年)冬10月15日、紫香楽宮にて、
★天皇は次のように詔された。(中略)ここに天平15年、天を十二年で一周する木星が癸末(みずのとひつじ)に宿る十月十五日を以て、菩薩の大願を発して、盧舎那仏の金銅像一体をお造りすることとする。★
有名な聖武天皇の盧舎那仏造営の詔です。
続いて、
10月19日、
★天皇は紫香楽宮に行幸された。盧舎那仏の像をお造りするために、初めて甲賀寺の寺地を開いた。行基法師はここで弟子たちを率いてひろく民衆に参加を勧誘した。★
その甲賀寺跡に行ってきました。
表紙写真は、世が世なれば大仏が建立された甲賀寺の金堂跡です。
引用した参考書などは、「元祖4トラベラー聖武天皇1」に列挙しました。引用に際し、僭越ながら敬称を略させていただきます。
- 旅行の満足度
- 5.0
- 同行者
- カップル・夫婦(シニア)
- 交通手段
- 自家用車
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
紫香楽宮跡と甲賀寺跡の位置関係です。真南に直線で約1.8km離れております。
-
1回目の甲賀寺、2020年11月16日です。中門を経て金堂にいたる参道です。ゆるい上り道です。のちの奈良の東大寺と違って、甲賀寺の金堂は岡の上にありました。
コロナ騒ぎの谷間でしたが、甲賀寺で出会った人は4人、そのうち2人は地元の方の散歩でした。 -
一書に曰く、
甲賀寺跡は、森の中にあって、入っていくとき、どこかによく似ているなあと、しばし考えました。
車から降りると、落ち葉が降りそそぎ、空いっぱいにまっかな紅葉の天蓋。
何という静けさ、なんという美しさ。
駐車場で、もう、うっとりして写真を撮りにうろうろします。
と、駐車場のすみに、趣のあるトイレ。
車で旅行すると、次にどこに行くのか分からないので、トイレを見たら、何はともあれ利用することにしております。
近づくと、その辺りの木は特に厚く繁っておりまして、よりしっとり湿気を感じます。ひんやり。
と、入口に札がかかっております。
「マムシ注意。」
ぎょっ。
回れ右。
でも、よくよく考えたら、季節はすでに冬に近い秋、こんなに紅葉がきれいなのですから、「あのかた」は、もう、冬眠していましたよね。
しかし、日本中いろいろなところで、この立て札を見ます。
「マムシ注意。」
ああ、そこで思い出しました。ここ甲賀寺跡の森は、軽井沢によく似ていました。
森の中の車道。そして落葉する木々。
そうか、聖武さんは、このときちょっと、立原道造入っちゃったんだ。
ま、気分は分かりますよ。
ときにはロマンティックになりたいときもあったでしょうよ。
やっとやっと生まれた坊やなんだからって、期待は重たかったでしょうし。
がんばる女達のなかの黒一点なのだから。
日本の女帝は、この聖武さんの周りに集中しております。
男はつらいよ。でございますね。
立原道造が、軽井沢で、心を休めたように、聖武さんもここで心を休めたかったのか。
それとも、元正天皇へのかなわぬ恋に傷ついて、ここに泣きにきたのか。
ロックだぜ!ベイビー。
あ、私、まだ光明皇后は樹木希林説から逃れられない。
森の中の坂道も、きれいに整えられて、階段にしてありました。両脇には木々が茂り、良い雰囲気の散歩道です。
お若いお二人が、降りていらっしゃいました。
デートですな。
こういう所をデートするって、つきあい始めなんだろうか、それとも結婚間近なんだろうか。
歴史の話なんかしたら、なかなか高尚な趣味だと、点数が高くなりそう。点数稼ぎのつきあい始め。
でも、お金かかんないよね。式のことを考えたら、無駄遣いはできないと考えたかな。
ま、どっちでもいいです。お幸せに!
By妻 -
中門あとの礎石です。
-
東大寺では中門から大仏殿まで約80mありますが、甲賀寺では写真中央の坂道だけです。写真手前は金堂の基壇。10mくらいでしょうか。
-
金堂跡は基壇が残っており、壇上には紫香楽宮という神社があります。
中門から金堂基壇まで。ご覧の通り、短い。 -
小さなお社です。甲賀寺と直接の関係はないようです。
一書に曰く、
登りきると、小さな、本当に小さな社殿がありました。
でも、備品がすべて小さくとも立派で、徳川将軍のお姫様のひいな遊びのようでした。
そして、その社殿の後は、開けた土地でした。
その開けているところが、跡なのでした。
By妻 -
現場パネルより。甲賀寺の復元図です。金堂は東大寺の大仏殿よりあきらかに小さい。聖武天皇がここで建立しようとした大仏は、後年の大仏よりはるかに小さい像だった。
-
現場パネルより。礎石図。
一書に曰く、
枯れた草の中に、規則正しく礎石が並んでいます。
by夫が、一歩二歩と、歩幅で石の間を測ったりしているとき、ビューンキーンと、チェーンソーの音がしました。
緑の中に、作業服の男の人が、木々の手入れをしています。
私たちが、礎石と礎石の間を、歩いて距離を測ったり、礎石の数を数えたりしているのを、何だと思っていらっしゃったことか。
お爺さんとお婆さんが、幼児にかえって遊んでいると思ったかも知れません。
というのも、チェーンソーの音が、一瞬途切れたのですよ。
ぎょっとして、じっとみつめたのかもしれません。
いえいえ、私らは、けっして、まだ、ぼけてはおりません。と一言申し上げたかったです。
が、あちら様は、働いている最中。声をかけていいものか。ふうっ。
変な人だと思われているんじゃないかと、気をもんでいるわたくしに、by夫は、うーむ、だいたい18メートルかな。とか無邪気なもんです。
まあ、いいか。この年になったら、恥も外聞もないや。
By妻 -
金堂東の塔跡。五重塔だったそうです。金堂跡からは明らかに一段低くなっており、岡の頂上の凸凹を利用して伽藍を配置したようです。
-
五重塔の第1階って、こんなに小さいかなと思いました。
-
見れば分かりますが。塔です。
-
僧坊跡です。
-
1房内に1人~数人が居住し、僧侶の読書、寝臥などにあてられた、とあります。
-
20室ありました。
-
経楼。
-
しっかりした礎石でした。
-
まだ貴重な写真があるのですが、説明板とばらばらになってしまい、どれがなんだか分からなくなりました。載せられません。残念。
-
ドローンの回転空撮は、全体の雰囲気をご紹介するにはいいと思いますが、木立が多すぎて、見通しがききません。
https://youtu.be/wRc6Cdg7Vm8 -
ここから本題。
甲賀の大仏さんを建立するはずだった金堂跡。 -
金堂は正面7間奥行4間。大仏を配したのは内陣で、正面5間奥行2間です。
-
写真は神社の裏手。
神社を囲んでいるのが内陣礎石正面です。左端1番目と右端5、6番目の礎石は木立に隠れて見えません。
礎石の中心から中心まで距離を測ってみました。1間はおおよそ2.52mとなりました。
私の歩幅ですから、おおよその距離です。
金堂本体は、
正面:約17.64m
奥行:約10.08m
内陣は、
正面:約12.6m
奥行:約7.7m
細かくこだわった理由は、東大寺大仏殿とくらべるためです。
あまりに有名なので写真はほんのちょっと。 -
ご存知大仏様と、
-
大仏殿。
大仏殿の縦横はすぐ分かりましたが、内陣の寸法が分かりませんでしたので、大仏殿本体からの類推です。
なおこれは鎌倉時代に再建された大仏殿の寸法で、創建当時は正面は86mで現在より大きかったのです。
内陣はあまり変わっていないようです。
大仏殿
正面:57.5m
奥行:50.5m
正面は7間ですから、ここで1間は8.2m
内陣
正面5間:41m
奥行3間:24.6m
本尊を安置する内陣は、甲賀寺は東大寺大仏殿の正面、奥行とも大体30%です。
甲賀寺に予定されていた大仏さんも、やはり東大寺に比べて30%くらいのものだったと推定されます。
大仏さんの創建時の像の高さは15.8m、幅は12mです。
したがってその30%、甲賀寺は像の高さ4.74m、幅3.6mくらいになります。 -
仏像のサイズは丈六、4.8mの整数倍、縮小するときは2分の1、3分の1などと決まっておりました。座像ならばその半分となります。
こちらは飛鳥寺の飛鳥大仏様。丈六の座像、2.4mです。
その2倍は4.8mとなります。
甲賀寺の仏像の推定サイズとほぼ一致します。 -
これは飛鳥資料館に展示されていた、飛鳥の山田廃寺の仏頭複製です。写真使用許可取得済みです。
撮影時By妻を横に並ばせてあとでサイズを推定しました。頭と冠の境目がはっきりしませんが、顎から頭まで約100cmでした。全体を類推すると、像の高さ4m~5mの座像です。丈六の2倍、約4.8mとなります。 -
東大寺大仏殿の脇侍如意輪観音様です。江戸時代の造立。台座を含めて高さ約7m、台座を別にすると丈六2倍でありましょう。
-
同じく東大寺の虚空蔵菩薩様。同じサイズ。
甲賀寺に予定されていたのは、このような大きさの盧舎那仏様だったと、推定されます。
私が不思議に思うのは、甲賀寺の大仏の小ささです。
丈六2倍の坐像なら、すでに山田寺にありました。山田寺の大仏様は685年には完成しております。1411年の火災で焼け落ちるまでは確実に存在しておりました。聖武天皇が実際に見ているかどうかは分かりませんが、存在を知らないはずがない。
それなのに、「盧舎那仏造営の詔」というたいそうな宣言をして造るほどのものか。
聖武天皇がイメージしていたものは、もっともっと大きなものだった。
それなのに実際に甲賀寺で作り始めてみると、思いのほか小さいものになる。
それじゃ、やめよう。
聖武天皇なら、このくらいの気まぐれはやりそう。
思い通りの盧舎那仏ができないなら、紫香楽宮なんかいらない。ついでに恭仁京も捨てちまえ。
この想像は、案外あっているかも、と思っています。
一書に曰く、
甲賀寺跡を見ると、その規模が思いがけなく小さくて驚きます。
奈良の東大寺と比較しているのですが、この小ささを考えると、最初は、気まぐれだったのだなあ。とにかく、現状を打破したい、というだけの思いだったのではないかと私には思えます。
最悪な今の世から、新世界へ!って、思ったのでしょうか。
ちょっと、グチの代わりに、思いついたアイディアを漏らしたら、プロがどんどん実現しようと計画が進んで、「ありゃ、そういうことなら、この場所はできません、もっと違う場所でないと。」とかいうことだったのかな。
アメリカへアメリカへ。希望を抱いて旧大陸から新大陸を目指した人々と同じ気持ちだったのかも。
ガラガラポン!と、最初から全てをやり直したかったのですかね。
不安で、追い立てられるように転々としたのか、気まぐれのアイディアが、次々出てきて、ワクワクドキドキで、引っ越したのか。
聖武さんをとっ捕まえて、きっちり問い詰めたいところです。
By妻 -
続日本紀天平16年(744年)11月13日、
★甲賀寺に初めて盧舎那仏の体骨柱を建てた。天皇は親しくその場に臨んで、自らの手でその綱を引かれた。★
「体骨柱」というのは、たぶん像の骨組みだと思います。私は、除幕式みたいなのがあって、聖武天皇が除幕の縄を引いたと、勝手に思っていたのです。
一方、諏訪の御柱の立ち上げみたいに、綱を引いて、体骨の中心になる柱を建てた、その縄を引いた、とも読める。
もしかして基礎堅めのえんやこらのことかな。儀式にしても、天皇がみずからえんやこらの縄を引いた。
「えんやこら」は私と同年代の方は、ご存知ですよね。昭和20年代、ご覧になったこともあると思います。お若いかたは、ググって下さい。
聖武さん、このときは、大仏建立に気合いが入っています。
このときは・・・
しかし、半年後、
天平17年(745年)5月5日、
★天皇は恭仁宮に還り、参議・従四位下の紀朝臣麻路を甲賀宮(紫香楽宮-訳注)の留守官に任じた。★
聖武天皇は紫香楽京を放棄しました。
甲賀寺の大仏は、このあと歴史から姿を消します。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
旅行記グループ
六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇
-
前の旅行記

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇4 紫香楽京ですみっこ暮らし
2021/07/09~
信楽
-
次の旅行記

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇7 天皇さん戻らはる
2021/07/09~
奈良市
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇6 特別番組、勅令発布実況中継、難波宮より
2020/11/14~
大阪城・京橋
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇1、恭仁京はコスモスの原っぱ
2021/07/09~
木津・加茂
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇2、だれも来たがらない恭仁京
2021/07/09~
木津・加茂
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇3 番外編 タヌキ街道
2021/07/09~
信楽
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇4 紫香楽京ですみっこ暮らし
2021/07/09~
信楽
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇5 甲賀寺、天皇のえんやこら
2021/07/09~
信楽
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇7 天皇さん戻らはる
2021/07/09~
奈良市
-

六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇8 大仏開眼の日、の朝
2021/07/09~
奈良市
旅行記グループをもっと見る
この旅行記へのコメント (10)
-
- mistralさん 2022/01/06 13:33:14
- 聖武天皇って?
- しにあの旅人さん
by妻さん
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくおつきあいのほどをお願い致します。
コメントを残すのを、しばらくの間ご無沙汰しておりました。
たまたま壬申の乱の周辺時代に興味を抱き、いまだにその界隈を
ウロウロしている私ですが、
しにあさんはその後もどんどん時代を下られ、聖武天皇の御代へと。
しにあさんの旅行記を拝見して、聖武天皇に対するイメージは覆っております。
待望の男子誕生で、周囲の女性たちは浮足だってしまい
結果、甘えん坊?なんでも思い通りになってしまう?ひ弱な男子に
なってしまったのでしょうか。
甲賀寺跡への参道、世が世なら、素敵なサイクリングロードとなっても不思議でない、
by妻さんがおっしゃるように軽井沢界隈の小道のような佇まい。
森の中の小道、落葉する木々
思索にふけるには絶好のロケーションですね。
一方、しにあさんは礎石間を一歩一歩歩幅でもって計測されておられて、
伊能忠敬さんのような佇まいだったことでしょう。
男性と女性の頭の中、胸の内をのぞいてみると全く違う動きをしているとは
良く言われることです (因みにこれは我が家のことです。)
そんな事はさておき、甲賀寺は思ったより小規模な寺院であった、
安置されるはずだった盧舎那仏も大きさは大したこともなく、
一体どういういきさつでそこに建立する運びになったことやら、、、
当事者がおられたら聞いてみたいことですね。
本年も健康で楽しい旅ができますように。
mistral
- しにあの旅人さん からの返信 2022/01/07 06:56:42
- RE: 聖武天皇って?
おはようございます。
大津の旅行記拝見しております。後ほどおうかがいいたします。
ここ数年奈良京都滋賀あたりをウロウロしてきました。大来大津だったり、聖武くんだったり、縦の旅をたのしんでおります。
現実主義と浪漫主義の夫婦ですから、立原道造と歩幅測りが両立しております。
恭仁京、紫香楽京、甲賀寺跡、とにかく人がいないので、悠々と見てきました。
コロナがぶり返しております。その前に九州を片づけてきたので、当面出かけなくてもなんとか旅行記のネタはあります。
今年も浮世離れしたお話で、盛り上がろうではありませんか。
「旅に病まなくても 夢は荒れ野で 盛り上がる」
おそまつ。
-
- kummingさん 2022/01/05 16:18:49
- 新年のご挨拶♪
- ご挨拶の前に、いいねぽちをする前に、横レスするとは、初春早々なんたるちあm(._.)m
あらためまして、初春のお慶申し上げます♪
甲賀寺の大仏さまは小粒だった説、ふむふむ、なあるほどでございます。
立原道造さん、24歳で早世された詩人さんなのですね、和歌も詩歌も全く未知の世界なのでm(._.)m
光明皇后→樹木希林説、ってどういうお話でしたっけ?
実は、聖武&日高さまの恋話シリーズ最終回という告知を前に、心ここにあらず(-。-;
ねこちゃんたちの為にに小屋を作られたとの事、タオルや毛布、抱き枕の貸し出しも、厳しい冬越しには最高のプレゼント♪
子どもの頃、捨てられねこを拾っては部屋に匿い、下校すると居なくなる(捨てられる)、探して来て匿う→居なくなる、を繰り返し、その攻防を潜り抜けた者にだけ与えられる特権(我が家の一員になる)を享受し、木から落ちて大怪我(ねこなのに)、車にぶつかり骨折、ゴルフボールに当たって骨折(犬なのに)などの挙げ句、父の治療(ギブスしたり、酸素吸入したり)の甲斐もあっての数奇な運命の末長寿を全うした、愛猫愛犬の想い出…。
今年もはじめから、ブログに無関係なカキコでm(_ _)m
格調高いコメントは、他の方にお願いします♪
本年もよろしくお願い致します^ ^
- しにあの旅人さん からの返信 2022/01/06 07:59:34
- RE: 新年のご挨拶♪
- あけましておめでとうございます。
コロナが来ようと時は流れ、このままコロナも流れると期待しております。それまで亀の子作戦、やむを得ません。
コロナが終わってもマスクはとらないという方が25%もいるそうです。ご婦人は化粧しなくていい。殿方はヒゲ剃らなくてもわからない。
光明皇后樹木希林説は、このシリーズの2です。継母にするなら誰がいいとかいうby妻のヒマなお話。11枚目の写真のあと。
聖武・氷高物語は、どうしようかな。尾ヒレをつけてこのシリーズの番外秘話で独立させようか、とも思っています。続日本紀の週刊誌的読み方です。
ネコどもはただいま玄関で食事中です。オスの方はメスを飛び越えてでも玄関にはいって来てゴハン第一、メスは私が新聞を取って戻ってくるまで、ご飯を食べずに戸口に立っております。「弟が不作法でごめんなさい」と言っているのではないかと。姉弟ではないのですが、そういう間柄です。
我が家の猫カリはだいぶ残して出ていくので、ほかにエサ場があるのでしょう。
今年も浮世を離れて、心を旅に浮かせて、楽しもうではありませんか。
-
- 前日光さん 2022/01/04 23:21:13
- 幻の甲賀寺「体骨柱」
- こんばんは&新年おめでとうございます!
今年も妄想話で盛り上がりましょう(爆)
それにしても聖武くんって、どんどん狭いところに入り込んで行きますねぇ。
かわいそうに。
恭仁京>紫香楽京>甲賀寺
最後には、みんなやーめた!、
奈良の都に戻るもんね、ついでに大仏は限りなく巨大なものをと、半ばヤケクソで詔を発したのでしょうか?
by妻さんは、聖武くんが氷高様を慕っていた説なのですね?
聖武と氷高の年齢差は40歳、長屋王と氷高は23歳、いずれも年上美女に対する思慕ですね。
不比等と氷高は、不比等が2歳年上、年齢的には一番似合うのがこの二人なんですよね。昔読んだ少女漫画の影響で、どうしても不比等・氷高の純愛という路線から逃れられません。氷高が一生結婚しなかったのも、不比等の父性的なものに対する憧れが常にあったからではないのかと。不比等の死(720年)から一年後の721年に氷高が亡くなっているのも運命的なものを感じてしまうのです。
もっともこの妄想は、不比等が少女漫画に描かれているようなイケメンだった場合に限られますが。
聖武くんは甲賀寺参道歩きしながら、立原道造が入っちゃったんですね?
分かる気はしますが、立原に聖武くんが取り憑いたのではないのですね?
聖武くんに立原が。。。っていう発想が、さすがにby妻さんです!
時代を超えて響き合う二人の魂「。。。しあわせは どこにある? 山のあちらの あの青い空に そしてその下の ちひさな 見知らない村に。。。」
二人とも儚いですね。
甲賀寺参道の紅葉が美しいです。
聖武の孤独や鬱屈した思いを包み込む紅ですね。
前日光
- しにあの旅人さん からの返信 2022/01/05 05:51:17
- Re: 幻の甲賀寺「体骨柱」
- おはようございます。
新年最初のコメントありがとうございます。
今年も浮世離れした旅行記、楽しみたいとおもいます。
聖武くんと氷高さんのお話は、2度の平城京旅写真を見ていたら、ちょっとした発見がありまして、このシリーズの最後でとりあげます。
山岸涼子などのコミックを本屋で探しましたが、全然見かけません。少年、少女、青年などと細かくジャンルが分かれていました。80、90年代の古典的な名作というのはどういうジャンルなのですかね。Book Offに行ってみようかと思います。
聖武くんが立原もびっくりのロマンチストであったことは間違いないでしょう。そうでなければあんなこと思いつかない。権力者がロマンチックであると、周りが迷惑するのです。
今年は房総でも珍しいくらいの寒さです。我が家の野良2匹にネコ小屋を作ってやりました。by妻がタオルやら毛布の古いのをいっぱい入れてやりました。2匹固まって寝ています。私が使わなくなった抱き枕もはいっています。春になったら返してくれるそうです。
- 前日光さん からの返信 2022/01/05 08:50:27
- 訂正します(>_<)
- おはようございます!
夕べ布団に入ってから、(?_?)不比等と氷高の年齢差が2歳?のはずはない!
あの漫画でも、氷高が幼い頃、不比等は充分に老成した大人だったはず!
うぬっ、何か勘違いしている自分?
そして気づきました!
元正天皇と元明天皇の生没年を取り違えておりました(^^;)
661年生まれ、721年没は元明天皇でしたσ(^◇^;)
元正天皇は681年生まれ、748年没です。
すると聖武と氷高の年齢差は21歳、長屋王とは4歳違い(どちらも氷高が年上)、
不比等とは21歳違い、ただしこれは不比等の方が21歳年上ということになります。
不比等と氷高の没年が一年違いだと、先に書いたようにロマンティックな解釈ができたのですが、残念ながら?不比等没後、氷高は28年生きながらえたようです。
聖武は氷高没後8年にして亡くなりました。
この天皇は、本当にどんな気持ちで生涯を送ったのでしょうかねぇ(-_-)
というわけで、勘違いの訂正でしたm(_ _)m
前日光
- kummingさん からの返信 2022/01/05 15:49:43
- 年初からの横レスm(_ _)m
- 初春のお慶申し上げます♪
で、さっそくですが、聖武&元正のおば甥恋ばなについては、昨年来のしにあさんにおわせに、ウズウズ。していた処へ前日光さんの追加情報♪
日高さんと不比等のあやしからん関係とは何ぞや??不比等がイケメンですって??
私の中で山岸涼子は「アラベスク」「日出る処の天子」で止まっていますが、Amazon 検索によると「月読」「青春(あお)の時代」「馬屋古女王」など歴史モノあるみたい。
里中満智子だと、持統天皇、称徳天皇、ギリシャ神話ものなど…。
あとあるとすると「あさきゆめみし」の大和和紀?
なんとしても、日高&不比等の恋ばなコミック、読んでみたいな^o^
おまけに、Amazonで「チェザーレ破壊の創造者」というコミックを見つけてしまいました♪
今年もよろしくお願い致します^ ^
P.S.しにあさんちでは、あれなので、後ほど『風ちゃん♪』話を別途、前日光さんちにお届けさせて頂きます♪
- 前日光さん からの返信 2022/01/05 17:01:36
- RE: 年初からの横レスm(_ _)m
- kummingさん、こんにちは&新年おめでとうございます!
今年も浮き世離れした話題で盛り上がりましょうね!(^^)!
> 日高さんと不比等のあやしからん関係とは何ぞや??不比等がイケメンですって??
→ええ!漫画の中ではかなりのイケメン、ていうか私好み(^▽^)
> なんとしても、日高&不比等の恋ばなコミック、読んでみたいな^o^
→えっへん!ではご教示いたしましょう!
それはですね、主として秋田書店から発行されているのですが、長岡良子さんという漫画家がおりまして(最近は執筆していないみたい。2016年以降の作品を見かけたことはありません)
で、この方の「古代幻想ロマンシリーズ」(全15巻)というものがありまして。
そこにほぼ不比等を中心とした物語が描かれているのです。
その中の「天(そら)ゆく月船(ふね)」というのが、氷高と不比等の物語です。
「眉月の誓い」(4巻)もシリーズのひとつですが、これはまさに不比等の話です。
これ読むと不比等はイケメンで頭脳明晰で、ホント、カッコイイです。
私は秋田の「ボニータコミックス」というので読みましたが、文庫本サイズなので、年寄りにはツライです(字が小さい!)
「天ゆく月船」は、「古代幻想ロマンシリーズ6」に、「夢の奥城(おくつき)」と一緒に入っています。ちなみに「夢の。。。」は、天智天皇と倭皇后(やまとのおほきさき)のお話、これもステキです。
これとは別に「暁の回廊」(4巻)がありますが、これは天智天皇のお話です。
どれもこれも、私やしにあさんにとってはお馴染みのキャラが登場するので、読んでみると面白いですよ。
上代という時代の人間関係や感情表現の豊かさみたいなものにヤラレます(^_-)
何と言っても、絵がきれい。
山岸凉子でもなく、大和和紀でもなく、ましてや里中満智子では絶対にない世界が展開されています。
私長岡さんの作品は、ほぼぜんぶ読んでいます。
ブックオフでも最近は見かけないので、アマゾンで入手するしかないと思います。
それから外国編では「ナイルのほとりの物語」(11巻)があります。
これも面白いですよ。
前日光
- kummingさん からの返信 2022/01/06 19:54:57
- RE: RE: 年初からの横レスm(_ _)m
- さっそくの詳細な情報提供、恐れ入りますm(_ _)m
ここはしにあさんちなので、個別のお話は手短に。
長岡良子さん、歴史ものコミックの大家なんですね、知りませんでした。
で、Amazonで「天行く月船」\220 見つけました♪
「眉月の誓い」は全部で6巻(1は上下巻)\440×6=\2640
とりあえず、「天行く月船」購入して、あとは図書館で探してみよー
うちの図書館、なくてもリクエストすると、かなりの確率で購入してくれるし^ ^
表紙見ただけでもイケメン(に描かれた)不比等、これは見なきゃ!
この世界、ハマったら大変な事に?15巻とか6巻とか(ーー;)
それにしても、前日光家には文学と万葉集、古典、古代史、の本棚+コミックコーナーも充実しているみたいですね(*_*)
ありがとうございました♪
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
信楽(滋賀) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?






































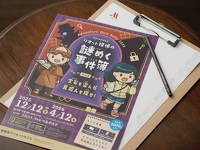





旅行記グループ 六国史の旅 元祖4トラベラー聖武天皇
10
29