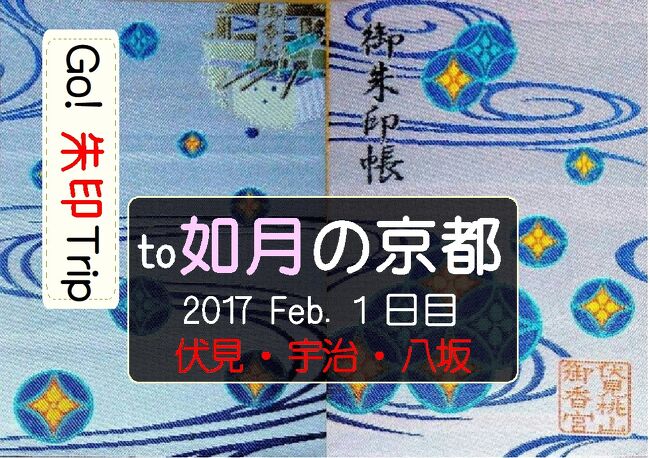
2017/02/03 - 2017/02/03
891位(同エリア1764件中)
![]()
nanochanさん
- nanochanさんTOP
- 旅行記160冊
- クチコミ2件
- Q&A回答6件
- 106,532アクセス
- フォロワー37人
この旅行記スケジュールを元に
2017年2月に仕事で京都に行き、仕事後に、伏見・宇治・東山の寺社を訪れました。
伏見の「御香宮神社」や黄檗の「萬福寺」は、以前から訪れたかった場所です。その後、欲が出て、宇治まで足を伸ばしました。素晴らしい御朱印をいただき、さらに、すごくラッキーなこともあった1日でした。
- 旅行の満足度
- 4.5
- 観光
- 4.5
- ホテル
- 4.0
- グルメ
- 4.0
- 交通
- 4.5
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 3万円 - 5万円
- 交通手段
- 新幹線 JRローカル 私鉄 徒歩
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
1<JR京都駅>
新幹線で京都に着き、JR在来線に乗り換え奈良方面へ。
新幹線から降りて一番近くのホームだから、とても便利。
まずは、仕事を頑張ろう。京都駅 駅
-
2<御香宮神社 表門>
無事に仕事を終え、寺社巡りに出発!
神社の名前に興味を持ち、最初に訪れたのは、伏見の「御香宮神社」。
この立派な門は、伏見城から移設したもの。そういえば、城の門っぽい。御香宮神社 寺・神社・教会
-
3<参道>
伏見の七名水の一つ「石井の御香水」がこの神社境内に湧き出ていて、それがいい香りだったため「御香宮」の名に。 雅(みやび)どすなぁ。
この神社は「日本第一安産守護之大神」の名もあり、安産にもご利益があるそうです。 -
4<拝殿>
拝殿は、真ん中が空いた「割拝殿(わりはいでん)」という変わった造り。正面上部にある軒唐破風には、 鮮やかな彩色の彫刻がなされていて美しい。
※画面をクリックしてみてください。 -
5<本殿(国指定重要文化財)>
左手が、1605年に家康の命により建立された「五間社流造」の本殿。
平成2年からの修理で、約390年ぶりに桃山時代の豪華絢爛・極彩色の社殿がよみがえったそうです。 -
6<御香水>
「石井の御香水」は、明治以降、涸れていましたが、昭和57年に復元され、昭和60年に環境庁より『名水百選』に認定されました。
「御香水」は、喉ごしが良く、まろやかな感じ。香りは??? -
7<御香宮神社 御朱印>
右上には、「御祭神神功皇后」の印。「御香宮」の墨書の下には「伏見御香宮神社」の大きな御朱印。
ちょうど節分だったため、日付は「節分之日」でした。 -
8<古札焼納>
この日は「燃納祭」があり、境内で古札やしめ縄などが燃やされていました。火の粉が飛んで火災が起こらないよう、鳥かごみたいなカバー付き。 -
9<酒まんじゅう>
境内で「酒まんじゅう」が売られていたので購入。
これは、地元の『京菓子司 富英堂』さんが、御香水や伏見産の酒粕等を用いて丁寧に作っている名物。
酒の香りがほんのりして、美味しかった。 -
10<JR桃山駅>
御香宮神社から5分ほど歩いてJR桃山駅へ。
京阪・近鉄とちがって、JR桃山駅は町外れにありますが、明治天皇陵・伏見城へ行くなら、こちらが最寄り駅。
ここから「萬福寺」のあるJR黄檗駅を目指します。桃山駅 駅
-
11<萬福寺 総門>
JR桃山駅から3駅。JR黄檗駅から東へ5分ほど歩くと、変わった造りの門が見えてきました。
これは、中央の屋根が高く、左右の屋根が低い牌楼式(ぱいろう)という中国式の門です。黄檗山萬福寺 寺・神社・教会
-
12<参道>
ここ黄檗宗・萬福寺は、中国僧・隠元禅師(いんげんぜんじ)が創建した禅宗の寺で、総門はもちろん寺全体が中国の明時代末期の様式で造られています。
参道も独特。高山寺で似たような石敷きの参道を見た記憶が・・・。 -
13<三門>
ここは禅宗寺院のため、山門と言わず「三門」と言います。
それには、貪(とん=貪欲)・瞋(しん=憎悪)・痴(ち=愚痴)の三つの煩悩を解脱する境界の門=「三解脱門(さんげだつもん)」という意味があるからです。
煩悩だらけの自分は、果たしてこの門をくぐれるのか??? -
14<扁額>
この三門にかかる二つの扁額「黄檗山」と「萬福寺」は、いずれも開山「隠元禅師」の書。
400年近くもよく残っていたものです。 -
15<開山堂>
煩悩だらけのまま三門をくぐり、左手に向かうと、そこは開山堂。
このお堂は、開山である「隠元禅師」を祀る場所。
白砂と周りの白壁が、ここが神聖な場所であることを示しています。 -
16<卍の勾欄>
中国風寺院の特徴の1つがこの「卍勾欄」。
シンプルでシンメトリーなデザインが美しい。 -
17<通路>
通路を通って開山堂から「天王殿」に向かいます。
足下の石の配置が独特で、ここも日本のお寺と違う感じ。 -
18<天王殿>
天王殿正面には、中国で弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化身と言われる金色の布袋様が祀られています。
日本では、七福神の一人として知られています。
布袋様に吉祥祈願をした後、奥にある「大雄宝殿」に向かいます。 -
19<大雄宝殿(だいゆうほうでん)>
「大雄宝殿」の中央に祀られているのは、ご本尊の釈迦如来。その両脇には、釈迦十大弟子のうち迦葉尊者(かしょうそんじゃ)と阿難尊者(あなんそんじゃ)の二体が祀られています。
京都の仏師の手によるもので、中国風という感じはありません。 -
20<十八羅漢>
左右の壁面には十八羅漢が安置されています。日本のお寺では十六羅漢が一般的ですが、萬福寺では「慶友尊者(けいゆうそんじゃ)」「賓頭廬尊者(びんずるそんじゃ)」が加わって十八羅漢となっています。
どの尊者も表情が豊かで、見飽きません。 -
21<卍崩し勾欄(まんじくずしこうらん)>
目の前は大雄宝殿。今いるのは、一番奥の「法堂(はっとう)」です。
ここの勾欄は、卍を崩した「卍崩し」。リズム感あるデザインです。 -
22<開梆(かいぱん)>
この魚の形をしたものは、「開梆」という木製の太鼓?です。
日常の行事や儀式の刻限を伝えるために鳴らされます。
1時間ほどいましたが、その音を聞くことはありませんでした。 -
23<雲版(うんぱん)>
こちらは、「雲版」という青銅製の鐘。朝と昼の食事と朝課の時に鳴らされます。 -
24<萬福寺 御朱印>
真ん中の墨書は、「大雄宝殿」。左下は、山号の「黄檗山」。
三つ葉葵の朱印が押されているということは、徳川家との関わりがあるのでしょう。 -
イチオシ
25<参道>
境内の参道は、正方形の平石を菱形に敷いた独特の造りで、これは、龍の背中のうろこを表しています。
黄檗山の僧侶の中で、この石の上を歩けるのは、住職だけ。 -
26<宇治上神社>
萬福寺まで来たついでに、もう少し足を伸ばすことにしました。
「宇治上神社」は、世界遺産に認定されている神社。
近くにある「平等院」は何度か来ていますが、ここは初めて。宇治上神社本殿 拝殿 寺・神社・教会
-
27<境内>
世界遺産ということで、大きな神社を想像していましたが、こぢんまりとした神社でした。
境内は人が少なく、静謐な空気が流れていました。 -
28<拝殿(国宝)・・・鎌倉時代>
拝殿は、普通の神社とは異なる2つの点があります。1つは、社殿が住宅風の「寝殿造り」になっていること。もう1つは、左右の屋根の先がさざ波のような形「縋破風(すがるはふ)」になっていること。
行かれたら、ぜひ見てみてください。 -
29<本殿(国宝)・・・平安時代後期>
拝殿の裏にあるのが、本殿。全面が格子で覆われた変わったかたち。
神社建築としては最古のもので、そのため世界遺産となっています。
ここには、「応神天皇」とその子どもの「菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)」、「仁徳天皇」が祀られています。 -
30<宇治上神社 御朱印>
宇治上神社は、知る人ぞ知る「カラフル御朱印」が頂ける神社。
季節限定のものも含めると、20種類ほどあると思います。
拝領したのは、宇治茶にちなんだ「茶加美」。 金泥がまたいい。 -
31<興聖寺>
宇治上神社から5分ほどの所に「興聖寺」があります。
この寺は、曹洞宗の開祖「道元」が初めて開いた曹洞宗最初の寺院「興聖宝林禅寺」が前身です。興聖寺 寺・神社・教会
-
32<琴坂>
宇治川に面した表門から山門に通じるまでの200m程の緩やかな参道は、春と秋には桜と紅葉が美しく、京都府の名勝となっています。
冬の今は、ただの坂道でした。 -
33<竜宮門>
琴坂を登り切ると、白の漆喰がまぶしい竜宮門があります。
この寺は、廃城となった伏見城の遺構を移設して造られたたそうで、この門の屋根もそういえば城郭風です。 -
34<この寺に来たかった本当の訳>
このお寺に来たかったのは、NHKの「京都人の密かな愉しみ」の舞台だったから。いつか訪れてみたいと思っていましたが、やっと叶いました。
「龍仁老師(伊武雅刀)」と、主人公「沢藤三八子(常盤貴子)」の母「沢藤鶴子(銀粉蝶)」とのやりとりは、本当に絶妙でした。 -
35<興聖寺 ご朱印>
曹洞宗の最初にできた寺ということで「曹洞宗初開道場」。
「高祖 承陽大師」とは、祖師の「道元禅師」のことです。
その下の大きな朱印は、三宝印だと思います。 -
36<特製甘酒をいただく>
興聖寺から京阪・宇治駅に向かって歩いていると、「あまざけ無料接待」の看板が。開運不動尊「正覚院」では、節分の福豆授与とあまざけの無料接待をしていて、境内に何人か人がいたので自分もお邪魔しました。
寒かったので、たっぷりのショウガを混ぜた特製あまざけは嬉しかった。開運不動尊 正覚院 寺・神社・教会
-
37<祇園四条>
京阪電車で「宇治駅」から「祇園四条駅」へ。
今日最後の場所は、八坂神社。
朱色の門は、夕日を浴びて一層朱く輝いていました。八坂神社 寺・神社・教会
-
38<八坂神社>
このときは、コロナの前だったので大陸のC国やK国の方々で一杯でした。聞こえてくるのは、外国の言葉の方が多いくらい。
コロナは収まって欲しけれど、過剰なインバウンドは望みません。 -
39<節分祭>
八坂神社では、節分祭として、「舞殿」で豆撒きが行われ、四花街による舞踊奉納も行われますが、残念ながらもう終わっていました。
でも、もう一つの目的には何とか間に合いました。 それは、・・・。 -
40<福引券>
それは、福豆の授与(300円)です。この福豆には、「福引券」が付いてきて、福占いができるのです。 さて、結果は・・・。 -
41<大当たり!>
やったぁ!! 103番は、京都の酒・大吟醸でした。
今年は、いいことがありそうだ・・・と、そのときは思いましたが、2017年は特に素晴らしいことはありませんでした。まあ、家内安全だったので、それが一番ですがね。 -
42<夕暮れの祇園小路>
ここは祇園の裏道。打ち水がされていました。
祇園の「花見小路」は、観光客でごった返していましたが、こちらは人通りもなく、濡れた路面とオレンジの灯りがいい雰囲気を出していました。 -
43<祇園「エルメス」>
今はもうありませんが、このときには花見小路に9ヶ月間の期間限定ブティック「エルメス祇園店」がありました。古い町家と「エルメス」の組み合わせは斬新。
もちろん、身分不相応の自分は、前を通っただけでした。 -
イチオシ
44<鴨川の夕景>
四条大橋からの鴨川の眺めです。
京都へは、年1~2回訪れていますが、コロナで県外への移動自粛の中でもう1年以上訪れていません。
外国人がほとんどいない「春の京都」をゆったりと愉しんでみたいものですが、今年はまだ厳しいでしょう。ワクチン接種が終わった秋には、「紅葉の京都」をぜひ味わえたらと思います。
「Go! 朱印 Trip to 如月の京都 2017 Feb. 1日目 ~伏見・宇治・八坂~」は、以上でおしまいです。最後までごらんいただき、ありがとうございました。
次回は、「Go! 朱印 Trip to 節分の京都 2017 Feb. 2日目」をアップする予定です。四条大橋 名所・史跡
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
伏見(京都) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?

























































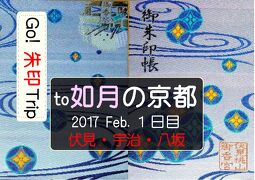
























旅行記グループ Go! 朱印 Trip 2017
0
44