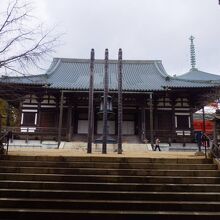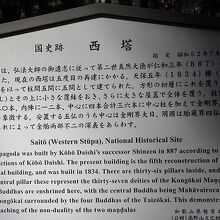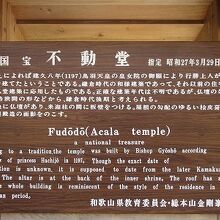壇上伽藍
寺・神社・教会
3.95
壇上伽藍 クチコミ・アクセス・周辺情報
高野山周辺 観光 満足度ランキング 4位
ピックアップ クチコミ
クチコミ・評判 4ページ目
61~80件(全786件中)
-
小ぶりで色も地味目ですが綺麗な塔
- 3.0
- 旅行時期:2021/03(約5年前)
- 0
-
五間四面のお堂
- 3.0
- 旅行時期:2021/03(約5年前)
- 0
-
お堂の四隅はすべて形が違っているのだそう
- 3.0
- 旅行時期:2021/03(約5年前)
- 0
-
-
真言密教の根本道場におけるシンボル
- 3.5
- 旅行時期:2021/03(約5年前)
- 0
-
高野山の総本堂
- 3.5
- 旅行時期:2021/03(約5年前)
- 0
-
高野山金剛峯寺の「一山境内地」の中核
- 4.0
- 旅行時期:2021/03(約5年前)
- 0
-
五間二階の楼門
- 3.5
- 旅行時期:2021/03(約5年前)
- 0
-
-
根本大塔=壇上伽藍だと勘違いしていました
- 4.0
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
把手を押して一周すると、一切経を一読したことになります
- 4.0
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
根本大塔と西塔が二基一対で密教世界を表しているんですね
- 4.0
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
快慶作の孔雀明王像がご本尊であることからこの名が
- 4.0
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
得度の儀式を行う際の准胝観音は弘法大師の作
- 3.5
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 4
-
弘法大師の「御影像」が奉られたことからこう呼ばれたんですね
- 4.0
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
あまりにも大きくて立派なのでこれが「大門」と勘違い
- 4.5
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
金色ではなかった
- 4.0
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
弘法大師が金剛峯寺の中心に据えて、さらに堂内そのものが立体の曼荼羅
- 4.5
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
見渡しても蓮が見当たりませんが?
- 3.5
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 4
-
なぜこれが国宝なの?
- 4.0
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
-
鳥羽法皇のために皇女が建立、現在は法会執行の準備室
- 3.5
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 8
-
壇上伽藍の中で最も小さなお堂
- 3.5
- 旅行時期:2020/11(約5年前)
- 3
投稿写真
基本情報(地図・住所・アクセス)
このスポットに関するQ&A(0件)
壇上伽藍について質問してみよう!
高野山周辺に行ったことがあるトラベラーのみなさんに、いっせいに質問できます。
-

夏ミカンさん
-

RON3さん
-

モモオカメさん
-

@タックさん
-

g60_kibiyamaさん
-

東京おやじっちさん
- …他




![夜歩きしてたら[壇上伽藍]の標識が…](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/tips_pict/19/52/60/650x450_19526018.jpg?updated_at=1699442464)