
2022/04/04 - 2022/04/05
6位(同エリア1222件中)
![]()
横浜臨海公園さん
- 横浜臨海公園さんTOP
- 旅行記156冊
- クチコミ812件
- Q&A回答125件
- 1,857,868アクセス
- フォロワー785人
該区間は、明治24年(1891年)11月3日開業である。
該区間内途中停車場として 松永(まつなが)驛が設置された。
該区間内に於いて隧道設置工事こそ発生しなかったが、長大橋梁として、芦田川(あしだがわ)橋梁架橋施工は当時としては大工事だった。
また、松永停車場前後の区間は連続軟弱湿地帯で泥土の為に地盤強固を必要とした。
尾道は一般周知の如く、背後に存在する山肌が尾道水道に急角度で落込み、且つ、更に狭隘な土地で住宅密集地帯である。
尾道町内に於ける鉄道敷設は困難を極めた。
即ち、該町内通過必要土地収用は予想通り折衝段階から紛糾した。
以前であれば、必要用地に対しては政府に依り一旦買収後、改めて願先に対し払下が可能だったが、明治22年(1889年)7月30日附施行の 土地収用法 に拠り、前述の如き手段に依る土地入手方が不可能になった事から、土地収用に関しては該社が直接行使しなければならなかった。
広島県内は、旧備後國、旧安芸國共に、地下水脈豊富にして水質秀逸な事から、古来より日本酒醸造が盛んで多数の醸造元が存在するが、何故か尾道のみ例外的存在で、水源僅少、且つ、水質不良を原因とする為に現在でも日本酒醸造元が存在しない該県内では珍しい地だが、然るに海岸縁鐵道設置予定地に該地に僅少な水源も存在した事から、尾道町長以下殆どの該町民が該地への鐵道敷設に対し猛反対した。
該社は、已む無く、県内松永村→山波村→尾道町北1.5km付近→栗原村に至る経路を調査測量したが、土地収用は容易な代り該経路に25/1000‰の勾配区間が発生する事が判明した。
他方、日清間は朝鮮半島権益を巡り、両国間外交関係が漸次冷却する内、明治19年(1886年)8月13日に長崎思案橋に於いて、来日中の清國海軍艦隊 定遠 鎮遠 乗組水兵達が乱暴狼藉騒擾事件を発生させ、鎮定に向かった日本人巡査が清國海軍水兵に依り殺傷された事で、我が国一般世論は清に対する危機的敵愾心が増幅された。
当時の第2代広島縣知事 鍋島 幹(なべしま みき)(天保15年(1844年)10月23日~大正2年(1913年)9月1日)(明治22年(1889年)12月26日~明治29年(1896年)4月23日在任)は、対清戦開戦に於ける鐵道軍事使用の重要性を認識していたが、反面、尾道に於ける特異性、即ち、尾道を基点とする瀬戸内諸島への発着培養地点と位置付け、鐵道線が該町内中心地通過に理解を示し、最終的に該町民に対し鐵道通過の為に土地収用を斡旋し、鐵道通過当該地住民は該社に対し土地を明渡す事に決し当該者は順次移転していったが、尾道には元来平地が僅少だった為に移転可能地は皆無に均しく、当該移転者が已む無く選択したのは山腹だった。
尾道名物の連続狭隘石段坂道脇家屋とは、要するに当該移転選択先であり、現在の居住者とは概ね当時の移転者子孫で、彼らは生活の糧として橙(だいだい)を植樹販売した。
現在、尾道が橙生産日本一たるは該歴史的背景に基くものである。
該社は尾道に於ける土地収用に難儀を要した事から、将来を見据え可能な限り複線用用地を取得したが、取得を確実とさせる為に、尾道町内に該社標入土地境界柱を多数建植したが、約130年を経過した現在でも数柱が現存する。
鐵道唱歌
第15番
浄土西國千光寺
(じょうど さいこく せんくわうじ)
寺の名たかき尾道の
(てらの なたかき おのみちの)
港を窓の下に見て
(みなとを まどのしたにみて)
汽車の眠りもさめにけり♪
(きしゃの ねむりも さめにけり)
要するに、該曲発表当時は線路下が海面だった事を示す。
該社は、明治36年(1903年)3月18日より四国連絡用尾道港-多度津港間航路が開設され、玉藻丸(223瓲)、及び、児島丸(223瓲)を就航させ讃岐鐵道との連帯運輸を開始した。
福山-松永間は10.7Kmを有し、当時は単線だった事から列車交換施設設置を決定し、大正5年(1916年)6月5日附で 水越(みのこし)驛が開設された。
但し、理由は不明だが、翌々年たる大正7年(1918年)1月1日附で 備後赤坂(びんごあかさか)驛に改称された。
松永-尾道間は9.4Kmを有し、列車交換施設増設の為に大正6年(1917年)7月13日附で 山波(さんば)信号所が開設された。
大正7年(1918年)7月10~13日に西日本地方を襲来した大型台風水害に依り、該線は福山-備後赤坂間芦田川橋梁橋脚に傾斜被害が発生した。
該区間複線化は、
福山-備後赤坂間 大正14年(1925年) 3月 9日
備後赤坂‐松永間 大正12年(1923年) 9月30日
松永-山波間 大正14年(1925年) 6月 8日
山波-尾道間 8月30日
である。
大正14年(1925年)4月11日13時24分頃、山波-尾道間神戸起点218.9km地点付近に於いて重大事故が発生した。
即ち、走行中の下り貨物第403列車60輌編成は、突然28両目米積 ワム37324貨車 第2位車軸折損の為に脱線、続く、29~32両目貨車は脱線築堤下転落大破、33~37両目貨車は脱線、38~41両目貨車は脱線転覆大破、42~48両目貨車が脱線する事故が発生したが、事故当該列車が貨物列車で、且つ、事故発生現場は尾道市住宅密集地にも拘らず、幸運にも公衆死傷者は発生しなかった。
該線使用分岐器は山陽鐵道時代に敷設された狭角度形式を継続使用していたが、C53型旅客用大型蒸気機関車導入に依る分岐器破損が多発傾向だった処、昭和6年(1931年)1月12日に該線河内驛構内で発生した列車脱線転覆事故に鑑み広角度形式交換が決定し、昭和9年(1934年)迄に現用分岐器形式に全部交換された。
大東亜戦争中に於ける該区間内空襲被害は記録上存在しない。
該区間内に於けるRTO設置駅は、
福山駅
昭和21年(1946年) 3月24日~昭和27年(1952年) 3月31日
尾道駅
昭和20年(1945年)11月 3日~昭和23年(1948年) 6月 3日
である。
昭和28年(1953年)3月21日6時35分頃、尾道駅構内に於いて重大事故が発生した。
即ち、上り貨物第962列車 D51型蒸気機関車D51896牽引貨車31両編成は該駅4番線到着後、該列車貨車15両を解放牽引し神戸方引上線に入換、該駅2番線に留置中貨車5両を連結し、6番線に1両、4番線に9両、2番線に1両を解放作業中、当駅構内土堂踏切に於いて踏切開放待機の通行人より、当該貨車残9両内4両目貨車台車軸バネ折損の事実が通報された事から、該駅当務駅長は事故貨車を解放すべく別線に入換作業中に5両目貨車 タム1418 濃硫酸積タンク車を含め突放厳禁の濃硫酸積貨車を突放した事が原因で連結時衝撃にタム1418天蓋部取付部が約10cm外れ、該部分より積載物たる濃硫酸が外部に飛散し、旅客第2番ホームに於いて上り旅客第412列車待機中の旅客15名、及び、該駅弁販売喜久屋立売従業員1名に飛散布し、当該被害者に1~4週間治療を要する劇薬性火傷を負わせた。
該区間は、倉敷-三原Ⅱ間として昭和36年(1961年)10月1日附で直流1500V電化されたが、該区間への入線は客貨共に電気機関車牽引列車に限定され、電車入線は昭和37年(1962年)6月10日附 三原Ⅱ-広島間電化時に、東京-広島間運転 特別急行 第1つばめ号151系、及び、普通急行 第1宮島号 第2宮島号153系計3往復計6本に限定され、普通列車への電車導入は昭和38年(1963年)4月1日附時刻改正時に広島運転所配置の80系使用まで全く無く、一般利用者にとって電車とは余所行きの縁薄き存在だった。
尾道市は市政制度導入以降、国有鉄道として該市内に於ける駅は尾道駅のみという全国でも稀有な存在だったが、該市内東部高須地区は、該市内尾道駅まで6Km以上在り、より至近として松永駅の利用を余儀無くさせられていたが、松永尾道双方に通じる道路が1本しか存在しない事から、道路渋滞が日常茶飯事となり地元住民から早期改善を求められていた。
尾道市は西日本旅客鉄道岡山支社に対し新駅開設に関する陳情を反復し、該新駅開設資金全額を地元負担とする事で双方合意した事で、平成8年(1996年)7月21日附で 東尾道駅が開業した。
平成30年(2018年)7月豪雨は、近畿西部地区、及び、中国四国地方に甚大被害を与えた。
即ち、6月28日から連日降雨は7月6日になり記録的集中豪雨状態となり、当該各地に於いて観測史上最大規模の雨量を記録した。
此の為に、当該記録的豪雨被害の為に該区間各地に於いて土砂崩壊、築堤崩壊、河川氾濫等々被害が続出し、山陽本線は7月6日より相生-下関Ⅱ間が不通になった。
復旧は、
福山-三原Ⅱ間 7月18日
である。
表紙写真は、
東尾道-尾道間持光寺前踏切に於ける
EF210型300番台電気機関車と山陽鐵道設置土地境界柱
山陽本線歴史的痕跡探訪記
~神戸-須磨間編 明治頌歌~
https://4travel.jp/travelogue/11342842
~神戸兵庫臨港線編~
~須磨-西明石編 明治頌歌~
https://4travel.jp/travelogue/11347902
~西明石-加古川間編 明治頌歌~
~加古川-姫路間編 明治頌歌~
~姫路-網干間編 明治頌歌~
~網干-相生間編 明治頌歌~
~相生-上郡間編 明治頌歌~
~上郡-三石間編 明治頌歌~
~三石-和気間編 明治頌歌~
~和気-瀬戸間編 明治頌歌~
~瀬戸-東岡山間編 明治頌歌~
~東岡山-岡山間編 明治頌歌~
https://4travel.jp/travelogue/11565121
~岡山-倉敷間編 明治頌歌~
~倉敷-新倉敷間編 明治頌歌~
~新倉敷-笠岡間編 明治頌歌~
~笠岡-福山間編 明治頌歌~
~福山-尾道間編 明治頌歌~
https://4travel.jp/travelogue/11717471
~尾道-三原Ⅱ間編 明治頌歌~
https://4travel.jp/travelogue/11693199
~三原Ⅱ-河内間編 明治頌歌~
~河内-西條間編 明治頌歌~
~西條-瀬野間編 明治頌歌~
~瀬野-海田市間編 明治頌歌~
~海田市-廣島間編 明治頌歌~
~廣島-宮島口間編 明治頌歌~
~宮島口-岩國間編 明治頌歌~
https://4travel.jp/travelogue/11694390
~岩國-由宇間編 明治頌歌~
~由宇-柳井間編 明治頌歌~
~柳井-光間編 明治頌歌~
~光-徳山間編 明治頌歌~
~徳山-防府間編 明治頌歌~
~防府-新山口間編 明治頌歌~
~新山口-宇部間編 明治頌歌~
~宇部-厚狭間編 明治頌歌~
~厚狭-長府間編 明治頌歌~
~長府-下関Ⅱ間編 明治頌歌
~下関Ⅱ-門司Ⅱ間編 明治頌歌~
- 旅行の満足度
- 5.0
- 観光
- 5.0
- ホテル
- 4.5
- グルメ
- 5.0
- 交通
- 4.5
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 1万円 - 3万円
- 交通手段
- JRローカル 徒歩
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
福山(ふくやま)駅
該駅は、明治24年(1891年)9月11日開業である。
該駅設置に鑑み、旧福山城内堀埋立に依り驛用地入手を可能にしたが、福山町内土地移転調整を必要とした為に、翌明治25年(1892年)3月6日附で全面竣工まで神戸方に仮設停車場を設置し取敢えず客貨取扱業務を行った。
陸軍省は、日露(にちろ)戦争(明治37年(1904年)2月8日~明治38年(1905年)9月5日)終結後に於ける帝國陸軍軍備拡張計画に拠り、福山町に 帝國陸軍第41歩兵聯隊 配置を決定し、該隊は明治41年(1908年)7月に駐屯完了し、該駅は事変発生時等々に於ける軍事動員輸送取扱業務発生時は煩瑣状態となる。
鐵道省は福塩北線と直通運転行使可能とさせるべく昭和10年(1935年)12月14日附で軌間改軌を実施させ、両備福山-横尾間路線切替に依り福山駅構内乗入が実現したが、此の為に該駅は必要拡張の都度、旧福山城址を開削活用した。
該駅は、昭和20年(1945年)8月 8日未明の福山大空襲に依り、駅本屋 上下線旅客ホーム上屋 貨物ホーム上屋 東部信号取扱所全焼の被害が発生した。
昭和40年代前半まで国有鉄道内部では該駅より笠岡駅が格上で、当時の岡山鉄道管理局内優等順位では1岡山 2糸崎 3尾道 4倉敷 5笠岡 6新見 7福山とされていたが、昭和46年(1971年)4月1日附で井笠鉄道笠岡駅乗入廃止以降、徐々に該駅が上位扱となり、昭和50年(1975年)3月10日附で山陽新幹線停車駅となり確定的となる。
現第4代駅本屋は、昭和46年(1971年)2月竣工である。
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650620福山駅 駅
-
福山駅
南口(ばら公園口)
旧駅本屋側。
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650620福山駅 駅
-
福山駅
北口(福山城口)
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650620福山駅 駅
-
福山駅
在来旅客第2番ホーム福山駅 駅
-
福山駅
在来線改札口
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650620福山駅 駅
-
福山-備後赤坂間
福山高架橋新幹線在来線分岐点 -
福山-備後赤坂間
芦田川旧橋梁接続築堤 -
福山-備後赤坂間
芦田川橋梁
左手旧初代橋梁橋台跡。 -
福山-備後赤坂間
芦田川(あしだがわ)橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。
全長301.5m(990.0ft)
(16.0m × 2連 + 22.3m × 11連 + 12.0m × 1連)
上路プレート・ガーダー桁
が架橋された。
該橋梁本体は鋼鐵製鋲締構造で、橋台は煉瓦積、橋脚は基礎部分が煉瓦積 脚部が花崗岩煉瓦積混合構造、煉瓦は全部英國積構造。
明治23年(1890年)9月15日着工、明治24年(1891年)10月竣工。
その後、該区間複線化時に、該橋梁上流側に新橋梁架橋が決定し、
上路プレート・ガーダー桁21.3m(70ft)×12連
が架橋された
該新橋梁は鋼鐡製鋲締構造で、橋台はコンクリート製、橋脚は基礎部分が煉瓦積、橋脚部が鉄筋コンクリート製である。
該橋梁は、大正14年(1925年)3月9日附で複線化され、該日より、新橋梁は上り線専用、既成橋梁は下り線専用となった。 -
福山-備後赤坂間
芦田川橋梁
該橋梁は老朽化を理由に、昭和52年(1977年)4月に、
複線型連続トラス橋梁
(52.0m×3連)×2連
に架替が実施された。 -
福山-備後赤坂間
橋台
右 大正14年(1925年) 3月 9日附複線化時設置。
左 明治24年(1891年)11月 3日開通時設置。 -
福山-備後赤坂間
橋台
煉瓦積橋台。
明治24年(1891年)11月 3日開通時設置。 -
福山-備後赤坂間
廃橋梁橋台 -
福山-備後赤坂間
門司方
煉瓦積橋台 -
福山-備後赤坂間
門司方
煉瓦積橋台 -
福山-備後赤坂間
小田川(おだがわ)橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。
5.12m -
福山-備後赤坂間
小田川橋梁 -
福山-備後赤坂間
加屋(かや)架道橋 -
福山-備後赤坂間
加屋川(かやがわ)橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。 -
福山-備後赤坂間
備後赤坂駅場内信号機 -
福山-備後赤坂間
駅構内
神戸方より門司方
俯瞰 -
備後赤坂駅
駅本屋
該駅は、大正5年(1916年)6月5日開業である。
但し、該駅は水越(みのこし)驛として開業したが、理由は不詳ながら翌々年大正7年(1918年)1月1日附を以って現駅名たる備後赤坂に改名した。
該駅本屋は相当改造されているが、大正5年(1916年)5月竣工の該駅開業当時の建築物である。
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650621備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂駅
駅構内
全景備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂駅
旅客第1番ホーム備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂駅
旅客跨線橋備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂駅
旅客跨線橋内部
古軌条支柱備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂駅
旅客跨線橋
旅客第2番ホーム取付部備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂駅
旅客跨線橋
旅客第2番ホーム階段備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂駅
広島支社リゾート用気動車
該列車は広島(呉線経由)尾道間運転だが、尾道-備後赤坂間は改回送扱。備後赤坂駅 駅
-
備後赤坂-松永間
駅構内
門司方より神戸方
俯瞰 -
備後赤坂-松永間
鍋田川(なべだがわ)橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。 -
備後赤坂-松永間
羽原川(はばらがわ)橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。
5.12m×2連 -
備後赤坂-松永間
羽原川橋梁桁
鐵道省銘板 -
備後赤坂-松永間
駅構内
神戸方より門司方
俯瞰 -
松永(まつなが)駅
該駅は、明治24年(1891年)11月3日開業である。
該駅開業当時は旅客より地元名産備後畳表、及び、当時の建築資材たる花崗岩出荷地として貨物取扱業務が多かった。
初代駅本屋は老朽化が著しい事から改築が決定し、昭和44年(1969年)4月に現第2代駅本屋が竣工し同時に橋上駅舎化された。
昭和50年(1975年)3月10日附時刻改正前まで急行列車停車駅だった。
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650622松永駅 駅
-
松永駅
南口
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650622松永駅 駅
-
松永駅
旅客第1番ホーム
古軌条支柱松永駅 駅
-
松永駅
旅客第1番ホーム松永駅 駅
-
松永駅
古軌条上屋支柱
八幡製鐡所製造
当該上屋は大東亜戦争後設置。松永駅 駅
-
松永駅
古軌条上屋支柱松永駅 駅
-
松永駅
旅客第1番ホーム松永駅 駅
-
松永駅
駅構内
該駅には大東亜戦争中まで赤帽常駐駅。松永駅 駅
-
松永駅
旅客第2番ホーム松永駅 駅
-
松永駅
旧貨物取扱施設跡
現在は車駐車場。松永駅 駅
-
松永駅-東尾道間
旧道標柱
大正2年(1913年)建立。 -
松永駅-東尾道間
旧道標柱
大正2年(1913年)建立。
現在では誰もが全く気付かぬ所に移設。 -
松永-東尾道間
小代立入川(こしろたちいりがわ)橋梁
6.66m -
松永-東尾道間
小代立入川橋梁 -
松永-東尾道間
小代立入川橋梁
煉瓦積橋台
門司方 -
備後赤坂-松永間
小代立入川橋梁桁
鐵道省銘板 -
松永-東尾道間
小代立入川橋梁付近
該区間開業当時は両側泥土沼地だった。 -
松永-東尾道間
今津川(いまづがわ)橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。
18.00m×6連 -
松永-東尾道間
今津川橋梁
上り線側 -
松永-東尾道間
今津川橋梁
下り線側 -
松永-東尾道間
今津川橋梁
橋脚 -
松永-東尾道間
今津川橋梁
煉瓦積橋脚 -
松永-東尾道間
今津川橋梁
煉瓦積橋台
門司方 -
松永-東尾道間
今津川橋梁
上り線橋梁 -
松永-東尾道間
藤井川(ふじいがわ)橋梁
12.90m×8連 -
松永-東尾道間
藤井川橋梁
下り線側 -
松永-東尾道間
藤井川橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。
12.90m×10連
上り線側 -
松永-東尾道間
藤井川橋梁
上り線側 -
松永-東尾道間
藤井川橋梁
上り線側
煉瓦積橋脚 -
松永-東尾道間
東新田(ひがししんでん)開渠 -
松永-東尾道間
東新田開渠
該付近泥土沼地大部分は明治末期に食糧増産を目的として干拓化され水耕地となる。
此の為に、真水水路として開削された。 -
東尾道(ひがしおのみち)駅
駅本屋
尾道市は市政制度導入以降、国有鉄道として該市内に於ける駅は尾道駅のみという全国でも稀有な存在である。
該市東部高須地区は尾道駅まで6Km以上在り、より至近として松永駅の利用を余儀無くさせられていたが、松永尾道双方に通じる道路が1本しか存在しない事から、道路渋滞が日常茶飯事となり地元住民から早期改善を求められていた。
尾道市は西日本旅客鉄道岡山支社に対し新駅開設に関する陳情を反復し、該新駅開設資金全額を地元負担とする事で双方合意し、平成8年(1996年)7月21日附で該駅が開業した。
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650629東尾道駅 駅
-
東尾道駅
南口
https://ssl.4travel.jp/tcs/t/editalbum/edit/11717471/東尾道駅 駅
-
東尾道駅
改札口
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650629東尾道駅 駅
-
東尾道駅
旅客ホーム東尾道駅 駅
-
東尾道-尾道間
駅構内
門司方より神戸方
俯瞰 -
東尾道-尾道間
黒崎水路(くろさき すいろ)橋梁 -
東尾道-尾道間
黒崎水路橋梁 -
東尾道-尾道間
旧山波(さんば)信号所跡
松永-尾道間は9.4Kmを有し、列車交換施設増設の為に大正6年(1917年)7月13日附で該信号所が開設された。
松永-山波間は大正14年(1925年)6月8日、山波-尾道間は8月30日に複線化された自動閉塞式導入に依り8月31日附で一旦廃止された。
然るに、尾道市中心部架橋の錬鐡桁を鋼鐡桁に更改する為に、昭和12年(1937年)9月5日附で山波仮信号場が開設され、該更改工事完了に依り昭和14年(1934年)5月16日附で廃止された。 -
東尾道-尾道間
浜田川(はまだがわ)橋梁
該橋梁は、明治24年(1891年)11月3日開通である。 -
東尾道-尾道間
防地口(さきちぐち)架道橋 -
東尾道-尾道間
防地口架道橋
神戸方
煉瓦積橋台 -
東尾道-尾道間
八幡社前(はちまんしゃまえ)踏切 -
東尾道-尾道間
八幡社前踏切参道
壱ノ鳥居 -
東尾道-尾道間
八幡社前踏切参道 -
東尾道-尾道間
八幡社前踏切旧参道 -
東尾道-尾道間
久保(くぼ)橋梁
煉瓦積構造 -
東尾道-尾道間
久保橋梁
煉瓦英國積 -
東尾道-尾道間
常称寺前(じょうしょうじまえ)踏切 -
東尾道-尾道間
常称寺前踏切付近
該地付近は該区間開通時に複線用用地を入手出来なかった事から、大正14年(1925年)複線化工事に鑑み、山肌を削る等々の難工事を要した。 -
東尾道-尾道間
長江口(ながえぐち)架道橋 -
東尾道-尾道間
長江口架道橋
神戸方
煉瓦積橋台 -
東尾道-尾道間
天寧寺(てんねいじ)架道橋 -
東尾道-尾道間
天寧寺架道橋
神戸方
煉瓦積橋台 -
東尾道-尾道間
信行寺前(しんぎょうじまえ)踏切 -
東尾道-尾道間
寺道(てらみち)踏切 -
東尾道-尾道間
持光寺前(じこうじまえ)踏切 -
東尾道-尾道間
持光寺前踏切 -
東尾道-尾道間
持光寺前踏切
山陽鐵道社標入土地境界柱 -
東尾道-尾道間
旧土堂(つちどう)井戸跡
水道完備以前に於ける尾道貴重水源跡。
大東亜戦争後、昭和30年代後半まで地元現役水源だった。 -
東尾道-尾道間
旧土堂井戸跡
尾道市民は水源不足に悩まされる生活環境を改善せんと、地元篤志家 山口玄洞(やまぐち げんどう)(文久3年(1863年)11月20日~昭和12年(1937年)1月10日)翁に依る功績に依り、大正13年(1924年)久山田水源開発、翌大正14年(1925年)に長江浄水場設置に依り、該市内上水道施設設置で該市に於ける長年の懸案たる水不足問題は解決を見る。 -
東尾道-尾道間
土堂(つちどう)跨線橋 -
東尾道-尾道間
土堂跨線橋
昭和57年(1982年)4月公開の 映画 転校生 に於いて、主役 小林聡美 が全速力でママチャリで漕ぎ登った坂橋。 -
東尾道-尾道間
尾道駅構内
神戸方より門司方
俯瞰 -
尾道(おのみち)駅
駅本屋
該駅は、明治24年(1891年)11月3日開業である。
該駅開設に鑑み、本来ならば当時の該町中心地は現在の天寧寺付近だったが、停車場設置有効収用可能地は皆無に均しく、該社は已む無く町外れの御所村海浜を大々的埋立施工に依り初めて設置可能とした。
尾道驛初代驛本屋は山陽鐵道時代に建設された為に、老朽化と狭隘さが災いしていた事から建替が決定し、昭和3年(1928年)9月に第2代驛本屋に改築された。
その後、昭和17年(1942年)2月、更に、昭和44年(1969年)4月に増築が実施された。
広島県、及び、尾道市が共同で該駅周辺再開発を決定した事から、駅改築が決定され、平成31年(2019年)3月10日附で、現3代目駅本屋が竣工した。
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650623尾道駅 駅
-
尾道駅
北口駅舎
昭和22年(1947年)7月15日開設。
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0650623尾道駅 駅
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (6)
-
- yuriさん 2023/03/15 20:48:43
- 井戸
- 横浜臨海公園さん
こんばんは。
横浜臨海公園さんはこれらの写真を
どれだけの時間をかけて撮影しているのかと
いつも思います。
手押し井戸、懐かしいです。
私が子供の頃は、まあまあ見かけたんですよね。
その頃はまだ現役な物もありました。
福山市も尾道も素敵な街だったので
また訪れてみたいと、改めて思いました。
- 横浜臨海公園さん からの返信 2023/03/16 09:36:25
- 拝復
- yuriさま、おはようございます。
掲示板にコメントを賜りまして、誠に有難うございました。
旅行記に掲載した手押しポンプは、明治期の尾道で数少ない水源跡だった所で、尾道町が鉄道通過を認める代わりに井戸として残存させた遺構です。
あの日は尾道で電チャリを借り計40キロにわたり各地を廻りました。
午後日も短くなって尾道に帰ってきた時は、足がガタガタ状態でした。
車で廻れば便利ではと言う事を仰る方が多いのですが、小生の場合、自動車進入禁止、駐車禁止の所が多く、自転車か徒歩しか手がないのが現状です!
横浜臨海公園
-
- bingoさん 2022/06/12 22:00:10
- ウチの近所。。。でした。
- 横浜臨海公園さん
こんばんは
中間地点のとある橋梁は、自宅の徒歩5分とかからない場所でした。
鉄道インフラの遅れた四国で育ったので、新幹線どころか複線電化だけでも先進的な感じがしました。恥
コロナで鉄道利用から遠ざかってますが、旅行記拝見して在来線のプチトラベルなど楽しんでみたくなりました。
JR西は、赤字ローカル芸備線の廃線を検討中です。様々なキャンペーンを催してますが厳しそうです。
bingo
- 横浜臨海公園さん からの返信 2022/07/09 10:19:14
- 拝復
- bingoさま、おはようございます。
拙稿に投票と掲示板にコメントを賜りまして、誠に有難うございました。
さて、当該橋梁がbingoさまの御自宅から至近距離との由。
当該旅行記は、福山駅のレンタサイクルで備後赤坂まで往復、尾道で」電動アシストで備後赤坂往復と云うコースで現地を訪れましたが、正直淡った段階でボロボロに疲れてしまい、次予定だった笠岡福山編作成を放棄してしまいました。
元現行そのものは神戸から新山口まで、ほぼ完成しておりますが、自裁に可燃完成まで、あと何年かかるか判りかねているというのが実情です。
横浜臨海公園
-
- ASARIさん 2022/05/11 11:33:55
- 初めまして
- この度はいいねとフォローまでしていただき、ありがとうございます。
すごく詳しく説明されてて、勉強になりました!3月にこの区間に乗車したので、その前にこちらの旅行記に出会えてたら、長い乗車時間も楽しくあっという間に過ごせていました。
名前はよく知った駅も降りた事はないので、駅舎を初めて見ました。尾道駅の北口も。
次の電車旅は冬の青春18きっぷで姫路か小倉に行こうと思っているので、横浜臨海公園様の旅行記で予習させていただきます!
なので、ちょくちょく訪問させていただきますね^ ^
私もフォローさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
- 横浜臨海公園さん からの返信 2022/05/11 12:57:22
- 拝復
- ASARIさま、こんにちは。
此の度は拙稿にお立寄りと投票、掲示板への過分なるコメント寄稿を賜りまして、誠に有難うございました。
小生、今まで言われていた事に余りに嘘が多い事から旅行記の体裁を保ちつつ、資料として活用可能な程度に仕上げております。
尾道駅北口など、知る人ぞ知る存在で、元々、廃止された尾道鉄道用の駅舎だったものを当時の国鉄と共用使用されたものです。
あの辺りの駅舎で備後赤坂駅以外、糸崎駅の昭和20年(1945年)に改築されたものが双璧だと思います。
今後とも末永く宜敷くお願い申します。
横浜臨海公園
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったホテル
この旅行で行ったグルメ・レストラン
尾道(広島) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?
















































































































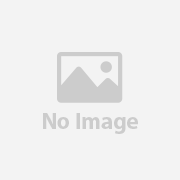
















旅行記グループ 山陽本線歴史的痕跡探訪記Ⅱ
6
100