
2015/09/21 - 2015/09/21
632位(同エリア1143件中)
![]()
ミズ旅撮る人さん
- ミズ旅撮る人さんTOP
- 旅行記699冊
- クチコミ162件
- Q&A回答23件
- 1,053,380アクセス
- フォロワー50人
2015年、開創1200年という特別な年を迎えた高野山。シルバーウィークを利用して、紀伊半島を西から東へと横断する旅行の中で、高野山を訪れました。
「弘法大師空海の手で密教の道場が開かれてから1200年目」として、春には大々的な法会も開かれました。
それらの行事が一段落した9月、高野山の人気は落ち着くどころかまだまだ参拝者でいっぱい。
山の上一体に堂宇が広がる高野山ですが、車でやって来る人が多く、早朝から大渋滞。
壇上伽藍を中心に半日かけてお参りして来ました。
伽藍の中には、みんなが笑顔になるステキなスポットがありました。
- 旅行の満足度
- 5.0
- 観光
- 5.0
- ショッピング
- 4.0
- 交通
- 3.0
- 交通手段
- 自家用車
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
高野山開創1200年記念の法会が終わったことを報告する大きな看板を見ながら、ずっと続く山道を登って行きます。
本来なら、南海電鉄の「天空」で橋本から極楽橋へ行き、そこからケーブルカーとバスで高野山を目指す筈だったのですが、残念ながら夢かなわず、車で行くことになりました。 -
途中、こんな標識を見ました。「町石道」って何?何故かお遍路さんの絵が・・・
これは「卒塔婆形町石(そとばがたちょういし)」を配した麓から高野山へ至る全長23kmの参詣道のことです。
こんな麓からもう参拝ムードが盛り上がります。 -
これが「卒塔婆形町石」です。
町石には上から「梵字」、壇上伽藍までの「町数」、寄進者の「願文」が刻まれています。
1町は約109mです。写真の町石には「37町」と見えますので、壇上伽藍までは4kmちょっとです。
補足ですが、卒塔婆とは、お墓の後ろに立っている木の板を言いますが、もともとは仏舎利を収蔵した塔(ストゥーパ)を表現したものです。
ストゥーパを日本語化したものが、卒塔婆(そとば)です。 -
「大門」です。ここから高野山に入って行きます。金剛力士像が高野山を守ります。
大門 名所・史跡
-
事前にHPから地図を入手して、駐車場の位置はわかっていましたが、壇上伽藍・金剛峰寺付近の駐車場は朝8時時点でもう満車です。すでに駐車場を探す車で渋滞が始まっています。
もう一周回ってみようかと思い、赤信号で停まっていた時です、地図に載っていない駐車場を発見しました。
砂利敷きの空き地で、駐車場の表示もわからなかったのですが、何台かの車が停まっています。係員もいないので、本当に停めていいのかもわからないまま駐車。
入口付近にこの看板を見つけました。
「神様、仏様のご利益だね。(まだ参拝していないけど)」
場所は、壇上伽藍の西の端、「愛宕前」バス停のすぐ前です。高野山高校へと曲がる、信号のある交差点の角にあるので、気にしていればわかります。
土日祝日限定の臨時駐車場です。 -
臨時駐車場のお向かいにある町石。壇上伽藍まであと3町(327m)です。
-
壇上伽藍まで歩きます。まだこの辺は車も人も少ないです。
-
高野山を形成する多数の塔頭(たっちゅう)のひとつ「報恩院」への入口です。
-
「町石1番石(慈尊院側)」です。
わざわざ「慈尊院側」と断っているので、他にも1番石があるようです。
町石はここから麓に向けて180基、奥の院に向けて36基設置されています。
当初は木製だったため、朽ちてしまいましたが、鎌倉時代に寄進によって石造となりました。 -
長い年月を経た巨木が並ぶ道の先に少し紅葉し始めたもみじが見えて来ました。
壇上伽藍の中門です。 -
壇上伽藍の中門です。この中門は何度も焼失し、2014年に8期目の中門が再建されました。
1843年に焼失して以来172年ぶりの再建だそうです。
2015年4月2日に落慶法要が執り行われました。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
中門の隣には蓮池もあります。朱塗りの橋が緑に映えます。
この橋と、中島の祠は1771年に寄進され、1996年に修復されました。 -
蓮池の周りには紅葉が植えられているので、紅葉の時期には大層美しいでしょう。
-
苔を纏った常夜灯とわずかに紅葉した葉がきれいです。
-
秋の空に新しい朱塗りの門がいいコントラストです。
-
中門に安置されている「持国天」です。
-
「多聞(毘沙門)天」です。
-
このように山門で背中合わせに四天王が立っているのは、初めて見ました。
今回の再建に当たって、前掲の「持国天」と「多聞天」に加え、後掲の2天が加えられたそうです。 -
新しい「増長天」です。前2天とは色が異なるのですぐにわかりますが、もっと異なる点があります。
胸にとまった「とんぼ」です。
どういう経緯で、こうなったのか知りたいのですが、HPにも書いてありませんでした。 -
足の下に踏まれている「邪鬼(じゃき)」です。天邪鬼(あまのじゃく)とも言います。邪鬼の手に血管が浮き出ています。
-
「広目天」です。こちらの胸には「アブラゼミ」がとまっています。何故アブラゼミなんでしょう???
個人的には四天王の中で、一番「広目天」が好きなのですが、蝉のとまった四天王なんて聞いたことがありません。
最高に素晴らしい四天王は、東大寺戒壇院の塑像です。
大仏殿の裏にひっそりとありますが、その中には天平の宝が収蔵されています。 -
金堂の前には3本の柱が立っています。真ん中の1本には紐がついていて、金堂の中に繋がっています。
これは、今年御開帳の年に当たる長野の善光寺と同様なので、本尊まで繋がっているものと思われます。
今年4月に訪れた善光寺では、この柱に触るために長い行列が出来ていましたが、高野山ではほとんど素通りでした。
有り難さを知らないのか、ご利益があるとは思わないのか、ちょっと不思議でした。 -
上部の中央から金堂に続く紐がそれです。
中に入って見ると、そのままずっと本尊目掛けて続いていました。
金堂のご本尊は薬師如来です。
秘仏ではありますが、今年の開創大法会期間中は特別に御開帳されました。
普段は厨子の中に安置されていますが、この秋はもう一度御開帳されています。期間は10月1日から11月1日です。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
イチオシ
金堂に向かって左側におもしろいものがあります。「六角経蔵」です。
ただの経蔵なら遠目に見て終わりなのですが、周りにいる人々の様子がおかしいです。経蔵から四方に飛び出した梁を押しています。なんとこの経蔵は廻せるのです。とても重いので、3人では廻りませんが、大人4人以上なら動きます。
そんな人数が必要では個人的には動かせないとお思いの方、大丈夫です。
誰かがうんうんやっていると、面白いくらい人が集まって来ます。みんな知らない人なのに、いい大人がうんせ、うんせと動かします。
上手く廻すコツは、初めちょっと上に浮かして一斉に前に押すことです。
意外と女性ががんばりますよ。若い人だけでなく、孫を連れたお年寄りまで。
一人二人では動かせないけれど、みんなで力を合わせれば、廻すことが出来る。仏教の寺らしいすばらしい仕掛けです。
廻るとみんな嬉しそうで、見ているだけでも笑顔になれます。
高野山の立ち寄り必須ポイントです。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
「山王院」。人の多い伽藍の中でも、この辺は静かな佇まいです。
壇上伽藍 寺・神社・教会
-
伽藍の中には寄贈された常夜灯がたくさん立っています。
-
「鐘楼」です。
-
西塔。木立に隠れて、ちょっと離れているので、あまり人が行かないようですが、これを見ないなんてもったいない。堂々たるものです。
ほとんど根本大塔と同じ造りなのに、人が来ないなんて侘しいなあ。綺麗に色を塗られた大塔より、こちらの方が個人的には好きです。
それにしても変わった造りをしていますね。2階部分は丸いし、1階の屋根との間に裳腰のようなものが付いているし、そもそも三重塔や五重塔は当たり前だけど、2階建てだし。
本当に「塔」なのかな?どうしてもう一方は「東塔」ではないの?
密教のお寺は普通の仏教寺院とは少しずつ違います。
調べてみると、この西塔は根本大塔と対になる塔として、建てられました(東西で対ではないんですね)。
大塔が胎蔵大日如来を本尊としているのに対し、西塔は金剛大日如来を安置しています。1834年の再建で、多宝塔様式の塔としては、日本最古と言われています。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
青い空に宝珠を捧げて立つ西塔の相輪(そうりん)。
下部の9つの輪は「九輪(くりん)」といい、五智如来と四菩薩を表します。
普通、九輪と宝珠の間には、「水煙(すいえん)」と呼ばれる飾りがあるのですが、随分と形が変わっています。 -
「孔雀堂」。鐘楼の向かいにあります。
壇上伽藍 寺・神社・教会
-
「孔雀堂」の本尊「孔雀明王」。
小さな穴から中を覗きます。新しいお堂らしく、明るいので、写真に撮れました。フラッシュはもちろん使っていません。
ISO400ですが、シャッター速度が1秒なのでブレました。ヘタクソ。
他のお堂は暗いので、撮るのはちょっと難しいです。 -
穴から中を覗きこむ姿は、隣の「御影堂」も同じ。
こちらは随分と多くの人が覗き込んでいます。
それにしても、覗き穴がたくさんありますね。正面だけでなく、側面も端から端まで。
御影堂は、旧暦3月21日に行われる「旧正御影供」の前夜、御逮夜法会(おたいやほうえ)の後のみ、一般人が外陣に入ることが許されているので、それ以外の時はここから覗いてくださいという配慮ですね。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
「御影堂」の中から読経が聞こえて来ます。それに引かれて人々が集まっているようです。
「御影堂」の周りは、金色の吊り灯篭が並んでいます。
見ていると奈良の春日大社を思い出します。春日大社の吊り灯篭は見応えがあります。
この景色も、紅葉が始まると随分と綺麗でしょうね。 -
「御影堂」の中からオレンジ色の袈裟を着たお坊様が出て来ました。先ほどの読経の主と思われます。
-
さすがに高野山の「御影堂」は大掛かりです。弘法大師の御影が祀られています。
奥の院には「弘法大師御廟」があります。「御廟」まで行かれない人はここで参拝ということでしょうか。
唐招提寺の鑑真和尚の御影堂は、本堂の裏手の静かな場所にありました。
高野山は規模の大きな寺だけあって、なんでも大きいですね。 -
「御影堂」から出て来たお坊さんの後姿。
首の後ろの襟が三角形に立っているのが「高野山風」? -
「根本大塔」。先ほどの西塔とほぼ同じデザインですが、こちらは真言密教のシンボル的存在。
中に入ると、太い柱にそれぞれ菩薩の姿が描かれているのが印象的です。
どれも新しい作品で、描かれている菩薩も一般的な仏教では聞かない名前ばかり。密教独特なのか、作家の独創なのかわかりません。ふだんは、かすれた古いものしか見られないので、これはこれで見て楽しいです。
手前左側にある松が「三鈷(さんこ)の松」です。
弘法大師が唐から帰る時に、日本での活動拠点を求めて「三鈷杵」を投げました。弘法大師の像がいつも握っている法具です。
これが、この松に引っかかっていたので、ここを拠点としたという伝説があります。
以来、参拝者はこの松の葉をお守りに拾っていくのだとか。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
「根本大塔」に入るには、入口で200円を賽銭箱に入れます。
受付があるわけでなく、監視がいるわけでなく、それでも次から次へとちゃんとお金を入れていく日本人は、やはり根っこは仏教徒なんですね。
この中は200円なら安いと思います。
古いものを見るのはもちろん意義あることですが、それらが描かれた当初はどんなだったかを、ここで見ることが出来ます。 -
ひときわ大きなお堂が「大会堂」です。その奥に東塔がありました。一つの伽藍の中に塔が3つもあるんですね。
壇上伽藍 寺・神社・教会
-
「大会堂」前です。今から紅葉の時期が偲ばれます。きっと混むだろうなあ。
-
「愛染堂」の前から「根本大塔」を臨みます。
根本大塔には、本尊の胎蔵大日如来を囲んで、金剛界の四仏(しぶつ)が配され、堂内の16本の柱には、堂本印象(どうもといんしょう)が1936〜1943年に描いた十六大菩薩が立体曼荼羅を形成しています。四隅には密教を伝えた八祖像の壁画もあります。
これらは本当に大きくて美しくて、密教の世界観を具体的に表していて、すばらしいです。
密教は、通常の仏教に比べて、仏たちの数が多く、また姿形が特異で目を引き、たいそう華やかです。
地味でたいへんな仏教より、派手で賑やかで、しかも「即身成仏」を唱える密教が流行ったのは当然でしょう。 -
「三昧堂」。たまにこうしたこじんまりとしたお堂もあります。
これは、929年に建立されたお堂で、その前の桜は西行法師お手植えの桜として「西行桜」と呼ばれています。1816年再建です。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
常夜燈と東塔。ああ、秋が深まってからまた来たい。
東塔は、当初の伽藍には無かったもので、1127年に白河院の発願により建てられました。
1843年に焼失した後、ようやく1984年に再建されました。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
寄進者の名前と金額が刻まれた石柱が並んでいます。
金300円。当時どのくらいの金額だったのでしょう。 -
壇上伽藍から金剛峰寺へと続く「蛇腹道」の紅葉は、色づいて来始めていました。
-
「蛇腹道」という名称ですが、まっすぐな道が通っています。
弘法大師が高野山を創建する際に、壇上伽藍を頭に、蓮花院までを龍が臥しているようにとイメージしたと言われ、ちょうどこの辺りが龍の腹に当たることからこの名が付いたそうです。
「蛇腹」という意味が違いました。 -
車道に出たところには「六時の鐘」という建物が建っています。
これは、1618年に豊富秀吉旗下の武将福島正則が建立しました。
現在でも午前6時から午後10時まで偶数時に時刻を知らせています。金剛峯寺 寺・神社・教会
-
高野山のもう一つの見どころ「金剛峰寺(こんごうぶじ)」の入口です。
この手前に大きな駐車場がありますが、もちろん早朝から満車で、入場待ちの車が渋滞を起こしていました。金剛峯寺 寺・神社・教会
-
総本山金剛峰寺。小さな橋を渡ってすぐに表門があり、その先に主殿があります。
-
主殿の前には、またあの柱がありました。
こちらもあまり注目を浴びているとは言い難いですが、紐が本殿の中に繋がっています。
桧皮葺の屋根の上には、「天水桶(てんすいおけ)」があります。雨水を溜めて置いて火事の際にはすぐに使えるようにしていました。
桶そのものが屋根の上にあるのは、あまり見ないと思います。金剛峯寺 寺・神社・教会
-
壇上伽藍の3柱のうち2柱に開創1200年の文字がありましたが、こちらには見られませんでした。
-
主殿の飾り。さすがにいい感じの彫り物です。
-
主殿の「大玄関」です。ここは天皇や皇族、そして寺の重職のみが使えます。
中の扁額(へんがく)に「金剛峰寺」の文字が見えます。 -
こちらが「小玄関」です。ここから見学の順路が始まります。
内部は広く、石庭などもあるようですが、時間がないので外側からだけの見学です。 -
主殿の右側に下門があります。その上部に配されていた木彫。
2羽のうさぎが波間を駆けています。とても珍しい絵柄だと思います。
由来は何か、興味が湧きます。 -
下門を出ると、右手にしゃくなげ園がありました。春には、色とりどりの花でいっぱいでしょう。
しゃくなげはブータンの国花で、「エトメト」と呼ばれます。
平成5年に訪れた時は、エトメトツアーのガイドさんにお世話になりました。
まだ、フィルム写真の時代だったので、紹介できないのが残念です。 -
下門を出て右に行くとすぐに国道に出ます。ずらっとお店が並んでいます。
左手方向が「奥の院」ですが、はるか先なので、駐車場に向かって戻ります。 -
「高野山 般若湯」これだけ読んでも何かわかりません。
実物を見ればお酒のこととわかります。僧侶は普通飲酒はご法度です。
しかし、寒さの厳しい高野山では、弘法大師によって認められていたそうで、酒とずばり言うより、「知恵」を意味するサンスクリットから転じた「般若」の文字を当てたそうです。 -
和歌山といえば南高梅。専門店がありました。
日高郡みなべ町に本店があり、南高梅の梅干はもちろん、梅酒や梅酢、梅肉を使った様々な商品を扱っています。
但し、ここにはほぼ梅干だけが置かれています。
お土産用各種は試食も出来て、気に入れば自宅用の廉価品もあります。
梅干の味の違いがよくわかって、ついついたくさん買ってしまいました。 -
「高野山大師教会」。高野山真言宗の総本部で、開創1100年記念で1925年に建てられました。本尊は弘法大師です。
高野山大師教会 寺・神社・教会
-
ようやく、開創1200年らしいものを見つけました。
春の大法会の時には、いろいろあったのでしょうか。
今回、1200年だからというものが何も無くて、ちょっとがっかりでした。 -
道すがら、木魚を抱いて寝ている小僧さんを見つけました。隣はベンチです。
-
増福院・明泉院の左の木戸です。
風情がいいので、御門ではなくこちらを撮ってしまいました。 -
「高野山霊宝館」。大正10(1921)年に開設された博物館です。
宇治の平等院を模して造られたという珍しい建物です。時間があればじっくり見たいです。高野山霊宝館 美術館・博物館
-
壇上伽藍の中門まで帰って来ました。
高野山の見学は、じっくり見るとものすごく時間が掛かります。
金剛峰寺の内部見学まではしたかったのですが、この後の都合があるので、今回は壇上伽藍だけです。壇上伽藍 寺・神社・教会
-
「こうやまき(高野槇)」と書かれた露店をいくつか見掛けました。弘法大師が花の代わりに供えたと言われ、ご仏前に供える慣習となったそうです。
神前に供えるお榊と同じですね。
同じように「高野」が付くものに、「高野豆腐」があります。これは、「凍や豆腐」「凍り豆腐」と同じもので、特に高野山原産ではありませんが、精進料理の一つですね。 -
帰りの道で見かけた看板です。スカイツリーの高さの634m地点にあります。
高野山の標高は800mくらいなので、それより高いと言いたいのでしょう。
金剛峰寺を中心に車の渋滞は半端ではなく、西から東に抜けることは諦めて、大門から下山することにしました。
この道は、上り車線は延々と車の列が続きます。
途中、やたらと人が歩いていました。どうやら、ケーブルカーの駅から歩いてきているようです。
バスは専用道路を通るのですが、途中からは一般道ですから、渋滞にはまって来られないのかもしれません。 -
道の途中には、季節柄、柿が売られていました。すごく美味しそうです。
-
国道480号線と370号線が交わる地点のドライブイン。
金剛峰寺からの車の列はここまで繋がっています。
この後、370号には車の列はなかったものの、480号の方はどこまで繋がっていたのか不明です。はなさかドライブイン グルメ・レストラン
-
南海電鉄高野下駅。曲がりくねった道路のすぐ脇に突然見えます。
開創1200年という高野山。たまたま訪れた時が、記念の年で、これもご縁というのでしょうか。
いつかまた落ち着いた頃に、ゆっくり散策したいと思います。高野下駅 駅
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
もっと見る
この旅行で行ったグルメ・レストラン
高野山周辺(和歌山) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?
















































































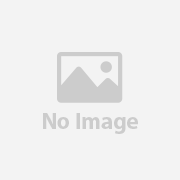












0
70