
2012/02/19 - 2012/02/19
837位(同エリア1789件中)
![]()
ドクターキムルさん
- ドクターキムルさんTOP
- 旅行記7569冊
- クチコミ134件
- Q&A回答247件
- 7,254,525アクセス
- フォロワー40人
横浜市栄区鍛冶ヶ谷2にある正翁寺は曹洞宗のお寺で本郷山正翁寺という。かつては源頼朝が創建した証菩提寺の一堂であったと伝えられている。永禄年間(1558年〜1570年)に、聖月但公和尚を開山、大谷加右衛門(大谷家元祖)を開基として創建された。2人は、永禄7年(1564年)に亡くなっているので、それより幾分か前に、寺の前身、正翁庵が開創されたと思われる。廿三世の沿革随縁誌によれば、慶長6年(1601年)に2世の鉄外和尚が、韓嶺良雄大和尚を法地開闢開山として、寺格を昇格し、寺名も本郷山正翁寺と改めたようである。
本尊様は虚空蔵菩薩で、木造の立像、雲慶作と伝えられている。雲慶とは運慶のことであろう。
また、境内裏の墓地入口には薬師如来、地蔵菩薩などの石仏が並んでいる。これらは「本郷の石仏散歩」で紹介されているという。特に、左端の石仏の右側面には「右かまくら道」、左側面には「左ぐミやふじ道」と彫られており、道標を兼ねている。近くの鎌倉街道にあったものが移設されたのであろう。
(表紙写真は正翁寺本堂)
-
正翁寺門前。
-
「曹洞宗 正翁寺」の寺号標石。
-
開基の子孫である大谷信義氏が施主となって平成5年(1993年)に建立した。寺の若い坊さん(小僧?)が450年経っても開基の家が檀家としてあるのは珍しいと言っていた。
-
正翁寺の掲示板。日曜座禅会の案内や正翁寺太陽光発電設備の紹介や萬燈供養会の案内、本覚寺萬燈供養会の案内などが掲示されている。
-
庫裡。平成3年(1991年)に竣工。
-
客殿。平成3年(1991年)に竣工。
-
本堂。鉄筋コンクリート製だ。昭和47年(1972年)に建立。
-
横の空き地の手前にある池。
-
墓地入口の石仏群。
-
地蔵菩薩。
-
石仏(貞享5年(1688年)銘)。
-
薬師如来(享和2年(1802年)銘)。「回国納経供養萬霊等」、「鍛冶ヶ谷村」などが彫られている。
-
石仏(馬頭観音(文化4年(1807年)銘))。「奉順禮西国秩父坂東百番供養塔 文化四卯年十月吉日」銘がある。
また、右側面には「右かまくら道」、左側面には「左ぐミやふじ道」と彫られており、道標を兼ねている。寺の若いお坊さんにこの道標のことを聞いたが住職がいないので分からないと言われた。郷土史研究家の柳下(やぎした)さんの講演なども行っている旨を知らせれた。しかし、JR本郷台駅周辺の道標は何基か知られているようだが、正翁寺の道標はどうだろうか?これは近くの鎌倉街道から移設されたのであろう。 -
歴代住職の墓石。左端は元禄17年(1704年)の銘がある。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
ドクターキムルさんの関連旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?


















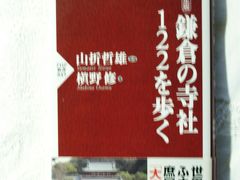




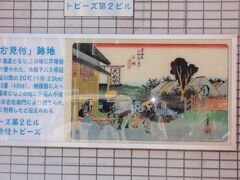












0
14