
2023/11/27 - 2023/11/27
4位(同エリア165件中)
関連タグ
![]()
たびたびさん
- たびたびさんTOP
- 旅行記850冊
- クチコミ41302件
- Q&A回答432件
- 6,960,636アクセス
- フォロワー687人
この旅行記スケジュールを元に
今日は、指宿を出発して、かつお節の枕崎から古くからの交易港、坊津へのコース。メインは、今回が初訪問となる枕崎と坊津ですが、指宿から枕崎にかけても瀬平公園、番所鼻公園、釜蓋神社といった名所があって、それなりに見どころは豊富です。枕崎の方からでも開聞岳は遠望できるので、この辺りでもやっぱり開聞岳が風景のアクセント。大洋の海の色は濃くなるし、遥かに見える開聞岳の眺めも伊能忠敬が「天下の絶景なり」と絶賛した番所鼻公園や火之神公園でも旅情を誘う趣があって、指宿辺りとはまたちょっと違う感じがしますね。
さて、まずは枕崎のこと。枕崎は鰹の水揚げが日本有数であることはもちろん、なんと言ってもかつお節の生産量が日本一というのが知られるところ。枕崎のかつお節は、江戸時代中期の宝永4(1707年)年頃、紀州の森弥兵衛がその製法を伝えたのに始まり、300年の歴史があります。かつお節は、生切り、煮熟、整形、煙でいぶしながら乾燥させるばい乾、カビ付けという工程。平均すると約3か月から長いものだと1年をかけて作られるようですが、紀州の森弥兵衛が伝えた製法はこのばい乾を基本とした技術だったのですね。そして、カビ付けは鰹節の腐敗防止と中に閉じ込められている水分を吸い出し日持ちさせるための技術。これが土佐式製法と呼ばれる土佐節の技術ですが、その技術を受け入れ、薩摩節も急速に品質が向上。寛政年間(1789~1800)には、土佐と並ぶ品質が認められるようになったということです。なお、こうしたかつお漁や鰹節製造普及の背景には、享保8年(1723)に起きた享保の唐物崩れという坊津の密貿易の徹底摘発がきっかけとなったという指摘もあるよう。密貿易に代わるものとして、かつお漁に精通する土州船を受け入れたことが商港から漁港への転換につながったというのですね。なお、出汁としての鰹節は昆布と並んだ二大調味料。水質の違いもあって西日本が昆布なら東日本は鰹節というのも知られていて、日本の食文化においては基本中の基本となりました。
ただ、今回の枕崎での一番の楽しみは、鰹節ではなくてかつお丼。枕崎お魚センターの食堂、ぶえんでいただいた朝獲れのかつおのかつお丼は感動もののおいしさ。もう一つのかつおの本場、高知はたたきが主流なこともあって、こんなのに出会ったことはないですね。これだけでも枕崎に来た甲斐があったかなと思います。
そして、坊津のこと。坊津は、中国明代の歴史書”武備志”で、安濃津(津市)、博多津と並んで日本三津として記されている古来からの港ですが、最も知られているのは鑑真の関係でしょう。天平勝宝5年(753)、7度目の航海で失明までしながらやっと日本にたどり着いた鑑真が上陸したのが坊津。ご案内の通り、その後、鑑真は大宰府経由、聖武上皇、孝謙天皇の待つ平城京に到着。東大寺大仏殿に戒壇を築き、多くの授戒を行うとともに、東大寺、大宰府観世音寺、下野国薬師寺に戒壇が設置され、戒律制度の基礎が完成します。天平宝字7年(763年)、唐招提寺で死去しますが、その功績は日本の仏教界においてはあまりにも大きなものだったと思います。
遣唐使船の時代、航路は北路、南路、南島路の三つがあって、北路は朝鮮半島沿いに進む航路で安全性が高かったのですが、天智2年(663年)の白村江の戦いで新羅との関係が悪化すると琉球を経由する南島路が開発され、その後、五島列島から一気に寧波を目指す南路の時代へと変遷します。坊津が中継地となったのは南島路の時代。702~752年の間です。また、遣明船の時代だと足利義満や有力大名、大内氏が使っていた瀬戸内航路に対して、応仁の乱以降、西軍方の大内氏と対立関係にあった足利義尚や細川氏が使ったのは土佐から坊津を経由する航路。対中国の主流の航路ではなかったと思いますが、歴史の中で何かあると使えなくはない裏ルート的な位置づけが坊津にはあったような気がします。そして、密貿易。寛永12年(1635年)に明船の入港を長崎一港とした徳川幕府の目を盗んできた坊津ですが、遂に享保8年(1723)の享保の唐物崩れにより、19人の豪商たちは逃散して坊津の貿易港としての地位は断たれることに。ただ、薩摩藩は慶長14年(1609年)の琉球侵攻により支配力を強めていた琉球との関係は生きていましたから、文化10年(1810年)、改めて、琉球王国救援の名目で琉球を経由する対明貿易が幕府から認められる。薩摩藩の長崎商法というものですが、薩摩藩の密貿易は、この正規の制度の裏側で続くことになるのですね。生糸、絹織物、薬種の輸入とその対価としての俵もの。これが幕府との競合関係となるので、一定の制限が付けられていたのですが、それを守っていては利益は出ない。財政が常態として困窮する薩摩藩があの手この手でかいくぐる。それが薩摩藩の密貿易の歴史です。いずれにしても、表立っての活動ではありませんから、あちこちで分散して行われたと見るべき。今残っている坊津の密貿易屋敷はそうしたあちこちに分散してあった拠点の一つと見るのが正しいと思います。享保の唐物崩れ以前の密貿易と薩摩藩の長崎商法以降の密貿易は別物。ちょっとややこしいところです。
坊津からは、加世田麓経由で鹿児島市へ。これでレンタカーの旅は終了。この日は鹿児島市内で泊まって、明日の最終日は、鶴の街、出水に向かいます。
-
指宿の宿を出発して、枕崎に向かうのですが、指宿市街でちょっといくつか。
時遊館COCCOはしむれは、指宿市考古博物館の愛称。指宿市街にあって、予想外に立派な建物。工事中でもその立派さはすぐに分かりました。
近くにある橋牟礼川遺跡は、縄文時代と弥生時代の前後関係を初めて学術的に明らかにした遺跡。それを考えるとこの立派さはそれに相応しいものなんでしょうね。 -
その橋牟礼川遺跡がこれ。
縄文時代と弥生時代の前後関係を初めて学術的に明らかにした遺跡 by たびたびさん指宿橋牟礼川遺跡 名所・史跡
-
縄文時代から平安時代にかけての遺跡で、縄文時代と弥生時代の前後関係を初めて学術的に明らかにしたというすごい遺跡なのだそう。それなら、国の史跡に指定されているのは当然ですね。火山灰層を挟んで、上層から弥生土器、下層から縄文土器が出土したことが決定的な証拠となったということですが、火山灰層は桜島かもしかしたら開聞岳の火山でしょうか。何でもないような遺跡ですが、こうした偶然性のようなことも考古学には必要なのだと思います。
-
指宿市街から出て、これは山川地熱発電所。白い湯気がもうもうと上がっています。
施設内ではシューシューと噴き出す蒸気の迫力がすごいので by たびたびさん山川地熱発電所展示室 名所・史跡
-
発電所の出力は3万kW。
-
1万戸分の電力を発電するということです。
-
館内に地熱発電を学ぶ展示室があって、それを拝見。
-
立派なジオラマのシアターがあって、丁寧に仕組みを解説してくれるのですが、施設内ではシューシューと噴き出す蒸気の迫力がすごいので、最終的にはそっちの方が印象は強く残るかもしれませんね。
-
指宿から枕崎に向かう国道226号線を進んでほどなく。国道沿いにあるのが瀬平公園。
ちょっとした岬の向こうに開聞岳が望めるというなかなかの眺め by たびたびさん瀬平公園 公園・植物園
-
イチオシ
公園から振り返るとちょっとした岬の向こうに開聞岳が望めるというなかなかの眺めがありました。
これは開聞岳ですけど、これが富士山なら東海道五十三次のどこかにでもあるような風景ですよね。 -
展望所のようなスペースから枕崎方面の方の眺めは
-
砂地の海岸線。
こちらもそれなりの眺めなのですが、やっぱり開聞岳のインパクトの方が強烈です。 -
そして、この辺りでは一番の名所と言われる番所鼻公園へ。名前は、薩摩藩の番所があったことからなんですが、
水平線に美しい稜線の開聞岳がどっしりと構えていて by たびたびさん番所鼻公園 公園・植物園
-
なんと言っても、伊能忠敬が「天下の絶景なり」と絶賛したという景勝地。
-
イチオシ
海のかなた、水平線に美しい稜線の開聞岳がどっしりと構えていて、この時はちょっと逆光の中、影絵のような姿でした。広島だと似島という島があって、広島港や広島市内から見るとこんな感じなんですけどね。ただ、開聞岳はどこから見てもこの形。そういう意味では富士山と同じです。
-
海の水もとってもきれい。ここまで来るとやっぱりちょっと違いますね。
-
この公園に、タツノオトシゴハウスというのがあって、そこにも寄ってみます。
-
ところで、今は11月の下旬なんですが、そんなのお構いなしで、蝉の声がやかましい。ミンミン、すごい声で鳴いていました。
-
タツノオトシゴハウスは、この先。タツノオトシゴを養殖するという変わった施設のようですね。
-
建物の二階、
-
上がったすぐは喫茶コーナー。
-
奥の方に水槽があって、
-
それがメインですね。
タツノオトシゴは、ちらりと拝見しましたが、タツノオトシゴを養殖するという変わった施設 by たびたびさんタツノオトシゴハウス 美術館・博物館
-
海を見渡すロケーションを利用したおしゃれなカフェとちょっとしたショップの方がなかなか。
一方で、番所鼻自然公園に来た人が連れ立ってどやどやとやってくるような感じ。施設の人に無遠慮な態度のおばちゃんたちもいて、もうちょっと考えてほしいなと思います。 -
では、タツノオトシゴハウスから
-
反対側の「伊能忠敬先生絶賛の地」の石碑の方へ。
-
そこから高台の方に上って、また遥かな開聞岳を眺めました。
-
続いては、釜蓋神社。
-
正式には射楯兵主神社(いたてつわものぬしじんじゃ)というようですが、
-
”釜蓋願掛け”というのがあって、
-
鳥居のところから本殿まで、この釜蓋を頭に乗せて歩きます。大きさの異なる釜蓋が用意されていて、いろいろ挑戦できるという仕掛け。私もやってみましたが、それなりに楽しいですね。
-
なお、神社は海に臨んでいて、境内からは開聞岳も海の向こうにきれいに拝めます。
-
イチオシ
ほどなく、枕崎に到着。市街のすぐ海側にある枕崎漁港です。
カツオの街、枕崎にあっては、やっぱり中心的な存在。堤防に囲まれて港内は悠々とした広さがあるし、これなら波の荒い日でも十分に防げる感じ。眺めもいいですね。 -
これならけっこう遠洋にも行けそうな漁船が何隻も停泊していました。
-
枕崎漁港の周辺には、商業施設がいくつかあって、これは南薩地場センター。
すぐそばに枕崎お魚センターというのもあって、どっちがどうなの?みたいな感じになるのですが、こちらは、地元名産のカツオの関係だけじゃなくて、お菓子類やお土産物全般を揃えたラインナップ。枕崎お魚センターは、市場の感じです。 -
で、市場に近い感覚がこちらの枕崎お魚センターです。
-
地元名産の
-
カツオ関係の商品もあれこれたっぷりあって、
-
賑やかは賑やか。
-
ただ、こうした商品は全国的も流通しているような気もするし
-
どうしてもここじゃないとダメ的な感じがあんまりしないですね。
-
品定めはちょっと面倒くさくなって、やっぱり二階にある食堂ぶえんの方へ。
-
枕崎に行ったら、絶対ここでかつお丼を食べようと決めていましたからね。
-
広々とした食堂は、まだお客さんはまばらです。
-
イチオシ
さて、期待のかつお丼ですが、
「今日は朝上がった生かつおです」と言われて、少し白っぽい脂ののったかつおです。ちょっと鰹節がまぶしてあったり、途中から山芋をかけて味の変化を楽しみますが、基本のかつおが何ともおいしいですねえ。とってもきれいなお味。そして、それが九州の甘い醤油ととてもよく合うじゃないですか。かつおで有名な高知で暮らしたことがある私にとっても、これはかつおの新境地。かつおの街、枕崎に来たなら、是非味わうべき逸品かと思います。
ちなみに、高知ではかつおはたたきが主流。刺身で食べるのもなくはないですが、刺身で食べるのは戻りかつおという時期。脂がのる時期でちょっとねっとりしたおいしさになります。つまり、かつおは本来おいしい魚ではない。それを工夫して食べる方法がたたきなんですね。たたき文化には高知名産のゆずのポン酢の存在もけっこう大きかったかもしれませんが、最近はけっこう塩たたきが流行っていたり、今でも進化が続いているような感じ。同じたたきでも、こんなにおいしかったかなあという驚きがありますね。一方、静岡もまぐろと並んでかつおはよく食べられていて、比較的刺身が多いような気がします。いろんな刺身のバリエーションの中で食べるので、マグロだけじゃなくて、かつおもおいしいよねと言った感覚だと思います。
枕崎のかつおは、どちらでもない。このさっぱりしたおいしさは、唯一無二だと思います。 -
では、ここから枕崎市街の探索。
まずは、枕崎駅です。 -
イチオシ
枕崎駅前にあるかつお節行商の像。枕崎駅がちょっとした高台にあるので、近くまで行かないと見えませんけどね。
像は、かつお節の行商をする母の姿。子供の手を引きながら頭に籠を乗せたり、かつお節の重さを測ったり。かつてはこういう姿が普通に見られたんでしょうかね。 -
これが駅舎。
-
あんまり本数もないのかな。ひと気がなくて、がらんとしています。
-
ちなみに、JR指宿枕崎線は、鹿児島中央駅と枕崎駅を結ぶ87.8 kmのローカル線。枕崎駅が終点です。しかし、鹿児島中央駅と枕崎駅間の所要時間は3時間近く。バスに比べると1時間以上多くかかりますから、利用者が限られるのは仕方ないですね。
枕崎駅には、本土最南端の始発・終着駅の碑がありましたが、ちょっとややこしい。本土最南端の駅だと西大山駅ですからね。 -
イチオシ
少し離れた場所にある「日本最南端の終着・始発駅 枕崎」灯台モニュメント。
これも枕崎では、ちょっとしたシンボルになっていると思います。 -
枕崎観光案内所は、そのモニュメントの隣り。モニュメントもそうですが、枕崎駅からは微妙に離れている場所なのでちょっと分かりにくかったです。
-
建物はそれなりにしっかり。入ってすぐの正面にはカツオのデザインもあって、いろいろ枕崎をアピールしています。
-
駅から歩いて行ける範囲にある枕崎市文化資料センター南溟館は、枕崎駅の南東側です。
-
山の上にあって、少し離れた場所からでも見えています。
-
枕崎市の美術館ですが、敷地内の芝生には現代アートの作品がいくつかあって、雰囲気的には現代アートの美術館ですね。山の上にあって見晴らしもいいし、開放感もありますね。
-
枕崎市かつお公社は、株式会社みたいですから民間の施設かな。
-
かつおのたたきや刺身の冷凍食品がメイン。
-
全体的には食品スーパーみたいな感じですが、「シビ(キハダマグロ)」「鰹腹皮」とかあんまり目にしたことがない商品名があって面白いです。
-
そして、これが薩摩酒造明治蔵。
鹿児島を代表する芋焼酎「さつま白波」の醸造所ですが、それが枕崎にあったというのは知りませんでしたね。強烈な匂いのする焼酎はかなりのインパクトがあって、お湯割りにしても九州以外の人だとなかなか馴染めない人も多いかも。私も始めはなかなか馴染めなくて、かなり苦手だったのを思い出します。 -
建物に入ると
-
見学ルートがしっかりあって、
-
メソポタミア発祥の蒸留器、さつまいもは中南米から。それらが日本に伝わって、芋焼酎が出来上がるという流れ。
-
ただ、さつまいもも焼酎の製造技術も直接的には沖縄からなんですけどね。
-
ところで、日本酒の製造は、米を糖化する醗酵と糖化した糖をアルコール発酵させるダブルの醗酵を同時に行うというのが世界でもまれな高度な技術。焼酎は蒸留酒ですから、大雑把に言えばその製造技術はそうした高度な技術ではないはずなんですが、しかし、そうは言っても伝統の技はいろんなところにあるんでしょう。
-
いろんなタイプの蒸留器や
-
仕込みを行った桶の類も
-
製造技術を高めるための試行錯誤の歴史を
-
物語るものだと思います。
-
通路の脇にずらりと並んだ仕込み甕もけっこうな迫力です。
-
と、こちらを
-
奥に進んで行くと
-
先ほど外から見えていた
-
展望塔ですね。
-
敷地内に立ち並ぶ建物が壮観です。
-
再び、順路に戻って
-
蒸留器や
-
現役の桶や
-
桶から
-
イチオシ
仕込み甕のエリアも拝見して、終了。
-
販売所の方に帰ってくると
ジョコのコレクションも -
こんなにたくさん。
ここまでくるとジョコって鹿児島の文化そのものではないかと感じます。 -
ショップの方は焼酎を中心に
-
枕崎のお土産物も置いていて、けっこう充実。多くの観光客がやってくることを想定した内容ですね。
-
最後にこちらで少し休憩させてもらいました。
-
ここから、枕崎の郊外にある火之神公園を訪ねます。
枕崎市街からだと真南に進んだ岬の先。山幸彦が旅の途中でここに立ち寄ったという神話があって、それが火之神の由来です。 -
駐車場から公園に入ると途端にこの眺め。芝生の広場の先には、ここでも開聞岳が見えています。
-
イチオシ
見どころは立神岩という情報でしたが、沖合遥かに望む開聞岳が素晴らしい。胸がすくような爽快感がありますね。今朝見た番所鼻公園の眺めも、逆光じゃなかったらこんな風にすっきりとした美しさだったかもしれませんね。
-
傍らには火之神公園キャンプ場。こうして正面はるか沖合に開聞岳を望む海原に、松林をバックにした美しい芝生の広場があって、その一帯。キャンプ場にしてはこれ以上ないロケーションかも。キャンプ場にはちょっともったいないくらいですね。
-
開聞岳を左手に見ながら、海沿いにもう少し進んで行くと
-
岬の先に見えて来るのが立神岩。沖合にそびえる岩で、高さは42m。
-
さきほども触れたとおり、火之神公園のシンボルともされているようですが、沖合に見える開聞岳と比べるとインパクトはイマイチかなという印象です。
-
では、枕崎を後にして、いよいよ坊津に向かいます。
坊津に到着して、まずは坊津歴史資料センター輝津館へ。坊津の市街から少し北に向かった湾を見下ろす高台にあって、小さな町にしてはかなり立派な建物です。 -
歴史ある坊津の交易資料や地元の文化を象徴する仏教関係のものということで龍巌寺絹本著色八相涅槃図(国の重要文化財)が特別公開中でした。
-
一方で、鑑真の関係は年表があるくらいで、ちょっと期待外れかな。
残念ながら展示室内は撮影禁止です。 -
ほか、建物のバルコニーからはこんな風に坊津の港が見下ろせまして。
坊津が周囲を山に囲まれた美しい港であることが分かります。 -
イチオシ
坊津歴史資料センターから集落の方に戻って、少し高い場所から海を臨む市街全体を改めて眺めます。正面の左手が海につながっているのだと思いますが、海がかなり奥に深く入り込んでいるのでぐるりが山に囲まれる地形になるんですね。確かにこれほどの天然の良港はめったにないような気がします。
-
では、港の方へ降りてみましょう。
-
船だまりは静かな雰囲気。
密貿易の商業港からかつお漁の漁港へと転換したのは江戸の前期。遥か昔のことですからね。 -
密貿易屋敷跡も訪ねるべく、八坂神社の近くという情報を頼りに向かいましたが、看板も何もなくて、結局、近所の方に尋ねてやっと分かりました。自分で探すのはちょっと無理だと思います。
-
外部を警戒する見張りの構造とかもあるようですが、外観からはよく分からず。門の辺りがちょっと雰囲気があるかなあというくらいです。
-
奥の方にある一本の細い路地。石畳の立派な通りで、これも密貿易で羽振りがよかったころの遺構ということでした。
ただ、冒頭に書いた通り、密貿易には二つの局面があって、これらは薩摩の長崎商法の時代のものではないかと思います。 -
なお、密貿易屋敷を探す頼りにした八坂神社はこれ。
-
周囲はすぐに海という場所でした。
坊津歴史資料センターの鑑真関係が薄かったので、ここから鑑真記念館にも足を延ばしたいところなんですが、ここからさらに15㎞も先の場所。これから鹿児島まで帰ってレンタカーを返さないといけないので、やっぱり無理。途中に加世田麓に寄るくらいがせいぜいです。 -
坊津から、加世田へ向かって。
この竹田神社は、島津氏中興の祖とされる島津忠良を祀る神社。島津忠良の菩提寺である日新寺がここにあったのだそうですが、神社の方だけが残ったという形ですね。 -
ちなみに、この島津忠良というのは、島津氏の分家、伊作氏の出身。忠良の嫡男、島津貴久が第14代当主、島津勝久の養子に入って島津氏第15代当主となり、16代当主、島津義久は薩摩・大隅・日向の三州を統一するという流れです。
本来は分家筋が宗家を乗っ取ったという見方もできなくはないのですが、その後、島津家が発展したのも事実。小さな事にはこだわらなくてもいいでしょう。 -
ただ、境内はけっこう荒れていて、駐車場もなし。意外に訪ねにくい神社です。
-
そして、これが加世田麓。鹿児島県では、知覧、出水、入来と並んで国の重要伝統的建造物群保存地区となっています。
-
ただ、こちらの特徴は、明治時代以降の文化遺産である民家や近代和風の住宅、洋風医院建築などが多数含まれていること。また、用水路に架かる石橋を渡って武家門をくぐる景観があること。
しかし、一本筋が違うと全然違った風景で、ここはかつての街道筋の緩く曲がった通り。 -
石造りの塀や見事な生け垣の続く通りで、一風変わった風景でした。
-
ついでに、道の駅 きんぽう木花館にも寄ってみます。
-
道の駅としてはちょっと小規模かな。産直のコーナーもややこじんまり。地元の特産品なのでしょうか。新そばのコーナーがあって、それはちょっと目立っていましたが、逆にそれくらいという感じです。
-
鹿児島市に戻って、レンタカーを返した後は、晩飯。
六白亭で黒豚のとんしゃぶをいただくことに。 -
イチオシ
鮮やかな色合いの豚肉のスライスに
-
野菜もたっぷり。
-
こうして食べるとんしゃぶがおいしくないわけはないのですが、
-
それでもこの芳醇で豊かな味わいは期待以上ですね。ポン酢と柚子胡椒で変化を付けたり、
-
最後のラーメンの締めなんかも抜群のおいしさ。
レンタカーの長旅の疲れがこれで一気に吹っ飛びました。 -
妹は先に帰ったので、ここからは一人。今日の宿のグッドイン鹿児島は、鹿児島中央駅の裏側すぐ。駅にこれだけ近いのに、値段はリーズナブル。裏側でも何の問題もないですね。
さて、明日は鶴の街、出水。早朝に鹿児島中央駅を出発です。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
もっと見る
この旅行で行ったグルメ・レストラン
枕崎(鹿児島) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?































































































































































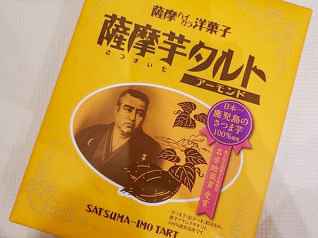




0
119