
2023/10/04 - 2023/10/04
33位(同エリア290件中)
![]()
akikoさん
- akikoさんTOP
- 旅行記435冊
- クチコミ9件
- Q&A回答2件
- 1,378,139アクセス
- フォロワー348人
この旅行記のスケジュール
2023/10/04
-
電車での移動
JR大阪駅(9:16発)ー 堅田駅(10:08着)湖西線経由敦賀行き 新快速
-
バスでの移動
堅田駅(10:15発)ー 佐川美術館(10:30着)琵琶湖大橋線 佐川美術館行
-
バスでの移動
佐川美術館前(12:45発)ー 今堅田出島灯台(12:54着)琵琶湖大橋線 堅田駅行
-
徒歩での移動
今堅田出島灯台 バス停から徒歩で約10分でR cafe at Marinaへ
-
『R cafe at Marina』でアフタヌーンティー
-
徒歩での移動
R cafe at Marinaから歩いて10分ほどのところにある「浮御堂」へ
-
浮見堂(満月寺)訪問
-
バスでの移動
「堅田出町」バス停 (15:45発)ー 堅田駅(15:55着)
もっと見る
閉じる
この旅行記スケジュールを元に
"ガウディ&サグラダファミリア展"は、今年、東京会場に続き滋賀・佐川美術館で現在開催されています。佐川美術館は琵琶湖のほとりにあり、“水に浮かぶ美術館”として有名で、前から訪問したいと思っていました。今回、ガウディ展が企画展示として来ると知り、絶好の機会だと思い訪ねることに...。
この日は、幼なじみの友人とこの展覧会を訪れ、その後、近くに『R cafe』の姉妹店があることを知り、ハワイの雰囲気を感じたくて訪問。その続きで、かつて広重の "近江八景" にも描かれたという、琵琶湖に浮かぶ『浮御堂』へ、そして"幸福を呼ぶ石"という霊石がある伊豆神社へも足を延ばしてきました。
- 旅行の満足度
- 4.5
-
東京国立近代美術館で、"ガウディとサグラダ・ファミリア展" が6月13日から9月10日まで開催され、引き続き琵琶湖湖畔にある『佐川美術館』で9月30日から12月3日まで開催されています。
以前から注目していたガウディとサグラダファミリアに関するイベントが、ずっと訪れてみたいと思っていた佐川美術館に企画展としてやって来ると知り、とても楽しみにしていました。
この日、JR大阪駅で友人と待ち合わせ、大阪駅から京都駅経由、湖西線で「堅田駅」へ。その後バスで「佐川美術館前」まで乗車し、徒歩すぐの佐川美術館にやって来ました。
<ガウディとサグラダ・ファミリア展>
◆場所:佐川美術館
滋賀県守山市水保町北川2891
◆会期:2023年9月30日[土]~12月3日[日]
◆開館時間:午前9時30分~午後5時
◆休館日:月曜日(10/9は開館)、10/10、11/28
◆入館料:一般¥1,300 事前予約要
※当初、ここに展覧会のポスターを使用しましたが、著作権の関係で差し替えました -
比叡山・比良山を望む琵琶湖の畔にある美術館。佐川急便が創業40周年記念事業の一環で、琵琶湖を望む美しい自然に囲まれた地に1998年3月に開館。
敷地には、和の印象を重視し切妻造の2棟からなる本館と、樂吉左衞門館の地下展示室並びに茶室があり、それらを取り囲むように水庭が配置され、周囲の風景と一体感ある美しさを醸し出しています。
この美術館には日本画家の平山郁夫氏と彫刻家の佐藤忠良氏、陶芸家の十五代樂吉左衞門氏の作品が常設展示され、併せて企画展も随時開催。 -
バス停からすぐのところに入館ゲート(受付)があり、事前にWEB予約した二次元コードを見せて中に入りました。
-
この日は曇りがちで、水辺もちょっとどんよりカラーでしたが、和のテイストを活かしながらコンクリートや鉄柱などの洋の要素もうまく取り入れられた建物の、水際の通路を歩いてエントランスに向かいました。
-
通路から水庭を望む風景。下の像は佐藤忠良作「エゾシカ」。
-
エントランス前まで進んできました。奥に樂吉左衞門館の茶室が!
-
エントランスホールです。手前の模型はガウディが設計した「ニューヨーク大ホテル」のレプリカ。ガウディはこのようなホテルも設計していたんですね~ まるでサグラダファミリアの一部のように感じられました。
※1908年にバルセロナを訪れたアメリカ人がサグラダ・ファミリア聖堂を訪れ、ニューヨークに建設する高層ホテルを依頼。この石膏模型は1980年代に日本でガウディ展が開催された際、建築家の石山修武氏を中心につくられたものなのだとか。 -
"ガウディ&サグラダファミリア展"の巨大ポスター看板
この企画展の趣旨は、チラシに次のように書かれていました。
"スペイン、カタルーニャ地方のレウスに生まれ、バルセロナを中心に活動した建築家アントニ・ガウディ。バルセロナ市内に点在するカサ・ビセンス、グエル公園、カサ・バッリョ、カサ・ミラ、サグラダ・ファミリアなど世界遺産に登録された建築群は、一度見たら忘れることのできないそのユニークな造形によって世界中の人々を魅了し続けています。
ガウディの独創性は、西欧のゴシック建築やスペインならではのイスラム建築、さらにカタルーニャ地方の歴史や風土など自らの足元を深く掘り下げることで、時代や様式を飛び越える革新的な表現に到達したことにあります。
今回開催されるガウディ展は、長らく「未完の聖堂」と言われながら、いよいよ完成の時期が視野に収まってきたサグラダ・ファミリアに焦点を絞り、この聖堂に即してガウディの建築思想と造形原理を読み解いていくものです" -
これは2014年5月にバルセロナを訪れた時に撮影したサグラダファミリア聖堂です。ポスターの写真(2023年1月撮影)を見て、9年の経過が感じられました。
2014年の時点では、ガウディ生誕100周年にあたる2026年に聖堂は完成すると聞いていましたが、コロナ禍で工事がストップ。来る、ガウディ生誕100周年の2026年には、最後のイエスの塔はできるそうですが、最終の完成はもう少し先になるとのことです。 -
エントランスホールには、常設展示されている彫刻家の佐藤忠良氏の作品も展示。とても動きのあるユニークな女性像で、企画展を観たあとで常設展も立ち寄ることに!
-
水庭を右手に見ながら回廊を進みます。
-
通路を右折したところで、コーヒーショップに向かって水庭をパチリ!
水庭を真ん中に回廊ができているような景観で、まさに"水に浮かぶ美術館"だと実感! -
奥にある特別展示室で行われていた"ガウディとサグラダファミリア展"の【展示構成】は次の4つに分けられていました。
第1章 ガウディとその時代
第2章 ガウディの創造の源泉
第3章 サグラダ・ファミリアの軌跡
第4章 ガウディの遺伝子
以前にバルセロナを訪れた時に、ガウディのこと、サグラダファミリア聖堂のことは調べたことがありましたが、今回は、ガウディの建築論を描き留めた学生時代からの自筆のノートや、バルセロナ建築学校在学中に制作した大変詳細で美しい図面などを目にすることができ、学生時代から秀でた能力を持ち合わせていたことがとてもよくわかりました。
ガウディの残した言葉の中で印象的だったのが、「人間は創造しない。人間は発見し、その発見から出発する」というもの。「自然は私の師だ」と言うガウディは、徹底した自然観察を行ない、造形の原理を発見していったのだそう。今年のNHKの朝ドラ「らんまん」の主人公、牧野富太郎博士と幼少期に重なる部分があるとも感じました。
幼少期にリウマチを患っていたガウディは友達と遊ぶこともままならず、ひとりで周りの自然や周囲の生活を観察して過ごしていたそうです。ガウディの当時の絵はすでに驚くほど精緻でリアルだったらしく、この幼少期の時間がのちの建築家ガウディのためにとても重要な時期となったのだそうです。 -
16歳の時に、故郷を後にして建築家の勉強をするためにバルセロナへ。建築専門学校入学の準備を始め、21才の時バルセロナ建築専門学校に入学。いろいろな建築現場でアルバイトをしながらの学生生活だったそうです。
でも、このアルバイトによって建築現場を知る貴重な経験を積みましたが、学校の出席率が低く、学校の成績はとても悪かったとか。でも図面の表現力は誰もが認めるほどズバ抜けていて、建築家としての素養は非常に高く評価されていたんだそうです。図書館にも入り浸り、ギリシアやローマ建築、カタルーニャゴシック、ムデハル等の様々な知識を蓄えていたことが、以後のガウディ建築に生かされていったとか。
これは第1章に関わるほんの一部だけで、他に初めて知ったことがたくさんありました。展示室は撮影不可で、もっといろいろ知ったことを紹介したいのですが、スペースもなく、展覧会の詳しい内容は次のウェブサイトに詳しく書かれていましたので、よかったらご覧ください。
■公式サイト:https://gaudi2023-24.jp
■東京国立近代美術館「ガウディとサグラダ・ファミリア展」:https://www.momat.go.jp/exhibitions/552 -
"ガウディとサグラダファミリア展" を鑑賞し、より詳しくガウディ建築やサグラダファミリア聖堂のことを知ることができました。完成した暁には、是非ともそのガウディの哲学や理論がぎっしり詰まった、集大成としての聖堂の姿を見に行きたいと改めて強く思いました。
ところで、この像は、水の庭に佇む、佐藤忠良氏による「冬の像」です。
このあと、この像の作家である佐藤忠良氏の常設展示コーナーに立ち寄りました。彼の作品は、人を見つめ、その一瞬の表情を作品としてきたリアリズムの世界が特徴。エントランスホールに展示されている女性像も動きの一瞬を捉えたものでダイナミックさが感じられました。あと、子供のころ読んだ「おおきなかぶ」という絵本の絵を描いたのは、佐藤忠良さんなんだそうです。 -
もう1カ所、陶芸家の樂吉左衞門氏の常設展示室へも行きました。樂吉左衞門館は水庭に埋設された地下展示室と水庭に浮かぶ茶室で構成。
そこに向かう通路から見える水庭には、琵琶湖周辺ではよく見られるヨシがこのように茂っていました。右下のプールのような水盤は、地下の明かり取りになっていたのでした。 -
樂吉左衛門展示室に向かう通路です。展示室は地下にあり、この先にある階段を下りていきました。
-
これは、地下ホールから階段を見上げたところ。
-
奥の明るいところには、先ほど見たプールのような水盤から光が届き、光の壁ができていました。
-
その反対側は茶室への導入として枕木などが並べられ、落ち着いた空間になっていました。
奥にある展示室には千利休も好んで愛用したとされる『樂焼』の茶碗をつくる樂家の当主 十五代樂吉右衛門氏の作品が展示されていました。ささっと見ただけでしたが、渋い色目の焼貫黒樂茶碗や黒樂茶碗、茶入、水指などの作品が展示されていました。
なお、茶室は別料金で予約も必要だということで、今回はパスしました。 -
佐川美術館で2時間ほど過ごし、次にやって来たのは『R cafe at Marina』でした。
美術館前からバスで「今堅田出島灯台」まで行き、そこから歩いて約10分。とてもわかりにくい道を歩いてようやく到着!お店はヨットハーバー・レークウエストヨットクラブの2階にありました。 -
『R cafe』といえば、昨年9月に近江舞子そばのハワイアンカフェにも行き、とても気に入りました。今回、同じ系列のお店が佐川美術館の近くにあると知り、ぜひ訪ねてみたいと思い、友人とやってきたのでした。
-
このお店はグリーンを基調とした色合いの建物内にあり、2階の窓から琵琶湖が見えるようになっていました。
紺色の螺旋階段を上っていくと... -
このような可愛いカフェが現れました。この時はランチタイムで多くの人がいたので、この店内写真はHPからお借りしました。
-
お店に入ったところに、ハワイの香りがする小物類やこの地に関係する琵琶湖パール、紅茶専門店の紅茶、モザイクタイルのコースターなどが並べられた販売コーナーがありました。
-
入るなりいきなりですが、一部、写真を撮らせてもらったのでした。
-
オーシャンリゾートが感じられる可愛い置物や壁掛けグッズ♪
-
キッチンも素敵でした♪
-
カウンター席は、マリーナ横の広場と琵琶湖が見渡せる特等席。
-
琵琶湖に面した広場からその背景に広がる琵琶湖の景色.:*☆*:.
対岸には山々が連なっていて、近江富士と呼ばれる三上山も見えていました。 -
テーブルの上に、「店内から見える対岸」のマップが置いてあって、友人と景色と見比べながらそれぞれの場所を確認していきました^ ^
-
青空だったら、もっと綺麗だったんでしょうね~
-
カウンターテーブルは青のモザイクタイルが敷き詰められていて、カモメの置物やカラーサンドが入った瓶、ヒトデなどがオシャレに飾られていたのでした。
-
さて、ランチのことですが、滋賀県産の野菜が使われたサラダバー&近江牛のローストビーフ、近江牛のビーフシチュー、パスタなどのランチも美味しそうでしたが、やはり『R cafe』といったらパンケーキが魅力的で、「フルーツたっぷりのパンケーキ」と「まるごといちじくパンケーキ」をオーダーすることに!
-
これが「フルーツたっぷりのパンケーキ」で...
-
これが「まるごといちじくパンケーキ」でした。
-
二人でシェアして食べたのですが...
「フルーツたっぷりのパンケーキ」はフレッシュなフルーツと甘さ控えめのホイップクリームとバニラアイスが添えられ... シロップもつけて食べると、期待通りのお味~.:*☆*:.
そして「まるごといちじくパンケーキ」は、見た目にもパンケーキの部分がいちじくのようで、半分にカットすると、いちじくがまるごととソースが入っていたのでした。溶けたバニラアイスと一緒に食べると、これまた美味!旬のいちじくもとっても美味しかったです。 -
場所が変わって、『R cafe』のあるマリーナから、湖岸沿いの昔の鄙びた町並みの地道を通って浮御堂にやって来ました。入口には立派な双松が!
-
入口に建つ楼門は、下部に漆喰塗りの袴腰がつく、いわゆる竜宮造の形式なんだとか。
手前の石碑には「浮御堂」、両脇の柱には「名所 堅田落雁」「海門山 満月寺」とありました。"浮御堂"は通称で、正式名は"海門山 満月寺"なんだそうです。 -
楼門上部はこの通り立派な造りで、扁額には「海門」と書かれているのでしょうね。
-
楼門を抜けたところに、説明板があり、 次のように書かれていました。
"近江八景 「堅田の落雁」で名高い浮御堂は、寺名を海門山満月寺といいます。 現在の建物は昭和12年の再建によるもので、昭和57年にも修理が行われ、昔の情緒をそのまま残しています。 境内の観音堂には、重要文化財である聖観音座像が安置されています"
"近江八景「堅田の落雁」"とは、歌川広重の描いた近江八景「堅田の落雁」のことで、「落雁(らくがん)」とは、雁が一列に連なってねぐらに舞い降りる様子を表わす言葉。琵琶湖につき出すように建てられた堂宇が、湖に浮いているかのように見えることから名付けられたんだそうです。下の絵がその様子が描かれた「堅田の落雁」です。 -
滋賀県の面積の実に6分の1を占めるという琵琶湖。その琵琶湖がいちばんくびれた部分のそばにある満月寺。
今から1000年ほど前、比叡山の恵心僧都が比叡山から琵琶湖を眺めて景色の良い所、そして琵琶湖の対岸まで距離が短いところにあるということで、湖上安全と衆生済度のため、湖上に仏閣を建立、浮見堂に自ら刻んだ千体の阿弥陀さまを奉納したのが始まりだそうです。(地図はJR堅田駅にある説明板:琵琶湖とその水辺景観 一祈りと暮らしの水遺産より) -
拝観受付で300円を納め、参道を進むと「観音堂」がありました。
この観音堂には、重要文化財である木造聖観音坐像(秘仏)が、そしてその左に十一面観音像と右に薬師如来像が安置されていました。また西国33カ所札所の観音像も並んでいました。
堂内は"撮影禁止マーク"があったので写真はないのですが、公式サイトの中の「動画」では天井に90枚の美しい花の絵がある様子が紹介されています。もし花絵に興味があれば、動画を早送りして天井画を見てくださいね。
公式ウェブサイト:https://www.otsu10shaji.jp/ukimido/ -
観音堂のそばに秋の花のキキョウが咲いていてパチリ!後方に白のキキョウもありました♪
-
参道を進むと、松の立派な大木の先に...「浮御堂」がちらっと見えていました。
-
浮橋を進むと、見たかった「浮御堂」が姿を現しました。
※以前の堂宇は1934年の室戸台風で倒壊、現在の堂宇は1937年の再建、1982年改修なんだそうです。 -
浮御堂内部には「千体阿弥陀仏」が祀られていました。かつて恵心僧都が湖上安全と衆生済度のため湖上に仏閣を建立し、千体の阿弥陀さまを奉納したそうですが、これがその千体阿弥陀さまのようでした。
-
お堂は、ぐるっと回廊を一周出来るようになっていました。左に棒のようなもの見えていますが...
-
これは高浜虚子の海上句碑でした。珍しいですよね!
「湖も 此辺にして 鳥渡る」という句だとか。 -
浮御堂は、江戸時代に桜町天皇より京都御所の能舞台を下賜され移築したものだそうで、今でも能舞台のようなところが湖面に迫り出していました。
かつては琵琶湖に舟を浮かべ、能舞台を鑑賞していたんだそうです。 -
北方を望むと、遠くに琵琶湖大橋が見えていました。
-
迫り出した舞台の反対側
-
友人が、「ここから写真を撮ると、面白い写真が撮れるよ」と声をかけてくれました。広い湖面には空が映り込み、ウユニ塩湖?、それは言い過ぎですが、確かに映り込んだ曇が面白い写真になっていました。
-
回廊を進むと...
-
石垣できれいに整備されている境内南側が見えていました。
-
境内南側に移動し、湖畔に立つ「芭蕉句碑」のところへ。
元禄4年の中仲秋の名月の翌日、十六夜にお月見をし詠んだ句:
「鎖あけて 月さし入よ 浮み堂」
"澄み渡る十六夜の月が湖上に銀の波を散らして素晴らしい夜景だ。 寺僧よ、堅く鎖を下ろした浮御堂の扉を開けて、あの月光を堂内に差し入れよ"という意味なんだそう。 -
イチオシ
そしてその句碑のあたりから見る浮御堂は、一番美しく見えました。
-
浮御堂をズームアップ
この"浮御堂"は、当初、来る予定にはしていなかったのですが、『R cafe』 の位置を確認するために見た地図に、徒歩圏内でこの"浮御堂"があったので訪ねてみたのでした。歴史的にも有名な一休和尚、芭蕉、一茶、広重、北斎なども訪問し、詩歌や絵画を残したところでもあるらしく、たまたまでしたが来てみてよかったです。 -
浮御堂から堅田駅までバスで帰ろうかと歩いていると、「伊豆神社」が見えていたので、「行ってみよう!」となりました。
この神社は、中世、琵琶湖の水運に絶大な特権をもっていた堅田の総鎮守で、室町時代には堅田大宮と呼ばれていた由緒あるお宮さんなんだそうです。 -
鳥居をくぐり進んで行くと、ミニひまわりがたくさん浮かんでいる手水舎が!
-
可愛くて写真を撮っていると、宮司さんの奥さまでしょうか、「ひまわりはもう終わりなんですよ。ようお参りくださいました」と声をかけてくれたのでした。
-
境内には、本殿、拝殿のほか、天満宮と稲荷大社もありました。
-
そして、何といっても目を引いたのが、この『幸福を呼ぶ石』でした。鳥居のところにも"幸福を呼ぶ石"と書かれた看板があったのですが、この石のことだったんですね!
調べてみると、この伊豆神社は縁結びのパワースポットとして今話題となっているんだそうです。 -
「伊豆の霊石」とも呼ばれていたこの石は、言われてみるとハートのような形状をしています。元々は境内の森の中に祀られていたそうですが、今は社務所横にありました。
この石の上部を撫でると幸せを呼んだり、愛しい人に思いが叶うと言い伝えられているのだそうです。 -
社務所のところにミニひまわりが飾られていました。
夏を代表する花のひまわりを見て、酷暑だったこの夏のことが頭をよぎり、ようやく秋を感じる頃になってきたと、しみじみ思ったのでした。 -
このあと、近くに「堅田出町」バス停があったので、バスで駅まで行き帰途につきました。堅田駅には、この周辺の地図があり、訪問したばかりの浮御堂などが紹介されていたのでした。
この日は、主として佐川美術館を訪ねましたが、交通アクセスとして大阪駅から米原方面行きの新快速で「守山駅」まで行き、バスで「佐川美術館前」まで行く方法もありましたが、私たちは湖西線で堅田駅まで行く方法を選び、結果、いろんなスポットも合わせて訪ねることができたので、こちらのアクセスを選んで正解だと思いました。
まだ"サグラダファミリア&ガウディ展"は12月まで開催されているので、興味があれば訪ねてみてくださいね。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (22)
-
- rokoさん 2023/10/29 21:26:47
- "ガウディとサグラダ・ファミリア展"
- akikoさん こんばんは~♪
行ってきました ガウディ展
akikoさんのこの旅行記を拝見して、即、旧友誘って出かけました
佐川美術館は我が家からだと車で1時間余り
今までも何度か行ってますが、今回の企画は素晴らしかったです!
akikoさん詳しく丁寧な説明、美しい画像
下準備万端で、有難かったです
その後のハワイアンカフェにも寄りたかったんですが、
足の疲れもあり、帰り道のお店サンマルクで我慢でした
また次の機会があったら、行ってみたいです。
色々教えていただけて、ありがとうございました。
roko
- akikoさん からの返信 2023/10/31 14:41:50
- RE: "ガウディとサグラダ・ファミリア展"
- rokoさん、こんにちは〜
日、月と1泊旅に出ていてお返事が遅くなりました。
rokoさんもガウディ展行って来られたのですね。
琵琶湖畔にある佐川美術館ってとても素敵な美術館
ですね!
ガウディ展が素晴らしかったと言ってくださって
とてもうれしいです。
サグラダファミリア教会は日本でも人気がありますが、
ガウディの類まれなる想像力&知恵と長年にわたる実験
の結果、あのユニークな形状の素晴らしい教会が可能に
なったと企画展で実感できましたよね。
R cafeは滋賀にしかないハワイアンカフェで、雰囲気
がとても気に入りました。
少し行きにくいところだと思いますが、機会があれば
行ってみてくださいね。
rokoさんのお住まいの滋賀は素敵なところがいっぱい
あって大好きです。またお邪魔しますね〜〜
書き込みありがとうございました。
akiko
-
- りぽちゃんさん 2023/10/18 02:08:20
- 佐川美術館
- akikoさま、こんばんは~☆
佐川美術館に行って来られたのですね!
とってもステキ~(p≧∀≦q)〃
佐川美術館とミホミュージアムは大阪から近いのに遠い、私の中ではなかなか行けない二大美術館です(笑)。
先日阪急電車の車内で、この「ガウディ&サグラダファミリア展」の吊り広告を見ました。
akikoさまが行かれた翌年の2015年に、私もサグラダファミリアを始めとするガウディ建築を見に妹とバルセロナに行ったのですが、ちょうど阪急電車に乗っていた時も妹と一緒だったので思い出話に花が咲きました♪
ポスター写真と、自分が撮ったサグラダファミリアの写真を見比べて「どの塔が出来たのか?」とかワイワイ話したりして・・・( *´艸`)
今回、旅行記グループにあったバルセロナ旅行記も「そうそう、そうだった!」となったり、「え~、そうだったんだ!」となったりしながら懐かしく拝見しました。
「ガウディ&サグラダファミリア展」、行きたいけど行けるかな・・・
名古屋の方が近いかな?とか思ったりしながら(いや、絶対遠いんですけど!笑)調べてましたww
展示室が撮影禁止だったのは残念ですが、佐川美術館の様子をご紹介いただけて嬉しかったです(´∪`*人)
りぽちゃん
- akikoさん からの返信 2023/10/18 21:25:57
- RE: 佐川美術館
- りぽちゃん、こんばんは〜☆
りぽちゃんも佐川美術館とミホミュージアムを注目されていたんですね!
私も同じで、今回ガウディ展がやってきたので、行くなら今とばかりに佐川美術館に行ってきました。
りぽちゃんがバルセロナのガウディ建築を見にいかれたのは、翌年の2015年だったんですね。当時からサグラダファミリアは人気でしたよね〜 ガウディは昔から知っていたわけではなくて、サグラダファミリアを通して興味を持ったような気がします。知れば知るほどすごい建築家で、バルセロナに行ったら教会だけでなく、市内にあるガウディ建築をぜひ訪れてみたいと思ったのでした。ふふふ、りぽちゃんもそうでしたか(^_-)-☆
今年、日本で行われている"ガウディ&サグラダファミリア展"は、いかにガウディは若い頃からずば抜けた才能を持っていたか知ることができ、またサグラダファミリアの奇抜な建物はこうして建設が可能になっていったか、実験なども含めて詳しく紹介されていました。
きっとミホミュージアムは桜が咲く頃が訪問するのにピッタリで、佐川美術館はこの展覧会が訪問の良いきっかけになるのでは?ちょっと行きにくいけど、行けたら行ってみてね!
akiko
-
- るなさん 2023/10/14 07:46:11
- 興味津々
- akikoさん、おはようございます♪
昨日はどうも~長文失礼しました(苦笑)
サグラダファミリアの完成も刻々と近づいてきてはいるんですよねぇ~
元気なうちに行けるかしら?なんて思っていますが...
私が行ったのはもう10年以上前になるのかしら?その頃でさえもあの圧倒的な空間は鮮明に覚えています。
ご飯も美味しくて何もかもが良かったスペインですが、未だ再訪は出来ていません。
以前、akikoさんがバスクへ行きたいって言ってましたよね?私もフレンチバスクから入って行きたい~なんて妄想は膨らむばかり...
滋賀県も未だ未踏の地なんですよねぇ。
コロナ禍の時に計画だけはしていたんですが。お伝えしたことありましたよね?紅葉の時期の滋賀を狙っていたって。
この美術館は水辺に浮かぶというコンセプトだけあって、あちこちにそんな雰囲気が漂い素敵だわぁ♪
そしてがらりと変わってハワイアン~!!!
以前にもハワイアンカフェに訪れていたakikoさんの旅行記を思い出しました。
一気に気分が上がりますね。なんでハワイってテンションが上がるんでしょうか?(笑)明るいイメージそのもの。昔から日本人の旅先としては人気なのもわかりますよね。
そしてハワイからの日本伝統美(笑)
1日で二度美味しい気分?
海上句碑なんて珍しいですね。曇り空でも十分にreflectionしてて美しいわぁ。
にしてもホントに琵琶湖って広い~もう海としか捉えられません。
どれもこれも興味津々で拝見!!日帰りでもこれだけ楽しめるなんて、いつかakikoさんのこのコースで行ってみたいわ♪
あぁぁぁでもちょっと京都とか滋賀はこれまた遠くなるなぁ(;_:)
大阪の方がちょびっと近いかしらん?大阪でも行きたいお店とかいっぱいチェックしているので付き合ってねぇ~(*'ω'*)
るな
- akikoさん からの返信 2023/10/14 17:41:30
- RE: 興味津々
- るなさん、こんにちは〜〜
こちらこそ! またお話し聞かせてね(^_-)-☆
るなさんがサグラダファミリアに行かれたのは10年以上前とお聞きし、そう言えば、旅行記を見せてもらったような記憶が!先ほど、その旅行記を見せてもらいました。サグラダファミリアも改めて見せてもらうと、また感動が蘇ってきました。今さらだけど、素晴らしい旅行記ですね!それに、その前の到着後の旅行記はまだ見せてもらっていなくて、まるで美術雑誌をめくるように、美しいバルセロナの建築やその装飾を紹介する写真が次々と... 。カサアシアなんて聞いたことがなかったけれど、こんなに素敵な館があったんですね。とにかく私が求めていたものの宝庫のような旅行記でワクワクしました。
前置きが長くなりましたが、あのサグラダファミリアの完成もおそらくあと数年後ではないかと思います。今かなりピッチをあげて建築が進んでいるみたいで... 完成したらぜひ見に行きたいですね!話はるなさんの旅行記に戻るんだけど、シッチェスはあるドラマの舞台になっていて、行きたいリストに入れていたのでした^ ^ スペインのご飯も美味しいですよね〜 行きたいと思っているバスクもきっと美味しいものがいっぱいありそう〜(#^.^#)
滋賀は全国的にはあまり知られていないけど、素敵なところがいっぱいあるんです。るなさんが計画していた湖東三山かな?紅葉も見応えがあるところもたくさん。それに、佐川美術館もいいでしょう!ちょっと足を延ばせば、ハワイアンカフェも、浮御堂もありますよ〜〜 また機会があれば、ぜひ滋賀に!
それから大阪へもぜひきてくださいね!るなさんがチェックされたお店、興味あります(^^)♪ どこへでも!(笑)楽しみにしています。
akiko
-
- チーママ散歩さん 2023/10/13 21:09:04
- ガウディの人物像を知りたくなりました。
- こんばんは akikoさん♪
ガウディの未完作品サグラダファミリア。
学生の頃スペイン語を学んでいた私は
「きっといつか行くだろう」と
漠然と思っておりましたが....
なにか結界でもあるのでしょうか?
この年になっても、スペインどころかヨーロッパ
方面に行ったことが一度もないのです。
あれほど巻き舌練習したのに....。
自分でも不思議です。
なんのために勉強したんだーーーーって。(笑)
300年もかかるって…私が生きていうちには
完成しないのねと思っていましたが
完成の時期が視野に収まってきたのですか?
すごい進捗ですね。
AI技術進歩のおかげなのでしょうか。
実際akikoさんも2014年に実物をご覧になって
いらっしゃるのですね? いいなあ。
確かにお写真とポスターとでは真ん中の複雑な
塔の部分が出来上がっているのがわかります♪
ガウディの設計図の表現力が評価されているとあったけど
そういえば、完成図ってあるのでしょうか( ´艸`)
見てみたいな。
そういうのに興味あるんです私。
ガウディの幼少期からのことにふれて書かれていて
心が動かされました。
自然を相手に一人過ごす中で養った観察力。そして想像力。
幼少期の辛い病気の経験がその後の創作に影響を与えたのですね。
なんだかもっと彼を知りたいって気がしてきます。
ガウディ展もすごいですがこの佐川美術館博物館の
デザインも素敵ですね。
自然と一体化して素敵です。
琵琶湖に面した『R cafe』
明るいイメージのかわいいお店ですね。
パンケーキがぷるんぷるんしていておいしそう。
これもまた芸術ですね。
そうか・・・芸術・食欲秋にぴったりのテーマ旅ですね。
- akikoさん からの返信 2023/10/14 14:19:31
- RE: ガウディの人物像を知りたくなりました。
- こんにちは、チーママ散歩さん♪
チーママさんはスペイン語を取っていたんですね。私はフランス語でした。いつかその国に!と思っていましたよね。スペインはイスラム建築様式が残り、ガウディ建築に見られるアール・ヌーヴォーのスペイン版のモデルニスモの建築などもたくさん見られ、訪ねてみてその面白さがわかった国でした。
サグラダファミリア教会は旅をする前も有名で知っていましたが、あんなに凝った石の彫刻装飾がびっしり施されていることに驚き、内部は木漏れ日が注ぐ森の中のようで、吹き抜けの大きな空間がステンドグラス越しの光によって虹色に照らされているのを見て、いたく感動したのでした。全てが奇抜で驚きっぱなしでしたが、そのような空間を作るのに計算し尽くされ、実験を繰り返してやっと実現したことが、今回の展覧会でよく理解できたのでした^ ^
チーママさんもいつか愛方さんとバルセロナ、そしてサグラダファミリアを訪れてみてくださいね。昔、習ったスペイン語も少し思い出すこともできそうです^ ^
ところで、展覧会のことですが、ガウディが卒業制作などで描いた設計図をはじめ、何点か展示されていました。ただ、サグラダファミリアの設計図はスペイン内戦でほとんど焼かれ、一部しかないそうで、今回は展示されていなかったと思います。完成模型は公式サイトに<サグラダ・ファミリア聖堂、全体模型>が最後の方に載っていました。よかったら、見てみてね。
https://www.momat.go.jp/wp-content/uploads/2023/05/momat-gaudi-pressrelease-20230508.pdf
> 自然を相手に一人過ごす中で養った観察力。そして想像力。
> 幼少期の辛い病気の経験がその後の創作に影響を与えたのですね。
仰る通りだと思います!ネット上にガウディの生涯の情報が多く紹介されていると思うので、知りたくなったら検索してみてね(^_-)-☆
佐川美術館のデザインも素敵ですよね〜〜 "水に浮かぶ美術館"ってネーミングもそそられます。自然豊かなところに建っているので、アクセスがちょっと...。でも一見の価値があると思いました。
今回は、たまたま芸術と食と名所観光が一日でできて楽しめました。チーママ散歩さんも先日の"中秋の名月"の旅行記など、素敵なテーマの旅が多くて、また新作を楽しみにしています♪
akiko
-
- Rolleiguyさん 2023/10/12 21:27:10
- 品の良い美術館ですね
- akikoさん、こんにちは。
ご無沙汰しています。ここに記されたいろいろの展示はその場所も含めて上品だなあと思いました。ズラズラと並べてあるのではなく、空間の余裕もいいですね。
サグラ・ダ・ファミリア教会は1978年の春に家族でバルセロナ旅行をしたときに
見学したのですが、当時は完成にはまだ100年以上かかるだろうと言われていました。その後45年経ち、完成へのスピードは上がっているようですね。
郊外にモンセラートという修道院があり、その背後の山にインスピレーションを受けて
ガウディが設計したとの説明でした。今は日本人も関わっているのだそうで、完成の
暁には行ってみたいと思いますが、果たして可能かどうか。
充実したご旅行でしたね。解説も詳細で行かなくてもよく分かるほどでした。
これだけの作成にはさぞ時間を要したことでしょう。報われたと思います。
次の旅行記をお待ちしています。
Rolleiguy
- akikoさん からの返信 2023/10/12 22:46:30
- RE: 品の良い美術館ですね
- Rolleiguyさん、メッセージをありがとうございます。
佐川美術館は琵琶湖のそばにあって、周囲も自然豊かな場所にあって、そこに溶け込むように佇んでいました。
Rolleiguyさんの仰る通り、ゆったり建てられた建物も展示も上品だと感じました。事前予約制ということもあって、それほど混み合うこともなかったのも良かったです。おそらく東京で開催された時はもっと混んでいたのではないでしょうか。今回は常設展はささっと観るだけでしたが、どれも見応えがあり、企画展がない時でも訪れる価値があるように思えました。
Rolleiguyさんは1978年にサグラダファミリア教会に行かれたそうですね。ちょうどその年に生誕のファサードの彫刻を担当した外尾悦郎さんがサグラダ・ファミリアの彫刻家に就任した年だったようですね。日本人が今や主任彫刻家になっているというのはとても誇らしいことですよね〜 ところで、ガウディがインスピレーションを受けたというモンセラートは私も教会を訪問後に行ってみたんです。もしよかったら旅行記をちらっとご覧いただけたらうれしいです。https://4travel.jp/travelogue/10907573
あと3年で少なくとも最後で一番大切な塔、イエスの塔ができるとのことです。私もぜひその頃には再訪したいと願っています。Rolleiguyさんも48年か49年、50年ぶりに完成したサグラダファミリアに行けるといいですね!
akiko
-
- ネコパンチさん 2023/10/12 09:26:11
- 佐川美術館いいですね~(*'▽'*)
- akikoさん、おはよう~(^O^)
佐川美術館、近江八幡あたりと組み合わせて
行ってみたいと思いながらなかなか実現しません。
整然とした建物と水庭との取り合わせが絶妙ですね。
曇っていても美しいわ~(*^^*)
小樽の似鳥美術館もですが
文化事業に力を注ぐ企業って、一目置くというか
応援したい気持ちになりますよね。
akikoさんは2014年にバルセロナを訪れたのですね。
約10年経過して外観は変化したようなそうでもないような…
何度となく延び続けた完成予定、
今更20◯◯年予定と言われてもにわかには信じられません(笑)
飛び抜けた天才ぶりの原点が病弱な幼少期にあるところは
なるほど「らんまん」主人公と重なりますね。
例年に比べてakikoさんの秋の花便りが少なく
寂しく思っていました。
さすがにここまで暑さが長引けば
引きこもりたくもなりますよね~
私も9月中は仕事以外の外出はほぼせず
写真は1枚も撮っていませんでした。
ようやく待ちわびた季節になってホッとしましたよね(*^^*)
ネコパンチ
- akikoさん からの返信 2023/10/12 22:12:46
- RE: 佐川美術館いいですね?(*'▽'*)
- ネコパンチさん、こんばんは〜〜
ネコちゃんもやはり佐川美術館をご存知だったのですね!京都の隣の滋賀は、少し地味めかもしれないけど、いいところがいっぱいあります。 映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』では、滋賀の車のナンバープレートの「滋」がいじられ、かつて東京から虐げられていた埼玉と同じく、ゲジゲジと揶揄され、京都と比べられるシーンがあるとか。華やかさはないかもしれないけど、滋賀には味わい深さがあると... 私は応援したいです(^_-)-☆
近江八幡も彦根も長浜もとても風情があって、佐川美術館と組み合わせて行くにはバッチリだと思います。
仰るように、ニトリを筆頭に文化事業に力を注ぐ企業は私も応援したい気になります。佐川急便がこのような広大で素敵な美術館を運営しているとは、あまり知られていないけど、一度行くと、イメージがかなり変わったような気がします。
ネコちゃんはバルセロナはまだ行かれてませんか。至る所に、写真を撮りたくなるフォトジェニックな建物がいっぱいなんです。次回、ヨーロッパに行かれる時は、ぜひ候補地の一つにしてね。サグラダファミリアは中に入ったら、「わぁ〜〜」ってため息が出ること間違いなしです!完成していなくても...ね!
今年の夏は、本当に暑かったですよね〜〜。どこにも観光には行く気がせず、お籠もりしていました(笑)最近やっと、涼しくなり、先日は滋賀へ、今日も青空だったので、午前に用を済ませた後で万博公園にコスモスを見に行ってきたんです。花の丘一面にコスモスが揺れているのを見て「秋だ〜〜!」と実感しました^ ^ ネコちゃんもどこかにお出かけされるのかな?
akiko
-
- たらよろさん 2023/10/11 21:20:15
- より楽しみになりました
- こんばんは、akikoさん
私もこの展覧会に行こうと思ってて。。。
本当は、サグラダファミリアを見たいと思っているんだけど、
なかなかスペインは遠く…。
ただ、やっぱりゲルニカも見たいし、
スペインはいってみたいんですよねー。
とは言いつつ、とりあえず、この展覧会は絶対に行くぞ!!と思っています。
ガウディのあれこれも知れて、
より造形が深くなれそうで、
ますます楽しみになりました♪
年末までにどこかで…
楽しんできますねー。
たらよろ
- akikoさん からの返信 2023/10/12 21:24:18
- RE: より楽しみになりました
- たらよろさん、こんばんは〜
たらよろさんもガウディ展に行かれるんですね!
この展覧会はガウディの建築に込められたエッセンスが
これでもかというほど紹介されていて、建築学に重きが
置かれている感じでした。
今回知ったことも多く、大変勉強にもなりました。
サグラダファミリアは、その集大成としての大聖堂で、
聖堂の中に入るとまるで森の中にいる不思議な感じがし、
自然光で美しく輝くステンドグラスに目を奪われる感動は、
実際サグラダファミリアに足を運ばないとわからないような
偉そうですが、そんな気がしました。
でも確かに、スペインは遠いですよね〜〜
私は利用しなかったのですが、城田優さんの音声ガイドは
とても声が素敵で、わかりやすいということも聞いたので
よかったら、利用してみてくださいね。より理解が深まる
かも...。
教会が完成した折には、行けたらいいですね(^_-)-☆
akiko
-
- yokoさん 2023/10/11 14:09:29
- 憧れのガウディ&サグラダファミリア♪
- akikoさん こんにちは(^^)
10月初めに滋賀に行かれるとのことでしたが、佐川美術館だったのですね。私は存在すら知りませんでした(^^;)
akikoさんがスペインを尋ねられたのは2014年でしたか。月日の経つのは早いですね。その間に建設が進んだ様子が見られて感慨深いですよね。
私はサグラダファミリアを一度見てみたいと思いながら、まだ実現していません。行ってみたい気持ちはあるけれど、4年の月日を経て行った海外旅行の13時間のフライトは正直きつかったです。ヨーロッパはもっと遠い・・・(>_<)
美術館で、ガウディの学生時代からの図面を見ることが出来るのは興味深いですね。実際に建築物を見た方だと、余計に引き込まれたことと思います。
水庭に浮かぶ茶室も面白いですね。夏は良いけれど冬だとちょっと寒そうですが。
「R cafe」なんだか聞いたことがあるような。。と思ったら、以前行かれたハワイアンカフェと同系列だったのですね。琵琶湖を臨む爽やかな雰囲気の店内で雑貨も可愛くて・・これは、直ぐに写真に撮りたくなりますね(^_-)-☆
メニューを見て、近江牛よりパンケーキを選択されたのはakikoさんらしいです。私なら間違いなく近江牛だわ~(^O^)/ でも、フルーツやまるごといちじくのパンケーキもとっても美味しそうです!!
観音堂にある90枚の天井の花の絵、見事ですね。浮御堂も能舞台があり、船を浮かべて能を鑑賞するだなんて風情があります。
たまたま寄った「伊豆神社」で、ミニひまわりの花手水に出会うだなんて、きっとひまわりさんに呼ばれたのでしょうね。
一気に季節が進んで涼しくなりました。暑かったこともあり、akikoさん同様に8月・9月と引きこもっていた私ですが、秋は少しお出掛けしないとね(^^♪
yoko
- akikoさん からの返信 2023/10/11 21:47:01
- RE: 憧れのガウディ&サグラダファミリア♪
- yokoさん、こんばんは〜
ようやく涼しくなり、お出かけするのに良い季節になりましたね〜 コスモスなどの花も咲き始め、お花を見に行きたくなってきました。そんな時ですが、滋賀の佐川美術館でガウディ展が少し前から始まり、友人と行ってきたんですよ。
yokoさんはサグラダファミリアはまだだったんですね。私は10年前にエルグレコの展覧会が大阪であり、とても魅了され、現地で作品が飾られているのを見たいと思って翌年スペインを旅したのでした。その時にバルセロナも訪問し、サグラダファミリアを間近で見て、そして中に入っても大感動。ガウディの天才的な建築にとても興味を持ち、街にあるガウディ建築群も合わせて見に行ったのでした。その時、2026年に聖堂が完成すると聞き、完成したら、夜はイエスの塔の上に掲げられる十字架から天と四方に向けてサーチライトが放たれ街を照らし、十二使の塔の鐘は弾いて鳴らされ、巨大な楽器による演奏を聖堂本体が石の共鳴箱となって響かせることになることがわかり、その様子を見たいとずっと思ってきました。そして今回、完成が視野に入ってきたということで、日本で"サグラダファミリア&ガウディ展"が開かれることになったと知り、これはぜひと思った次第なんです。
その会場となる佐川美術館も、水庭がとても印象的で素敵な美術館でした。常設展も見応えがありますし、企画展は例えば「藤井フミヤ展」や「アリスインサイエンスワールド」という体験型の展示イベントなどもあったとか。もし興味があれば、面白そうな企画展がきたら佐川美術館に行ってみてね!
そのあと行った「R cafe」は、車だと行きやすいのかもしれないけど、バスで行くにはちょっと迷いました。こんな道行く??なんて言いながらGoogleマップを頼りに行き着いたのでした。でもアクセス以外は良かったです。食べ物はランチに何種類かサラダバイキングがついた美味しそうなものがあって、ほとんどの人はそれを食べていたようですが、シニアの私たちがパンケーキを迷わず選択するという... yokoさんは近江牛を選ばれますよね!普通はそうですよね(笑)でも、いちじく好きのyokoさんは、きっといちじくのパンケーキも捨てがたいハズ(^^)♪
浮御堂もなかなかいいところでしょ!観音堂の天井の花の絵は、改修中にたまたま発見されたんですって! これもyokoさんに気に入ってもらえそうです。そばにある伊豆神社も単独で行くのは?ですが、立ち寄るにはいいかも。。。
これから観光にぴったりの季節ですが、yokoさんの旅行記もとっても楽しみです♪ できたら見せてもらいますね〜〜
akiko
-
- cheriko330さん 2023/10/10 23:08:53
- ガウディ展☆・゚:*
- akikoさん、こんばんは☆彡
ガウディ展、見れば3ヶ所のみで、次は愛知が会場なのね。
福岡であれば行ってみたかったです。残念ながら写真はダメだったのね。
佐川美術館は、水に浮かぶ美術館として有名なのですね。高知美術館も
水庭があったり、ホテルもしかりでデザイン的に人気なのでしょうか。
特に、ここ佐川美術館は群を抜いていますね。
サグラダファミリアは私も完成を心待ちにしていて、完成の折には是非に
行ってみたいと思っています。私が行ったのはユーロになったばかりの時で
サグラダファミリアの内部は、工事現場の足場ばかりでした。
2026年の完成は、遅れたのね。
佐川美術館の常設は、平山郁夫氏と佐藤忠良氏の作品が中心なのですね。
こちらも興味があります。
その後、立ち寄られた『R cafe at Marina』こちらは爽やかなグリーンが
基調なのね。ディスプレイもとても可愛くて、パンケーキのどちらも魅了的。
迷います。シェアが一番ね。
その後、「浮御堂」や、また「伊豆神社」へも急きょ寄られて一日を
ご友人と楽しまれて、良い一日を過ごせましたね。お疲れさまでした。
cheriko330
- akikoさん からの返信 2023/10/11 00:28:11
- RE: ガウディ展☆・゚:*
- cheriko330さん、こんばんは〜☆
そうなんです。ガウディ展は日本で3ヶ所のみだけなんです。cherikoさんもバルセロナにあるサグラダファミリアを訪れられたと前にお聞きした記憶がありますが、ずいぶん前のことで、内部は足場ばかりだったとか。あと数年、完成した折には、ぜひバルセロナまで見に行きたいですよね!!!
それにしてもガウディ氏はすごい才能があったんですね!想像でいろんなユニークな建築物を考え出すことはできるでしょうが、巨大な聖堂を建てるのに、10年もの月日をかけて逆さ吊りの研究をしていたそうで、緻密な計算をし尽くし、あのようなとうもろこしのような形状の塔がが何本も立つようなユニークな聖堂を可能にし、しかも装飾も、内部の造りも自然界を具現化したような素晴らしいもので...。今回の展覧会でも初めて知ることがとても多くて、さらにサグラダファミリアに興味がわき、再訪したい気持ちが強くなりました。
佐川美術館は行きたいと思っていたところで、ここでガウディ展をやってくれたのでとてもラッキーでした。水庭のある美術館、素敵でしょう!確かに、高知県立美術館ともとてもよく似ていますね! どちらもとてもフォトジェニックな美術館で、建物を観るだけでも訪れたくなります。佐川美術館の常設展のことですが、平山郁夫さんの作品が展示されているところもありました。時間がなくて、ささっとだけでしたが、有名なシルクロードの絵もあり、「平和の祈り」というコンセプトで作品展示されていて、戦争がまた起きつつある今、とても心に響く展示でした。
『R cafe』は、以前に行った時にとても気に入ったので、姉妹店のこちらのお店にも訪問してきました。可愛さは本店の方が優っていましたが、食べ物はどれも美味しそうで、ハワイを思わせるメニューがたくさんあったんです。お天気がもっと良ければ、眺めもかなり良さそうでした。パンケーキは他にも種類があったんだけど、定番のフルーツたっぷりのパンケーキとまるごといちじくのパンケーキにしたのでした。幼なじみの友人とは気が合って、気持ちはいつまでも若い時のままなんです。ふと自分の年齢を考えると、いつまでもパンケーキじゃないでしょと思うのですがやめられません(笑)
この日は、芸術も鑑賞でき、美味しいものを食べ、風光明媚な名所も訪問できて久しぶりに楽しい一日でした(^^)♪
akiko
-
- ドロミティさん 2023/10/10 17:05:23
- 佐川美術館素敵ね!
- akikoさん、こんにちは!
みかんさんも仰ってらっしゃいますが、akikoさん本当にフットワークが
軽くて羨ましい。いえ見倣わなくては~!
佐川美術館を初めて知りましたが、サグラダファミリア&ガウディ展を
さておき、この美術館自体が素晴らしく斬新!
まさに水に浮かんだ美術館、「水上の神殿」のよう☆彡
重たそうな屋根が日本の切妻造りのようでとても印象的でした。
湖面にせり出している浮御堂もとても魅力的で、まだ琵琶湖には
行ったことがないので、行くときは美術館とセットで訪れたいわ。
Rcafeのパンケーキも美味しそうで食欲をそそられます。
イチジクはどちらかというとお酒のお供としていただくことが多いけど
スウィーツもイケるのね~。
akikoさん、フットワークだけでなく仕事も早い!!私なんか先月の
上高地ももったらもったらやる気のなさが現れてます^^;
少し気合いれていっきに仕上げようっと(笑)
ドロミティ
- akikoさん からの返信 2023/10/10 23:35:44
- RE: 佐川美術館素敵ね!
- ドロミティさん、こんばんは〜
みかんさんのお返事にも書きましたが、最近腰が重くなってしまい、何でも"無理をしない"がモットーになってしまいました(笑)先日も、仲秋の名月の日に京都の大沢池で「観月の夕べ」が催されるのを知り、きっと趣のあるイベントで行きたいなと思いながら、「でも、まぁいいか!」と諦めることがあったばかり。少々、年齢も関係してきたのかなと思いつつ、でも無理のない範囲で楽しいことはやりたいなって思っています(^^)♪
佐川美術館、いいでしょう!滋賀には、あとMIHO ミュージアムというとても素敵な美術館もあるんですよ。佐川美術館はドロちゃんが書いてくれたように「水上の神殿」のように見えますよね!常設展を観るだけでも訪問する価値があると思いました。
浮御堂のある満月寺は歩いてまわっても10分もかからない小さな禅寺で、浮御堂は素敵でしたが、どこかとセットで訪れるのが良さそうです。佐川美術館もいいですし、琵琶湖周辺には他にもいろいろ見どころがあるので、いつか機会があれば訪ねてみてね!
今の旬のいちじくは、ドロちゃんにとってお酒のお供なんですね〜 そのまま食べても美味しいですよね!あとドライフルーツになったいちじくも好きです。カフェでいただいた包み焼きされていたパンケーキは、とてもおいしかったんですよ♪ ただあのR cafeのある場所は分かりにくくて、行き着くのに苦労したのでした^ ^
そうそう、ドロちゃんの軽井沢の旅行記、まだかなと思っていたんです。ちょうど行かれる頃に、河童橋から明神池に行く道で熊が出て一部通行止めになったニュースが流れていたので、大丈夫かなと心配していたんです。気合を入れて旅行記完成させてね(^_-)-☆
akiko
-
- あまいみかんさん 2023/10/10 10:55:18
- 佐川美術館、そんな行き方もあるのね~。
- akikoさん、おはようございます。
ガウディ展、佐川美術館で開催されているのですね。
「遠い!」ってのが、刷り込まれていて、ついつい敬遠ですが、
斬新な美術館ですね。一度だけ、お茶室、楽茶碗目当てに
ツアーで訪ねたことがあります。
akikoさんは、フットワーク軽く、楽しまれるの凄いなあっといつも
思います。カフェのパンケーキ、美味しそう。まるごとイチジクの
パンケーキ、こんなの出てきたら、思わず「うわ~っ」と歓声もの。
お友達となら、両方楽しめていいなっ。
浮御堂、丁寧に解説して下さって、想像以上!!
古今の俳人が沢山訪れて、句碑で見れるのもいい。御堂の中には、
花絵の天井があったり、能舞台があったりと、小さなお堂だと思っ
てたけど、手の込んだもので、流石に憧れの風景。
神社には、ひまわりの花手水があって、akikoさんの行く先々には、
いつでもお花が綺麗!
湖西線だと不便かなっと思ったけど、琵琶湖大橋があったり、
前にご紹介下さった比叡山もあるし、見どころがいっぱいですね。
日本の歴史の故郷のような琵琶湖行でした、ありがとうございました。
あまいみかん
- akikoさん からの返信 2023/10/10 22:50:40
- RE: 佐川美術館、そんな行き方もあるのね?。
- あまいみかんさん、こんばんは〜
みかんさんは佐川美術館に行かれたことがあるのですね!
私は初めてだったのですが、建物を見るだけでも行く価値がある素敵な美術館ですね。
ガウディは9年前にスペインを旅した時に調べてその素晴らしい建築に魅せられたのでした。今年東京、滋賀、名古屋で展覧会があることを知り、楽しみにしていたんです。展覧会では、そのとてもユニークな形状も、ちゃんと計算し尽くしてできていたことを知ることができました。そして手書きの設計図なども大変美しいことに驚きました^ ^
フットワークが軽いと言っていただきましたが、最近はそうでもなくなったんですよ。「行きたいけど、まっいいか〜」と諦めることがよくあります。コロナ禍から"無理をしないでおこう"という姿勢が染み付いてしまったようです(笑)ただ楽しむことは大好きで、TVなどで素敵なところやお店を紹介されていると、つい行きたいと思ってしまいます。いちじくのパンケーキ、美味しそうでしょう。パンケーキにいちじくをのせるのではなく、中に入れて包み焼きをしていたんです。今旬のいちじく、とても美味しいですよね〜♪ 普通に食べても大好きです。
浮御堂は名前は知っていましたが、あまりクローズアップされることがなく、それほど行きたいと思ったことはありませんでした。今回、カフェの近くにあったので、訪問してみたんですが、湖に浮かぶように見えるお堂がフォトジェニックで、歴史的にも由緒があるお寺で来てよかったと思いました。伊豆神社は全く知らなかったのですが、花手水が施されていたり、縁起が良さそうな"幸福を呼ぶ石"があったりで、訪問できてラッキーでした。
琵琶湖周辺には、みかんさんがおっしゃってくださるように、見どころがいっぱい!(次は、秀吉の極楽橋の唐門が移築された神社がある竹生島なんかにも行ってみたいと思っています)
akiko
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?






![東京国立近代美術館で、"ガウディとサグラダ・ファミリア展" が6月13日から9月10日まで開催され、引き続き琵琶湖湖畔にある『佐川美術館』で9月30日から12月3日まで開催されています。<br /><br />以前から注目していたガウディとサグラダファミリアに関するイベントが、ずっと訪れてみたいと思っていた佐川美術館に企画展としてやって来ると知り、とても楽しみにしていました。<br />この日、JR大阪駅で友人と待ち合わせ、大阪駅から京都駅経由、湖西線で「堅田駅」へ。その後バスで「佐川美術館前」まで乗車し、徒歩すぐの佐川美術館にやって来ました。<br /><br /><ガウディとサグラダ・ファミリア展><br />◆場所:佐川美術館<br /> 滋賀県守山市水保町北川2891<br />◆会期:2023年9月30日[土]~12月3日[日]<br />◆開館時間:午前9時30分~午後5時<br />◆休館日:月曜日(10/9は開館)、10/10、11/28<br />◆入館料:一般¥1,300 事前予約要<br /><br />※当初、ここに展覧会のポスターを使用しましたが、著作権の関係で差し替えました](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/travelogue_pict/79/04/22/650x_79042261.jpg?updated_at=1697544723)




















































































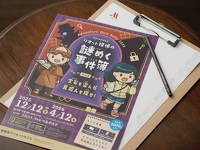





旅行記グループ ガウディ建築を訪ねる旅
22
66