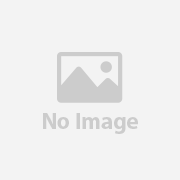大日堂
寺・神社・教会
3.21
クチコミ・評判
1~2件(全2件中)
-
木造百体観音もあります。
- 4.0
- 旅行時期:2021/09(約4年前)
- 0
-
格式の高さを感じさせる江戸時代に建立された御堂です!
- 4.0
- 旅行時期:2019/11(約6年前)
- 3
『大日堂』は、甲斐の戦国大名「武田信玄(武田晴信)」と越後の戦国大名「上杉謙信(長尾景虎)」が北信濃の支配権を巡り、155... 続きを読む3年(天文22年)から約12年間(計5回)に渡り繰り広げられた「川中島の合戦」の折、信濃の「善光寺」焼失を恐れた「武田信玄」が「甲斐善光寺」の本尊となる「善光寺如来」をはじめとする「善光寺」の諸仏寺宝類を1558年(永禄元年)に創建した「甲斐善光寺」へ奉遷する際に1555年(天文24年)から約3年間に渡り一時安置場所にしたと伝わる、もともと東御市祢津地区西宮の「古大日」という地籍にあった「善光寺」・「甲斐善光寺」と関係の深い御堂です。
現在の『大日堂』の建物は、平安時代中期の975年(天延3年)に創建し鎌倉時代初期に現在の地に移転した山号を「智光山」と号する「長命寺」(真言宗智山派)の別当として、江戸時代初期の徳川幕府第4代将軍「徳川家綱」の時代となる1679年(延宝7年)に現在の地に建立されたものです。
御堂内には、平安時代(794年~1185年)中期から後期の藤原時代に制作されたものと伝わる本尊「大日如来像」(秘仏)のほかに善光寺三尊型式の仏像が安置されており、桁行き5間、梁間4間の建物は3間向拝付の銅瓦棒葺き入母屋根の正面部分に大きな千鳥破風が設けられ、向拝部分も唐破風にするなど格式の高さを感じさせる御堂建築の遺構として貴重なことから、1994年(平成6年)に「東御市指定文化財(建造物)」として指定されています。
また、御堂内に掲げられている1853年(嘉永6年)に奉納された「算額」(横:107センチメートル、縦:62センチメートル)も1994年(平成6年)に「東御市指定文化財(書跡)」として指定されています。
「算額」とは、江戸時代中期の寛文年間(1661年~1673年)ごろから始まった風習で和算の問題が解けたことを神仏に感謝するとともに益々勉学に励むことを祈願して額や絵馬に和算の問題や解法を記して奉納したもののことです。
今回は、所要で「弥津公民館」を訪れた際に2時間程度の空き時間を利用して弥津地区を徒歩で散策しながら『大日堂』に立ち寄りました。
木々に囲まれて誰もいない静寂な境内のひっそりした空間に歴史を感じさせる『大日堂』を見ていると時の流れが止まったかのような感覚でリフレッシュすることができました。
弥津地区周辺には、『大日堂』のほかにも江戸時代に建立された本格的な舞台装置を完備した「東町の歌舞伎舞台」や「西宮の歌舞伎舞台」など歴史的な史跡が点在しており、天候にめぐまれ自然に囲まれた木々の間からこぼれる秋の日差しを感じながらのウォーキングによる「史跡めぐり」を堪能することができました。
最寄り駅となる「田中駅」(しなの鉄道)からはタクシーで10分程度、上信越自動車道「東部湯の丸インターチェンジ」から車で5分程度の場所に位置し、周辺に公共の駐車場が存在しないので少し不便ですが、『大日堂』ほかの弥津地区周辺の「史跡めぐり」はお薦めできます。
閉じる投稿日:2020/07/11
1件目~2件目を表示(全2件中)
基本情報(地図・住所)
このスポットに関するQ&A(0件)
大日堂について質問してみよう!
真田・東御に行ったことがあるトラベラーのみなさんに、いっせいに質問できます。
-

はなももさん
-

hiroさん