
2023/11/28 - 2023/11/28
17位(同エリア222件中)
![]()
たびたびさん
- たびたびさんTOP
- 旅行記850冊
- クチコミ41302件
- Q&A回答432件
- 6,968,462アクセス
- フォロワー687人
この旅行記スケジュールを元に
今日は、鹿児島の最終日。鹿児島市を早朝出発して出水に向かいますが、その前に、川内で途中下車して川内の市街を散策です。
ちょこっとのつもりでしたが。。川内には薩摩国分寺跡があって、古代薩摩国の中心は川内。薩摩国の一宮、新田神社やニニギノミコトの陵墓と言われる可愛山陵もそれに相応しいなかなかのスポットですね。時代は下って、薩摩・大隅・日向の守護大名となった島津氏第5代当主、島津貞久も川内碇山城を居城としていましたが、三男、師久に薩摩国を四男、氏久に大隅・日向を譲って、これが総州家と奥州家の始まり。鹿児島は、その際に奥州家の居城が鹿児島の東福寺城となったことからの歴史です。ちなみに、総州家は内紛から奥州家との対立によって、5代で滅亡。島津氏第9代当主、忠国の時代に騒動は集結しますが、島津貞久が四男、氏久に大隅・日向を譲っていなければ、今でも鹿児島の中心は川内だったかもしれませんね。明治以降も、ジャーナリストで改造社の創業者、山本實彦や有島武郎、有島生馬、里見弴の有島三兄弟を輩出。川内が育んできた歴史の重みは軽くないような気がしました。
そして、今日のメインの出水。さっそく訪ねたのは、出水市ツル観察センター。出水駅からツル観光タクシー、片道2000円を利用しました。この日、11月25日のツルの総数は11856羽。うち、ナベヅル11392羽、マナヅル452羽、クロヅル6羽、カナダヅル4羽とナベヅルが圧倒的です。北海道のタンチョウヅルは絵画でもお馴染みのツルで気高い印象があるのですが、ナベヅルはどうかなあ。ちょっと期待半分でしたが、ナベヅルも飛ぶ姿とかやっぱりツルらしい気品があって、素晴らしいですね。それにこれだけ数が多いし、自由に飛ぶさまは圧巻。出水のツルがこんなにすごいとは。。楽しくてドキドキの連続でした。ところで、別途、越冬地環境保全協力金を払うと無料で望遠レンズ付きのカメラが借りれます。こんなカメラは初めてでしたが、ものすごいズームが効いてリアルなツルの息づかいが感じられて、肉眼で見る以上の迫力は予想外に衝撃的。バードウォッチングってこんなに楽しかったんですね。鳥を追いかける人の気持ちが初めて分かったような気がしました。
ちなみに、出水とツルの歴史を調べると最初の記録は元禄7年(1694年)。江戸幕府の呼びかけもあって、薩摩藩もツルの保護を命じます。しかし、明治期に入ると一転、ツルは狩猟の対象となり、明治中期には1羽も渡来しなくなる時期も。その後、再び保護の時代に入り、大正から昭和初期にはそれなりに復活。ただ、本格的なツルの飛来地として成長するのは戦後。鹿児島県ツル保護会の結成や韓国の軍事境界線での環境悪化もあって、渡来数は飛躍的に増加。今では、世界に生息するナベヅルの9割、マナヅルの5割が出水に飛来すると言われるようになったのだそうです。ちょっと驚きの事実ですね。
出水市ツル観察センターの後は、出水麓武家屋敷群へも。今回の旅では、知覧、加世田に続いての重要伝統的建造物群保存地区。薩摩藩の防衛拠点であった街並は、丸石を積んだ石垣と高い垣根に挟まれた通りとかやっぱりそれなりの迫力がありますね。公開している武家屋敷は竹添邸と税所邸。立派なお屋敷だし、保蔵状態も良好です。ただ、その精神的な支柱となっているのは山田昌巌。寛永6年(1629年)出水郷第3代地頭で、薩摩藩の家老職も勤めた人物ですが、出水兵児と呼ばれる武勇の気風を残したことが今でも地域の誇りとなっているようで、ちょっといい話ではありますね。
鹿児島は広くて、小さな歴史があちこちに眠っているんですね。旅の最後になって、その思いがまた強く心に残ったような気がします。
-
鹿児島中央駅を出発して川内駅に到着。
川内駅からまずは新田神社、可愛山陵に向かいますが、これが3キロちょい。朝からいきなりハードです。
これが入口みたいですね。 -
いやいや、この長い階段はきつそう。
-
鬱蒼とした森の中に続く石段を上がった先に
何か見えてきましたが、これはとんでもない御陵だと思います by たびたびさん可愛山陵 名所・史跡
-
それが可愛山陵。
可愛山陵はニニギノミコトの陵墓とされていて、例によって、宮内庁の掲示板が立っています。しかし、ニニギノミコトは天孫降臨の主人公。御陵もいろいろありますが、これは本当にルーツ中のルーツ。とんでもない御陵だと思います。 -
そこから回り込んだすぐ隣りが新田神社でした。
新田神社は、薩摩国の一宮。ニニギノミコトがここに高殿(千台)を築いて by たびたびさん新田神社 寺・神社・教会
-
伝承によると、川内の地に来たニニギノミコトがここに高殿(千台)を築いて住まったということ。この千台から川内ですね。
-
ニニギノミコトは天孫降臨の地とされる霧島の方が有名ですが、それだけではない。鹿児島にはこんなところにもニニギノミコトゆかりとされる地があるし、知覧や指宿ではニニギノミコトの息子、山幸彦の妻となった豊玉姫ゆかりの地がいくつかありました。鹿児島って、神話の本家、宮崎にもけっこう負けていないような感じになってきますが、薩摩国、大隅国ももとは同じく日向国。薩摩国、大隅国は日向国から分かれたものですからね。風土や伝承に似たようなところがあるのはおかしなことではないかもしれません。
-
続いては、泰平寺。けっこう荒れ寺っぽいですね。
天正15年(1587年)、九州征伐で肥後路から薩摩に入った豊臣秀吉がここを御座所として接収。秀吉と義久の像や和睦を記念した和睦石も by たびたびさん泰平寺 寺・神社・教会
-
イチオシ
降伏し剃髪した島津義久と会見し、和睦した舞台となった場所です。
-
敷地内には、秀吉と義久の像や和睦を記念した和睦石も。
-
ちなみに、九州征伐軍は25万。日向路の秀長軍と肥後路の秀吉軍が二手に分かれて南下しています。
-
ほか、これは官修墳墓。
西南戦争の際に亡くなった政府軍の兵士の墓です。 -
また少し移動して。
これは、薩摩国分寺跡。
南北130m、東西120mの区域に、”一塔二金堂”の川原寺式の伽藍配置 by たびたびさん薩摩国分寺跡 名所・史跡
-
南大門から中門を入ると
-
右手に
-
五重塔、
-
左手に西金堂。
-
正面に中金堂があるという”一塔二金堂”の川原寺式の伽藍配置だったよう。
規模は少し小ぶりですが、けっこうきれいに整備されていて、古代の世界に迷い込んだような感覚に浸れます。 -
薩摩国分寺跡史跡公園の隣りに、川内歴史資料館もありまして。
ただ、いずれにしても川内が薩摩国の中心地だったという事実がそもそも新鮮かな。薩摩国国分寺のあれこれを目玉にしつつ、土器類とかの考古学的な展示も網羅的に揃っています。 -
なお、このあと訪ねる川内まごころ文学館と並んで建っていて、川内歴史資料館が主で川内まごころ文学館が従のようなことかなと思っていましたが、結果としては川内まごころ文学館の内容が想像以上に豊富。時間の配分はむしろ川内まごころ文学館を主にした方がいいかもしれません。
-
その川内まごころ文学館がこちら。想像していたよりずっと立派な施設です。
-
1階展示室では、川内出身のジャーナリストで改造社の創業者、山本實彦をキーにして、大正から昭和にかけて中央公論と並ぶ支持を集めた改造に寄稿された芥川龍之介、谷崎潤一郎、武者小路実篤らの直筆原稿などを展示。時代の最先端を行く作家の競演といった活躍の場を提供した山本實彦の重鎮ぶりがかなりの迫力で伝わってきます。
二階の展示室では、有島武郎、有島生馬、里見弴の有島三兄弟のコーナーがなかなか。薩摩藩士の家柄の色濃い有島生馬に文化勲章も受賞した里見弴。
ちょっと頭がくらくらするような盛りだくさんの内容でした。
なお、後日、里見弴の作品をちょっと拝見してみましたが、江戸の粋な文化を細かく描いた洒脱な世界は、鹿児島出身とは思えない奇想天外なレベル。化け物みたいな作家だと思います。 -
川内駅に戻りますが、その途中、川内川を渡ります。この川は、熊本県最南部、宮崎県南西部と鹿児島県北西部を流れ、東シナ海に注ぐ一級河川。九州では筑後川に次ぎ第二の規模を誇ります。
つまり、川内市街はこの滔々と流れる川で川内駅のエリアと上川内駅のエリアが分かれることになっていて、ちょっと邪魔くさい感じもなくはないように思います。 -
薩摩川内市観光物産協会は、川内駅の一階。地元のお土産品、お菓子類などを程よくそろえたきれいなショップです。ちょっと変わったところだと、さつま揚げ、麦みそデザートのコーナーがあって目を引きました。なお、観光案内は二階の別の場所(さつませんだい観光局)にあります。
-
その観光案内のさつませんだい観光局がこれ。二階のちょっと奥まった場所にあるし、外観も目立っていないので、観光客がこれに気が付くのは難しいかもしれません。小さな対面式のブースとパンフレット類が揃っています。オレンジ鉄道の一日フリー切符も扱っていました。
-
川内駅からは、オレンジ鉄道で出水駅に向かいます。
-
途中、海の車窓。なかなかダイナミックな眺めです。
-
出水駅の到着して、昼飯にします。
魚松は、事前に調べた感じだと出水駅周辺では人気ナンバーワンみたいなお店ですね。 -
イチオシ
昼間は、おばちゃんが一人で切り盛りしていますが、いただいた豚骨の定食は、焼酎で煮込んだもののようでさっぱりした味わい。骨も簡単に取れるし、食べやすいです。小鉢でついていたポタージュスープも少し甘めの仕上げで、最後にデザートを食べる感覚かな。郷土料理だけどそれぞれの品にしっかりサプライズもあるというかなり実力派のお店だと思います。
-
イチオシ
さて、落ち着いたところで、出水市ツル観察センターに向かいます。
冒頭触れましたが、出水駅からはツル観光タクシーの利用。実際、総合的に考えて、アクセス方法としてはこの一択ですね。楽しくてドキドキの連続 by たびたびさん出水市ツル観察センター 自然・景勝地
-
本日のツルの数。1万羽を越えているし、これなら十分でしょう。
(ちなみに、23年の最高羽数は12,972羽だったみたいですから、ほとんどピークの時期だったようです) -
建物から周囲の田んぼを眺めると確かにツルがいっぱい。
-
ここは視界を遮るものがないので、外敵の侵入があればすぐに分かる。
ツルがねぐらにするには好都合なのですね。 -
空には飛んでいるツル。
二羽で飛んだり、 -
もう少し多かったり。
-
しかし、どっちにしても
私のカメラではこれが限界。 -
これではどうにもなりませんね~
-
とそういえば、カメラを貸してくれるというのがありましたよね。
自分のメモリーカードを使えば、それに写真は保存できますから、せっかくだしチャレンジしてみましょうか。 -
イチオシ
おー
-
おー
-
これはすごいじゃないですか!
-
肉眼で見るより余程よく見えて
-
ツルたちの息づかいまでが間近に感じられますよ~
-
いやいや
-
望遠レンズの威力って
-
凄まじいものがありますね!
-
イチオシ
今度は飛んでいるツル。
-
これもすごい。
-
瞬時にピントが合って、ブレもなし。
-
三脚とかなくても
-
全然、問題ないですね。
-
イチオシ
もしかして、これこそがバードウォッチングなのかも。
-
一瞬一瞬のツルの動きは
-
気品と美しさ、生命力にあふれていて
-
イチオシ
本当にすばらしいです。
-
そして、楽しい!すごく楽しいです!!
-
我を忘れて、夢中になっていたかも。
バードウォッチングの楽しさって、つまり、こういうものなんですね。初めて知りましたけど、けっこう衝撃的。ハマる人の気持ちが分かったような気がしました。 -
資料関係も最後に拝見して、大満足。最後の出水はもしかしたら少し無理をしたかなとも思っていましたが、なんのなんの。これは思わぬところで冥途の土産ができたような気がします。
-
出水市ツル観察センターからは、またツル観光タクシーを利用して、出水麓武家屋敷群の方を訪ねます。
出水麓歴史館は、出水麓武家屋敷群の一角。 -
けっこう立派な施設で、
-
出水麓の歴史を幅広く紹介していますが、
-
注目は山田昌巌の関係でしょう。
-
山田昌巌は、島津義弘に従い、関ケ原の戦いにも参戦。
-
撤退戦を含めて義弘に軍功並ぶものなしと言わしめるほど。
-
寛永6年(1629年)、ここ薩摩国出水地頭に任じられ、
-
「出水兵児」と呼ばれる気風を造ったということです。
-
日置流秘伝の古武道、
-
弓道とか出水兵児修養掟とか。
-
かつての歴史に誇りを持つ地元の気概を感じました。
-
出水麓歴史館のすぐ近くにある出水御仮屋門は、控柱付腕木門という16世紀末頃の建造とされる門です。
今では出水小学校の正門ですが、もともとここは島津家から派遣された地頭の役所があった場所。島津家の藩主は、参勤交代の際はここで一泊して江戸に向かったのだそう。由緒正しい雰囲気がある端正な意匠です。 -
では、ここから出水麓武家屋敷群にある公開建物を回ります。
まずは、竹添邸。 -
この竹添氏は、もともとは人吉城主、相良氏の一族で、
-
島津氏との和睦の後、島津氏に仕えたのだとか。
-
出水麓に移ってからは、
-
代々郷士年寄噯などの重職を勤め、140~170石の家柄。なお、現在の建物は幕末から明治にかけて建てられたもののよう。
-
玄関から
-
上がってすぐのいろりのある広間から、左手に向かうと
-
なかえ、次の間、奥座敷へと続きます。
次の間の方から見る玄関の方向や -
次の間から奥座敷の方向もとても余裕を感じるし
-
イチオシ
奥座敷は赤い土壁の床の間が格式を示すもの。重々しくも品格があるように感じます。
-
広間から右手に向かうと、仏間、
-
座敷へと続きます。
薩摩の上級武士は意外に豊かだったのではないかと感じました。 -
表通りに出て、
-
今度は、税所邸です。
-
税所家も竹添氏と並ぶ重役クラス。
-
加世田から移り、代々、上級郷士噯などの要職を勤めた家柄だとか。
-
最初に庭の方をチェックしましょうか。
-
平庭に向かって、緩みのない意匠の平屋建物です。
-
玄関から正面に向かって下座敷から、あって、
-
広間、奥座敷への動線と
-
下座敷から左手に向かう次の間から、
-
上座敷へ。
二つの動線があるのは竹添邸と同じですが、 -
イチオシ
座敷と奥座敷と言っていたのが竹添邸なら、こちらは、下座敷、奥座敷、上座敷となっていて、上座敷がある分、竹添邸より一格上のような構えかな。とても見応えがある武家屋敷だと思います。
-
上座敷から先ほどの平庭を眺めるとこんな感じ。
ちょっと殿様気分になれるような気がしますね。 -
知覧麓の武家屋敷では屋敷には上がれず、庭だけを拝見したのであまり分かりませんでしたが、薩摩藩の上級武士というのはかなり立派な身分だったみたいですね。
城下には住んでいないけれど、格式はあって悠々とした暮らし。それこそ、西郷や大久保とかは城下には住んでいても下級武士。大きな身分の違いがあったのではないかと思います。それを乗り越えて、大藩の薩摩藩を動かしていった熱量はどれほどのものだったのか。また、彼らの才能を見抜いた島津斉彬の慧眼にも改めて敬意を表したいと思います。 -
出水麓武家屋敷群から出水市歴史民俗資料館にも寄ってみます。
-
出水麓歴史館とちょっとダブるのかなと思っていましたが、こちらは、石器や土器から始まって、戦前の時代からの生活道具類までを網羅。確かに民俗資料の展示が多いですね。その分、ちょっと雑多な印象もなくはないですが、こういう施設は伝統のある街には必要なもの。しっかり地元の思いに守られている施設だと思います。
-
出水駅に戻ってきて。
出水市出水駅観光特産品館は、出水駅に併設されたお土産物のショップ。 -
ちょっと古風な感じもしなくはないですが、それなりの品揃え。観光案内もやっていて、駅近くの食堂の情報をいろいろ教えてもらいました。
-
ということで、紹介してもらった中から、味処 心へ。ホテルに入っている居酒屋さんです。お酒は飲まないのでどうかなと思ったのですが、特に問題はないですね。
-
イチオシ
ウリは地元の名物、鳥の料理のようで、鳥の刺身を使った親子丼ぶりや追加で鳥刺しを注文しましたが、いやいやこれはおいしいですね。
-
それに、九州の甘い醤油がとても良く合う。それもけっこうなサプライズでした。
これで長かったような短かったような七日間の旅はおしまい。出水駅からは新幹線で帰ります。お疲れさまでした。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (2)
-
- ももであさん 2024/11/09 09:02:00
- 鶴の一声
- 明治中期には1羽も渡来しないなんて、危険を察知する
ツルは賢いですね。これもボスヅルの一声?
世界の5割のツルが出水とはすごい!!
でもそれって感染症でも起こせは一気に絶滅の危機
誰かの一声で対策が必要ですね
急に寒くなってきたから自分も越冬したい...
- たびたびさん からの返信 2024/11/10 20:46:19
- RE: 鶴の一声
- ももであさんは、お初でしょうか。コメントありがとうございます。
ご指摘のように鳥インフルエンザのリスクがあるので、飛来地の分散化の計画もあるよう。先を読んで、いろんな取り組みがあって、さすがだなあという感じですね。
たびたび
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
もっと見る
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?









































































































































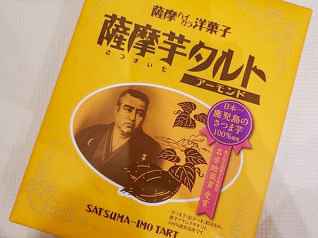




2
102