
2023/08/28 - 2023/08/30
652位(同エリア2204件中)
![]()
公共交通トラベラーkenさん
- 公共交通トラベラーkenさんTOP
- 旅行記546冊
- クチコミ3900件
- Q&A回答0件
- 1,016,792アクセス
- フォロワー38人
この旅行記のスケジュール
2023/08/29
-
二葉姫稲荷神社
もっと見る
閉じる
この旅行記スケジュールを元に
2023年8月28日(月)~30日(水)の2泊3日で京都観光に出かけてきました。今までJR東海ツアーズの「フィフティプラス」という格安プランを利用して関西旅行に出かけていたのですが、そのプランが2023年9月をもって終了することになりました。今回は最後の「フィフティプラス」プランということで四条駅近くのホテルを起点に、主に京都の北側を観光します。猛暑の中、汗だくの観光で体力の消耗は激しかったのですが、カフェで休憩をしたりしながらなんとか2泊3日の行程をこなしてきました。
【旅行記その2】は、鞍馬山ハイキングから貴船神社、少し移動して上賀茂神社の観光です。相変わらずの猛暑日ですが、鞍馬山は風が涼しくて案外快適なハイキングを楽しめました。
- 旅行の満足度
- 5.0
- 観光
- 5.0
- グルメ
- 5.0
- 同行者
- カップル・夫婦
- 一人あたり費用
- 3万円 - 5万円
- 交通手段
- 高速・路線バス 私鉄 徒歩
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
旅行2日目、ホテルの朝食は1階にあるイル・キャンティというイタリア料理のお店で食べます。
-
メインのソーセージパン(何かとてもカッコイイ名前が付いていました)がとても美味しかったです。それ以外のサラダとスープのバイキングもかなり美味しかったです。
-
地下鉄烏丸線四条駅から乗って、終点国際会館駅下車。そこから叡山電鉄鞍馬線八幡前駅まで徒歩で移動しました。今日も朝から日差しが強く、歩くのは少しきつかったです。
八幡前駅 駅
-
電車が来ました。叡山電鉄はローカル感あふれる良い電車です。
-
終点の鞍馬駅に到着。
鞍馬駅 駅
-
鞍馬といえば天狗です。
鞍馬山大天狗 名所・史跡
-
叡山電鉄デナ21保存車両の展示があります。
とりあえず記念撮影しておきます。 -
それでは鞍馬山に登りましょう。山の南面には鞍馬寺があり、参道が整備されています。
-
鞍馬山というと密教系の山岳修験の場というイメージだったのですが、鞍馬寺は鞍馬弘教という天台宗系の新宗教教団の総本山なんだそうです。教義には神智学協会の影響が強いのだとか。
仁王門で愛山費500円払って中に入ります。 -
こちらの狛犬は犬ではなくて虎です。
-
ご本尊の毘沙門天の使いが虎なんだそうです。
昨日は護王神社の狛猪、今日は鞍馬寺の狛虎です。 -
ケーブルカーに乗って行く予定だったのですが、ほんのわずかの差で乗り損なってしまいました。大した距離でもなさそうなので、徒歩で登ることにしました。
-
参道の途中にいろいろと小さな社があるようです。
-
放生池。
-
滝行の場ですかね。
-
吉鞍稲荷社。
-
白長龍神・白姫龍神言う神様が祀られていました。
-
参道の階段をさらに登ると少し広くなった場所に古びた鳥居と崖の上の小さな社がありました。どうやら鬼一法眼を祀る社らしいです。
-
どなたかいらっしゃいますね。
-
由岐神社(ゆきじんじゃ)という表示があります。
由岐神社例祭 鞍馬の火祭 祭り・イベント
-
940年、御所内に祀られていた祭神をこの地に勧請したのが始まりの神社です。ここで行われる「鞍馬の火祭」は京都三大奇祭の一つとして有名なんだそうです。
-
鳥居をくぐって階段を登ります。
-
拝殿の真ん中を階段が通っています。これは割拝殿という珍しい拝殿で、桃山時代の代表的建造物でもあり現在は国の重要文化財に指定されています。
-
この拝殿は慶長12年(1607年) 豊臣秀頼により再建されました。
-
拝殿を過ぎると参道の脇に巨大な一本杉がそびえ立っています。
-
階段の両側に小さなお社がいくつか並んでいます。冠者社はもともと鞍馬の冠者町に祀られていたもの。商売繁盛のご利益あり。
-
岩上社、御祭神は事代主命(ことしろぬしのみこと)。
-
先ほど見えた杉の根元には大杉社があります。
-
白長弁財天社。
-
古い拝殿、杉の巨木、小さな社が並ぶ急な階段、神聖な雰囲気がギュッと詰まったエリアです。
-
拝殿は現在工事中でした。
-
完成したらかなり立派なものになりそうです。
-
さらに先に進みます。この参道は九十九折参道(つづらおりさんどう)というそうです。途中に川上地蔵堂がありました。遮那王(源義経)が日々参拝したお地蔵様なんだそうです。
-
義経供養塔。この辺りに幼少の源義経が住んでいた東光坊があったそうです。
-
中門に到着。本殿まではもう少しです。
-
福寿星神と書いてあります。御祭神は寿老人・福禄寿です。
-
なかなかたどり着きませんね。
-
巽の弁財天社。
もう少しで本殿です。 -
寝殿。貞明皇后の行啓の際、休息所として建造された寝殿造りの建物です。普段は非公開になっています。
-
転法輪堂。
-
木造阿弥陀如来坐像がおわします。
-
本殿金堂に到着しました。
-
京都の町を見渡せるような展望台があると思ったら立ち入り禁止になっていました。なにか神聖な役割があるのでしょう。
-
とても良い景色です。
-
本堂の前にある金剛床。「宇宙のエネルギーである尊天の波動が果てしなく広がる星曼荼羅を模し、内奥に宇宙の力を蔵する人間が宇宙そのものである尊天と一体化する修行の場となっています。」ということらしい。
-
真ん中の△に立って瞑想しているお兄さんが去った後、私たちも順番に立ってみましたが、エネルギーは感じませんでした。とりあえず記念撮影スポットとしては良いと思います。
-
本堂の裏にある閼伽井護法善神社(あかいごほうぜんじんじゃ)。水の神を奉安しています。
古典の授業で、「閼伽」はラテン語の「アクア」と語源が一緒だと習った記憶があるのですが、調べてみるとこれは俗説だったようです。 -
本堂の中は撮影禁止でした。続いて奥の院に続く参道を進みます。
-
ここからさらに鞍馬山を登って、貴船川の方まで降りて行くコースになります。
-
義経公息つぎの水。
-
屏風坂の地蔵堂。
お堂の前の坂道が以前は一枚岩で屏風を立てたような急坂になっていたためにこの名前が付いたと案内看板にありました。 -
義経が鞍馬山を出て奥州平泉に向かう際、名残を惜しんで背比べをした岩があります。矢代の中にあるのかと思って覗き込みますが、いくら何でも小さすぎですね。
-
こっちでした。それでも結構小さいですね。義経公16歳の時の話なんだそうです。
-
木根の道という表示がある場所に来ました。
確かに木の根っこで覆われた道です。木の根道 自然・景勝地
-
大杉権現社という所に来ました。
大杉権現社 寺・神社・教会
-
肝心の大杉は台風の影響で根元から倒れてしまったそうです。
-
参道のあちこちに倒れた樹木があります。
「鞍馬山では、お山自体を尊天の御身体と考えており、お山の清浄さを保ち、豊かな自然を守ることが何より大切に思っています。・・・・倒木は、出来るだけそのままにして、空間や時間や「いのち」の大いなる自然の循環を妨げないようにしています。」とホームページにありましたので、わざとこのままにしてあるのでしょう。 -
倒木から生えてきた白いキノコ。たぶんこれが「大いなる自然の循環」ですね。
-
僧正谷不動堂までやって来ました。
僧正谷不動堂 名所・史跡
-
この辺りで牛若丸が鞍馬天狗から兵法を学んだそうです。
-
義経堂もあります。
-
奥の院魔王殿。
鞍馬山の本尊は三身を一体の「尊天(そんてん:この世に存在するすべてを生み出している宇宙生命・ 宇宙エネルギー)」として仰いでいます。
三身とは月輪の精霊であり愛の象徴「千手観世音菩薩」、太陽の精霊であり光の象徴「毘沙門天王」、大地の霊王であり力の象徴「護法魔王尊」のこと、らしい。 -
奥の院には護法魔王尊が祀られています。
護法魔王尊は全宇宙の創造主たる存在に命ぜられ、650万年前というはるか昔の地球に、人類を救済するため金星から降り立ったそうですよ。 -
さらに護法魔王尊のオリジナルはサナト・クマラというインドの神様らしい。ヒンズー教の創造神ブラフマーの息子です。
信仰心のない私にはもう理解が及ばない世界です。 -
貴船川の方まで降りてきました。
-
貴船側からの入り口。
-
貴船川といえば川床料理。
お昼にはまだ時間があるのでお客さんが入っていない座敷をのぞいて撮影させてもらいました、無断で。 -
貴船神社に入ります。
貴船神社 寺・神社・教会
-
貴船神社は全国に二千社を数える水神の総本宮です。主祭神は高龗神(たかおかみのかみ)。龗(オカミ)は龍の古語であり、龍は水や雨を司る神として信仰されていたそうです。
-
貴船神社は絵馬発祥の地でもあるそうです。
-
貴船神社奥宮に向かいます。川沿いの細い道を歩きますが、川床料理を食べに来たお客さんの車が頻繁に通るので大変歩き難い道でした。
-
貴船川の清流と参道の樹木のおかげで、この辺りはかなり涼しいです。
-
手水の水も山からの湧き水でしょう、とても冷たくて気持ち良かったです。
-
奥宮に到着。
-
すっきりとした境内です。
-
御船形石。海上安全のご利益があるそうです。
-
奥宮は大体シンプルなつくりをしていますね。
-
玉依姫命(神武天皇の母)が黄船に乗って浪速(大阪)から淀川、鴨川、貴船川をさかのぼって当地に上陸し、そこに祠を営んで水神を祀ったのが始まりとのこと。貴船の起源が「黄船」であるという説もあるそうです。先ほどみた船形石はこの伝説にまつわるものです。
さらに、本殿の下には巨大な龍穴があるそうです。 -
社伝を聞いただけでも只者ではない感じがします。
その他にも宇治の橋姫伝説や和泉式部の恋願成就などの逸話もあるそうです。昨日観光した金輪の井戸でも貴船神社まで丑の刻詣りにくる話が出てきました。 -
思ったより見ごたえのある神社でした。川床料理は高いのでパスして、このまま川沿いの道を下って貴船口駅まで移動します。
-
川床料理店の並ぶエリアが昼時で渋滞を起こしていました。歩道もない細い道を料理屋の送迎マイクロバスや自家用車が行き来するので、歩行者にはかなり迷惑な状況です。なんとか電車の時間に間に合って駅に到着しました。
貴船口駅 駅
-
鞍馬山から貴船神社へのハイキングはこれで終了。
ここから電車とバスで移動します。 -
市原駅で下車します。
ここからバスに乗り換えて御薗口町[上賀茂神社前]バス停まで移動します。
あまり観光客の利用する駅ではないようで、バスも地元の学生やご老人ばかりでした。市原駅 駅
-
上賀茂神社を観光します。
-
その前にお昼ご飯にします。
-
一膳飯屋りぃぼんというお店が良さそうなのでここにします。
一膳飯屋 りぃぼん グルメ・レストラン
-
ごはんセット。主菜は和風ハンバーグを選びました。
京風豚汁白味噌風味、お釜でその都度焚いてくれる近江米のご飯、高菜漬とサラダ、全部美味しかったです。もちろんハンバーグも最高でした。 -
こちらもごはんセット、主菜は京九条葱たっぷり葱豚巻き。女性に人気NO.1のメニューらしい。葱豚巻きが最高に美味です。ボリュームも満点です。
-
移動中のバスの中で検索して飛び込んだお店でしたが、大当たりでした。
いつかまた来たいと思いました。 -
上賀茂神社を参拝します。
賀茂別雷神社(上賀茂神社) 寺・神社・教会
-
ユネスコの世界遺産に「古都京都の文化財」の1つとして登録されている、京都最古の歴史を有する神社です。主祭神は賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)。
-
二つの大きな円錐の山が有名な立砂(たてずな)。
-
境内には珍しい建物がたくさんありますね。
これは橋殿という建物。境内を流れる、ならの小川に架かっています。 -
とてもきれいな小川が流れています。
-
ちょうど「国宝・本殿特別参拝とご神宝拝観」をやっていました。
私たちのような信仰心のない者が入ったらきっと神罰が下ると思ったので、入るのはやめました。 -
小川に沿ってきれいな砂利の参道を歩きます。
-
渉渓園という庭園に入りました。
-
さらに奥に進むとたくさんの鳥居が見えてきます。
二葉姫稲荷神社という神社があるようなので行ってみます。 -
元々ここには上賀茂神社の第一摂社、片山御子社(片岡社)の神宮寺(神社に附属して建てられた仏教寺院や仏堂)があって、その神宮寺の鎮守社(お寺を護る神社)として祀られたのがこの二葉姫稲荷神社なんだそうです。
つまり上賀茂神社の摂社の神宮寺の鎮守社ということですね。 -
明治時代の廃仏毀釈で神宮寺は廃絶、二葉姫稲荷神社だけが残ったという経緯があるそうです。
-
鳥居の続く階段を登ると二葉姫稲荷神社の末社がいくつか並んでいます。上賀茂神社の摂社の神宮寺の鎮守社の末社です。
八嶋龍神は神宮寺にあった池に祀られていた龍神で、神宮寺廃絶にともない池も埋められてしまったそうです。その後龍神が村人の夢に現れたため、二葉稲荷神社に祀られることになったという伝説があります。 -
八嶋龍神様は神宮寺の池の中央にあった辨天島に鎮座していたそうで、ご神体はその辨天島の主岩石である、と解説の木札に書いてありました。
-
御影龍神。
神宮寺の池には、水を抜くと日照りが続くという伝説があったそうで、神石を御神体としたこの御影龍神には、手桶にいっぱいの水が備えられているらしい。
御影龍神と八嶋龍神は別の龍神様なのかな?よくわかりません。 -
天之斑駒神社(あめのふちこまじんじゃ)。
スサノオが皮を剥いで家忌服屋(いみはたや)に投げ込んだ馬のことらしい。なぜここに祀られているのかはよくわかりません。 -
金毘羅社。
-
そして二葉姫稲荷社
-
いろいろ書いてきましたが、結局「二葉姫」の由来が良くわかりませんでした。ネットで調べると、なんだか胡散臭いスピリチュアル系の記事が散見されます。
歴史が古い場所なので、色々な経緯があるのは確かですが、すぐに心霊だのパワースポットだのにこじつける現代人の発想の貧困さに、神様も辟易していることでしょう。 -
世界遺産の神社らしく見ごたえ満点でした。
-
上賀茂神社の観光はこれくらいにして先に進みましょう。
-
賀茂川沿いを少し歩きます。地図を見ると、出町柳の高野川との合流地点を境に、それより上流は賀茂川、下流を鴨川と表記するようです。
下流の鴨川に比べて川幅も狭く、流れも静かです。心が落ち着く穏やかな風景が続きます。 -
地下鉄烏丸線北山駅に到着。駅の隣にある京都府立陶板名画の庭という野外ミュージアムも見学する予定だったのですが、暑すぎて野外は無理だろうということになりました。
-
丸太町駅で下車。
-
昨日も眺めた大丸ヴィラ(中道軒)。
大丸ヴィラ 名所・史跡
-
昨日も眺めた聖アグネス教会。
日本聖公会 聖アグネス教会 寺・神社・教会
-
京都府庁旧本館にやって来ました。
京都府庁旧本館 名所・史跡
-
明治37年(1904)に立てられた洋館で、国の重要文化財に指定されています。
-
設計は京都府の技師を務めた松室重光。
-
内部に入るのは今回が初めてです。
-
昭和46年まで京都府庁の本館として使用されていました。現在でも執務室として現役で使用しています。創建時の姿をとどめる現役官公庁建物としては日本最古なんだそうです。
-
旧議場。現存する日本最古の議場とされています。一般見学の他、催し物等の会場として有料で開放しているそうです。
-
とてもオシャレな内装です。
-
2階には上がれないみたいです。
-
本館の2階を見学します。
-
知事の執務室。
スタッフの女性が詳しく説明しながら案内してくれます。 -
暖炉。装飾が凝っています。
-
天井に小さな隙間があります。
-
よく見ると天井裏にレンガが見えます。外観からはわかりませんが、この庁舎は実はレンガ造りです。
-
庁舎1階に「salon de 1904」という喫茶店が7月にオープンしているので、そこに立ち寄って見たら、お客さんがいっぱいで、30分から1時間待ちと言われました。待ち時間を利用して2階を見学していたので、スタッフの女性が気を遣って少し急ぎ目に案内してくれています。
-
急ぎ目に、というのは内容を省略して案内するということではなく、解説のスピードを1.5倍速くらいにするということらしいです。かなりの早口で建物に関する情報を詰め込んできます。おかげであまり頭に入って来ませんでしたが、とにかく現役で使用している貴重な近代建築だということは理解できました。
-
見学を終えて1階の喫茶室に来てみるとちょうど私たちが呼ばれる番でした。
-
店内は天井が高く明るい雰囲気です。
-
前田珈琲という、京都市に何軒か店舗があるお店が運営しているようです。店員さんの対応もとても丁寧でいい感じです。
-
プルプルカプチーノパフェとアイミを注文。
-
パフェの上に載っているのがプルプルゼリーでした。かなり美味です。
-
アイミ。
前田珈琲といったらコレというぐらい長い間親しまれたアイスミルクティー、という解説どおり、大変美味しいミルクティーでした。紅茶の風味がしっかりとしていてミルクの甘みに負けていないのが良かったです。 -
京都府庁旧本館は近代建築好きな方なら間違いなく満足できるスポットです。見学自体は無料ですのでオススメです。
-
入り口の守衛所の奥に京都慶應義塾跡の石碑があります。「独立自尊」の文字は福沢諭吉のもの。
-
本日は山歩き、寺、神社、近代建築と、バランスの良い観光ができました。
若干歩き過ぎで足が疲れていますが、一晩寝れば治るでしょう。 -
今日もスーパーの惣菜で夕飯は簡単に済ませます。何を買ったか忘れましたが、結構美味しかったんだと思います。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
もっと見る
この旅行で行ったグルメ・レストラン
八瀬・大原・貴船・鞍馬(京都) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?



















































































![市原駅で下車します。<br />ここからバスに乗り換えて御薗口町[上賀茂神社前]バス停まで移動します。<br />あまり観光客の利用する駅ではないようで、バスも地元の学生やご老人ばかりでした。](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/travelogue_pict/78/74/54/650x_78745457.jpg?updated_at=1694519747)





































































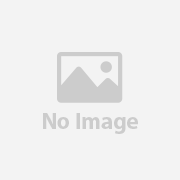





















旅行記グループ 2023年8月28日~30日 夏の京都旅行
0
139