
2015/01/04 - 2015/01/04
1029位(同エリア4449件中)
![]()
belleduneさん
- belleduneさんTOP
- 旅行記839冊
- クチコミ134件
- Q&A回答177件
- 1,388,789アクセス
- フォロワー62人
昨年10月に、旧三菱一号館のレストランへ行って、当初の銀行営業室の内部を見て来たのですが、時間がなくて、美術館の庭園や建物を細かく見ることが出来ませんでした。お正月で混んでいるかとは思いましたが、日比谷図書館へ行った序でに、行って来ました。それ程混んでなくて、ゆっくり建物を見ることが出来ました。
- 旅行の満足度
- 4.5
- 交通手段
- 徒歩
PR
-
1月4日から日比谷図書館が開館したので、新書を受け取りに来ました。ここは、日比谷図書文化館として色んな展示もあり、緑豊かな公園を目にしながら、読書できるので気に入っています。いつもは3階のオープンな閲覧室の窓際の机に座って、本を読んだりするのですが、お昼頃には満席状態になってしまいます。4階の内田嘉吉文庫や有料の特別室なども一度覗いてみてください。
-
日比谷公園を抜けて、旧三菱第一号館へ歩いて行きます。風もなく、穏やかな晴天の1日です。
-
ザ・ペニンシュラ東京を通り過ぎて...
-
右から書かれた竣工当時の「第一生命保険株式会社」
1938年に竣工した第一生命館は、渡辺仁、松本与作の設計で建てられましたが、一体街区による建て替えで、隣接する産業組合中央金庫事務所(1933年)と共に、建て替えられました。 -
お堀の方向角に、現・明治安田生命ビル明が見えます。明治時代には馬場先通り辺りは、赤煉瓦街の景色が倫敦の街に似ていたので、「一丁倫敦」と言われ、東京駅の方へ行ったところは、「一丁紐育(N.Y.)」と呼ばれていました。
-
当時の写真ですが、上が「一丁倫敦」の赤煉瓦街と言われていたもので、下が20年程後の「一丁紐育」辺りの景色です。市区改正と共に、区画が整理されて、最初のオフィスビルとして旧三菱一号館の建設が始まりました。ジョサイア・コンドルを中心に当時の英国ヴィクトリア時代の正統クイーンアン様式で統一され、明治27年(1894)に竣工しました。
-
やっと到着しました、旧三菱一号館と34階建ての丸の内パークビル。
-
三菱が丸の内の払い下げを受けた後、三菱社の二代目社長・岩崎弥之助と管事・本社支配人の荘田平五郎が、この地区の開発において、文化開化の時代に洋風の街造りが相応しいと考えました。荘田は、ジョサイヤ・コンドルを三菱社の建築顧問に迎え、曽禰達蔵を三菱地所の前身である「丸ノ内建築所」に入社させて、丸の内建築計画をスタートさせました。
-
江戸時代の地図で見ると、+印を付けたところが馬場先通りと大名小路の交差する辺りです。
-
右が旧三菱一号館で、左は、ジョエル・ロブション丸の内店が1階に入っている丸の内ブリックスクエアです。
-
簡単な手描きですが、馬場先通りに面した両端4つの角を埋めるように、コンドル、曽禰が設計した三菱二号館(1895)、三号館(1869)が建設され、その後、妻木黄頼の設計による東京商工会議所(1899)が建ち、「三菱村の四軒長屋」と呼ばれました。次第に、四軒長屋の間に煉瓦造りのオフィスビルが建設され、明治44年(1911)に三菱十三号館が完成し、大名小路から内濠までの約200mの馬場先通りの両側に、軒高50尺(約15m)の煉瓦造り建築が建ち並びました。「一丁倫敦」と呼ばれたのも分かりますね。
-
当時の丸の内辺りの地図ですが、黄色のところが旧三菱一号館(後の東9号館)で、左手の東京駅から行幸通り辺りを「一丁紐育(N.T.)」と呼んでいました。大正3年(1914)の東京駅完成後、駅前地区にアメリカ式の大型事務所建築が続々と建ち並んでいったので、こう呼ばれたのでしょう。
-
地下1階、地上3階で、煉瓦と石を積み上げて、壁を積築する組構造になっています。基礎形式は、摩擦杭の役割をする松杭による浮地形でしたが、復元工事後は免震構造になっています。三菱本社とテナント(5区画)が其々地下1階から3階までを縦割りに使用する棟割長屋形式でした。1950年代になると、築50年以上の第一世代のオフィスビルが老朽化し、機能的、規模的に維持し難くなってきます。三菱財閥解体後の建物資産を引き継いでいた三菱地所は、昭和34年(1959)に建て替える「丸の内総合改造計画」をスタートしました。保存・移築も検討されましたが、結局、昭和43年(1968)に取り壊され、1971年跡地に地下4階、地上15階建の「三菱商事ビルヂング」が建てられました。
-
2004年に、旧三菱一号館の建っていた敷地を含む街区の再開発事業が始まりました。三菱商事ビル、古川総合ビル、丸の内八重洲ビルの街区で、「日本における近代オフィス街丸の内の原点となる建築を原位置に復元することで、近代都市の歴史を発信する意義がある」というスローガンの元に工事が進められました。
-
レストラン内部を見たかったので、早めに来て良かったです。まだ席が空いていたので、店内を撮ることが出来ました。
-
営業室の格天井は、3階の床を支える6本の独立柱と取り合い格子状にデザインされたもので、柱頭に細かい装飾が施されています。柱頭飾りの木材はトネリコ属で、復元に際してはタモ材を使用したそうです。仕上げはワニス塗装で、柱脚、柱、柱頭、格天井、腰羽目板、建具関係は全て同じ仕上げになっています。当初、木材の塗装を剥して形状を確認したところ、アカンサスの葉をモチーフにした部分に虫食いの跡を彫るという当時の職人の遊び心が見られたということです。
-
回廊は、吹き上げ上部の窓の開閉、メンテナンスのために付けられたと考えられました。当初の写真から壁上部は漆喰仕上げになっていました。
-
-
銀行の営業室カウンター近くの席だったので、窓口の細かい仕様を見ることが出来ました。カウンターは、木の腰羽目板で、天板も木製。その上に真鍮とガラスのスクリーンが立てられていました。実存している例として、佐立七次郎が設計した旧日本郵船小樽支店や辰野金吾が設計した旧日本銀行小樽支店に残されている木製カウンターも参考にしたそうです。照明は、当時ガス灯だったので、その形状を復元してあります。
-
カウンター下の引き出し部分です。
-
壁にアーチ型に凹みがあるのは、煉瓦組構造では、壁に開口を設ける場合、予め開口する上部にマグサを入れるか、煉瓦アーチを組んでおく必要があります。煉瓦壁は後から、自由に開口を開けることができないのです。設計の段階で、貸事務所のテナントが、壁に開口が設けられるように、アーチが仕込まれていたと考えられています。これが、復元時にとても有効に機能することになっています。チケット売り場やショップの内部は撮影禁止なので、行って見るしかありませんが、扉の上部の煉瓦アーチやその下のマグサ、梁受け石、木煉瓦などを見ることが出来ます。
-
1階のチケット売り場とショップだけは、復元後、床以外、壁や天井の内装仕上げは行わないで、躯体をスケルトンで見せることにしたそうです。煉瓦壁で黒く見えるのは、木煉瓦で、床から20cm程上の横方向に点々と並ぶ木煉瓦は、幅木を取り付けるためのもの、また天井近くに並んでいるのは、天井廻縁と取り付けるためのもの、扉の開口周りに見られるものは、化粧枠を取り付けるためのものだということです。
-
当初、床仕上げは、客溜りが英国ミントン社製のタイル貼り、執務エリアがフローリングでした。復元に際して、ミントンと同じヴィクトリア時代から続く「MAV&Co.」のタイルで代替したそうです。
-
お正月に来た時は、丸の内ブリックスクエアのコーナー入り口から一号館広場へ入ります。この右側1階がジョエル・ロブションが入っています。左は、ブリックス・アネックスで、色んな店舗が入っています。
-
丸の内パークビルが見えます。
-
一号館庭園へ
-
日中の中庭のガス灯が
-
夜になると、こんな風にガス灯が灯っていて、炎がゆらゆら揺れていて、辺りにノスタルジックな雰囲気が出ていました。電気だとこういう感じにはなりませんね。
-
旧三菱一号館の外壁に使用されていた煉瓦は、解体時に石や鉄は採取されていたが、肝心な煉瓦は採取保管されていませんでした。解体前の最後のテナント、富士電機が外壁の化粧煉瓦を大切に保管されていたことを知り、同社の厚意で借用して、詳細な分析をすることができたということです。その結果、当時東京には大規模な煉瓦工場がなく、大量に必要な時は、小菅集治監(現・小菅刑務所)で造っていたそうです。
-
旧三菱一号館の化粧煉瓦は、表面のテカリがなく、しっとりした滑らかな質感だったという。明治期の煉瓦は、木枠に粘度を上から落すように叩き入れ、木枠を外して成形する方法でした。こうすると、成形のための圧力は高くなく、木枠と煉瓦表面が擦れる跡が付かないのです。現在では、機械で、金型に粘度を圧入して、押し出されてきたものを切断するという方法なので、煉瓦の色は似ていても、当初の質感がでないそうです。230万個もの煉瓦を昔ながらの方法で、作ることはできないかと探したところ、中国上海の西方、太湖にある長興(チャンシン)に、木枠による単品製造をしている工場があるということが分かりました。230万個を製造するのに、1年以上掛かったそうです。
-
外壁に使用されていた石材は、2種類だったそうです。窓枠、蛇腹、角石などに使用され、彫刻を施された安山岩は、伊豆石の一種、横根沢石で、また基壇に使用されていた白い花崗岩は、瀬戸内海の北木島の北木石でした。其々の石は、中国福建省の泉州(厦門)の工場へ運ばれて、加工されました。
-
-
-
屋根の復元設計には、解体時の写真や図面が少なくて、大変苦労したそうです。屋根はスレートと銅板で葺かれていました。
庭園に置かれたヘンリー・ムーア作の「腰かける女」。 -
左部分が、復元時に取り付けられた透明ガラスの避難設備、エレベーター、トイレなどの設備エリアとなっています。
-
棟割長屋形式の事務所建築だったため、中廊下が通っていませんでしたので、煉瓦アーチ部分を活用して、観覧者が展示空間を移動する開口を設けました。当初、煉瓦アーチではない壁にやむを得ず開口を新たに開ける場合は、PC製のマグサを挿入して、竣工当時のオリジナルと区別したそうです。
-
-
-
屋根の頂部には棟飾りや避雷針が取り付けてあります。どちらも、当初と同じ製造方法で復元されたということです。
スレートは、粘板岩の板状に割れる性質を利用した屋根材で、宮城の雄勝産のものでしたが、現在では、文化財などの修復でしか使用されることのない天然スレートの工場は小規模で、職人の高齢化などもあって、結局、スペイン産の天然スレートの中から雄勝産に近いものを使用することになったそうです。 -
この写真は、馬場先通りに面した建物表側ですが、その正面小屋根にのみ、雄勝産の天然スレートを調達することができたそうです。平成23年の東日本大震災ので、この雄勝町の工場は津波に飲み込まれてしまったそうです。
-
美術館の展示室は、精密な空調設備が必要だったため、地下1階と小屋根に空調機器が設置され、1階は地下から、3階は小屋根からダクトで振り回し、復元された廊下の内部空間や展示室の旧事務室の天井を改変ぜずに済んだそうです。しかし、2階は上下からの供給ができないため、展示室に隣接して空調機械室やダクトスペースを設けて、2階展示室のみ天井高を下げて、天井の復元を行わなかったということでした。
-
外部建具は木製で、窓は木枠にパテでガラスを留めていましたが、復元時はパテの代わりにシールを使用しています。窓は、左右両開きとなっていましたが、階段室だけが上げ下げ窓になっていました。明治期のガラスは、手拭き円筒法という手作りのものでしたが、現在では入手困難でした。1952年に東京駅前の新丸ビルが解体された時の古いガラスを使用したそうです。特に大きなガラス以外は、この古いガラスが再利用されました。
-
3階の展示室は、天井とマントルピースを復元し、空調の吹き出し、消防設備、展示照明などの設備機器を設備プレートという金属パネルに仕込み、天井とは切り離して、下部に独立して設置してあります。
-
当時、馬場先通りにあったガス灯も復元されています。
-
夜に来てみると、写真では、ガス灯の炎が撮れていませんが、実際に見ると、ゆらゆら揺れていますよ。
-
-
-
-
-
屋根には多くの煙突があります。1つの煙突は、1つの暖炉と煙管で繋がっているため、煙突の数だけ暖炉があることになります。陶器の煙管の周りに、コンクリートを巻いて固めていたのは、地震で折れて落下するのを防止するためでしたが、今回の復元では、内部に鉄の骨を入れて固めてあります。煙管は束ねて大きくし、空調ダクトとして活用してあります。
-
丸の内パークビル1階は、ピロティとして庭園の圧迫感を軽減するような設計がされています。
-
-
庭園から見た美術館のガラス躯体部分。
-
旧建物の庭園側に、避難階段と廊下を新たに付けて、避難設備を整えたそうです。その部分は透明ガラスとし、煉瓦外壁が見えるようにしてあります。空調設備の給排気口を表側(馬場先通り側や大名小路側)には設置せずに、こちら側の外壁建具やドーマー窓を利用して、組み入れたそうです。また1階に中庭側から入れるようにエントランスを設け、美術品の搬入用大型リフトも設置してあります。
-
当初、庭園に面したこちら側には、場所置き場や石炭搬入などのユーティリティとして使われていました。地階への搬入のために設けられていたドライエリアや貸事務所エリアのトイレが配置されていた下屋の外壁も一部復元され、この下屋には、バリアフリーに対応したエレベーターを設置してあります。
-
-
-
コンドルは、耐震煉瓦造りのために、外壁の内部に各層毎に窓開口の上と下、各々1段の目地の中に、帯鉄という細長い鉄板が壁厚に応じて数枚ずつ敷き込んだそうです。この帯鉄は、壁が崩れる現象を抑える役割があります。明治24年(1891)に起きた濃尾地震の後、床の構法が、鉄骨梁と鉄製折板とコンクリートという防火床に変更されていました。また、床梁の端部を煉瓦壁中に差し込み、緊結させて対面する壁同士を固定する役割もあると考えられていました。木造小屋組にも、トラス面を桁行方向に互いに繋ぎ合わせる振れ止め材を設けるなど、随所に耐震の工夫が見られました。これによって、大正12年の関東大震災でも被害を受けなかったそうです。
-
外壁の煉瓦壁は、4層に亘って、計238段積まれ、外側の面を揃えながら、上に行く程壁厚が薄くなっています。煉瓦が割れるのを防ぐため、煉瓦壁内に梁受石を入れて、その上に鉄骨梁が挿入されます。現代の建築基準法に適合させるために、明治期の耐震煉瓦造りに、現代の耐震技術である免震構造を組み合わせることで、特別な補強を加えることなく、コンドルの設計した煉瓦造りの復元が可能になったということです。
-
-
-
-
-
スレートで葺かれた屋根周りや樋、ドーマー窓には、銅板金が使われていました。銅板は耐久性が高く、柔らかい性質を持っているため、加工し易く、防水が必要される箇所に使われました。屋根を飾るドーマー窓は、彫刻された木の下地を銅板で覆ったものでした。棟飾りは、繰り返しのデザインに対応した合理的な製造法の鋳鉄。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
細かいところまでよく復元されています。
-
-
-
ここからだとドーマー窓や大小の避雷針がよく見えます。
-
-
馬場先通りと大名小路が交わるところに建つ復元された外観です。
-
竣工当時の写真です。
-
馬場先通り側
-
大名小路方向
-
大名小路の三菱東京UFJ銀行本店側から見た三菱一号館美術館
-
藤村朗設計の丸ノ内八重洲ビルヂングは、昭和3年(1928)に竣工した地下1階、地上8階の建物でした。昭和21年に占領軍に接収されて、八重洲ホテルと改称。2006年に解体されてしまいましたが、丸の内パークビルディングの外壁には、当初の建物の基壇部、尖塔部が一部の石材が再利用されて、造形されています。
-
-
斜向かいにあるJPタワー側から見た丸ノ内パークビルの外観です。
-
外観の基壇部分や尖塔部にその名残を思わせる造形が見えます。
-
-
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
belleduneさんの関連旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?




































































































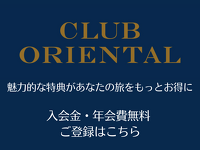









0
88