
2013/05/22 - 2013/05/22
112位(同エリア851件中)
![]()
kubochanさん
- kubochanさんTOP
- 旅行記535冊
- クチコミ499件
- Q&A回答4件
- 403,742アクセス
- フォロワー36人
石清水八幡宮界隈の散策
- 旅行の満足度
- 3.5
- 観光
- 3.5
- 一人あたり費用
- 1万円未満
- 交通手段
- 私鉄
-
京阪・八幡市駅
-
一ノ鳥居
表参道入口に立つ、石清水八幡宮の山麓の顔「一ノ鳥居」は、高さ約9m、最大幅約11mの花崗岩製。最初は木製でしたが、寛永13(1636)年に松花堂昭乗(1548〜1639)の発案により石鳥居に造り替えられました。
この鳥居に掛かる、紺地に金文字で「八幡宮」と書かれた額は、元は、一条天皇(980〜1011)の勅額で、長徳年間(995〜999)に小野道風・藤原佐理とともに平安の三蹟と称えられる藤原行成(972〜1027)が天皇の勅を奉じて筆を執ったものでしたが、現在の額は寛永の三筆と称された松花堂昭乗が元和5(1619)年、行成筆跡の通りに書写したものです。
特に「八」の字は、八幡大神様の神使である鳩が一対向かい合い顔だけを外に向けた独特のデザインとなっています -
五輪塔(航海記念塔)
頓宮殿から西側200mほどに日本最大級、超ド級と称される石造りの「五輪塔」が建っています。高さ6m、下部の方形の一辺2.4mの石塔で国の重要文化財に指定されています。
この五輪塔には、刻銘がないため、誰がどのような意図で制作したのか謎のままですが、高倉天皇の御代に「宋(中国)と貿易をしていた尼崎の商人が、石清水八幡宮に祈り海難を逃れたため、その御礼と感謝のために建立した」との伝承から「航海記念塔」とも呼ばれています。五輪塔(航海記念塔) 名所・史跡
-
頓宮
年に一度、勅祭石清水祭において山上の御本殿より御神霊が御遷しされる頓宮殿は重儀が斎行される重要な社殿です。 幕末の鳥羽伏見の戦いで焼失ののち、男山四十八坊の一つ「岩本坊」の神殿を移築し、仮宮としていましたが、現在の社殿は大正4年に造営されたもので、平成22年から同23年にかけて修復工事が行われ、昭和24年以来、実に62年ぶりの屋根の葺き替えとなり、桧皮葺であった屋根から、より耐久性のある銅板葺に葺き替えられました -
高良神社
徒然草第52段、仁和寺のある法師が山麓の極楽寺・高良神社などを本宮と勘違いし山上まで上がらずに帰ってしまったという話は有名ですが、高良神社は当宮の摂社の中でも、八幡地区の氏神様として篤い崇敬を受けています。 -
高良神社
-
エジソン記念碑
八幡の竹を使っての白熱電球の長時間点灯、実用化に成功した世界の発明王エジソンとのゆかりにより、昭和9年当宮境内の隣に「エジソン記念碑」が建立されました。そして昭和33(1958)年には現在の位置に移転され、昭和59(1984)年にはデザインを一新し建て替えられました。 -
石清水八幡宮
男山山頂にある石清水八幡宮は、応神天皇、比メ大神、神功皇后をまつる旧官幣大社である。八幡宮の遷座以前は、男山山中から湧き出る清泉を神としてまつっていた。 -
源義家は7歳にして石清水八幡宮において元服、「八幡太郎義家」と名乗り、源氏一門を隆昌に導いた。
-
-
展望台から八幡市内を眺望
-
谷崎潤一郎の文学碑
-
男山ケーブル
所要時間約3分で男山山麓−山上をつなぐ男山ケーブルは、大正15(1926)年、男山索道が八幡口 - 男山間を開業、昭和3(1928)年には男山鉄道に社名変更するが昭和19(1944)年に戦時中の鉄資材供給のため廃止されました。昭和30(1955)年、京阪電気鉄道鋼索線として八幡口(現・八幡市)− 八幡宮(現・男山山上)間を再開業し、毎年多くの参詣者を運んでいます。
鉄道の中程には、ケーブルカーの鉄橋としては日本一の橋脚(約50m)があり、車窓から途方を望めば、眼下に木津川・宇治川を擁した南山城平野が一望できます。 -
泰勝寺
-
善法律寺
三代将軍足利義満の母の実家
建物は本堂を中心に庫裡、阿弥陀堂、聖天童が配されている。その本堂は、弘安年間(1278〜1288)に石清水八幡宮の社殿を移して建立したものである。堂の柱がすべて中途で特殊な方法を用いて接いであるのは、耐震の工夫と考えられている。当初の丹朱塗は剥落しているが、純然たる鎌倉様式を伝えている。 -
正法寺
-
正法寺
-
正法寺
-
-
松花堂庭園
庭園は、泉坊の庭園を東車塚古墳の上に復元したもので、松花堂昭乗自らの手による造園といわれている。庭の中心部は、古墳の前方部の平坦なところを利用して作られており、灯篭や立ち木を除いて空間を作り、地に這う潅木と巧みな飛び石の配置、それを埋める苔によって平面の美が構成されている。ただ一本、老松が臥龍のように枝を延ばしているが、これらは旭の美を鑑賞し、その美を強調する意図が秘められている。雄大な旭の美を借景にとらえようとする昭乗の豪快な気風の一端を偲ぶことができる。 -
松花堂庭園
-
吉兆
-
航空安全祈願
-
飛行神社
飛行神社は、大正4年(1915)、航空界のパイオニア、二宮忠八が八幡市八幡土井の自宅邸内に創建したのが起こりである。 忠八は、慶應2年(1866年)6月、愛媛県八幡浜に誕生。独学で作った凧は、独創的かつ奇抜で「忠八凧」と呼ばれた。明治20年(1887)12月、丸亀歩兵連隊に入隊。四国山岳地帯で演習中、烏が残飯を求め滑空する姿に興味を示し、空を飛ぶ機械の発明に大きなヒントとなった。以後、研究を重ねて明治24年(1891)4月29日、日本人初のゴム動力による「カラス型飛行器」の飛行に成功。次に人の乗れる玉虫型飛行器を考案に着手。明治26年(1893)に設計を完了し、軍で研究開発してもらおうと願い出たが却下され、独力完成を決意。資金を貯え、自力で飛行機開発の条件が整った明治33年(1900)、京都府八幡町に土地を求め、開発に努力していたところ、明治36年(1903年)12月17日、ライト兄弟が飛行機を完成させ、飛行に成功したとの報を聞くことになった。忠八は無念の涙を流し、「飛行機を作ったとしても真似という評価しか受けない」と製作を断念したという。 -
飛行神社
-
飛行神社
-
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?














































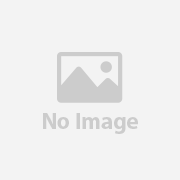
0
27