
2012/06/10 - 2012/06/10
1445位(同エリア1906件中)
![]()
滝山氏照さん
八王子駅北口から北進、甲州街道と交叉する位置に市守(いちもり)・大鳥(おおとり)神社があります。
天正18年(1890)に八王子城が落城、関東を支配する徳川家康は大久保長安(おおくぼ・ながやす)を代官頭に任命し、長安は廃城となった八王子城から浅川の南側に位置する横山の地に地割をして現在の八王子の原型を造り上げます。そして横山宿や八日市宿では定期的に市が開かれます。
市守神社についてはこの市の平穏無事を守り人々に幸せを与える市神として倉稲魂命(うかのみたまのみこと)が祀られ、これを横山市守稲荷と呼ばれ今日には市守神社となります。
現在でも毎年2月初牛の日には市守祭と呼ばれる例祭が行われています。また毎年11月の酉の日には「商売繁盛」を祈願する大鳥祭が行われ、現在でも酉の市と呼ばれ賑わっています。
2022年7月25日追記
境内入口に建立の説明板には詳細にわたって記載されています。
『 市守神社
大鳥神社 由 緒 略 記
両社の御祭神
市守神社は、武州八王子宿の入口近くに鎮座し、古くは「市神社」「市守稲荷」「出世稲荷」などと言われていた。祭神の倉稲魂命(うかのみたまのみこと)は、市場の守護神で、厄除け・開運・出世・商売繁盛・学業成就・縁結び・交通安全など霊験あらたかな神様である。
大鳥神社の祭神である天日鷲命(あめのひわしのみこと)は、殖産および武勇の守護神で、広く庶民の間に人気がある。開運・出世・商売繁盛・厄除け・縁結び・学問や技芸成就などの広大な神徳があると言われる。又、大鳥神社の祭神を日本武尊(やまとたけるのみこと)とする説もある。
両社の創立
天正18年(1590)6月23日、豊臣秀吉の天下平定戦によって八王子城は落城した。戦後処理のため、市場の再開と物資の調達が急がれ、現在の横山・八日・八幡の各町のあたり(横山の庄と言われた)に大胆な地割が行われ、今日の八王子の市街地の原型ができ上がった。そして、横山宿では毎月4の付く日に市が開かれた。六斎市である。
そして、この市の取引の平穏無事を守り、人々に幸せを与える市神として倉稲魂命が祭られた。市守神社である。市守神社の縁起に、「当社神実の履?(御神体の覆い箱)裏面に人皇五代孝照天皇勅願と記載これあり並びに長田作左衛門とあり、これ北条氏照の家臣長田氏の守護神にして京都伏見稲荷の分霊ならん」とある。
江戸時代の中期に、授福開運の神として、天日鷲命が配祀された。
なお、市守神社に八王子開宿の功労者である長田作左衛門を併祀したとする説もある。
両社の例祭
市守神社の例祭は初午祭で、毎年2月の初午の日に執り行われる。
大鳥神社の例祭は、11月の酉の日に執り行われ、古くから寿福開運を祈る
善男善女で賑わう。大鳥祭である。俗に「お酉様」とか「酉の市」と呼ばれる。最初の酉の日が「一の酉」で次が「二の酉」、その次が「三の酉」である。
大鳥祭には、社務所で神社熊手・神札・お守りなどが神社背崇敬者に頒布され、福が授けられる。
もともと、酉の市で実用品として売られていた熊手は、「福を取り込む」という縁起から酉の市の名物となった。この他、酉の市の縁起物に増えるという意味の八頭(やつがしら)や黄金餅(金持ち)、切り山椒、べったら漬けなどがある。
その他
昭和31年7月28日、市守神社は八王子市の史蹟に指定された。』
- 交通手段
- 徒歩
PR
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?













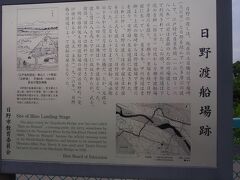










0
6