
2010/07/18 - 2010/07/18
1230位(同エリア1480件中)
![]()
まみさん
**********************
2010/07/18日 タリン観光2日目
**********************
・聖ニコラス教会見学&弦楽四重コンサート鑑賞
・アダムソン・エリック博物館見学&写真撮影
・トームペアの丘へ(アレクサンダー・ネフスキー寺院見学、大聖堂見学)
・カドリオルク公園
・KUMU(エストニア国立美術館)見学&写真撮影
【タリン泊:ホテル・バロンズ(Barons)】
**********************
タリン滞在3日目の観光は、旧市街のミュージーアムとトームペアの丘の教会2つ、それから郊外カドリオルク地区にあるクム美術館ことエストニア国立美術館へ行きました。
この日は1日曇りがちで、夕方には一時期強い雨が降りました。
後半、猛暑でうんざりし続けた今回のバルト3国旅行の中で数少ない天気のぱっとしない日でした。
そのため、この日の観光ターゲットは屋内が中心になりました。
戸外での撮影が一番楽しみなところで、曇りや雨というのはやっぱり残念ですもの。
なので、トームペアの丘めぐりは、アレクサンダー・ネフスキー教会と大聖堂を回ったらすぐに切り上げ、その時点で午後2時すぎでしたが、クム美術館へ行きました。
本日は旧市街散策の日に決めていたので、ホテルをゆっくり10時20分に出ました。
前日のラヘマー国立公園5時間サイクリングですっかり疲れたので、早起きできませんでした。
まず向かったのは、ホテルのすぐ近くの聖ニコラス教会です。
そこは、現在は教会としては機能していなくて、ミュージーアム扱いされているところです。
タリン観光では、この聖ニコラス教会の「死のダンス」の絵をとても楽しみにしていました。
‘09〜’10年版の「地球の歩き方」に、タリンで見られる中世芸術の一つとして大きく取り上げられています。
そのページには、「死のダンス」だけでなく、聖ニコラスと聖ヴィクトルの生涯を描いた主祭壇も紹介されています。
それもこの聖ニコラス教会で見られます。
さて、タリンで楽しみにしていた「死のダンス」の絵ですが、ペストが大流行した中世ヨーロッパで流行った「死」がテーマの絵は、現存しているものはとても少ないそうです。
どうりで、「死のダンス」の絵を見る機会があんまりないと思った!
タリンの聖ニコラス教会にあるのはその数少ない現存作品です。
思い起こせば「死のダンス」のテーマの絵に初めて魅せられたのは、1992年春のイタリア旅行でピサに行ったときです。
見た絵の記憶は薄れてしまったのですが、今でもあのときの感動はよく覚えています。
当時、ピサの斜塔は立入禁止でしたので、ピサでの思い出は、死のダンスの壁画もあったカンポサントのシノピエ美術館が一番印象に残っています。
かのシノピエ美術館で見られる壁画の中でも有名なのが1360年から80年にかけて描かれたという「死の勝利」「最後の審判」「地獄」「テーベ地方の隠修士達の大虐殺」です。
死をテーマにした絵というのには、もともと怖いもの見たさで興味はあったのですが、あれらの壁画を見て、深く心をゆすぶられました。
まず理屈ぬきの感動がありました。ショッキングな絵は、ある種の感動を呼び起こすものです。
そのあとで、「死のダンス」のテーマの絵が好きな理由を考えてみましたが、理由はいくらでも挙げることができます。
平等ではありえない人間社会において唯一平等な「死」についての痛烈な皮肉と真理。
「死のダンス」にこめられたそんな哲学的とも諦念的とも逆に前向きともとれる世界観や、さまざまな階級の人々の切実な叫びに惹かれるんだと思います。
別の理由として、私自身の生への執着もあるかもしれません。
聖ニコラス教会の「死のダンス」も非常にすばらしかったです。
取り上げられている人物は、法王や王侯貴族のような身分制度の頂点の人間のみで、痛烈に皮肉くられていました。
庶民や下級層が登場しないなんて、「死のダンス」にしては珍しいなぁと思ったら、農民や町民、貧乏人や物乞いといった人々の部分は、単に失われて現存しないだけでした。
失われたその階級の人々が扱われた部分もぜひ見たかったです。
人物の足下にいわばその人物の台詞が描かれていました。
それが擬人化された死(骸骨の絵)に対する思いや、生きたいとのあがきと懇願なのですが、これがとても面白いです。いや、これがなければ「死のダンス」の絵の魅力は半減します!
原画にはラテン語で書かれていましたが、聖ニコラス教会には英語翻訳もありました。
その台詞もあとでまた読み返したいと思って、カードの形の複製画を買ってしまいました。
聖ニコラス教会では、11時15分から30分ほど、弦楽器カルテットのコンサートがありました。
教会は音響効果が良いし、厳かな雰囲気があって、とても良い気分で拝聴することができました。
外に出たら、雨が降っていました。
なので、本日はトームペアの丘めぐりをするつもりでしたが、いったホテルに戻って、宿泊客に無料で提供されるコーヒー&ケーキを頂いて軽くランチ代わりにしました。
それでもまだ雨が降っていたので、トームペアの丘に上る坂道の途中にあるアダムソン・エリック博物館を見学しました。
アダムソン・エリックなる画家───いや陶芸もジュエリー制作もやっているので画家というよりアーティストというべきでしょうか───は、よく知らないので、はじめこの美術館は別に見学しなくてもいいと思っていました。
他にも見に行きたいところがたくさんあるので、優先順位が低かったのです。
でも、ポスターを見たら、ジュエリーも展示していると知り、ジュエリーを見るだけでも見学しがいがありそうだと思いました。
写真撮影OKでしたので、それも私にとってプラス・ポイントでした。
絵画自体、ものすごく!……というほどではないけれど、なかなか私好みでした。
見学後、雨がやんでいたのでトームペアの丘を回りましたが、曇天なのでどうにも写欲がわかず、いまひとつテンションが上がりません。
アレクサンダー・ネフスキー寺院や大聖堂などトームペアの丘でぜひ見学していたいと思っていたところは屋内なので見学しましたが(残念ながら内部の撮影は禁止)、その後は展望台まで行かずにさっさと丘を下りて、郊外のカドリオルク地区にあるエストニア国立美術館ことクム美術館に行くことにしました。
アダムソン・エリック美術館で、館員のおばあさんにクム美術館の入場割引券をもらっていたことにも後押しされました。
最近の私は、観光で美術館に行くことに固執しなくなったので、クム美術館も、時間が足らなければ行けなくてもいいやと優先順位を下げていたのですが、せっかく割引券をもらったので、やっぱり行きたい、という気持ちが強まりました。
その途中でギフトショップで買い物をしてしまったので、またホテルにいったん戻って買った荷物を置いてから、トラムでクム美術館のあるカドリオルク地区に向かいました。
買い物した店の看板とモノはこちらです。
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/pict/20044439/
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/pict/20044451/
関連の旅行記
「2010年バルト3国旅行ハイライトその16:ゲットしたものゲットしたところなど(完)」
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10488479/
2010年バルト3国旅行の旅程一覧はこちら。
簡易版「2010年バルト3国旅行プロローグ(旅程一覧)地図付」
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10481279/
詳細版「2010年バルト3国旅行の詳細旅程(写真付き)」
http://mami1.cocolog-nifty.com/travel_diary1/2010/07/2010-ccbf.html
PR
-
聖ニコラス教会の四角い塔
大半曇天だったり雨に降られたりした本日でしたが、朝の10時台はまだ、こんなにきれいな青空を見せていました。 -
聖ニコラス教会の前の広場にあった記念碑のようなもの
-
聖ニコラス教会へ、いざゆかん!
入場料は50.00エストニア・クローンでした。
(旅行前に調べた2010年6月30日現在の換算レート:1.00エストニア・クローン(EEK)=6.91円)
「聖ニコラス(ニグリステ)教会(Niguliste Kirik)
船乗りの守護聖人ニコラスに捧げられ、13世紀前半にドイツ商人の居住区の中心に建てられた教会。非常時には要塞としての機能も果たしてきた。1944年のソ連の空襲で破壊されたため、オリジナルの内装は残っていない。現在は博物館とパイプオルガンのコンサートホールとして使われている。
展示品は点数こそ少ないが、非常に貴重なものが多い。まず、ベルント・ノトケによって描かれた15世紀の「死のダンス(Surmatants)」は必見。縦1.6m、横7.5mのカンバスに生者と死者がダンスを繰り広げる様子が描かれている。
15世紀のリューベックの職人、ヘルメン・ローデ(Hermen Rode)(1468?〜1504)による主祭壇も宝物のひとつ。二重の観音開きの構造になっており、普段は聖ニコラスと聖ヴィクトルの生涯を描いた第二面が開かれている。最内面には40体の聖人が塑像から彫られているが、滅多に見られない。
ほかにも聖ルチアの生涯を描いた15世紀の聖母マリアの祭壇、16世紀の聖アンソニーの祭壇などが展示されている。」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より) -
中に入ってすぐの内ゲート
ここまでは撮影OKでした。
外側の近代的な姿に比べて、こちらは中世の香りがたっぷり残っていました。
「(前略)現在は往時の姿はない。1944年3月9日のソ連の空襲で大きく破壊され、1953年に補修に着手されるが、1984年に再建されたのは尖塔だけだった。典型的なバジリカ様式といわれるこの教会の内部には、移転で災害を免れた16世紀の彫刻、絵画、シャンデリアなどがある。1478年から1482年にかけての作といわれる船乗りの守護聖人、聖ニコラスの生涯を語る絵が祭壇を飾っている。この教会は現在、博物館になっていてコンサート・ホールとしても使われている。」
(「バルト三国歴史紀行 エストニア」(原翔・著/彩流社/2007年発行)より引用) -
内ゲートのどくろ部分
内部は写真不可なので、主祭壇と「死のダンス」の複製カードを買いました。
それぞれ35.00エストニア・クローンでした。
聖ニコラス教会で買った、「死のダンス」と主祭壇の複製カードの写真はこちらです。
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/pict/20044440/
関連の旅行記
「2010年バルト3国旅行ハイライトその16:ゲットしたものゲットしたところなど(完)」
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10488479/ -
向かって左半分が聖ニコラスの生涯で、右半分が聖ヴィクトルの生涯を描いた主祭壇
「タリンの中世芸術:聖ニコラス教会の主祭壇
15世紀のリューベックの職人、ヘルメン・ローデ作の木製祭壇。開かれた第一面には、左側に船乗りや貧しい人々を救う聖ニコラスの生涯、右側に異教の偶像を破壊し殉教した聖ヴィクトルの生涯が描かれている。さらに第二面があり、彩色された聖人像が彫られているが、開かれることはほとんどない。」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より) -
めったに公開されないという、主祭壇の一番内側の聖人像
実際、私が見に行ったときも、この部分は閉じられていて見られませんでした。 -
複製カードより、一番楽しみにしていた「死のダンス」のはじまり部分
説教師とプロローグを語るバグパイプの死神と地上で一番偉い法王です。
「タリンの中世芸術:死のダンス
リューベック(生まれはタリン)の画家、彫刻家ベルント・ノトケによる15世紀後半の作品。左から法王、皇帝、皇妃、枢機卿、国王が“いやいやながら”「死」とダンスを繰り広げる様子が描かれている。絵の下には「死」が語る皮肉に満ちた警句が記されている。
現存するのは絵の最初の部分で、もとは社会のあらゆる階層の人々が50あまりも描かれた長い作品だったらしい。残りの部分は失われてしまった。戦乱と疫病の時代だった中世にはこのような「死のダンス」のモチーフが普及したが、現存するのものはほとんどない。」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より)
プロローグの死神はこんなことを語っています。
「みんなダンスに加わりな、法王、皇帝、すべての生けるものたちよ、貧しいものも富めるものも、大物も小物も、さあ一歩踏み出して、自己憐憫など約にはたたぬ。おぼえておきな、罪の許しを得るために、善行かさねておきなされ。さあ、おいらのバクパイプにあわせて、みなの衆、今がそのとき踊るとき……」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より)
説教師の台詞はすごく説教くさくて、あまり好みではありませんでした。
「良き人々よ、貧しいものも富めるものも、若者も老人も、鏡の中を覗いて、心に刻んでおきなさい。誰も死から逃げられないのだと。死がやってくるとき、我々にはそれが見える。もし、自分の評判を高めるために善行をたくさん行っていたら、必ず神と一体になれる。すべては自分に返ってくるものだ。だから、愛しい子らよ、私の忠告を聞きなさい。道を誤ってはならない。良い手本にだけみならいなさい。なぜなら、死は全く予期しないときにやってくるのだから。」
(複製画カードの英訳より私訳)
法王の台詞
「おお、この地上で最も高い私の地位が一体なんになるだろう。もし私が完全におまえのようになってしまうなら──ほんのちょっぴりの地上の塵。栄誉はいらない、力もいらない。どうせみんな捨てなければならないのなら。気をつけろ。誰がある日、法王になろうとも。これが私の人生だ。」
(複製画カードの英訳より私訳) -
「死のダンス」の皇妃と枢機卿と国王と死神たち
皇妃の台詞
「分かっているわ、死が私のことを指しているのは。こんなに恐ろしい思いをしたことは今までにないわ。死は、いったい何を考えているの。だって私は若いし、皇妃なのよ。私はに力があると思っていた。私のところに死が来るなんて、誰かが私に触れることができるなんて、これっぽっちも考えたことはなかった。ああ、もっと長生きさせて、お願いよ!」
(複製画カードの英訳より私訳) -
「死のダンス」の壁画のほぼ真ん中部分、皇妃と皇帝と死神たち
皇帝の台詞
「おお、死よ、おまえはなんてひどいやつなんだ。おまえは私のすべてを変えようとしている。私は豊かで力があった。私の力は他者を遙かに超越していた。王であれ王子であれ貴族であれ、みんな私を崇拝し、褒め称えないではいられなかった。でも今、おまえが来てしまった、おそろしいやつよ。私を虫けらの餌に変えるために。」
(複製画カードの英訳より私訳) -
トームペアの丘に向かう途中にあった、アダムソン・エリック博物館
入場料は30.00エストニア・クローンでした。 -
アダムソン・エリック博物館のポスター
このポスターから、アダムソン・エリックが絵画だけでなく、ジュエリー制作を含めて、いろんなジャンルで作品を制作していることに気付きました。
少なくともジュエリーだけでも急に見たくなりました。 -
タペストリーのための原画
1937年制作
入ってすぐの小さなロビーに飾られていた絵です。
とても私好みで、すっかりこの博物館を見学する気になりました。 -
「ホルンのある静物画」
1929年制作
はじめはだいぶ写実的だけど、絵画らしい筆のタッチが感じられるところは好きです。 -
「農家の庭I(コスミ農場)」
1928年制作
少しだけうらぶれたかんじが、いいかんじ@ -
「トームペアの丘の眺め」
1937年制作
旧市街の比較的高層階の窓から眺めた景色だと思います。
トームペアの丘は左上に確かにあります。
でも、タイトルでそうと書かれていなければ、気付かなかったかも。 -
「農場(コスミ)」
1937年制作
だいぶ印象派チックになってきました。 -
「ミツバチの巣箱」
1939年制作
すてきな田舎風景です。
家の前に3つ並んでいる小さな小屋が、ミツバチの巣箱でしょう。 -
「プーカ(Puka)の景色」
1938年制作
エストニアのどこか田舎でしょうか。
平らな土地が続いていて、いかにもバルトの国です。 -
「自画像」
1936年制作
まだ随分若々しい顔つきですが、頭髪は寂しいです。 -
「農家の庭」
1938年制作
画家のお気に入りか、身近な場所なのか、1928年に描いたのと同じ場所のようです。 -
陶器の絵・その1
1939年制作
プリミティブな動物の絵がものすごく可愛らしくて、とても気に入りました。 -
陶器の絵・その2
1939年制作
何を盛るのに適しているかしら。 -
陶器の絵・その3
1939年制作
先史時代の壁画チックです。 -
陶器の絵・その4
1939年制作
ますます先史時代の壁画チックで、幾何学的になってきました。 -
壺
1939年制作
手前の壺の模様には、キリスト教のモチーフがいっぱいです。 -
1960年制作のジュエリー
ニョロニョロ〜。
すごく気に入りました。欲しい〜。 -
1960年制作のジュエリー
身につけるには大ぶりでしたけど、とてもステキなデザインです。 -
1960年制作のジュエリー
古代に使われたデザインに似ていますが、どこか現代らしさも感じられます。 -
「ラヘマーの松」
1959-1961年制作
昨日、サイクリングした、ラヘマー国立公園です!
確かにそうです、こんなかんじでした@
関連の旅行記
「2010年バルト3国旅行第14日目(1)ラヘマー国立公園:パルムセやサガディの宮殿を眺めて、アティジャ村にたどり着くまで」
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10572371/
「2010年バルト3国旅行第14日目(2)ラヘマー国立公園:アティヤ村から後半最後のふんばり&タリンに戻った後」
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10572373/ -
「白馬のいる風景」
1961年制作
えーと、白馬はどこ? -
1900年パリ万博で名誉賞を受賞したタペストリー
生命の賛歌を謳ったデザインというかんじがします。 -
タイルアート・その1
たくさんあったタイルアートの一つ。
公園を散歩する……別れの危機に面した恋人たち!? -
タイルアート・その2
抽象絵画にも見えるし、マンボウにも見える@ -
古代の壁画チックなデザインの皿
-
カフェ・タリンのための装飾絵画・その1
1967-1988年制作
おお、なんとなく1990年代っぽいです。 -
カフェ・タリンのための装飾絵画・その2
1967-1988年制作
そしてこちらは陶器デザインっぽい。 -
カフェ・タリンのための装飾絵画・その3
1967-1988年制作
お得意のニョロニョロ。
でもこんなステキな内装のカフェには入ってみたくります。 -
しっとり雨にぬれた中庭
雨が降ったりしなければ、中庭で少し休んだりできたのでしょう。 -
母子像(?)のある中庭
-
トームペアへ上る階段(リュヒケ・ヤルク通り)
「山の手
タリンの見どころは、約2.5kmの城壁に囲まれた旧市街(Vanalinn)にほぼ集中している。
その旧市街は、支配者や貴族たちが居を構えた「山の手」のトームペア(Toompea)と、商人や職人たち市民が築き上げた「下町(All-linn)」とに分かれている。
トームペアは市街を見下ろす高い約24mの丘だ。この上にはトームペア城や大聖堂など、かつての権威を代表する建物があり、周囲のたたずまいもどことなく厳格な表情をしている。丘の上には下町のすばらしい景色が広がる展望台もあり、タリン観光の出発としても最適の場所だ。
トームペアは2本の坂道、ピック・ヤルク(Pikk Jalg)通りとリュヒケ・ヤルク(Luhike Jalg)通りで下町と結ばれている。両方の通りを下りて少し進むと、ラエコヤ広場がある。」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より) -
一部がカフェになっていた、トームペアの丘の城壁
「侵略者たち(デンマーク人のこと)は要地を守るために、これまでの要塞に変わる新しい要塞の建設を開始した。エストニア人はこの要塞を「Taanilinnus」(デンマークの要塞の意味)と呼んでいた。これが後に短く省略され、タリンという名前になった。同時に教会建設も開始され、1240年にはエストニア司教区の大聖堂として聖母マリア教会が奉納された。大聖堂の見どころは、エストニア国の騎士団に属していたドイツ系貴族の紋章のコレクションで、最古のものは1686年製である。またいくつもの石棺や墓石も現存しており、そのうち最も美しいのはスウェーデン総司令官のポントゥス・デ・ラ・ガルディーとその妻で王家の血筋をひくソフィーア・グーレンヘルムの石棺である。」
(タリンで買った日本語カラーパンフレット「タリン 歴史あふれる町」より) -
城壁の内側から
-
おしゃれな公衆トイレ
アレクサンドル・ネフスキー寺院の横にありました。
中もおしゃれかな?(未確認@) -
現在、議会なので中は見られないトームペア城
「トームペア城
かつてエストニア人の砦があった場所に、13世紀前半に建てられた騎士団の城。外城の中に修道院型の内城がある強力なもので、支配者が替わるたびに補強改築された。現在の姿になったのは18世紀後半のこと。当時の権力者エカテリーナ2世は知事官邸として使うための改築を命じたので、正面から見ると城というよりは宮殿に近いものとなっている。
現在の建物のうち、北側と西側の外壁と3つの塔が15世紀当時の姿を留めている。そのため裏側から見てみると、かつての城の姿が容易に想像できる。南側の50.2mの塔「のっぽのヘルマン(Pikk Hermann)」は、エストニアの三色旗を誇らしげに掲げ、今は国を象徴する存在となっている。
現在も政府の一部と国の議会が城内に入っているので、内部を見学することはできない。」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より) -
ロシア正教会のアレクサンドル・ネフスキー聖堂
修復中の覆いをなんとか目立たせないように撮りました。
「アレクサンドル・ネフスキー聖堂
1901年に支配者の帝政ロシアによって建てられたロシア正教会。タリンの街並みとの調和を考えると、この教会は異端児的。エストニアが最初に独立を果たした時代には移転する計画があったそうだが、実現はしなかった。今もなおロシアの脅威を感じているエストニアの人々の心情からすると、議会のすぐ前にロシア正教教会が立ちはだかっているのは、やはり気持ちのいいことではないようだ。
教会に入ってすぐ右手の壁には、日露戦争で沈没したロシア艦隊を記念したプレートがかけられている。」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より) -
アレクサンドル・ネフスキー聖堂のドーム前の正面モザイク
-
正面入口のすぐ上のモザイクとドーム
-
アレクサンドル・ネフスキー聖堂に入る直前の見上げるアングル
「トームペアにはロシアの17世紀の教会をモデルとし、1900年に完成された旧市街で最も美しい教会、アレクサンデル・ネヴスキー大聖堂がある。教会内部は黄金に塗られたイコノスタスや数多くのイコンで飾られており、各入口の上部に施されたモザイク壁画は現在でも珍しいものばかりである。教会には合計11もの鐘があるが、そのうちのひとつは重さが15トンもあり、北欧で最大のものである。このロシア正教会はモスクワに総主教庁が置かれており、現在のモスクワ総主教アレクシー2世(俗名はAleksei Ridiger)はタリン出身者である。」
(タリンで買った日本語カラーパンフレット「タリン 歴史あふれる町」より) -
ロシア正教会らしい、美しい玉ねぎ型ドームが林立
-
ポストカードより、アレクサンダー・ネフスキー聖堂の内部
ポストカードは1枚10.00エストニア・クローンでした。
「議会の正面にあるのが「アレクサンドル・ネフスキー聖堂」である。この場所は1894年までは城を囲む城壁の外の空き地だった。ロシア皇帝アレクサンドル3世はそこにエストニアでの民族運動を抑える目的でロシア正教の豪華な聖堂を建てる。でも、完成が1901年だから、ロシア帝国が消滅したのが1917年だったことを考えると、あまり効力を発揮する機会がなかったことになる。内部を飾るイコンやモザイク、15トンの鐘はサンクトペテルブルグから運ばれてきた。入り口には日露戦争の対馬沖海戦を記念した銘板がある。1904年9月17日にクロンシュタット軍港を出港した第二太平洋艦隊主力は18日から20日にかけて当時レヴァルと呼ばれていたタリンの軍港に集結し、9月26日にはヨットでやってきたニコライ2世を迎えての観艦式をおこない、9月28日に港を出ていった。この艦隊にはエストニア人も乗船していた。銘板はそういった戦死者を悼んでのものである。
この聖堂はあまりにもロシア色が強すぎてトームペアには不似合だと1930年代に撤去の話がおこり、いまでも依然としてくすぶっている。ロシア系の人たちを刺激するのを心配する政府はいまだに決断しかねているという。」
(「バルト三国歴史紀行 エストニア」(原翔・著/彩流社/2007年発行)より引用) -
ポストカードより、アレクサンダー・ネフスキー聖堂の豪華なイコノスタシスと、礼拝者がいつもその前で十字を切るイコンのある台
-
白塗りの壁の大聖堂
「大聖堂(トームキリク)
1219年にデンマーク人がトームペアを占領してすぐに建設した、エストニア本土では最古の教会。聖母マリアの大聖堂 Tallinna Neitsi Maarija Piiskoplik Toomkirik とも呼ばれ、創設以来タリンにおける中心的教会の地位にある。一度は1684年にトームペアを襲った大火災により消失したが、その後約100年の歳月をかけて現在の教会が再建された。入口から入るとこの教会が地面に沈み込んでいるように見えるのは、このとき古い基礎の上に建て直されたためだ。
教会内部は薄暗く、古色蒼然とした空気に包まれている。この教会の特異さは、教会であると同時に大規模な“墓所”でもあること。それは壁にかけられた無数の墓碑銘や紋章、墓標や石棺、また教会の床に残る墓石(最古のものは13世紀から)などからも感じられる。創設以来トームペアのおもに貴族たちがここに葬られており、後にトームペアの職人も加わった。(後略)」
(「‘09〜’10年版 地球の歩き方 バルトの国々 エストニア・ラトヴィア・リトアニア」より) -
3枚つづりのポストカードより、大聖堂の主祭壇と説教台
ポストカードは30.00エストニア・クローンでした。
1枚分は10.00エストニア・クローンと考えると、アレクサンダー・ネフスキー聖堂で買ったポストカードと同じ値段です。
2010年7月現在、このくらいがポストカードの相場といえるかしら。 -
大聖堂の3枚つづりポストカードより、巨大な紋章がずらりの壁面
-
大聖堂の3枚つづりポストカードより、天使の像があるパイプオルガン
-
今日のところはこれでトームペアの丘を下りる
「ローマ教皇ケレスティヌス3世の命令により派遣された十字軍の一環として、1227年にドイツ騎士団がタリンに侵入した。ドイツ騎士団は要塞を占領し、デンマーク人を追い出した後に独自の要塞の建設を開始した。現在のトームペア城の外観のほとんどは13世紀から14世紀の間にドイツ騎士団の統治時代に形成され、後の支配者たちによって独自に手を加えられていった。北方戦争後(1700年〜1721年)には、ロシアのエカチェリーナ2世が知事官邸として改築を命じている。このころすでに無用となっていた要塞は、1767年に開始された改築により、美しい後期バロック様式の正面外観を持つようになった。その後表現主義的様式の国会議事堂は1920年代に要塞の中庭に建てられた。ソ連時代はエストニア・ソヴィエト社会主義共和国閣僚評議会が置かれ、現在、再びエストニア共和国の国会議事堂として使われている。トームペア城はかつて何度も改築されてきたが、いくつかの塔も含めたオリジナルの部分が多く現存している。中でも最高の塔はのっぽのヘルマン塔と呼ばれ、頂上にはエストニアの国旗が掲げられている。」
(タリンで買った日本語カラーパンフレット「タリン 歴史あふれる町」より)
「2010年バルト3国旅行第15日目(2)タリン:カドリオルク地区再び&絵画で触れるエストニア絵画(クム美術館・前編)」へとつづく。
http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10575253
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
まみさんの関連旅行記
タリン(エストニア) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?
タリン(エストニア) の人気ホテル
エストニアで使うWi-Fiはレンタルしましたか?

フォートラベル GLOBAL WiFiなら
エストニア最安
419円/日~
- 空港で受取・返却可能
- お得なポイントがたまる
































































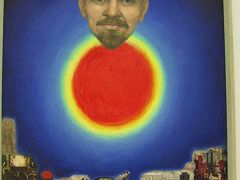









0
57