
2011/03/31 - 2011/03/31
655位(同エリア842件中)
![]()
ゆらのとさん
願わくは 花の下にて春死なん
その如月の望月のころ
これは西行の有名な歌である。私がこの歌を初めて知ったのは高校2年の国語?の古文の時間であった。「満月の桜の下で死にたいなんて、浮世離れした人もいるもんだ」と、あまり感動はしなかった。
それから、50年以上の歳月を経て、私が外国の桜に関心を持つようになってから、ようやく、西行法師(平安末期から鎌倉初期)の気持ちが少し解るような気がしてきた。
先にも述べたが、私は再来年の喜寿になる年に「外国の桜」の本を出版したいと願っている。その中で、日本の代表的な桜も7,8ヵ所入れたいと思っている。
古代より、最も愛されている桜の名所は吉野山である。吉野山の桜を最も愛したのは西行である。貧困の中で72歳の生涯を桜を愛しながら全国を行脚し、1500首の歌(主に山家集)を詠んだ。 西行ゆかりの地、吉野山を是非訪れたいと思ったのは5年前からである。
それが、この度、実現したのである。西行が吉野山の奥の渓谷の庵(場所)を訪れることが出来たのである。
感動であった。不思議なことに出会った。そして、私の志を貫こう、というパワーを貰うことができた。この旅は終世忘れえぬ私の心の財産となった。
西行庵に行く途中までは前回の私のブログに書いた。
商店街の芳泉堂のご主人、横矢保夫さんから金峯神社前まで車で送っていただいた。これも感動だった。(このご親切を終世忘れまいと心に誓った)
そこで横矢さんにお別れしてからは車の入らぬ山道である。未だ、日暮れまでは遠かったが、空はうす曇りでつめたい風が吹いていた。風が吹くと木の枝が鳴り、不気味であった。途中、たった一人だけ50代の女性に会った。この女性も西行庵を訪ねたのだと直感した。彼女はリュックを背負ってスニーカーの軽装だった。私は西行庵の道程を尋ねた。「15分くらい歩くと標識があり、そこからは坂を下るようになります。急斜で道が悪いからお気をつけて」 優しい上品な女性だった。私と同じように西行を尊敬し、慕っている方だと思った。
彼女が行ったように標識があって、そこから坂道を下るのだ。右側は山の斜面で鉄棒の手すりが張られていたけれど、私は手すりに掴まらず。急ぎ早に坂を下りた。
10分ほど下りた時、私は大失態をしてしまったのである。石ころに滑って仰向けに転んでしまった。尻を打ってかなり痛みが走った。2,3分後痛みが薄らいだので、立とうとしたら、ふらふらとして立てないのである。冷たい脂汗が額や背中に湧いてきた。
私は原因は分かっていた。私は糖尿病の持病があり、長く風呂に入ったり、疲れた時、立ち上がろうとする時、立ちくらみを起こすことがあるのである。私は、外国に行く時はブドウ糖をポケットに入れておくのだがその時は持っていなかった。
「どうしよう、このまま歩けなくなったら、遭難してしまう」 不安が過ぎった。
「あった、芳泉堂から買った落雁(砂糖菓子)がある、私は横になったまま、カバンを手探りで開けて、ビニール袋の中の落雁を口の中に放り込んだ。
しばらくしたら、立ちくらみが治まり、歩けるようになった。「よーし、せっかくここまで来たのだから頑張るぞ」私は平らな所に座り直して、カバンの中のおにぎり(JR大阪駅構内で買ったもの)や、ウーロン茶を胃の中に詰め込んだ。
私はカメラだけをジャケットのポケットに入れ、カバンはそこに放り出した。今度は右手の鉄棒の手すりに両手で掴まり、一歩、一歩注意してゆっくり歩いた。
5分位歩いた時、私は驚嘆の声を上げた。左手は崖で滑れば40m位の谷底に転落してしまうのである。崖には硬い蕾の桜が何百本も聳えていた。
10分ほど下ってようやく西行庵に辿り着いた。庵といっても、西行庵があった所で鎌倉時代の西行庵がそのまま残っているわけでない。近年、それに似せて造ったたものだが、充分に西行を偲ぶことが出来た。変わらぬものは当時そのままの吉野山の桜である。
西行は春の桜の花だけを愛でたのではない。夏の葉桜、秋の桜の紅葉、冬の桜の梢に降り積もる桜も愛でた。西行はここで庵を造り四年間山桜と共に暮らした。 その中から人生を感じ取って歌を詠み続けた。(西行は吉野山を詠んだ歌は60首ある) そこに吉野山を詠んだ歌のいくつかが石碑に刻まれていた。
あの時の私の心境にピタリののがあるのを帰ってきてから図書館で見つけた。
誰かまた 花を尋ねて吉野山
苔踏み分けて岩つたうらん
私は15分ほど西行庵の前で佇んでいた。見上げれば天空はあまり広くない。渓谷のせせらぎの音と辺り一面の、桜木しか見えない。「西行は托鉢に麓の里に出ることはあっても、4年間ここで暮らしていたんだ」、私はドカーンと打たれたような衝撃が走った。
もっと居たかったけれど時間がない。私は坂道を上り始めた。その時アッという感動に出会った。来る時は気が付かなかったが、道沿えの崖の桜の中に2m位の若木があった。その桜に五輪の花が咲いていたのである。
あれは不思議であった。能天気な私は西行様が私に仕向けてくださった桜としか思えなかった。(写真を拡大してご覧あれ)
それを見たら、すっかり元気になった。勇気が湧いてきた。途中、放り出しておいたカバンを拾って、中千本のバス停まで2時間は歩いた。バス停の近くの民家の庭に咲いている桜も写真に収めることが出来た。 私は歩きながらお粗末な短歌が湧いてきた。今の私はこのような心境である。
奥山の西行庵を訪ぬれば
わが志(こころざし) 新たなりけり ゆらのと
- 同行者
- 一人旅
- 交通手段
- JR特急
- 旅行の手配内容
- 個別手配
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?









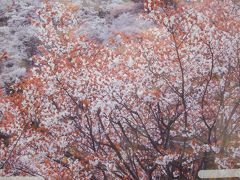











0
2