
2024/03/31 - 2024/03/31
318位(同エリア369件中)
岳人28号さん
- 岳人28号さんTOP
- 旅行記101冊
- クチコミ934件
- Q&A回答10件
- 151,887アクセス
- フォロワー3人
この旅行記のスケジュール
もっと見る
閉じる
この旅行記スケジュールを元に
ベッセルホテル福山で朝食を済ませ、近くの佐波城山公園から草戸山に登り明王院に下山。桜が咲いてるかもと思い、福山市園芸センターにも行ってみましたが、ソメイヨシノはまだ咲いておらず、咲いていた修善寺寒桜は盛りを過ぎて散りつつある状況でした。
- 旅行の満足度
- 4.0
- 観光
- 4.0
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 1万円未満
- 交通手段
- 自転車 徒歩
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
じゃらんネットにあったベッセルホテル福山の朝食ビュッフェプラン(1200円)を利用。
ベッセルホテル福山 宿・ホテル
-
芦田川に架かる神島橋を渡り
-
坂道を登って佐波城山公園のある場所まで来ましたが、旧佐波浄水場の正門に通じるこの道からは入れないようで
-
いったん引き返して新しく整備されたらしい広い坂道を行くと
-
佐波城山公園に入れました。
佐波城山公園 公園・植物園
-
公園内には大正14年(1925年)に建造された旧佐波浄水場の遺構があり、国の登録有形文化財に指定されています。こちらは浄水井上屋。ろ過された浄水を一時的に貯める浄水井を上から点検・管理する建物です。
-
浄水井から送られた浄水を貯める配水池。建物の入口の上には初代福山市長阿武信一直筆の「不舎晝夜」の文字を刻んだ額が掲げられています。
-
立入禁止になっていて引き返した正門の門柱を含め、登録有形文化財に指定されている遺構は、どれもフェンスで囲われています。「城山公園」という名前がついてますが、山城については案内板等は何もなく、どこらへんに痕跡があるのかよくわかりません。
-
公園のアクセス道の途中に草戸山の登山口のひとつがあります。登山口の標識などはなくテープが目印です。
-
入口の様子から荒れた道を想像してましたが、思いのほかちゃんと整備されていました。
-
急登を登り切って尾根道に出ると道標があります。
-
登山道には掃除道具が設置されており、落ち葉がきれいに掃き清められています。
-
ところどころにベンチもあります。
-
平城天皇の第三皇子で弘法大師空海の弟子になった高岳親王(真如法親王とも)が、承和4年(837年)ころしばらく幽栖した地と伝わる親王院旧跡。
-
親王院旧跡の横にあるのは草戸愛宕神社本殿(市重要文化財)ですが、覆屋の中に納められていて見ることはできません。棟札により寛永5年(1628年)の建築と判明しているそうです。
-
覆屋の隣に参拝用の代わりの社殿があります。
-
道標にしたがって展望台へ。
-
少し展望の開けたところに東屋がありますが、展望台はこの上にあります。
-
上水道の給水タンクを利用した展望台。展望台の下に草戸山の標識があります。
-
展望台からの芦田川河口・瀬戸内海方面の眺め。空気が澄んでいれば四国の山並みまで見えるところですが、かすみがかかっています。
-
展望台には地元の高校生が市内の名所などを描いた壁画があります。
-
壁画を制作した明王台高校の校舎は展望台の目の前です。
-
明王院へ下山。
明王院 寺・神社・教会
-
国宝の五重塔の傍らに枝垂桜が咲いてました。
明王院五重塔(国宝) 名所・史跡
-
鎌倉末期建立の本堂も国宝。
明王院本堂(国宝) 名所・史跡
-
本堂の前に植えられていた「浩宮徳仁親王御来山記念」の松。昭和56年7月9日ですから、今の天皇陛下が21歳のときということになります。
-
江戸初期の再建で県指定重要文化財の書院と
-
同じく県指定重要文化財の庫裏(くり)。
-
庫裏にはひな人形が飾られていました。
-
山門も県指定重要文化財。
-
明王院のすぐ隣にある草戸稲荷神社。境内の桜が咲き始めていました。
草戸稲荷神社 寺・神社・教会
-
ここも桜が咲いてるかも、と思い園芸センターへ。
福山市園芸センター 公園・植物園
-
園内案内図を確認して
-
西の端にある桜林に行ってみましたが、まだぜんぜん咲いてません。
-
上のほうの桜林は修善寺寒桜という品種らしく、盛りは過ぎているもののある程度咲き残ってました。
-
白いのはスモモの花。
-
スモモ畑があります。
-
ハーブの一種ローズマリー。
-
園内の見晴らし台からは海が見えます。
-
こちらは「ニュートンのリンゴの木」。万有引力の法則を発見するきっかけになったと伝えられるニュートンの家のリンゴの木から接ぎ木で増殖したものらしいです。
-
園芸センター近くの道端でみかけた「永代茶接待」の石碑。「六月七月」とありますから、暑さが厳しい夏に峠越えする人たちに茶を振舞って渇きをいやしてもらおうということだと思います。文化十四年(1817年)に事業をはじめ、文政九年(1826年)に石碑を建てたということです。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったホテル
福山(広島) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?






















































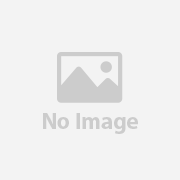















0
41