
2009/06/28 - 2009/06/28
2805位(同エリア3748件中)
![]()
morino296さん
- morino296さんTOP
- 旅行記1218冊
- クチコミ20件
- Q&A回答1件
- 2,567,271アクセス
- フォロワー110人
京都市観光協会のHPに「初夏のもみじ狩り〜青もみじを愛でる、京の旅をおすすめします。〜」とあったので、行ってみました。
前日の天気予報では「曇り時々雨」、ところが予報はどんどん好転、真夏日のような青空の下、暑さとの闘いとなった散歩でした。
前半:東福寺塔頭の霊雲院→天得院→東福寺→光明院
後半:泉湧寺→今熊野観音寺→戒光寺→即成院
PR
-
-
霊雲院(東福寺塔頭)
明徳元年(1390))、岐陽方秀によって開かれ、はじめは不二庵と呼ばれていました。
山門は、最近、建て替えられたようです。 -
霊雲院の玄関にて
何をお考えでしょうか? -
遺愛石を置いた九山八海の庭
-
寛永年間(1624−44)に住持の湘雪守げんに帰依した熊本藩主細川忠利・光尚父子から、遺愛石と銘づけた須弥台と石船を贈られたもの。
枯山水の庭は、戦後、重森三玲の手で復元され、遺愛石を置いた九山八海の庭。 -
九山八海の庭
律動的な砂紋は、仏説の宇宙世界を象っているそうです。 -
小書院の西の庭、臥雲の庭
-
臥雲の庭
空をゆく雲はゆうゆうとして来たり、ゆうゆうとして去り、何にこだわるでもなく、何にわだかまるでもなく、ただ無心に・・・。(パンフレットより) -
臥雲の庭の片隅にマサル
-
桃山様式という二階建て茶室観月亭
下に4畳半、上に5畳半の茶室があるそうです。 -
霊雲院の甍
霊雲院、訪れる人も少なく、ゆっくりと庭を楽しませてもらいました。 -
東福寺
青もみじに包まれる通天橋 -
-
東福寺 臥雲橋
-
天得院
正平年間(1346〜70)東福寺第30世、無夢一清禅師が開創。
慶長19年(1614)に文英清韓長老が住持となった。清韓は、豊臣秀頼の請に応じ方広寺の鐘名を撰文したが、銘文中の「国家安康、君臣豊楽」の文字が徳川家を呪詛するものとして家康の怒りを招き、寺は取りこわされたといわれる。
現在の堂宇は天明9年(1789)に再建されたもの。
「桔梗の寺」として有名です。 -
南庭のスギゴケと桔梗
-
-
天得院の桔梗
逆光気味に撮ったため花が透きとおっているように見えます。 -
天得院 南庭に面した縁側
人が写らないシャッターチャンスはなかなかありません。 -
天得院 華頭窓から見る西庭の桔梗
-
天得院 南庭の縁
大勢の人が、団扇をあおぎながら桔梗を愛でています。 -
天得院 南庭の木戸にも桔梗です。
-
東福寺の甍
-
東福寺 本堂の軒下から望む方丈
-
東福寺 本堂天井の画龍
-
-
東福寺 三門
三門は空門・無相門・無作門の三解脱門の略。南都六宗寺院の中門にあたります。
東福寺は新大仏と呼ばれるような巨大な本尊を安置するなど南都二大寺に影響を受け、この三門は大仏様(天竺様)、禅宗様(唐様)、和様をたくみに組み合わせた建造方式となっています。
五間三戸、重層入母屋造、両脇に階上へのぼる山廊を設けた、日本最大最古の遺構です。
応永年間(1394-1428)、足利義持の再建で、昭和52年に大修理が完成しました。 -
東福寺 六波羅門から
南正面に立つ惣門。
もと北条氏の六波羅政庁にあったものを移したと伝えられており、この名があります。 -
東福寺を囲む青モミジ
-
光明院 東福寺塔頭
明徳2年(1391)金山明昶の開創。
東福寺六波羅門から南に下ったところにあります。 -
光明院 門前に置かれた注意書きです。
「大勢入山者は好みません。庭の自尊心も傷つけますので・・・」 -
光明院の玄関
門前の注意書きのせいか(?)訪ねる人も少なく、ゆっくり楽しめます。
時々、観光タクシーの運転手さんが得意げに説明をされていました。 -
光明院
玄関を入ると桔梗がお迎えです。
受付はなく、拝観料(300円)は、竹筒の中に入れます。 -
光明院 方丈前の庭園「波心の庭」
明徳2年(1391)に金山禅師が東福寺境内に創建したお寺で、明治以降に廃仏毀釈で荒廃しますが、その後徐々に復興し、当時、東福寺の方丈庭園を手がけていた重森三玲の作。
この庭は、昭和十四年から24年の年月を経て昭和三十八年に完成したそうです。
「虹の苔寺」と呼ばれるだけあって、苔が豊かで美しいです。
雨後の苔は、ひときわ美しさが増すそうです。 -
光明院 波心の庭
-
-
-
-
-
-
-
-
光明院 波心の庭
静かな時間が流れます。
ずっと座って庭を眺めるのも良いですね。 -
東福寺から泉涌寺へ向かう途中
仲恭天皇九条陵・崇徳天皇中宮皇嘉門院月輪南陵の参道からは、京都タワー方面が見渡せます。 -
仲恭天皇九条陵
-
泉涌寺へ向かう道
地図にも乗っていないような細い山道を下ります。
京都一周トレイルの標識があったので助かりました。
14時頃、暑さも最高潮です。
後半へ続きます。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (2)
-
- あんみつ姫さん 2009/07/01 15:20:20
- 緑が映えるこの頃、枯山水と石庭はグッドタイミング?
- morino296さん、こんにちは。
久しぶりに、穏かな石の庭、枯山水を見せていただきました。
コメントまだのときですが、
写真から、訴えるモノを感じ取らせていただきました。
今日は、雨は降っていませんが、
梅雨時独特の湿った風が窓から入ってきます。
あんみつの住むところは、
車道から奥になっているので比較的、静かなのです。
今日は、なんかさらに静か…
この庭の写真を見せていただくのに、
とてもいいときでした。
あんみつ
- morino296さん からの返信 2009/07/02 00:27:15
- RE: 緑が映えるこの頃、枯山水と石庭はグッドタイミング?
- あんみつ姫さん
こんばんは!
いつも有難うございます。
写真をUPしただけで、コメントを書けおらず済みません。
京都は、観光客が減っているようです。
梅雨のまっただ中、雨を覚悟に出掛けたのですが、
真夏の太陽が照りつける散歩となりました。
お陰さまで、東福寺の界隈も、ゆっくり楽しませてもらえました。
今週は、梅雨空が続きそうですが、体調に気をつけて下さい。
morino296
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?

























































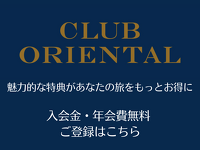







2
46