
2006/09/16 - 2006/09/18
930位(同エリア1905件中)
![]()
MechaGodzillaⅢ&703さん
- MechaGodzillaⅢ&703さんTOP
- 旅行記1805冊
- クチコミ0件
- Q&A回答0件
- 4,042,344アクセス
- フォロワー326人
■豊臣秀吉の大阪城■
秀吉は天下統一の拠点として権威と権力を象徴する難攻不落の巨城を築いた。豪壮華麗なその姿は「三国無双」と称された。
大坂城は、豊臣氏が築城した当初の城と、その落城後に徳川氏が再建した城とで縄張や構造が変更されている。
現在、地表から見ることができる縄張はすべて、江戸時代のものである。ただし、堀の位置、門の位置などは秀吉時代と基本的に大きな違いはないとされている・・・。
【手記】琵琶湖一周旅行のスタートとして、ルート上の神戸異人館・大阪城と見物していきました。懐かしい大阪城です。
琵琶湖近辺は何度も来ています。とは言っても昔はナビなどなかったですから、この辺りの地理は右も左もよくわからないまま、ただぶつ切りのように来ていただけです。
琵琶湖を完全一周!したのは今回が2度目です。今回は神戸異人館・大阪城などを見物してから琵琶湖を一周しました。台風!若狭湾直撃情報の中の旅でした。3日目は小浜市から天橋立へ向かいました。
- 一人あたり費用
- 5万円 - 10万円
- 交通手段
- 自家用車
-
大阪城へ「法円坂交差点」
●石山本願寺の繁栄
明応5年(1496)、本願寺8世法主蓮如が山科本願寺の別院として大坂御坊を建立し、これが石山本願寺の起源となった。
その経緯を述べた蓮如の御文章は「大坂」という地名が見られる最初の文献である。 -
「神戸異人館をあとにして」
大阪城へ 阪神高速走行中
〜大阪城公式サイトより〜
秀吉の大坂城は「旧城」を改造して築かれたという。では、秀吉以前の城郭とは、いったい誰のどのような城だったのだろう? -
大阪城の北側「大阪城新橋」手前です。
天文元年(1532)、山科本願寺が戦国の争乱に巻き込まれて焼き討ちに合い、逃れた十世証如らは、翌年大坂御坊を本願寺とした。
この石山本願寺は、堀・塀・土塁などをもうけて武装を固め、戦国武将細川晴元らの攻撃に備えたため、次第に難攻不落の城砦として強化された。
また、次第に寺内町も発展し、11世顕如の代に本願寺隆盛の絶頂期を迎えた。 -
「大阪城ホール」
●石山合戦
織田信長の天下統一の野望に最も頑強に抵抗したのは一向宗(浄土真宗)本願寺派の門徒集団であり、その総本山が法主顕如を推戴する石山本願寺であった。
-
「大阪城ホール」
元亀元年(1570)から11年に及ぶ長い戦争の結果、天正8年(1580)信長は顕如を本願寺から退去させることに成功したが、堂塔伽藍は全焼し、現在もこの時代の遺構は謎に包まれている。 -
「大阪城ホールよりお堀ウォッチ」
『信長記』には、「そもそも大坂はおよそ日本一の境地なり」に始まる有名な一節があり、大坂の優れた地勢について詳しく述べられている。 -
「大阪城パンフ」?4
●築城の規模
秀吉の大坂城は、本丸の築造に約1年半を費やし、その後も秀吉が存命した15年の全期間をかけて、徐々に難攻不落の巨城に仕上げられた。 -
「大阪城パンフ」?3
秀吉創建の大天守は外観5層で、鯱瓦や飾り瓦、軒丸瓦、軒平瓦などに黄金をふんだんに用いた。
また、秀吉は自ら好んで多くの来客に本丸内を案内してまわり、金銀の装飾にあふれた奥御殿の内部、大天守の各階に納められた財宝の山など、空前の富の集積を誇示して来訪者を驚嘆させた。 -
「大阪城パンフ」?2
●黄金色に輝く大天守
天正11年(1583)、秀吉は石山本願寺跡に大坂城の普請(築城工事)を開始した。
一般には日本のお城のシンボルは天守閣であるが、空にそびえる大天守が初めて作られたのは織田信長の安土城である。
信長の後継者を自認する秀吉は、安土城をモデルとしながらも、すべての面でそれを凌駕することをめざした。 -
「大阪城パンフ」?1
★豊臣秀吉の大阪城
秀吉は天下統一の拠点として権威と権力を象徴する難攻不落の巨城を築いた。豪壮華麗なその姿は「三国無双」と称された。 -
「大阪城ホール」
信長は本能寺の変に倒れたが、この地に築城を期していたことは想像に難くない。 -
大阪城「青屋門」
また、城づくりと同時に町づくりが行われ、秀吉時代の大坂は近世城下町の先駆けとなった。
領主の邸宅である城を中心とした広大な領国の首都、そして政治・経済・軍事・文化の中心都市として城下町大坂が建設されたのである。 -
大阪城「青屋門」
●大坂冬の陣
秀吉の死からわずか2年後の慶長5年(1600)、徳川家康が関ヶ原の戦いに勝利した。
慶長8年、家康は江戸に幕府を開き政権を掌握したが、豊臣家は徳川幕府成立後も天下掌握の夢を捨てられず徳川家との間に緊張関係を持続させていた。 -
「大阪城」
こうした状勢のなか、京都東山に豊臣秀頼が再建した方広寺大仏殿の鐘銘(釣鐘の銘文※)に家康がクレームを付けたことをきっかけに、慶長19年(1614年)大坂冬の陣が開戦された。
※家康は銘文中の「国家安康」「君臣豊楽」の二句をとりあげ「家康の文字を分断し、豊臣を主君として楽しむとの下心がある」と難くせを付けた。 -
大阪城「極楽橋」
約10万の豊臣方は軍勢の大半が浪人衆の寄せ集めで統制力に欠けていたにもかかわらずよく防ぎ、攻めたてる徳川方20万の大軍を惣構の中へは一兵も突入させなかった。 -
「大阪城」
●大坂夏の陣
大坂冬の陣講和によって城を裸城とされた大坂方は、埋められた堀の掘り起こし等の復旧工事を手がけた。
これが再軍備とみなされ、冬の陣からわずか5カ月余りで夏の陣開戦となった。 -
大阪城「極楽橋」
慶長20年(1615)の夏、河内方面、大和方面から攻め上ってくる徳川方15万5千余りの軍勢に対し、豊臣方は防御の薄くなった大坂城では籠城作戦がとれず、敵の大軍が一つに合流する前に撃破することとした。 -
「大坂城」
5月6日早朝大阪方は河内方面に兵を進め、先制攻撃を仕掛けたが、結局は大坂城へ退却せざるを得なかった。
そして、その翌日、決戦の場となった大坂の町中を悲惨な混乱に巻き込みつつ、ついに大坂城は落城したのである。
さらに、翌8日、山里曲輪にひそんでいた豊臣秀頼・淀殿らも発見されて自刃、豊臣家も滅亡するに至った。 -
「大阪城」
大坂城は、豊臣氏が築城した当初の城と、その落城後に徳川氏が再建した城とで縄張や構造が変更されている。 -
「大阪城」
秀吉の大坂城本丸は、現在も残る徳川幕府再築のものとは堀の形状や天守の位置も全く異なり、二重三重の複雑な石垣が立体的に構築されていた。 -
大阪城「残念石」
秀吉が築き上げた天下の名城は、やはり難攻不落の堅城だったのである。
しかし、講和による終戦の結果、大坂城は講和条件であった惣構・三の丸の破却に続いて強引に二の丸の堀まで埋め立てられ、本丸ばかりの裸城にされてしまった。 -
「大阪城」
●大坂夏の陣
大坂冬の陣講和によって城を裸城とされた大坂方は、埋められた堀の掘り起こし等の復旧工事を手がけた。
これが再軍備とみなされ、冬の陣からわずか5カ月余りで夏の陣開戦となった。
-
「大阪城天守閣入場口」
5月6日早朝大阪方は河内方面に兵を進め、先制攻撃を仕掛けたが、結局は大坂城へ退却せざるを得なかった。
そして、その翌日、決戦の場となった大坂の町中を悲惨な混乱に巻き込みつつ、ついに大坂城は落城したのである。 -
「大阪城」
慶長20年(1615)の夏、河内方面、大和方面から攻め上ってくる徳川方15万5千余りの軍勢に対し、豊臣方は防御の薄くなった大坂城では籠城作戦がとれず、敵の大軍が一つに合流する前に撃破することとした。 -
大阪城「天守閣入場口」
さらに、翌8日、山里曲輪にひそんでいた豊臣秀頼・淀殿らも発見されて自刃、豊臣家も滅亡するに至った。
〜大阪城公式サイトより〜 -
「大坂城
■号砲
明治3年(1870)から時刻を知らせる号砲として用いられ、はじめは日に3度、明治7年からは正午のみ空砲が大阪市内にとどろきわたり、「お城のドン」、「お午(ひる)のドン」の名で親しまれてきました。 -
「大阪城天守閣入り口」
■号砲
この大砲は、全長348cm、砲口の内径20cm、外径40cm 先込め式の旧式砲で、材質は青銅の一種とみられます。
1863年、幕府の命令により、美作津山藩(岡山県津山市)の鋳工、百済清次郎らが製造し、大坂天保山砲台の備砲として据え付けられ、明治維新後、大阪城内に移されたものと伝えられています。 -
「大阪城内部」
★徳川幕府の大阪城再築
幕府は西日本支配を確立するために、大坂城と結びついた豊臣氏の威光を完全に払拭し、より豪壮な新城を築く必要があった。 -
「大阪城内部」
●大坂城再築
大坂夏の陣で廃墟同然となった大坂城は、家康の孫である松平忠明に与えられた。忠明は、大坂の町の復興に努めたが、この間、大坂城の本格的な再建はなかったと考えられる。
元和5年(1619)大坂は幕府直轄領となり、翌6年(1620)2代将軍徳川秀忠により大坂城再築工事が起こされ、3期に渡る工事を経て3代将軍家光の時に完成した。 -
「大阪城公園」
●築城の経過
秀忠は普請総奉行に選ばれた藤堂高虎に、「石垣を旧城の2倍に、堀の深さも2倍に」と強調したという。
築城工事のうち、堀の掘削や石垣の構築は西国と北陸の諸大名64家が幕府の命を受けて担当し、建物の建設は幕府の直営で行われた。 -
「大阪歴史博物館」
天守の建設は第2期に行われ、その石垣は熊本城主の加藤忠広が築いた。天守建物は寛永3年の竣工で、外観5層・内部6階、高さ58、5mに達する巨大な建造物であった。 -
大阪城「歴史博物館」
「旧第四師団司令部」
元和6年から始まる第1期工事では、東・北・西の外堀の構築と西の丸などの建物、寛永元年から始まる第2期工事では内堀の構築と本丸御殿など、さらに寛永5年から始まる第3期工事では南外堀の構築と二の丸南部の建物の建設が行われた。 -
大阪城「大阪歴史博物館」
●旧 第四師団司令部
司令部は大阪府大阪市東区(現中央区)の大阪城内に設置された。
当初は大阪城内の各所に司令部機能が分散していたが、1931年に天守が再建された際に司令部も天守の隣接地に建設された新庁舎(写真)に移転し、司令部機能を集約した。
閉鎖中、2000年3月に入場して見物しました。 -
大阪城「桜門」内側から
●石造りの巨城
大坂城は、石垣の規模が格段に大きいだけでなく、堅くて良質の花崗岩からなり、しかも要所には、比類のない巨石が多く使われている城として全国の城郭のなかでも抜きんでた存在である。 -
「大阪城」
●蛸石(たこいし)
桜門枡形の正面にあるのが城内第1位の巨石として知られる蛸石(59.43・=36畳敷)である。厚さ平均0.9mとして、重さは約130トンと推定される。
-
大阪城「桜門」
各大名の競争心に加え、築城技術の完成期に再築されたため、大坂城の石垣には高度に洗練された技術が見られる。 -
大阪城「桜門」
2000年3月、妻と訪れた時に記念写真を撮っている場所です。懐かしい門です。 -
大阪城「桜門前」
泰平の世に大坂城を守っていたのは、幕府から任命された城代をはじめとする大名や旗本たちの武士であった。 -
「大阪城」
●城主の訪れない城
徳川時代大坂城の城主は歴代の徳川将軍であるが、3代将軍家光が訪れた後、幕末動乱のさなかに14代家茂が入城するまで230年もの間、大坂城を訪れた将軍はいなかった。 -
「大阪城石垣」
●最後の将軍慶喜と落城
14代将軍家茂が征長戦争の最中に大坂城中で病没、後を継いだ徳川慶喜は15代将軍として幕府崩壊までの1年余り大坂城と二条城を舞台に、諸外国の代表との会見などに活躍した。 -
「大阪城」
しかし、慶応4年(=明治元年1868年)幕府軍が鳥羽伏見の戦いに敗れると、慶喜は大坂城を脱出、江戸へ逃げ戻った。
その混乱の中で本丸台所付近などから出火し、近世城郭建築の精華であった城内の建造物はほとんど焼失してしまった。
こうして、再築以来約250年を経て、大坂城は再び落城の憂き目を見ることとなったのである。 -
「大阪城」
●明治以降の大阪城
明治以降、大阪城跡は陸軍の軍用地として整備され、維新の大火で焼け残った櫓や城門・焔硝蔵・金蔵などもすべて実用に供された。
本丸内にも軍用建物が建て込み、市民や観光客の城内への出入りは禁止されていた。 -
「大阪城」
●立地
大坂城は、上町台地の北端に位置する。かつてこの地のすぐ北の台地下には淀川の本流が流れる天然の要害であり、またこの淀川を上ると京都に繋がる交通の要衝でもあった。 -
大阪城「多聞櫓」
台地北端に立地する大坂城では、北・東・西の3方は台地上にある本丸からみて低地になっている。
北の台地下には淀川とその支流が流れており、天然の堀の機能を果たすとともに、城内の堀へと水を引き込むのに利用された。 -
「大阪城大手門より」
●重要文化財
現在、城内には、大手門、焔硝蔵、多聞櫓、千貫櫓、乾櫓、一番櫓、六番櫓、金蔵、金明水井戸屋形、桜門などの遺構が残っており、国の重要文化財に指定されている。 -
「大阪城大手門より」
2003年には大手前三の丸水堀跡の発掘調査で、堀底からは障壁のある障子堀が検出され、堀の内側の壁にトーチカのような遺構も見つかった。
また、この発掘によって、堀自体が大坂冬の陣のときに急工事で埋められたことを裏付ける状況証拠が確認されている。 -
大阪城「大手門」
6年3ヶ月ぶりでした。想い出の写真を持って。
時の中を潜り抜けているようです。 -
「大阪城大手門と千貫櫓」
大手門とは城の正面玄関のこと。「追」手門と書かれることもある。
ちなみに裏口は搦手(からめて)と呼ばれ、大阪城の場合は大手門以外の玉造、青屋、京橋の三門は搦手口となる。 -
「大阪城」
お堀のベンチにて。仲の良さそうなスペイン系のご夫婦かな?いい絵です。 -
「大阪城」
●ロードトレイン
大阪城公園で平成18年3月25日(土)から機関車をデザインした車両による移動交通システムの運行を開始しました。
このシステムは、大手門前から城南地区のバス駐車場を経て桜門前までを4箇所の停留所を結ぶルートで運行を行うものです。 -
「大阪城」
●ロードトレイン
機関車はガソリン/LPガスのハイブリッドエンジンの車で、大阪城内では環境を考えLPガスによる運行となります。 -
大阪城「ロードトレイン」
また、リアルな外観デザインで、車輪と連動したピストンシリンダーは実際に駆動し、機関車本来のイメージを表現しています。
さらに、警笛には「汽笛音」を採用しています。 -
大阪城「ロードトレイン」
大手門から外堀南側を通って桜門まで行きます。 -
「大阪城公園」
はとポッポさん
ロードトレインはシュッポッポ(^^;) -
大阪城「ロードトレイン」
大 人(中学生以上70歳未満)200円
こども(3歳以上小学生以下) 100円
高齢者(70歳以上) 100円
障害者の方 無料
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (2)
-
- 紫陽花さん 2009/05/16 18:19:43
- 大阪城が詳しくわかりました^^
- Godzilla.T&N様
初めまして。紫陽花と申します。
大阪人の私ですが、全く大阪城のこと知らなくて、
とても勉強になりました^^;
あと、とてもお写真が綺麗ですね。
私は下手っぴカメラマンなので^^;
少し前に映画「GOEMON」を見てたので、
すごく、わかりやすい説明がいっぱい書いてあって、映画の意味もわかった気がします。ありがとうございます^0^
私の好きな紫陽花のお写真だったので、何度がお邪魔してました^^;
これから、紫陽花の綺麗な季節なので、楽しみです。
では、また。
紫陽花より。
- MechaGodzillaⅢ&703さん からの返信 2009/05/17 22:01:51
- RE: 大阪城が詳しくわかりました^^
- 紫陽花さん、こんばんは。
広島市在住の Godzilla.T&N と申します。よろしくお願いします。
> 大阪人の私ですが、全く大阪城のこと知らなくて、
> とても勉強になりました^^;
大阪城訪問は2006年9月ですね。わたくしは2度目でした。車旅、大阪は右も左も分からなくて、駐車場探しで右往左往した記憶があります。
> あと、とてもお写真が綺麗ですね。私は下手っぴカメラマンなので^^;
そんなことはないですよ。旅行ブログですので、旅中の景色や思いが自然に出ていて、よい写真だと思います。
> 私の好きな紫陽花のお写真だったので、何度がお邪魔してました^^;
ありがとうございます。わたくしも紫陽花には特別な思いがありまして、お邪魔させていただきました。
> これから、紫陽花の綺麗な季節なので、楽しみです。
そうですね。
それでは、これからもよろしくお願いいたします。
Godzilla.T&N
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
MechaGodzillaⅢ&703さんの関連旅行記
大阪城・京橋(大阪) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?




































































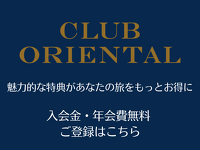









2
55