
2007/01/27 - 2007/01/27
410位(同エリア667件中)
![]()
マキタンさん
三渓園に行きました。三溪園は生糸貿易により財を成した実業家 原 三溪によって、1906年(明治39)5月1日に公開されました。175,000m2に及ぶ園内には京都や鎌倉などから移築された歴史的に価値の高い建造物が巧みに配置されています。(現在、重要文化財10棟・横浜市指定有形文化財3棟)
東京湾を望む横浜の東南部・本牧に広がる広大な土地は、三溪の手により1902年(明治35)から造成が始められ、1908年(明治41)に外苑、1923年(大正12)に内苑が完成するに至りました。三溪が存命中は、新進芸術家の育成と支援の場ともなり、前田青邨の「御輿振り」、横山大観の「柳蔭」、下村観山の「弱法師」など近代日本画を代表する多くの作品が園内で生まれました。その後、戦災により大きな被害をうけ、1953年(昭和28年)、原家から横浜市に譲渡・寄贈されるのを機に、財団法人三溪園保勝会が設立され、復旧工事を実施し現在に至ります。
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 1万円 - 3万円
- 交通手段
- JRローカル
-
三渓園入口。国の名勝に指定され特別公開がされた。
-
-
-
-
-
-
鶴翔閣(旧原家住宅) 横浜市指定有形文化財
1902年(明治35年)三溪が建て、三溪園造成の足がかりになった。広さ290坪に及ぶこの住宅は、主に、楽室棟、茶の間棟、客間棟から構成されている。 上空から見た形があたかも鶴が飛翔している姿を思わせることから、“鶴翔閣”と名づけられた。 -
鶴翔閣には日本を代表する政治家や文学者が集い、横山大観、下村観山といった日本美術院の画家が創作活動のために滞在した。
-
-
白雲邸【横浜市指定有形文化財】1920年(大正9年)建築
三溪が建て、亡くなる前までの約20年間を過ごした住居で数寄屋風の建物。。 玄関から入ってすぐの洋間は食堂や談話室に使用され、三溪が友人と語りあい、美術品を鑑賞する場として使用された。
和風の木造住宅だが、当時は珍しい電話室やシャワーなど近代的設備が取り入れられていたそうで・・。 -
-
-
-
ご夫人の個室は取り分け入念な細工が施されている。
-
臨春閣 【重要文化財指定】 1649年(慶安2年)建築
もとは、紀州徳川家初代徳川頼宣が夏の別荘として、現在の和歌山県岩出市に建てたもの。1906年(明治39年)、三溪の手に渡り、1915年(大正4年)から1917年(大正6年)にかけて園内に再建されました。 第一屋、第二屋、第三屋で構成され、襖絵は狩野探幽、狩野安信などによって描かれています。 -
-
部屋の境にある欄間には、波の彫刻(第一屋)や、歌が詠まれた色紙をはめ込む(第二屋)などの工夫が凝らされている。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
春の七草が揃っていた。
-
旧燈明寺本堂【重要文化財】室町時代建築
三重塔と同じ京都燈明寺にあった建物。 三溪園には、1988年(昭和62年)に5年がかりで移築・保存作業が行われ、 中世密教寺院の姿がよみがえった。
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
マキタンさんの関連旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?






































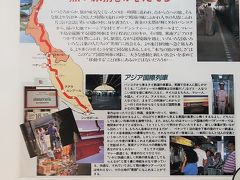
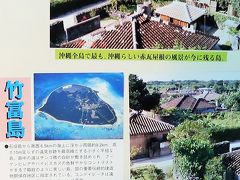














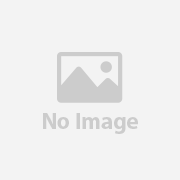
0
35