
2006/10/16 - 2006/10/16
125位(同エリア194件中)
![]()
まみさん
2006/10/16(月)第9日目:ブダペストからエステルゴム日帰り
エステルゴムの大聖堂&宝物館、水の町地区(Vizivaros)〜セーチェーニ広場まで散策
ブダペストに戻った後:エルジュベート広場からインターコンチネンタルホテルそば
での夜景撮影
エステルゴム散策は、いまから思えば、たとえ博物館が休館の月曜日でも、もっといろいろ歩き回れるところがあったと思います。
エステルゴムに限らず、ですが、行こうと思っていたところでも、現地で「やーめた!」としてしまうことは、よくあります。
あまり時間がなかったり、疲れていて気力が萎えてしまったり、疲れた体にムチ打ってまで行く気がなくなったり、他に優先したいところが出てきたり。
しかし、帰国後、写真やガイドブックをもう一度ひっくり返していると、もっとしっかりしなさいよ、そこ行くのをやめると、後で後悔するよ───と、旅行中の自分に注文つけたくなるものです。
といっても、後から自室でくつろいで言ってるんですから、なんとでも言えますよね。
「エステルゴムはハンガリー発祥の地である。建国以来ハンガリーの国王たちは、政権争いを繰り返しながら異教徒を鎮圧し、外敵と戦い、1526年にモハーチュでトルコに敗れるまで、ひたすらマジャル王国を守ってきたのである。」
(「旅名人ブックス ハンガリー “千年王国”への旅」(日経BP社)より)
-
エステルゴム大聖堂前から周辺を見回して
修道院が見えます。
手前の木の葉はもう少しきれいな赤に染まっていたのですが、逆光気味だったせいで、あまり色がきれいにでませんでした。
でもこうやって近景と遠景をコントラストにして写真を撮るのが好きなのです@
大聖堂内部の見学を始める前に、まず先にドーム(Kupola)の展望台に登ろうと思いました。
東欧の教会に、エレベータなんて洒落たものがあると、はじめから期待してはいけません。階段です。体力があるうちに登るべし。
ところが、ドームの展望台は修復中で閉まっていました〜(泣)。
大聖堂に近づいたとき、一部、修復用の覆いがあるのを目にして、いやな予感がしていたのです。
代わりに、なにやら歴史ある鐘なら見ることができる、というので、あんまり興味はなかったけれど、それを見に行くことにしました。
入場料は200フォーリントでした。
(2006年10月現在、1フォーリント=約0.6円)
鐘にはほとんど期待していなかったけれど、代わりに見に行くことにして結果的には良かったです。
というのも、途中でテラスに出ることができて、この景観を得ることができたのですから。
ドームよりは低いですが、大聖堂自体が丘の上に立っているため、十分な高さでした。
一方、鐘はどうだったかというと、やっぱり私にはあんまり面白くなかったです。 -
エステルゴム大聖堂から見下ろして
ドナウ川とマーリア・ヴァレーリア橋
手前は水の町地区(Vizivaros)の一部、対岸はスロヴァキアの産業都市ストロヴォ
「ハンガリーとスロヴァキアの間を東に流れるドナウ川は、完全にハンガリー領へ入ってから向きを南に変え、ブダペストに向かう。この辺りはドナウベント(ドナウの曲がり角)と呼ばれ、エステルゴムはその最初の町。」
(「旅名人ブックス ハンガリー “千年王国”への旅」(日経BP社)より)
これも、鐘を見に行く途中のテラスから撮ったものです。
さすが、ドナウベントの最初の町だけあって、ドナウの大きく歪曲した様子がよく見えます。
それにしても、こうして眺めてみると、ストロヴォは思いっきり産業都市です。
あのマーリア・ヴァレーリア橋を渡って国境を越えるのもいいかもしれない、と思ってやって来ましたが、なんだかわざわざストロヴォまで足をのばす気がなくなってきてしまいました。
ストロヴォには観光客の興味の引くものが特にあるわけではない、とは聞いていました。
もともと、橋を渡れば異国、という、島国の日本人の私にとってあまり経験のないシチュエーションを楽しみたかっただけというのもありました。
しかし、こうして上からストロヴォの町を眺めて見ると、工場ばかりに見えます。
その周辺を囲むレンガ造りの高層建築は、工場に勤める人たちの住居かしら。
古めかしいレンガ造りの建物が並ぶ通りにはちょっと興味が沸きましたけれど……それにしても、こうして見ると、やっぱり工場ばかり。ちょっと小洒落たショッピングエリアでもあれば楽しいかもしれませんが、あの様子では、たとえあっても、住民にとって必要なものがそろうだけで、回って見ているだけで楽しそうなお店があるように思えません。
それに、工場からは、白い煙がもくもくと空に上っていきます。
風邪気味で、ただでさえ喉が痛くて咳がとまらないのに、あんな煙、見ているだけで、また咳が出てきそうです。
もっとも、その気がなくなった一番の理由は、そんなにたくさん時間があったわけではなかったからですね。
日帰り旅行をするなら、朝、もっと早くにホテルを出ればよかったのに、エステルゴムに着いたのは昼なんですもの。
いくら月曜日で、どうせ博物館には入れないから、と思っていたにしても、10月は日が暮れるのも早いのです。ちょっとのんびりしすぎました。 -
エステルゴム大聖堂から見下ろして
ドナウ川とマーリア・ヴァレーリア橋
手前は水の町地区(Vizivaros)の一部、対岸はスロヴァキアの産業都市ストロヴォ
「10世紀、アルパードの曾孫であるゲーザ公はエステルゴムに城を築き、ここを拠点とする。ここで生まれた息子のヴァイクをキリスト教に改宗させ、名をイシュトヴァーンとあらためた。ゲーザ公が997年に亡くなると、イシュトヴァーンが後を嗣いで首長となる。彼は首長の位を狙う従弟のコパーニュを破り、西暦1000年に神聖ローマ帝国皇帝オットー3世の同意を得て初代ハンガリー王となる。彼はローマ教皇から贈られた王冠をもって、エステルゴムで戴冠式をあげた。つまり、ハンガリー一千年の歴史はここエステルゴムから始まったのである。」
(「旅名人ブックス ハンガリー “千年王国”への旅」(日経BP社)より)
ちょうど正午の大聖堂の丘は、ドナウを見下ろす写真を撮るには逆光で、撮りにくくなる時間帯に入ってしまったようです。
写真を撮るときに、気持ちの良い晴天の空と青きドナウを優先させると、両岸の都市は暗くなってしまうし……露出を調整するのがむずかしかったです。 -
エステルゴム大聖堂から見下ろして
ドナウ川とマーリア・ヴァレーリア橋
「1944年にドイツ軍により破壊されたままになっていたスロヴァキアのシュトロヴォを結ぶドナウの川のマーリア・ヴァレーリア橋は、第二次世界大戦後初めて再建され、2001年10月に修復が終わった。現在は対岸のスロヴァキアへ徒歩でも渡ることが出来るようになった。また、この橋からは壮麗なエステルゴム大聖堂を眺めることが出来、撮影の名所となっている。」
(参考「ハンガリーを知るための47章」(明石書店)ほか)
写真は、はるかかなたに見えるなだらかな山脈に露出を合わせました。
少し暗くなってしまうけれど、ブルーのモノトーンチックで物憂げな写真として、これはこれでいいかな。
うまい具合に船が視界に入ってきました。
エステルゴムの歴史やマーリア・ヴァレーリア橋については、ブダペスト在住の「さがみ」さんのHPが面白く、また、とても参考になります。
マーリア・ヴァレーリア橋を渡ったときの迷道中(!?)もなかなか@
HP「ハンガリー良いとこ一度はおいで」
http://www.szagami.com/index.htm
同HP「各街での歩き方」─「エステルゴム」
http://www.szagami.com/cities/ab-esztergom.htm -
大聖堂の裏から、丘のふもとの水の町地区(Vizivaros)とドナウ川を見下ろして
大聖堂を出て、その裏側から見下ろしても、これだけ見晴らしがよいです。
もっと右手の方へ進むと、少し川に向かって突き出していて展望台のようになっています。
そこでも写真を撮ろうとしましたが、水の町地区(Vizivaros)が見えなくなってしまうのでやめました。
この位置から見下ろす景色の方が気に入りました。
水の町地区(Vizivaros)の中で目立つ大きな館は、修道士館ではないかと思います。 -
大聖堂の裏の白い彫像
ひざまずいているのはイシュトヴァーン王ではないかと思います。
では、彼の頭に手をかざしているのは誰?
神でしょうか、あるいは洗礼をほどこしている聖者とかでしょうか。
ひょっとして、イシュトヴァーンが少年のときの教師で、最期は異教徒に殺されたという聖ゲッレールトかも……!?
聖ゲッレールト説は一番可能性が低いですが、しかし、進む道に迷ったとき「先生、私はどうしたらよいのでしょうか」と、すでに亡くなった師に語りかける図、なんて、ちょっとロマンチックかも!
ああ、でも敬虔なキリスト教徒なら、そういうときは神に問いかけるのですね。
あるいは聖母マリアかしら。
なにしろイシュトヴァーンといえば、後継者である息子のイムレ王子を亡くしたときに、マリアに向かってハンガリーの行く末を嘆き、庇護を求めた、という伝説があって、それゆえにハンガリーは、「聖母マリアの国」とされているというのですから。 -
大聖堂の裏の崖から水の町地区(Vizivaros)へ下りる小道
この道は見つけづらかったです。
実際にこの小道をたどって下へ下りる人たちを見かけなければ気付かなかったでしょうし、彼らがどこからこの小道に出たか、すぐには分かりませんでした。
大聖堂の裏に、石造りのすてきなカフェがありました。
もっとも、シーズンオフなのか、営業していませんでした。
そのカフェの、使われていない野外席の脇に、店の地下室にでもいくような石造りの階段がありました。
階段の先は扉になっているので、一見、入れないように見えます。
でも、ひょっとして……と思って下りてみたら、この小道に出たというわけです。
ちなみに、遠景に見える双塔を抱く教会は、フランシスコ派教会です。 -
水の町地区(Vizivaros)へ下りる大聖堂の裏の崖沿いの小道から大聖堂の方を見上
げて
きれいな青空。上空は風が強いのか、雲がぐいぐい流れています。
綿雲が視界に入るのを待って撮りました。
崖沿いの小道を歩くのは気持ちが良かったです。
いちいち背後を振り返って、大聖堂の見え具合を確認しながら下りました。
頭上の石壁からドナウ川を見下している人たちから、どうやったらこの小道に出られるのだろう、と思って私の方を見ている気配が伝わってきます(そんなような気がしたのです@)。
そうなのよ、この小道に出るのは、分かりにくいのよ〜。見つけられるものなら、見つけてごらんなさい@
もっとも、誰もが私にように方向音痴で状況判断が悪いわけではないですから、きっと小道はすぐに見つけられてしまうでしょう。 -
水の町地区(Vizivaros)へ下りる細い石段
ゆったりと下へ向かう石階段。ごつごつした白い石壁に、緑と赤の植物が鮮やかに映えています。
行き先が見えるようで見えない、微妙な曲がり具合。この先に何が待っているのかな、とわくわく期待させます。
人影が入っている写真と入っていない写真と両方を撮ってみて、人影がある方が私は気に入りました。
そのほうが距離感と、それから寂寥感のようなものがよく出るのではないかと思ったのです。
それにしても、街並みの写真を撮るには、晴天すぎるのも考えもの。
日ざしが強くて、日のあたるところは本来の壁などの色が飛んでしまい、逆に影のところは真っ暗になってしまうのです。
これも、最初は撮るのをあきらめようと思いました。
でも、あんまりイイ雰囲気なので、撮らずにはいられませんでした。
これでも、あまり影が目立たないように撮ったつもりですが……。 -
水の町地区(Vizivaros)のパステルカラーな家屋の窓
ハンガリーではありふれた家の1つでしょう。
でも、この窓枠と壁に映る木影と、太くて黒い窓枠から覗く、今にも揺れそうなカーテン。
これら全部を合わせて、いいなと思ったのです。
一昨日のセンテンドレの街中の写真撮影で、私は窓枠写真を撮りたいのだと自覚しました。
ここエステルゴムでも、その趣味に走った写真撮影を楽しめそうです。
正直いって、最初、水の町地区には、期待が大きかっただけにがっかりしてしまいました。
バロック様式の建物があったにはあったのですが……道路が工事中だったのです。
大胆にえぐられた舗装。道の両側に積み上げられた瓦礫やトラックが邪魔。ぼこぼこで歩きにくいし、空気が乾燥しているから、剥がされた舗装の下のさらさらの白い土から、もくもくと砂煙がたち、風邪で敏感になっている喉に響きます。
でも、その工事中の道を抜けると、こんなすてきなパステルカラーな家が並ぶ通りに出ることができました。 -
水の町地区(Vizivaros)から大聖堂のある丘を見上げて
ビビッドなカラーの家に目が惹きつけられました。青空とのコントラストが強烈です。
それだけではなく、この写真も、壁に映る街灯の影がいいアクセントになると思って撮りました。
ちなみに、背後の崖の上に、大聖堂があります。 -
水の町地区(Vizivaros)から大聖堂を見上げて
ここもとってもすばらしい景観です。
大聖堂の裏から下りて正解でした。表からバス通り沿いを下りていたら、ここに出るまで遠回りになったでしょう。気付かずに通り過ぎてしまったかもしれません。
「ベーラ3世の時代に立てられたエステルゴムの王城や礼拝堂はフランス・ゴシック様式の影響を受けているが、今日までほとんど残っていない。」
(「ハンガリー」(クセジュ文庫)より)
王城は、もしかしたら大聖堂と共にあの丘の上にそびえていたのかもしれません。
セント・イシュトヴァーン広場(大聖堂もある広場)にある城博物館には、エステルゴム城の歴史を紹介する展示があったそうなので、かつての王城跡などが分かったかもしれません。
しかし……今日は月曜日なので、博物館は休館です(泣)。 -
水の町地区(Vizivaros)のフランシスコ派教会の双塔と、その間から顔を出す大聖堂のドーム
この後、マーリア・ヴァレーリア橋の方に向かおうと思ったのですが、むしろ早めにブダペストに戻りたくなってしまったので、ゆっくりと駅の方向へ向かうことにしました。
ただし、大聖堂から駅まで約1.2km。歩いて30分かかるといいます。写真撮影をしながらでの私の足では、その倍はかかるかもしれません。
とりあえず、町の中心のセーチェーニ広場まで戻り、そこから市バスを拾うことにしました。
市バスの運賃は、片道たったの140フォーリントですもの。
(2006年10月現在、1フォーリント=約0.6円) -
リスト・フェレンツィ通りの家屋の窓
再び趣味に走った窓枠写真撮影開始!
一度始めると、とまりません。あ、いいな、と思うところが、あちこちにあるのです。
行きに、エステルゴム駅から大聖堂に向かうバスの車窓から、この町にはパステルカラーな可愛い家がたくさんあるなぁと思ったものです。
大聖堂周辺にも、こんなに私の目を引く家屋があったなんて!
本当はドナウの支流キシュ・ドナウ沿いを散策して町の中心に戻ろうと思いました。
でも、美しく気持ちのよい並木道になっているとは思ったのですが、「それだけ」とも思ってしまいました。それに町の中心のセーチェーニ広場に戻るにはやや遠回りです。
というわけで、メインストリートのバイチ・ジリンスキー通りに出る横町に入ってしまいました。
でもそこに、このように趣味に走った窓枠写真撮影の被写体がたくさんあったのです。かえって良かったと思いました@ -
リスト・フェレンツィ通りの家屋の窓
なんだか、「眠れる森の美女」のオーロラが奥で眠っていそうな……。そんな想像がかきたてられます。
あるいは、毒リンゴにのどをつまらせた白雪姫が眠るこびとの家かな。 -
リスト・フェレンツィ通りの家屋の窓
この壁の色に青の窓枠と扉というのがマッチしているのがなんだか意外です。 -
リスト・フェレンツィ通りの家屋の窓
これも木影が窓に映っているのがいいアクセントになっています。
うーむ、この窓枠、ちょっとマイメロディーを連想してしまいました。
(サンリオのウサギのキャラクターです。ピンクの帽子をかぶったようなところが、ちょっと似てるかなぁ〜と@) -
バイチ・ジリンスキー通りにて
これはエステルゴムで撮った写真の中では一番のお気に入りです。
崖の上には、大聖堂の前から見えた、もう1つの丘の上の礼拝堂が見えます。
そして、道路の向かいのお店。南国にいるようなこの明るい色使いは、どうでしょう。ハンガリーにいるとは思えません。
あるいはこういうセンスこそ、ハンガリーらしいのでしょうか。
撮ろうと構えているところへ、通行人がやってきました。
ただの街角の写真でも、人が入ると画面が引き締まり、面白い写真になる───少なくとも、センテンドレで、そしてさきほど大聖堂から水の町地区に下りる最後の石段でそう思いましたので、通行人が通りすぎるのを待つのではなく、ファインダーの中に入るように狙いました。
人影がファインダーの中に入ると、だいたい適度なタイミングで何回かシャッターを切ります。
その中で一番バランスがよいと思ったこの1枚を残しました。
少年、ちょっと猫背気味ですけどね@ -
バイチ・ジリンスキー通りにて
信号で止まった市バスを、とっさにファインダーに収めました。
白い壁に青い窓枠、赤い看板、そして白と緑のペイントのバス。
うーん、我ながらこの配色が気に入りました@@
直感的にシャッターを切りましたが、チャンスを逃さなくてよかったです。 -
セーチェーニ広場の交差点にて
バス停で駅に向かうバスを待っているときです。
向かい側のあの赤い建物が気に入りました。
写真を撮ろうとして、ふと、交差点の向こうで信号待ちの女性を一緒にファインダーに収めた方が雰囲気が出るのではないかと思いました。
チャンスは二度ありません。
女性がそこにいるうちに、何回も何回もシャッターを切りました。
こちらを向いているより、上着に手をつっこむ、背を向けているポーズのこの1枚が一番気に入りました。
14時に大聖堂を出て、展望台の方へ行ったり、もう一度大聖堂に戻ったり、もちろん写真を撮りながらのんびり歩いていたら、町の中心のセーチェーニ広場に着いたときには、15時になっていました。
さすがに町の中心だけあって、バス停が3つほどあり、バス路線がいくつも交差しているようです。
さて、「地球の歩き方」の情報によると、駅から大聖堂に行くバスは、1番と6番。
行きは、バス路線にBazilikaとあるのを探せばよかったので、番号は気にせずにすみました。といっても、この情報は正しく、乗ったのは6番バスでした。
でも、帰りは?
セーチェーニ広場で拾えるバスは、町のあちこちに行き、必ずしも駅に向かうとは限りません。
それに、運転手さんに何と言って切符を買えばよいでしょうか。
「駅」のハンガリー語は、ものすごーく覚えにくいです。ブダペストで地下鉄などの車内放送で何度聞いても頭に入りませんでした。
スペルに頼ったからいけないのでしょう。スペルは、palyaudvarです。しかし、そのまんま「パーリアウドヴァル」と言おうとすると、「パーリアウ」のあたりでもたもたしてしまいます。
しかも、地下鉄の車内放送ではどう聞いても、「パーリアウドヴァル」と言っているように聞こえません。
あるとき、やっと気付きました。「パーリドヴァー」でいいんです、「パーリドヴァー」で@
しかし、パーリドヴァーは、ターミナル駅となるような大きな駅にしか使われません。
なので、一度地方都市で、「パーリドヴァー」に行きたい、と道を聞いたときに、「ないっ!」と言われたことがあります。
そのときは、「嘘つき!」と思ったものですが、確かに小さな町の駅はパーリドヴァーと言わないので、嘘ではなかったのです。
例えば日本で外国人が、「ハイスクール」に行きたいと思って日本人に道を聞くとき、「高校」か「中学」か区別していなかったとしたら、同じようなことになるのかもしれません。
地方の小さな駅は「アーロマーシュ(allomas)」です。
このくらいなら、ちょっと調べたら、旅行会話集の巻末の語彙集などにちゃんと載っていました。
でも、アーロマーシュはバス停にも使われます。そのせいか、バス停の路線を見ても、ただのAllomasでは見つけることはできませんでした。
もしや、と思って、「鉄道」のハンガリー語を調べてみたら、vasutとありました。
すると、鉄道駅とは、Vasutallomas。
ありました、ありました!
そういえば、Vasutallomasといったら、いままでさんざん列車やバスの車窓から目にしていた単語です。通り過ぎた駅に、よくVasutallomasと駅舎に書かれてあったものです。
私はてっきり、「待合室」という意味かと思ってましたよ〜(笑)。いつも、そんな雰囲気の部屋の扉の上に書かれてあったんですもの。
もとあれ、15時11分頃にやってきた1番バスを無事に捉まえることができました。
運転手さんに、おっかなびっくり、「アーロマーシュ!」と言ったら、一瞬、けげんそうな顔をされた気がしますが(発音が悪いからでしょう@)、ちゃんと通じました。ほっ@
しかし、行きに利用した駅から大聖堂に向かう6番バスは、地図どおりにメインストリートであるバイチ・ジリンスキー通りを素直に大聖堂前まで走ったのですが、帰りに利用した1番バスは、途中でバイチ・ジリンスキーを外れ、住宅街をぐるぐる周り出しました。
行きに比べると、いやに時間がかかっている気がいます。だんだん不安になってきました。
というのも、駅前のバス停は、駅からちょこっと離れた、ふつうっぽい通り沿いにありました。駅前の様子をしっかり覚えていたとは言い切れず、しかもあまり駅前らしいにぎわいのない小さな駅でした。車窓から確認できるかどうか、自信がなかったのです。
一度、車窓の外に線路が見えたのですが、またバスはあらぬ方向に曲がってしまいました。
しかも、ブダペスト行の列車は15時半。それを逃すと、1時間待つことになります。できれば15時半の列車を捉まえたいものです。
駅はまだかと、ハラハラしてきました。
あるいは私は降り損ねてしまったのでしょうか。
運転手さんのすぐ後ろの席で、顔をきょろきよろ、ときどき腰を浮かせながら車窓の外を眺めていたら、やっと見覚えのあるところに着きました。駅です、駅です!
さすがに鉄道駅前だけあって、降りる乗客も多かったですし、降りようとしたときに運転手さんの方を見ると、運転手さんもうなずいてくれました。
駅に着いたのは15時半前を5分切っていました。ぎりぎりです。
駅舎の掲示の発車案内で、ブダペスト行が2番ホームであることを確認して、大急ぎでホームに出ました。
列車は2台、ホームに入っていました。
でも、どちらもいわゆる2番ホームに停車しているように見えます!
ハンガリーの小さな駅は、何番ホームかという表示がとても見づらいのです。長〜いホームの、いま自分がいる位置からうんと離れたところに一箇所だけ、ぽつんと表示されていたりします。
駆け込み乗車は苦手な私。慣れない駅できちんと確認せずに飛び乗ると、ほぼ必ずといっていいほど間違えます。
しかも、日本と違って海外の駅では、発車しまーす!の予告もなしに、扉が閉まって、すっと発車してしまいます。
ということを知ってるから、あせる、あせる、あせる!
といっても、2台あるうち、片方は乗客は全然乗っていませんし、あと1〜2分で発車するようには見えません。
なら、こっちか?
でも念のため、これから乗ろうとする人をつかまえて確認しました。ブダペストに戻る場合は、同じ方向へ行く人を見つけやすいから助かります。
そして17時15分に、無事、ブダペストの西駅に着きました。
ちなみに、西駅は、ハンガリー語で、ニュガティ・パーリドヴァーです。
ターミナル駅なのでパーリドヴァーなのです@
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
まみさんの関連旅行記
ドナウベント(ハンガリー) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?
ドナウベント(ハンガリー) の人気ホテル
ハンガリーで使うWi-Fiはレンタルしましたか?

フォートラベル GLOBAL WiFiなら
ハンガリー最安
538円/日~
- 空港で受取・返却可能
- お得なポイントがたまる































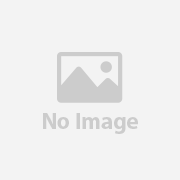





0
20