
2024/05/11 - 2024/05/11
537位(同エリア1704件中)
![]()
玄白さん
連れ合いのかつての茶道の師匠K女史の米寿の祝いで伊豆に温泉旅行に行くというので、アッシー君を務めることになった。いつもの友人の山中湖ロッジに前泊し、翌日は義母の墓参りをしてから三島在住のK女史をピックアップして修善寺の温泉宿に2人を送り届け、その日は一人で城ケ崎海岸に移動、車中泊して星空撮影を楽しむ、翌日はK女史を自宅に送り届けた後、箱根のオーベルジュ、オー・ミラドーで美味しいフレンチとワインを楽しみ、最終日はかねてより一度訪れたいと思っていた小田原の江の浦測候所を訪ねるという、盛りだくさんの3泊4日の旅でした。
第4巻は今回の旅の最終日に訪れたユニークな現代美術の展示で人気の江の浦測候所の鑑賞記録です。
- 旅行の満足度
- 4.5
- 同行者
- カップル・夫婦(シニア)
- 交通手段
- 自家用車
PR
-
なんとも不思議な名前「江の浦測候所」という名の現代美術の展示施設である。日本よりは海外でよく知られた写真家にして現代美術、古美術収集、造園、インスタレーション、演劇など多岐にわたる分野で活動する杉本博司氏が、ミカン畑だった山の斜面を買い取り、自らが収集してきた古代からの建築や石、自ら設計した冬至、夏至に貴重な景観が出現する施設を配した独特の施設なのである。
この施設は、完全予約制で午前、午後の2回だけ2時間限定の見学時間が定められており、入場料は\3,300とけっこうな値段であるが、以前、TVの美術番組で紹介されていたことがあり、機会があれば訪れてみたいと思っていた次第。
駐車場から細い上り坂の歩道を進む。入り口には「不許葷酒(ふきょぐんしゅ」と書かれた石柱が置かれている。江戸時代の禅寺の山門にあった石柱で、匂いの強いものと酒は入山してはならぬという意味らしい。 -
坂を上り切ると「Stone Age Cafe」というカフェがあるのだが、そこは素通りして受付に急ぐ。何しろ3000坪の高低差がある広大な敷地を歩き回るので時間がもったいない。
右手には室町時代創建の寺の山門がある。鎌倉の名刹、明月院の正門だったが、関東大震災で半壊し、建築家で茶人の仰木魯堂という人が解体保存していたが、その後サッポロビール、アサヒビールの前身の大日本麦酒創業者、馬越恭平の邸宅の門として再建、昭和20年、米軍の空襲で邸宅は焼けたが門だけが残った。残った門は再度解体移築され、根津美術館正門として使われたが、2006年に、江の浦測候所を所管する小田原文化財団に寄贈され、ここに至っている。なんとも数奇な運命をたどった室町時代の建築物である。 -
まずは全面ガラス張りの待合棟へ。休憩所兼受付である。中央に置かれた大きなテーブルは、樹齢1000年超の屋久杉の一枚板である。
ここで、スマホの予約画面を見せて、受付したという証拠のワッペンを渡され、見学開始となる。 -
同時に立派な作りの展示物のガイドパンフレットを渡されるので、これを片手に施設内を見て歩くことになる。
-
まずは、江の浦測候所の主要施設である、夏至光遥拝100mギャラリーへ。海抜100mの地点にあり、左側は総ガラス張りになっている。
-
イチオシ
中に入る。右側の壁は大谷石でできており、所々に杉本氏の写真集「海景」に収録されている作品が飾られている。夏至の日には、ギャラリーの先端に見える海上から太陽の光が差し込むように設計されている。
-
杉本氏の代表的写真集「海景」シリーズ215作品を収録した「杉本博司 SEASCAPES」 ほとんどの作品が、海と空を2分割したシンプルな構図の写真ばかりで、正直なところ、これらの作品が高く評価されているというのが凡人フォトグラファーの玄白には理解できない。
2016年5月ロンドンで開催されたクリスティーズでは「海景」が386,736 US$で落札されたというから驚く。 -
100mギャラリーの突端は展望台になっていて、東洋のリビエラとも言われる風光明媚な相模湾、真鶴半島の景観が望める。遠くには大島の島影がみえる。
-
100mギャラリーを出て、もう一つの目玉展示、光学ガラス舞台と古代ローマ円形劇場観客席へ。舞台は、檜の懸造り(京都の清水寺の舞台と同じ構造)の上部に連続溶解炉から取り出されたレンズの材料である光学ガラスを敷き詰めている。おそらく光学ガラスでは一番安価でポピュラーなBK7という種類のガラスと思われる。
左の鉄板製の四角い通路が冬至光遥拝隧道で、先端近くまでその上を歩くことができる。高い位置にあり、手すりもなにもないのでけっこうスリルがある。冬至には、隧道の中を朝日が通り抜けるともに、光学ガラス舞台では、ガラスを通過した太陽光が、舞台の手前のガラス小口から射し込み、ドラマチックな情景になるのだろう。ただ、普通のガラスより透過率がよい光学ガラスとはいえ、これだけの長さのガラス内を通過する光はかなり減衰するはずなので、どれだけ冬至の太陽光がでてくるのか、元レンズ設計者としては気になるところではある。 -
イチオシ
空と海と光学ガラスのシンプルな構図でパチリ。偶然、蝶々が一匹飛んでいるのが写り込んでいる。杉本博司氏の作品、海景を意識して撮影してみた。
-
少しアングルを変えてみると、光学ガラスの表面の不規則なヒダに太陽光があたって虹色の点の密集がきれいだ。
-
冬至光遥拝隧道内部。冬至の日には、ガイドパンフレットの表紙のような光景が見られるはず。
-
隧道の中間付近に採光のために天井が開けられていて、井戸の枠が設置されている。中には光学ガラスの破片がぎっしり詰まっている。
-
内山永久寺の十三重塔。内山永久寺は石上神宮の付随寺で平安時代末期に鳥羽天皇の勅願で建立されたが、明治の廃仏毀釈で破壊されてしまった寺である。塔は近隣の豪族の家で保存されていたものだという。
-
十三重塔の奥に見えるのは、旧奈良屋門。箱根宮ノ下にあった旅館「奈良屋」別邸前にあった門だが、2001年に旅館が廃業し、箱根町を通して小田原文化財団に寄贈された。旅館廃業後の別邸は岸信介の夏の別荘として使われていたそうだ。
-
茶室「雨聴天」 質素なわずか2畳の茶室だ。
中には入れないが茶道家の連れ合いは、覗き込むと同時に京都山崎の待庵にそっくりだと声をあげた。ガイドパンフレットを読むと、確かに杉本氏が待庵を正確に採寸して作ったものだと書かれている。
待庵は、千利休が作った現存する最古の茶室で、国宝に指定されている。全国に茶室は数あれど、国宝に指定されているのは3か所しかない。大徳寺 龍光の「密庵」、犬山城下の有楽苑にある「如庵」、そして妙喜庵の待庵である。 -
躙り口の前に置かれた沓脱石も光学ガラス!
-
石造りの鳥居
パンフレットによると、山形市小立にある重要文化財の石鳥居に準じて作られたという。柱には中世以前と推測される矢のキズがあり、踏込石は古墳時代の石棺の蓋石を使ったとある。
杉本氏がこの施設のコンセプトだという「人類の意識とアートの起源に立ち返る」というのが、なんとなくわかるような気がする。
長文になるが、パンフレット冒頭に書かれている杉本博司氏の言葉を引用しておこう。
”アートは人類の精神史上において、その時代時代の人間の意識の最先端を提示し続けてきた。
アートは先ず人間の意識の誕生をその洞窟壁画で祝福した。
やがてアートは宗教に神の姿を啓示し、王達にはその権威の象徴を装飾した。
今、時代は成長の臨界点に至り、アートはその表現すべき対象を見失ってしまった。私達に出来る事、それはもう一度人類意識の発生現場に立ち戻って、意識のよってたつ由来を反芻してみる事ではないだろうか。
小田原文化財団「江之浦測候所」はそのような意識のもとに設計された。
悠久の昔、古代人が意識を持ってまずした事は、天空のうちにある自身の場を確認する作業であった。そしてそれがアートの起源でもあった。 新たなる命が再生される冬至、重要な折り返し点の夏至、通過点である春分と秋分。天空を測候する事にもう一度立ち戻ってみる、そこにこそかすかな未来へと通ずる糸口が開いているように私は思う。” -
旧奈良屋門
箱根宮ノ下にあった旅館「奈良屋」別邸の門だった。 -
夏至光遥拝100mギャラリーの先端を下から見上げる。下の道は竹林エリアに通じている
-
隠れキリシタン地蔵の石像。前面、左右側面には地蔵像が彫られているが・・・
-
背面には十字架が彫られている。秀吉がキリシタン禁教令を出した桃山時代のものだという。
-
光学ガラス舞台と冬至光遥拝隧道を下から見上げる
-
化石窟と名付けられた元ミカン畑の道具小屋の中に入ってみた。
5億年前の古生代オルドビス期から中生代ジュラ紀、白亜紀、新生代始新世期まで30点余りの化石が展示されている。
写真はワイオミング州で発見されたレプトメリックス・エバンシという鯨の祖先らしい -
古生代の夥しい三葉虫の化石。これら化石も見ようによっては現代アートと言えるかもしれない。
左下の黒い石はナミビアで発見されたギベオン隕石という鉄隕石である。
杉本博司氏は、化石収集家でもあったか! いやはやなんとも、その多彩な活動ぶりには圧倒される -
竹林エリアに移動した。
-
竹林の中に置かれた 「数理模型0004オンデュロイド」というモニュメント。
杉本氏が東大でこの数理モデルの形を見て製作したという。オンデュロイドは平均曲率がゼロでない回転面という説明だが、これだけではよくわからん! -
イチオシ
もう一つのモニュメントは、「数理モデル0010 負の定曲率回転面」。
パンフレットには、面の形状を表す数式が三角関数と双曲線関数を用いて示されている。微分幾何学の一つの例題であろうが、この歳で、数式を弄り回す元気はなくなっている。
杉本氏は数学の素養も持ち合わせているのだろうか。 -
モニュメントの土台は反射式天体望遠鏡の主鏡の材料である光学ガラスの上に置かれている。このガラス、BK7ではなく、ゼロデュアガラスか?!
-
イチオシ
ミカン畑の中を歩いて行くと、朱色のコンパクトな社にたどり着く。奈良の円成寺の春日堂を採寸し、同じ形に作り上げ、春日大社から分霊する儀式まで執り行ったそうだ。円成寺春日堂は日本最古の春日造り様式なのだという。海を背に立つたたずまいには、荘厳な美しさがある。
-
もともとミカン畑だった場所なので、今でもミカンの木が残っている。
ちょうど花が咲いている時期なのだ。静岡県生まれの玄白だが、ミカンの花を見るのは初めてだ。 -
ミカン畑の坂を登って、明月門がある方にもどる。
そこそこの高低差があり、バリアフリーになっているわけではないので、年配者には、ここを鑑賞するのは難しいかもしれない。足元もしっかりとしたハイキング用の靴にするなど、それなりの足回りを準備しないといけない。
坂を登りきると、春日社が、はるか眼下に見える。 -
相模湾の水平線と手前の新緑を眺めながら一息つく。
-
三角塚
一番上の三角形の岩の頂点は、春分・秋分の正午の方向と日の出の方向を指すように置かれている。この石は地元の根府川石が使われ、下には古墳の石室に使われた石が土台になっているという。
冬至、夏至、春分秋分は暦では重要なイベントであり、古代人にとっては生活面、意識の上で大切な節目であった。杉本博司氏のコンセプトの一つの表現ということだろうか。 -
ミカン畑の石組みを再利用した野点席
-
このエリアは随所に古代の礎石などを配した現代版石庭になっている。砂利にはきれいな箒目が付けられている。画面中央の石は東大寺七重塔の礎石である。
-
“伽藍道”の石標の立つ枯山水庭園の中の石はそれぞれ奈良・川原寺の礎石、奈良・元興寺の旧域で発掘された礎石、世界遺産『法隆寺』の旧域から発掘され民間へと渡った礎石などが配置されている。正に伽藍道である。これだけの由緒ある石を集めるには時間と手間がかかっているのだろう。
左側の岩壁は、夏至光遥拝100mギャラリーである。
杉本博司氏が構想10年、建設10年かけて造営し、2017年に一般公開されたこの現代アートの施設・庭園は、とても見ごたえがあり、見終わってみると、最初は随分高いと思った入場料\3,300は決して高いとは思えないという感想に変わったのであった。
<完>
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
小田原(神奈川) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?














































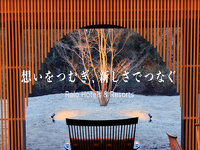








0
37