
2009/06/07 - 2009/06/07
494位(同エリア678件中)
![]()
まみさん
最初に言い出したのは母だけど、調べ始めたら私の方が乗り気になりました。
だって近所の菖蒲の最も良い見頃はまだだから、特に予定を入れていなかった週末ですもん。
言い出しっぺの母が「意外に遠いわね」と、日がたつにつれて気分がそがれていくのもいつものこと。
そんな母をたきつけて、行って来ました、柴又と水元公園へ。
どこぞのツアーパンフレットにあったコースを参考に、これっくらいなら自分たちで行けるよね、と。
どうせ柴又に行くなら、立派なお寺さんらしいので、被写体にしたい───。
そんな気持ちで、なんの予備知識もなく、うんちく好きの私が特に下調べもせずに行ってみた柴又帝釈天。
参道の突き当たりにそびえていた最初の二天門から、その立派な木彫りに惚れ惚れです。
日光東照宮を思わせるすばらしさ。
PowerShot SX 200 ISの12倍ズームなら、頭上の彫刻もズームで近影が撮れます。
食事処が開くまで時間があったのと、あまりおなかがすいていなかったので、400円払って彫刻ギャラリーと庭園も見て回りました。
彫刻ギャラリーとは、帝釈堂内陣の外側の、仏教経典の中の「法華経」の説話を題材にした10枚の彫刻。
これは圧巻でした。
一方母は、彫刻のこともすばらしいと感心していましたが、庭園の方が気に入ったようです。
はじめ400円でもケチってごねた母ですが(たいしたものはないだろうと思って)、「こんないいものが見られて良かった」と喜んでいました。
* * * * *
母に誘われて出かけた、他作自演(母がもってきたツアーパンフのパクリだから@)の柴又&水元公園の花菖蒲めぐり。
撮ってきた写真は、次の4つの旅行記にまとめました。
□(1)古き香りの寅さんの柴又
■(2)木彫りにうなった帝釈天
□(3)水元公園の花菖蒲散策と、帰りに寄ったしばられ地蔵
□(4)水の向こうの世界で咲く花菖蒲
柴又帝釈天公式サイト
http://www.taishakuten.or.jp/
またたび東京ガイドより「柴又帝釈天とは」(http://www.tokyoguide.net/spot/20/)
「柴又帝釈天は日蓮宗の寺で題経寺ともいう。行方不明になった日蓮がみつかったのが庚申の日だったので、庚申の日には縁日が行われる。駅から柴又帝釈天までの帝釈天参道には「男はつらいよ」のモデル(撮影現場)となった「とらや」をはじめ江戸時代から続く店が連なっている。柴又七福神の一つで、駅前の地図には七福神の寺の場所が記されている。
大正から昭和初期に彫られた彫刻が公開されている彫刻ギャラリーと回遊式庭園の邃溪園は共通券400円、9:00〜16:00」
- 同行者
- 家族旅行
- 一人あたり費用
- 1万円未満
-
帝釈天の境内へ
背景の門は、二天門です。 -
立派な構えの二天門
-
二天門の見事な彫刻
飛び出す獅子たちは、こうしてみると、なかなか可愛いです@ -
見事な浮彫彫刻から天井へ
いつも思うのですが、あの札みたいなのは、いったいなんでしょうね。 -
見事な浮彫
PowerShot SX 200 ISの12倍ズームは望遠鏡の代わりにもなります@ -
すばらしい浮彫の雉たち
-
二天門を背に、帝釈堂(左)と本堂(右)
-
左手に手水場を入れて
団体さんをやり過ごした後に撮りました。
そのときは、こういうアングルで撮影すると、どうしても人が入ってしまうなぁと思ったのですが、午前10時前のこの時間帯は空いている方でした。
彫刻ギャラリーと庭園でゆっくりした後、11時すぎにここに戻ってきたときは、かなりの人出でした。 -
柴又帝釈天境内案内図
400円払って彫刻ギャラリーと庭園も見学しました。
こうしてみると、庭園は結構な面積があります@ -
振り返って境内から二天門を眺める
日光東照宮の陽明門を模したそうです。
明治29年、江戸期建築の最後の名匠と言われた坂田留吉の作品。 -
手水場のそばに、浄行菩薩さま
菩薩さまを洗うことで、罪や穢れをあがなってもらえるようです@ -
帝釈堂から本堂へ向かう渡り廊下からの眺め
靴を脱いであがりました。 -
ここからは彫刻ギャラリー
PowerShot SX 200 IXの12倍ズームに頼らなくても、目線の位置なのでじっくり眺めることができました@ -
下から撮ると、威厳が出ます@
これって1本の幹から彫られているんですよね?
母は、人物だけは別に作ってあとからはめ込んだんじゃないか、なんて言ってましたが。 -
獅子と見事な浮彫群
-
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の1枚目「塔供養の図」の一部
※胴羽目=壁の下部の羽目板。山車なら彫刻が入れられている胴の部分
「塔供養の図
今、日月灯明佛の眉間から光が放たれると、東方一萬八千の佛國土が照らし出されます。それらの佛國土では、さかんに塔供養が行われているのが見えます。このような光景が見られることは「法華経」が演説される前ぶれです。
金子 光清 作」
(展示説明より)
おやっ、左下の人は、髪の毛をすいてあげているんでしょうか。 -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の2枚目「三車火宅の図」の一部
「三車火宅の図
三車とは、羊・鹿・牛がひく三種の車のことで、火宅とは、も得る家のことです。われわれ凡夫は、火宅の中で遊びたわむれる子供と同じで何のおそれも感じません。父親は、子供たちを救出するために三つの車を用意したのです。
木嶋 江運 作」
(展示説明より)
羊・鹿・牛が引く車を中心に。 -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の3枚目「慈雨等潤の図」
「慈雨等潤の図
佛の慈悲深い教えは、あまねく地上を潤す慈雨と同じです。今、雷神と風神が現れて、雨をふらし、大地には、緑があふれ、さまざまな花々が咲きほこります。天人たちも地上の楽園に舞いおりて来ました。
石川 信光 作」
(展示説明より)
花車や植物がすばらしいです。
人物に比してちょっと巨大すぎますけどね。 -
帝釈堂の外壁
見事に三次元な浮彫がぎっしり@ -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の4枚目「法師修行の図」の一部
「法師修行の図
インドでは、法師たちは森の中や洞窟の中で独り静かに修行しています。しかし、虎や狼の危険があり、心淋しく、修行はきびしいものです。その修行者たちを励ますために、佛が立ち現れたり、象に乗った普賢ぼさつが姿を現わすのです。
横谷 光一 作」
(展示説明より)
象が雲に乗っています。
地上世界ではありえない光景@ -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の5枚目「多宝塔出現の図」の一部
「多宝塔出現の図
「法華経」を信仰するところでは、多宝塔(多宝如来の塔)が、地面から涌き出してきて人々の信仰をほめたたえます。人々は歓喜にふるえ、一心にその塔を礼拝します。人々の顔には、法悦のほほえみが浮かんでいます。
石川 銀次朗 作」
(展示説明より)
多宝塔の中にもちっちゃな佛様が@ -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の6枚目「千載給仕の図」
「千載給仕の図
阿私仙という仙人が、「法華経」という尊い教えを持っていました。この仙人について私は千年の間、給仕のまことを捧げ、水を汲み、薪を拾い、果の実を採り、あるときには仙人の腰掛けになりました。法華経を知りたいための修行でした。
加府藤 正− 作」
(展示説明より)
水を汲んだり、薪を拾ったり、果の実を採ってるらしい仙人の姿はすぐに分かりましたが、腰掛けになってあげてるところはどこじゃろ? -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の6枚目「千載給仕の図」の一部
薪を運んでるところを中心に。
なんとなぁく気に入ったので@ -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の7枚目「竜女成佛の図」
「竜女成佛の図
「法華経」では、女性が成佛できることを説示します。今、龍王の娘で、八才になる智慧にすぐれ弁舌さわやかなこの娘は、多くの教えを理解し、不動の境地に達しました。波の上にあって龍女が宝珠を佛に捧げています。
山本 一芳 作」
(展示説明より)
龍王の娘はどこかな。 -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の7枚目「竜女成佛の図」の一部
宝珠を捧げている龍王の娘。 -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の8枚目「病即消滅の図」
「病即消滅の図
「法華経」は、全世界の人びとの病いの良薬です。もしある人が病いにかかり、この「法華経」を聞く幸運に恵まれたら、たちどころに病いはなおり、不老不死の境地を得ることができるのです。
今関 光次 作」
(展示説明より)
おおーっ、巨大なパイナップル!
と思ったけれど、ソテツですよね。 -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の8枚目「病即消滅の図」の一部
病いの人を看病しているところを中心に。 -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の9枚目「常不軽菩薩受難の図/法華経功徳の図」
「常不軽菩薩受難の図/法華経功徳の図
常不軽ぼさつは、「常に人を軽べつしない」という修行をしていましたが、却って迫害を受けました。又、「法華経」は、寒さに火を得たように、子のところに母親が来たように、渡りに舟を得たように、闇に灯りを得たように救いの道を示すのです。
小林 直光 作」
(展示説明より)
枠の上の天女も一緒に写しました。 -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の9枚目「常不軽菩薩受難の図/法華経功徳の図」の一部
渡りに舟@ -
帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻の10枚目「法師守護の図」の一部
「法師守護の図
「法華経」を受持(ジュジ)・読(ドク)・誦(ジュ)・解説(ゲセツ)・書写(ショシャ)することを、法師の五種の修行と言います。まず経をたもつことを誓い、読み、あるいは誦して、解き明かし、経文を書写して法華経をひろめます。修行する法師を天人も阿修羅も協力して守護するのです。
加藤 寅之助 作」
(展示説明より)
屋根の上の人々は天人で、左の鬼のような人々は阿修羅ですね。 -
すばらしい彫刻が施された帝釈堂外壁
柴又帝釈天の公式サイトの境内案内によると、柴又帝釈堂の背後は「喜見城」とあります。 -
縁の下の龍
-
縁の下の龍と腰羽目彫刻
-
本堂へ続く渡り廊下
今度はお庭に行くのです。
渡り廊下の屋根の下にもすてきな浮彫が施されていました。
一つ一つ熱心に見ていたら、一時間くらいかかってしまいそうです。 -
本堂の裏のお庭に続く渡り廊下から
-
庭を見渡せる大客殿
ここで冷たいお茶をいただきながら、ちょいと一休み。
といいつつ、私はせっせと撮影していましたけどネ。 -
庭園(邃渓園)
ううーん。
つつじが満開のときか、紅葉の季節だと、もっと見ごたえあったでしょうね。 -
大客殿に飾られていた……折り畳まれた屏風?
棟方志功の絵のような素朴でユニークな顔つきの絵に惹かれて。 -
大客殿に飾られていた、横山大観による彫刻下絵
下絵として描かれたものが、そのまま屏風になっていました。 -
庭園の緑
-
大客殿の大広間
-
渡り廊下をぐるっと回って池のある景色
-
庭園の五重の塔の裏側から
さきほどまったりとひと休みした大客殿がチラッと写っています。 -
母は庭園が気に入ったけれど……。
私はむしろ、渡り廊下のこういう景色の方が気に入りました@ -
庭園の隅に……。
-
庭園の一角
-
渡り廊下が続くよ@
-
本殿から・その1
右手にあるのが帝釈堂、真ん中の奥が大鐘楼、その左手が二天門。 -
本殿から・その2
-
二天門と大鐘楼
このあと、参道沿いの店で昼食をとり、柴又駅から金町まで一駅戻り、そこからバスで水元公園に向かいました。
「母に誘われて柴又と水元公園(3)水元公園の花菖蒲散策と、帰りに寄ったしばられ地蔵」へつづく。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (4)
-
- 茂右衛門さん 2010/11/19 12:36:30
- 白い札
- 千社札といいまして参拝した証として貼るものでとても迷惑千万な代物です。
- まみさん からの返信 2010/11/19 12:45:48
- RE: 白い札
- はじめましてー。
> 千社札といいまして参拝した証として貼るものでとても迷惑千万な代物です。
そうだったんですか。知らなかったです。
あんなに高いところに簡単に貼れないから、一応許可をとっているのでしょうか。勝手に貼っちゃうのかな。
ほんとは迷惑なものだったんですね。
木が傷むからかな。汚れるからかな。
教えてくださってありがとうございます。
-
- コクリコさん 2009/06/10 14:51:21
- とうとう行かれましたか!
- まみさん、こんにちは〜
とうとう帝釈天に足を踏み入れましたか(^^)/
私もまだ2回しか行ったことないです。
この前行ったのが既に10年前という。。。
その時にじっくり帝釈堂の浮き彫り見ましたが、私も度肝を抜かれました。
だって、たいしたことないだろうと思っていたんですもの。
まみさんが夢中になって写真撮る気持ちわかります!
お母様は庭園がお気に入りだったとか。
私はまみさん同様本堂の渡り廊下、それにお座敷が気に入っています。
私が帝釈天で育った子供だったら、渡り廊下をダダーっと走り、広い座敷も駆け回りかくれんぼ、、、遠い昔お寺でそんなことしたような思い出があるのでこんな建物見ると凄く懐かしいのです。
10年前に行った時は千葉から行ったので、野菊の墓とか、矢切の渡しを渡って柴又入りしました。
なんか長閑で良いよね〜あそこらへん。
まみさんの旅行記見ていたら私も親孝行を兼ねて久しぶりに母と行ってみようかなと思いました。
お団子食べて、短い参道を歩いてお参り、矢切の渡も渡ったら世の母親というものは絶対喜ぶわよね。
- まみさん からの返信 2009/06/10 19:47:28
- RE: とうとう行かれましたか!
- コクリコさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
コクリコさんにとって「とうとう」なのですねー。
実は私は母に誘われるまで、「柴又」知らなかったです、わはは。
矢切の渡しの話は母もしていました。
なんでも20年前?に出かけたときは、雪の日だったとか。
帝釈堂の渡り廊下は、小学生くらいのときの教室のぞうきんがけを思い出させました。
全然つやがなくて、ワックスがかかっていないんじ。
歩いたら靴下が汚くなりそう。。。って思ってしまいましたが、ちゃんと掃除されてたようで。
そんなへんななつかしさがありました@
私が子供の頃はこんな立派な渡り廊下には縁がなかったですが、コクリコさんの思い出はなんとなーぁく目に浮かぶようです。
彫刻はすばらしかったです@
ほんとは全体をなるべく入れるようにした写真も撮っているのですが、それをアップすると多すぎるし、「個性!?」がないから、部分の写真を中心にアップしました。
コクリコさんもぜひ行ってみてください。
コクリコさん視点の写真みたいです@
柴又の参道で、団子、食べましたよー。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
まみさんの関連旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?







































































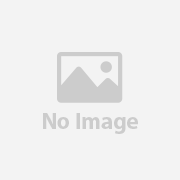
4
50