
2022/10/19 - 2022/10/20
1485位(同エリア1956件中)
gianiさん
- gianiさんTOP
- 旅行記241冊
- クチコミ53件
- Q&A回答0件
- 814,028アクセス
- フォロワー16人
この旅行記スケジュールを元に
うどん、うどん、栗林公園、うどん、県立博物館、うどん。
有名店を梯子しつつ、名園と博物館を網羅した一日でした。
さすがに一日では屋島まで足を延ばせませんでした、、、
個人的には、香川が仏教大国である背景が学べました。
一筆書きの旅行地図(位置情報)も、ぜひ参考にしてください。
- 旅行の満足度
- 5.0
-
空港バスを途中下車して、まずは有名店で腹ごしらえ。
写真の左奥は、公道側に壁のない立食専用スペース松下製麺所 グルメ・レストラン
-
開店早々に入店したので、空いていました。
麺はゆでた玉を、注文後に湯を通すスタイル。
つゆとネギや天かすは、自分で入れるセミセルフ店。 -
寺町巡り後に入店。
開店前に、既に何人も並んでいました。
半熟卵のてんぷらが有名。
麺に腰があり、価格も良心的。竹清 本店 グルメ・レストラン
-
高松藩の下屋敷跡です。
長江流域を模した大名庭園が魅力。絶対に押さえておくべきスポットです。
松も枝ぶりが見事栗林公園 公園・植物園
-
回遊式庭園には、赤壁も。
三国志でお馴染みの古戦場です。 -
桶樋滝
西湖に注ぎます。
滝の上に桶があり、家臣が汲んだ水を流します。
現在は電動ポンプです。 -
紅葉前に行って正解です。
-
静かな湖面
-
松の木越しに見る南湖
-
中島も
-
回遊式庭園は、観る角度で変化を楽しめます。
-
奥が深いです。
-
紫雲山を借景しています。
-
風が凪ぐと、湖面に山が反射します。
-
ここだけ江戸時代です。
-
一段後ろの通路より。
-
さらに後ろの飛来峰頂上からの眺め
庭園のハイライトとして設計されました。 -
飛来峰は杭州の名山です。
-
根上り五葉松
-
見事な幹のねじれと枝ぶり
-
高松を治めた松平家は、水戸光圀の長男の家系です。
-
檜御殿のあった場所に、商工奨励館が建てられました。
現在は伝統工芸の実演および製品の展示スペースです。 -
讃岐うどんについても展示が。
小麦、塩、醤油、出汁(カタクチイワシを原料とするいりこ出汁)の4つの生産要素が揃って初めて実現した食文化です。 -
園内には鴨場が築かれ、鴨猟も行われました。
鴨の習性を利用した、おとり猟です。
アヒルを餌付けして、板木を叩いた後に餌を与えることを繰り返します。
アヒルは、板木の音=餌の合図と認識するようになります。 -
大覗(おおのぞき)
鳥たちの警戒心を刺激しないよう、板木を叩いて餌を与える作業は、大覗と呼ばれる小屋から行いました。
目線の位置に、細い覗き窓があります。胸の高さにある2本の筒は湖面まで伸びており、ここから餌を投入します。 -
鴨引き堀
池の先には細長い水路(鴨引き堀)が続き、行き止まりには小覗があります。
今度は小覗から板木を叩いてアヒルを誘導し、餌を投入します。
鴨はアヒルの後をついて行く習性があり、鴨引き堀へ誘導されます。
鴨引き堀の両側は土手になっており、堀の左右は鳥の死角になります。 -
土手に潜んでいた搦め手が一斉に網を出し、驚いて飛び始めた鴨を捕獲します。
これは明治以降の方法で、江戸時代までは鷹匠が放った鷹が鴨を捕獲しました。 -
小覗から鴨引き堀を覗くと、こんな感じ。
-
公園を出て、移動。
カレーうどんを出す変わり種の店。
麺、つゆ共に芸術的です。でも価格は高めです。たも屋 女道場 グルメ・レストラン
-
城跡の南側にある博物館。
企画展は撮影禁止ですが、常設の香川県の歴史部分はOKです。香川県立ミュージアム 美術館・博物館
-
須恵器(5世紀)
縄文弥生式土器の延長線である土師器(はじき)の古墳時代に、福岡大阪香川では百済伝来の須恵器が焼かれていた。
前者との違いは2つ。紐状の粘土を巻き上げて成形するスタイルから、轆轤(ろくろ)を使用したこと。焼成が、野焼きから登りに変わったこと。共通点は、素焼きである(釉を使用しない)こと。
成形した粘土に藁や薪を被せて焼く野焼きは、焼成温度は800℃と低温かつ有酸素焼成なので、相対的に割れやすい。登り窯での焼成温度は1000℃を超し、外気が遮断されるため粘土中の酸化物が還元され、相対的に割れにくい。 -
縄文弥生土師器は酸化物の影響で褐色なのに対し、須恵器は写真のように若干青味を帯びている。
-
律令国家
7世紀末に律令国家「日本」が誕生した。五畿七道のうち、讃岐国は(伊予.土佐.阿波.淡路.紀伊と共に)南海道に分類され、11の郡で構成された。現在の高松市は、香川郡の一部だった。特産物を納める「調」では、白米・塩・須恵器・絹製品等が含まれた。
※小豆郡は江戸時代まで備前国に属した。 -
律令では(南海)道>国>郡>郷>戸という行政区分だった。戸は世帯のことで、各世帯には戸籍が作成され、6年ごとに更新された。50戸集まって郷を形成した。戸籍上の6歳以上の男女には、日本国から耕作地を貸与され、死亡すると返還する仕組みだった(班田収授)。貸与=納税の義務がセットなので、かなりハードです。
条里制
南海道を基準線にして、109m四方の碁盤の目状の地割(町)が為された。
東西の区画線を里、南北の区画線を条と呼んだ。1町は36等分された(坪)。例えば、讃岐国香川郡七条四里一坪といった感じで、国家は土地の住所を特定できた。 -
仏教
6世紀末に伝来した仏教は、大陸の科学や文化と密接に結びついており、いち早く天皇家に受け入れられた。白鳳期(7世紀)以降には権威と文化のシンボルとして、讃岐国でも南海道沿いに寺院が建立された。四国は古代寺院の数が圧倒的に多く、仏教先進地帯=先進文化だった。
国家による仏教庇護は奈良時代にはピークに達し、天平13年(741年)に聖武天皇は国分寺建立の詔を出した。 -
入唐僧
空海(写真)と円珍は共に讃岐国出身の遣唐使で、修行と併せて多くの経典を持ち帰った。空海は804年に唐に渡り、帰国後真言宗を開く。円珍は854年に唐に渡り、帰国後延暦寺(天台宗)座主となる。 -
荘園
律令を貫く公地公民制度(土地と人民は国家のもの)と並行して、荘園開発もなされます。仏教の庇護により、仏教伝来時の飛鳥三大寺の法隆寺・弘福寺や奈良時代の東大寺などの寺社の土地並びに耕作人の私有が認められます。讃岐国には、多くの荘園が存在しました。 -
武士団の台頭と支配
(讃岐)国は中央政府が任命した国司によって治められるが、文化があるのは都だけ、畿内を出れば其処は人間界でないと認識していた人々は、任官後も都に留まり(遥任)、代理(目代)を派遣して、実務は地元の有力者任せた。国の治安は悪化し、地元の有力者は自衛のために武装し、防備を固めた。武家政権が鎌倉で設立されると、公領と荘園は武家の支配下にシフトする。
足利尊氏の挙兵に協力した細川氏は、室町幕府で管領を歴任し、讃岐国を始めとする8か国の守護を務めた。宇田津に守護所を置き、貿易で国は発展した。港は軍港を兼ね、代官が統治した。 -
中世の仏教
鎌倉時代前期に讃岐に流された法然は、浄土宗の開祖として念仏を唱える重要性を説いた。鎌倉時代後期には、秋山氏に招聘された日仙が日蓮宗を布教している。 -
応仁の乱後には細川氏の勢力が弱体化し、群雄割拠の戦国時代に突入した。東は十河氏、西は香川氏に整理されるが、四国を統一した長曾我部元親、豊臣政権を経て、江戸幕府では生駒氏が統治する。
-
三藩体制
生駒家は御家騒動で改易させられ、東讃岐は水戸徳川家出身の松平頼重(光圀の実兄)が高松藩(赤)、西讃岐は京極高和の丸亀藩(黄)が誕生。高和の次男が分家して多度津藩(碧)が誕生。三藩体制が確立されて明治維新に至る。 -
現在の香川県の島嶼部は、要所のために幕府直轄地だった。讃岐平野の水源である溜池も御料地として、幕府領とした。法然寺や金毘羅といった寺社は、幕府から領地(朱印地)を与えられた。
江戸時代には海運が発達し、塩飽(しわく)諸島・直島・小豆島の船乗りは卓越した航海術を武器に幕府の廻船を運行し、全国を股に掛けた。
高松藩の引田・三本松は、砂糖積出港として発達した。 -
海の神としての金毘羅信仰は、塩飽の水夫らによって全国に広められた。朝廷により日本一社の勅願所として認められ、幕府の祈願所にもなり、全国から参拝者が訪れた。四国八十八霊場も整備され、多度津・丸亀は参拝・巡礼者の受け入れ港として繁栄し、「へんろ道」も整備された。
-
黒船来航を経て、幕府は開国の井伊直弼と尊王攘夷の徳川斉昭(水戸藩主)に2分される。高松藩第9代藩主松平頼恕は斉昭の実兄、10代藩主頼胤の嫡子の正室は直弼の次女という複雑な関係だった。
桜田門外の変の起きた1860年、幕府は日米修好通商条約書の交換のために、使節をアメリカへ遣わす。日本人による太平洋横断に初めて成功した咸臨丸の乗組水夫50人の内、35名が塩飽の水夫だった。1862年の幕府による初の留学生16名の内、2名は塩飽出身の海軍留学生だった。 -
戊辰戦争では、高松藩は幕府軍、丸亀・多度津藩は新政府軍に味方する。明治6年に香川県が誕生するが、徳島や愛媛に編入された期間が長く、最終的に香川県として独立したのは明治28年で、最後の置県だった。面積は埋立の進む大阪府に抜かれて、最下位になった。
-
近代産業
近世の特産品だった讃岐三白(綿・砂糖・塩)は、開国後の価格競争にさらされた綿と砂糖は衰退。代わりに養蚕・麦わら編みが台頭した。製塩は、政府の専売法も後押しして大いに発展した。 -
交通
四国2番目の鉄道として、讃岐鉄道が琴平(金毘羅)~丸亀(港)~多度津(港)間を明治22年に開通。全国からの金毘羅参拝者を運ぶことが目的だった。明治30年には高松まで延長し、日露戦争対策で国鉄に買収される。残りの3社も社名に琴平の文字が含まれ、参拝者輸送のために建設された。
明治30年に開通した四国新道は、多度津・丸亀を起点に各県を結ぶ道路。 -
香川県は降水量が少ない上に大きな河川が無く、古来から溜池への依存度が大きかった。
県南部の讃岐山脈を貫通して、吉野川から水を引いた香川用水が完成したのは昭和49年。県内の水道水の約半分を賄っている。 -
高松駅に隣接したうどん屋さん。
早朝から営業し、ライダーが多いです。味庄 グルメ・レストラン
-
おまけ
今回の讃岐うどん店評価。
再訪したいのは、たも屋女道場。カレーつゆは魅力。麺の腰も文句なし。
そして堂々の第一位は、竹清(写真)の一杯。麺の腰、つゆ、価格、全てが突き抜けています。毎日通いたいです。
次(新居浜)の旅行記↓
https://4travel.jp/travelogue/11772502
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったスポット
高松(香川) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?



























































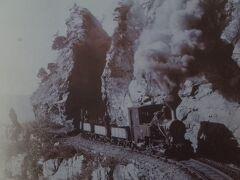
















0
50