
2022/03/25 - 2022/03/25
15位(同エリア850件中)
![]()
横浜臨海公園さん
- 横浜臨海公園さんTOP
- 旅行記156冊
- クチコミ812件
- Q&A回答125件
- 1,857,832アクセス
- フォロワー785人
該驛は、昭和7年(1932年)1月1日開業である。
但し、該駅開業当初は阪和電気鐵道に依り現位置より阪和天王寺(現 天王寺)方で国道24号線を挟んだ102m地点に設置され駅名も中之島(なかのしま)驛と命名されたが、大阪市内中心部に中之島が存在し紛らわしい事から、早くも同月15日附を以って阪和中之島(はんわ なかのしま)驛に名称変更された。
その後、鐵道省和歌山線交差地点に昭和10年(1935年)1月1日附で
紀伊中ノ島(きいなかのしま)驛が開設され阪和電気鐵道も駅位置を現位置に移転したが駅本屋は別個に設置されたが、利用者側から見れば不便極まりない事から、該駅は翌昭和11年(1936年)6月10日附で共同使用形態となり、更に阪和電気鐵道は駅名を鐵道省に合せ紀伊中ノ島驛に再変更した。
阪和電気鐵道は該駅移転に鑑み、鐵道省から新駅建設用に古軌条相当数の払下を受け建設したが、該古軌条に我が国製鐡黎明期に於ける軌条相当数が現存する。
当時の和歌山市に於ける中心駅は現在の紀和駅付近であり、此の為に阪和電気鐵道は該駅全列車停車を実施し対応した。
阪和電気鐵道は沿線人口希薄に依る旅客収入僅少が原因で経営困難となり、昭和15年(1940年)12月1日附で南海鐵道(現 南海電気鉄道)に吸収合併を余儀無くさせられ南海鐵道山手線として存続したが、南海鐵道側は高圧的態度に終始し、旧阪和電気鐵道保有の動産多数を持去り該社山手線は満身創痍状態だった。
南海鐵道山手線は政府決定に拠り唱和19年(1944年)5月1日附で戦時買収され阪和(はんわ)線となったが、政府買収時に目ぼしい動産は殆ど南海鐵道に持去られ存在せず、当時の大阪鐵道局は運輸逓信省鐵道総局に対し現実的窮状を報告せざるを得ない状態だった。
和歌山機関区は元々 和歌山Ⅰ(現 紀和)駅構内に存在したが敷地狭隘で拡張の余地が存在無き為に、天王寺鉄道管理局は和歌山線田井ノ瀬-紀伊中ノ島間に移転を決定し、東和歌山(現 和歌山Ⅱ)駅連絡の為に、昭和36年(1961年)7月1日附で田井ノ瀬-東和歌山(現 和歌山Ⅱ)間4.6Km新線を設置し、当初は回送列車、及び、貨物列車に限定し運転を開始したが、和歌山市中心地が徐々に山側に転移するに従い、和歌山線和歌山市駅発着列車は東和歌山(現 和歌山Ⅱ)駅発着へと変化を見せ、特に昭和43年(1968年)2月1日附で和歌山Ⅰ駅は紀和(きわ)駅に名称変更され、3月1日附で東和歌山駅は和歌山Ⅱ駅に名称変更された。
昭和47年(1972年)開催の和歌山国体に合せ3月15日附時刻改正時より和歌山線全列車が和歌山Ⅱ駅発着となり、田井ノ瀬-紀伊中ノ島-和歌山市間は支線化し凋落が著しい事から昭和49年(1974年)10月1日附で廃止され、紀和-和歌山市間は和歌山線所属から紀勢本線所属に変更された。
該駅乗降客は激減した事から昭和60年(1985年)3月14日附を以って無心化され、下り線連絡構内踏切を廃止し新に下り線連絡通路階段を設置した為に該駅構内構造が複雑化させた。
我が国は、明治13年(1880年)に陸海軍省、及び、工部省に依り、製鐡国産化に依る軍用鋼板製造を目論み、製鐡所創設稟議書が議会に提出された。
明治20年代中期ともなると内乱勃発の可能性は殆ど消滅し、殖産事業を中心とした重化学工業国産化への暗中模索の時代となる。
我が国に於ける近代製鐡事業は岩手縣釜石に於いて開始されたが、該地は岩手山地存在の為に内陸部間と交通断絶地故に、輸送路は海路しか手段が無いに均しく、此の為に全国各地を検討した結果、福岡縣遠賀郡八幡村(現 北九州市八幡東区)新製鐵所設置が決定し、第5代第Ⅱ次 伊藤博文(いとう ひろふみ)(天保12年(1841年)10月16日~明治42年(1909年)10月26日)内閣(明治25年(1890年)8月8日~明治29年(1896年)9月18日組閣)は、明治29年(1896年)3月30日附で製鐡所官制を公布施行し、該法に拠り、第10代農商務大臣 榎本武揚(えのもと たけあき)(天保7年(1836年)10月5日~明治41年(1908年)10月26日)(明治27年(1894年)1月22日~明治29年(1896年)9月18日在任)の管理下に、独逸グーテホフヌンクスヒュッテ(GUTEHOFFNUNGSHUTTE)社依頼に依り該地に於いて独逸人技術者派遣指導に依り近代式製鐡所が建設開始し、明治33年(1900年)に東田第1高炉が完成し翌明治34年(1901年)2月5日には点火稼働開始したが、当時の溶鉱炉から産出された粗鋼鐡は製造黎明期故に試作的要素が強く、且つ材質自体が不安定だった事から高品位製品とは程遠い状態であり、同年軌条完成後に直ちに東海道本線に敷設試用されたが、敷設後48時間後測定数値では約2.5mm弱の強摩耗が検出され、即ち、明治期最初期に敷設された英國製錬鐡双頭軌条と同質程度とされ、欧米製造品とは比較対象すらなり得ぬ低級品質と判定された。
それ故、該軌条群は、敷設数年後には本線から側線用、更に現地より撤去され貯留品として保管された後、ホーム上屋支柱転活用例等々が複数見られた。
東海道本線保土ヶ谷駅旧旅客ホーム上屋支柱は、該年度製造軌条に依り建築構成され大東亜戦争後も残存したが、東海道線、横須賀線電車分離運転工事支障の為に、惜しくも昭和54年(1979年)に撤去解体されたが、現存していれば産業遺産登録指定最有力候補対象となったものと思われる。
該高炉製造品が欧米製造品と遜色無き安定高品質製品と判定されるのは昭和初期以降の事で、第1次世界大戦勃発に依り欧米から重化学工業製品輸入が途絶し、その結果、他力本願を自身実力とならない事態となり、急激に実力をつける事となり進化したのであり、それまでは軌条類は当時の我が国にとって貴重な外貨を用い輸入せざるを得ない時代が続いた。
官営八幡製鐡所は、日露戦争終結と共に、生産された鋼材を、機械製造業界、造船業界等々部門に対し供給し、更に、鐵道部門に対し軌条供給を決定した。
明治44年(1911年)第27回帝國議会に於いて、鋼材生産力を33万瓲増産が決定し、軌条製造予算計12389929円が認められた。
他方、同時期に民間に於いて製鐡事業が創設された。
1)住友財閥
明治34年(1901年)住友鋳鋼所設立
明治40年(1907年)鐵道用品専門工場に発展(現 住友金属)。
2)鈴木商店
明治38年(1905年)小林製鋼所買収 神戸製鋼所成立 海軍、鐵道、鉱山用品製造。
3)三井財閥
英國アームストロング・ホワイトワーズ社、及び、メトロポリタン・ヴィッカース社との技術提携に依り、明治44年(1911年)日本製鋼所室蘭製鋼所操業開始。
4)浅野財閥
日本鋼管設立、大正3年(1914年)川崎工場操業開始。
欧州に於いて勃発した戦争は第1次世界大戦として欧米を巻き込む事態となり、我が国は未曽有の好景気を迎えたが、他方、該戦争に依り欧米からの鋼材輸入途絶に依り、該戦争継続に必要たる鋼材輸出の為に、鋼材生産量は、開戦前の大正2年(1913年)対開戦後大正7年(1918年)では鋼鉄生産量240000瓲→580000瓲、鋼材鉱石250000瓲→540000瓲と飛躍的増加に依る技術向上を見せる。
産業考古学会 2009年度推薦産業遺産
表紙写真は、
鐵道作業局発注品 本邦初製造 官営八幡製鐡所 1901年(明治34年)製造軌条使用 上屋支柱。
- 旅行の満足度
- 4.0
- 観光
- 4.0
- ホテル
- 4.0
- グルメ
- 4.0
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 3万円 - 5万円
- 交通手段
- 新幹線 JR特急 JRローカル 徒歩
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
紀伊中ノ島(きなかのしま)駅
駅本屋
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0621932紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
駅本屋
昭和9年(1934年)建築。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
駅本屋紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
駅本屋
幾何学的直線建築
テラコッタ装飾紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
駅本屋
内部玄関部
幾何学状装飾紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
駅本屋
内部玄関部紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
出札口跡、及び、手小荷取扱窓口跡
正面出札口跡 右手手小荷物取扱所跡
該駅は、昭和60年(1985年)3月14日附を以って無人化。
因みに、県庁所在地中心駅隣接駅4駅が全駅無人は、全国でも和歌山駅と大分駅2例である。
但し、大分駅は日豊本線西大分駅はJR貨物有人駅たるを以って、完全無人は和歌山駅だけである。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旧手小荷物一時預取扱所跡
手荷物: 当該区間有効乗車券所持旅客が、指定小型荷物は発送受領時に当該有効乗車券提示に拠り送達した。
該当乗車券券面裏に「手」と印字された〇印を押印。
昭和61年(1986年)11月1日限で廃止。
小荷物: 上記以外の者が託送に依り小型荷物送達を依頼するもの。
布団、衣類、リンゴ木箱等々が対象。
民間宅急便普及に反比例して利用者が漸次減少し、昭和61年(1986年)11月1日限で原則一般取扱小荷物制度は廃止されたが、全国紙本社刷地方発送、放送局に依るビデオテープ送達は現在も残存。
テレビ地上波時代に、12時放送基準の笑っていいともが岩手県青森県では17時から方法されていたのは新幹線ビデオテープ送達の為だった。
一時預り:有料コインロッカー普及前に有人駅各駅に存在した。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
駅前
野良猫1匹通らぬ超閑散とした駅前に旅館が2軒存在。 -
紀伊中ノ島駅
ビジネス旅館 石田屋
https://www.ishidaya-ryokan.com/ -
紀伊中ノ島駅
改札口
簡易型自動改札機では無く通常型自動改札機が設置。
無人駅たるを以って交通系電子カードに依る不正突破下車が後を絶たず、抜本的対策として不正通過防止効果発揮の為に無人駅にも拘らず通常型自動改札機に更改した。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
阪和線連絡階段
開設当初、連絡階段は上り線側のみ設置されたが、昭和60年(1985年)3月14日附無人化を前に、構内踏切を廃止し下り線連絡階段を新設置した。
下り線側連絡通路が歪な階段レイアウトは後付の為。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
阪和線下り旅客ホーム連絡階段
昭和60年(1985年)3月無人化に伴い構内踏切廃止に代り設置された。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
阪和線上り旅客ホーム連絡階段紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
下り線連絡階段
元来、下り線側は構内踏切使用に依り客扱を行使していたが、昭和60年(1985年)3月14日附無人化の為に安全面を考慮して設置。
旧和歌山線旅客ホームを旅客通路として活用し、素人考えでも阪和線ガードを超えた地点に階段を設置したほうが安上がりでもあったと考えるが、何故か不思議な構造である。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
下り線連絡通路
昭和60年(1985年)3月14日附無人化の為に安全面を考慮して設置。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
下り線旅客連絡通路階段
昭和60年(1985年)3月14日附で該駅無人化に伴い設置。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
上り線連絡通路
該駅有人駅時代は手前右側柵部に構内踏切が存在。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旧下り線旅客ホーム連絡踏切跡
該踏切は、昭和60年(1985年)3月14日附で該駅無人化時に廃止撤去跡。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
下り線旅客ホーム連絡踏切跡紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第1番ホーム紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第1番ホーム紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客ホーム
全景紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客ホーム
全景紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
第1番旅客ホーム紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第1番ホーム紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第1番ホーム
上屋古軌条支柱
No60B 1901
(官営八幡製鐡所 1901年(明治34年)製造 鐵道作業局発注品)紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第1番ホーム
上屋古軌条支柱
No60A 1901
(官営八幡製鐡所 1901年(明治34年)製造 鐵道作業局発注品)紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第1番ホーム
上屋古軌条支柱
No60A 1906
(官営八幡製鐡所 1906年(明治39年)製造 鐵道作業局発注品)紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第2番ホーム
上屋古軌条支柱群紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旅客第2番ホーム
上屋古軌条支柱群紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旧和歌山線旅客ホーム跡
昭和49年(1974年)9月30日まで、該旅客ホームに和歌山線列車発着が存在した。
特に、昭和43年(1968年)10月1日附時刻改正時まで急行大和号東京-湊町間に併結され東京-和歌山市間にB寝台車1両が運転されていた。
急行第203列車→普通第519列車
東京22時45分発→王寺8時50分発→紀伊中ノ島11時16分着→和歌山市11時27分着
普通第528列車→急行第204列車
和歌山市17時52分発→紀伊中ノ島18時00分発→王寺20時50分発→東京6時40分着
現在では当時の盛況は想像すら困難な衰退状態。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旧和歌山線旅客ホーム跡
王寺方
前方上部は阪和線跨線橋。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
王寺駅方面
線路跡紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
旧紀伊中ノ島駅構内跡
旧列車交換施設が存在したが現在は全線路が撤去され、跡地は西日本旅客鉄道社員社宅。紀伊中ノ島駅 駅
-
紀伊中ノ島駅
和歌山市方面
該線廃止前に於ける隣接駅たる和歌山Ⅰ駅には、和歌山機関区、和歌山車掌区が存在した。
然し、和歌山Ⅰ(現 紀和)駅構内用地が狭隘な事から気動車のみ和歌山市新在家に機関区派出所を設置し移動させた為に、昭和36年(1961年)7月1日附で東和歌山(現 和歌山Ⅱ)駅間に連絡線が設置された事で旅客は漸次新連絡線経由となり、特に、昭和46年(1971年)秋開催の第26回黒潮国体開催に依り、和歌山市全体が近代化時機会に、鉄道の中心は従来の和歌山Ⅰ(現 紀和)から東和歌山(現 和歌山Ⅱ)に移転した。紀伊中ノ島駅 駅
-
六十谷-紀伊中ノ島間
初代阪和電気鐡道中ノ島駅跡 -
六十谷-紀伊中ノ島間
阪和電気鐵道初代紀伊中ノ島驛跡
該駅開業当時は別々に駅舎が存在したが、旅客乗換に不便で不動産を合算させた方が有利との判断から、昭和11年(1936年)6月10日附を以て、鐵道省和歌山線側驛本屋に一本化され、同年9月25日に旧阪和電気鐵道驛舎は解体撤去された。 -
和歌山(わかやま)駅Ⅱ
該駅は、大正13年(1924年)2月28日開業である。
即ち、紀勢西線(現 紀勢本線)和歌山Ⅰ(現 紀和)-簑島間開業に伴い開設された。
但し、該駅開業時は 東和歌山(ひがしわかやま)驛と称した。
昭和5年(1930年)6月16日に阪和電気鐵道(現 阪和線)開通に依り連絡駅となったが、該社駅は現近鉄百貨店所在地に設置され、鐵道省線間とは出改札口は別個に設置されたが、同形態は、石巻線仙石線石巻駅Ⅰ、東北本線仙石線仙台駅Ⅰ、東海道本線飯田線豊橋駅、香椎線勝田線宇美駅等々、全国各地に存在したが、現存するのは鶴見線南武線浜川崎駅だけである。
和歌山市新在家に機関区派出所を設置し気動車のみ移動させた為に、昭和36年(1961年)7月1日附で東和歌山(現 和歌山Ⅱ)駅間に連絡線が設置されたが、
https://www.jr-odekake.net/eki/top?id=0622091和歌山駅 駅
-
和歌山駅Ⅱ
旧阪和電気鐵道阪和東和歌山驛跡
国有化後に阪和線となったが、阪和線乗換時は一旦改札を出なければならなかった。
昭和20年(1945年)7月9日未明の和歌山大空襲で全焼し、戦後もそのままの状態が継続したが、昭和46年(1971年)秋開催の第26回黒潮国体開催時に阪和線列車が本駅に乗入可能構造に改造し、該跡地は近鉄不動産に払下られ近鉄百貨店和歌山店が開業。和歌山駅 駅
-
和歌山駅Ⅱ
旧阪和線用列車専用ホーム跡和歌山駅 駅
-
和歌山駅
和歌山県内
旅客鉄道線は全線電化済
和歌山県内日本国有鉄道線は阪和線を除き全線非電化線だった。和歌山駅 駅
-
和歌山市(わかやまし)駅
該駅は、明治36年(1903年)3月21日開業である。
https://www.jr-odekake.net/eki/timetable?id=0622099和歌山市駅 駅
-
和歌山市駅
紀勢本線旅客ホーム
東京-名古屋-湊町(現 JR難波)間に運転されていた 急行大和号に、昭和37年(1962年)3月10日時刻改正時に、東京-王寺-和歌山市間2等寝台車1両が連結運転となり、和歌山県民長年の悲願だった和歌山県庁所在地 対 東京間直通運転が開始された。
当該寝台車は急行大和号に連結され、王寺-和歌山市間は下り普通列車525列車、上り第534列車に併結された。
運転開始初日の和歌山市駅ホームでは、出征兵士を送るがの如くホームから溢れんばかりの大勢の市民が見守る内、盛大に出発式が行われ、万歳三唱の下、東京に向かって出発して行った。
王寺-和歌山市間は普通列車に併結されたが連日満席の状態だった。
該列車は該駅到着後、紀勢線方面への乗降客も多かったとされる。
東海道新幹線開通後の利用率低下に依り、昭和43年(1968年)9月30日限りで急行大和号は王寺以西区間が廃止された余波を受け該列車も廃止され、その後、東京-和歌山間定期直通列車は実現していない。
更に、和歌山市駅旅客鉄道発着ホームは閑散として、嘗て東京行列車が運転されていた面影は皆無で正に夢の叉夢の世界である。
因みに、急行大和号は東京-湊町(現 JR難波)間車掌・列車給仕は全区間天王寺車掌区が担当していた。
https://www.jr-odekake.net/eki/timetable?id=0622099和歌山市駅 駅
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (4)
-
- yuriさん 2023/03/08 20:10:36
- 紀伊中ノ島駅
- 横浜臨海公園さん
こんばんは。
紀伊中ノ島駅周辺は
昭和の時間がそのまま止まっているかのようで、味わいがありますね。
そして、営業している旅館が2軒も存在するのですね。
近くで工事などのお仕事に就く方用、などでしょうか。
蔦が絡まった旅館の外観など、想像力を掻き立てられる紀伊中ノ島駅でした。
- 横浜臨海公園さん からの返信 2023/03/09 11:44:08
- 拝復
- yuriさま、こんにちは。
拙稿に投票と掲示板にコメントを賜りまして、誠に有難うございました。
仰せの様に、紀伊中ノ島駅は昭和50年代がそのままストップした状態です。
旅行記に掲載しませんでしたが、トイレなど便所の表現そのままで、一時代前の阪和線名物汲取り式トイレが該駅では現役でした。
件の駅前旅館は、高校の対抗試合時宿泊利用が多いそうです。
宿泊者など限られた世界だと言えるかもしれません。
横浜臨海公園
-
- レッドウイングさん 2023/03/07 07:30:30
- 阪和線懐かしいです。
- 横浜臨海公園さん
こんにちは。
いつもありがとうございます。
阪和線の紀伊中ノ島~和歌山市駅の旅行記ですが、懐かしながら拝見しておりました。
住んでいたこともあり、通学や大阪方面へ行く際に和歌山駅から利用してましたが、和歌山も変わってないなと感じました。
紀伊中ノ島は、無人駅で降りこともなく通過してましたね。
駅前の風景も阪和線車内から見てました。
レッドウイング
- 横浜臨海公園さん からの返信 2023/03/07 08:37:06
- 拝復
- レッドウイングさま、おはようございます。
拙稿に投票と掲示板にコメントを賜りまして、誠に有難うございました。
紀伊中ノ島駅は令和の世の中にあって昭和のまま時間が止まった雰囲気が濃厚でした。
小生、駅周辺を散策しながら、遂に駅利用者に出会いませんでした。
駅前旅館2軒が頑張っている様子でしたが、嘗ての紀伊中ノ島駅の繁栄の残滓を見ている様な感じがしてなりません。
横浜臨海公園
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったホテル
この旅行で行ったグルメ・レストラン
和歌山市(和歌山) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?




















































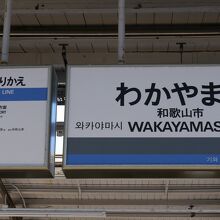












4
44