
2012/11/23 - 2012/11/24
451位(同エリア2375件中)
![]()
kubochanさん
- kubochanさんTOP
- 旅行記469冊
- クチコミ416件
- Q&A回答4件
- 328,041アクセス
- フォロワー28人
宮島で宿泊してホテルを出発。
島内を散策しながらロープウェー駅まで行き、ロープウェーを乗り継ぎ獅子岩駅へ
獅子岩駅から起伏の激しい山道を歩くこと30分から1時間。日ごろあまり歩かない私にとっては苦しい時間でした。
しかし弥山から瀬戸内海の眺望は素晴らしいものでした。
再び紅葉の山路を下り、途中大鳥居を木々の間から見ながら大聖院そして厳島神社へ。
- 旅行の満足度
- 4.5
- 観光
- 4.5
- 一人あたり費用
- 3万円 - 5万円
- 交通手段
- 新幹線
PR
-
宮島口
連絡船乗り場 -
厳島神社説明文
-
ライトアップされた宮島のシンボルの大鳥居
本社火焼前(ひたさき)より88間の海面にそびえる朱塗りの大鳥居は、奈良の大仏とほぼ同じ高さの16m、重量は約60t。主柱は樹齢500〜600年のクスノキの自然木で作られており、8代目にあたる現在の鳥居を建立するにあたっては、巨木探しに20年近い歳月を要したといいます。また根元は海底に埋められているわけではなく、松材の杭を打って地盤を強化し、箱型の島木の中に石を詰めて加重するなど、先人の知恵と工夫によって鳥居の重みだけで立っています。 -
ライトアップされた宮島のシンボルの鳥居
-
世界一の大柄子
長さ7.7m、最大幅2.7m、重さ2.5トンの樹齢270年のケヤキから作られた「世界一の大杓子」 -
町家通り
江戸時代初期に埋め立てられ、宮島が最も華やいだ時代のメインストリートとなったのが当時本町筋と呼ばれた町家通り。 -
金鳥居の辻
-
五重塔
千畳閣の隣に建つ五重塔は、和様と唐様を巧みに調和させた建築様式で、桧皮葺の屋根と朱塗りの柱や垂木のコントラストが美しい塔です。高さは27.6m。応永14年(1407年)に建立されたものと伝えられています。またこの五重塔が建つ塔の岡は、厳島合戦で陶軍が陣を構えたと伝えられています -
-
紅葉谷公園
弥山麓の谷あい、紅葉谷川に沿って広がる公園。江戸時代に開拓されモミジの苗木が植えられたのが始まりといわれ、この時代の文献には「清き流れあり、樹木蒼古にて一区の幽境なり、楓樹多きを以って名とす」と紹介されています。厳島八景の一つ「谷原麋鹿」は、紅葉谷東の「谷ヶ原」を指します。昭和20年(1945年)の枕崎台風で一帯は土石流に飲み込まれましたが、その後昭和23年(1948年)から2年間、8000万円の巨費を投じて災害復旧工事が行われ、今日に見られる砂防庭園が完成しました。 作庭は地元広島の庭園師が手がけ、石材は現地にあるものを傷つけず自然の形のまま使用。樹木は切らない、コンクリートの面は眼にふれないよう野面石で包むなど、安全性はもちろん自然環境に配慮した美しい庭園です。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉と季節ごとに変わりゆく自然を満喫できるのが魅力。とりわけ約200本のモミジが一斉に色づく秋の彩りは圧巻です -
-
-
ロープウェイー「紅葉谷駅」
昭和34年(1959年)、誰でも弥山登山が楽しめるよう建設されたロープウェイーです。瀬戸内海の絶景や原始林の眺めを楽しみながら空中散歩。紅葉谷駅から榧谷(かやたに)駅までは少人数乗りゴンドラの循環式で所要時間約10分。中間駅の榧谷駅から展望台のある獅子岩駅までは大きなゴンドラの交走式で所要時間は約5分。獅子岩駅から山頂へは歩いて約30分の道のりです。榧谷駅は宮島の景観を壊さないようにゴンドラや鉄塔等の施設が海上から見えない工夫がなされています
-
-
-
弥山本堂
唐から帰国した弘法大師が霊地を探し求めて宮島に立ち寄った際、御堂を建て100日間の求聞持秘法を修されたところと伝えられます。平清盛、足利義尚、福島正則など戦国武将の崇敬を集めた古社で、本尊は虚空蔵菩薩。脇に不動明王と毘沙門天を祀ります -
霊火堂
弘法大師空海が100日間に及ぶ求聞持(ぐもんじ)の秘法を修し弥山を開基された際、使われた火が「消えずの霊火」として1200年間守り継がれています。ここにかかる大茶釜の霊水は、万病に効くとして有名。明治34年(1901年)に操業を始めた八幡製鉄所の溶鉱炉の種火や広島平和公園の「平和の灯火」のもと火にもなっています -
くぐり岩
弥山山頂へあともう少しのところにある巨大な岩のトンネルで、通称「くぐり岩」といわれます。近年の地震により、天井部がだんだんと低くなってきたとか。山頂付近にはこうした巨岩が重なり合い、神秘の景観を描き出しています。 -
獅子岩展望台
紅葉谷から弥山の北側の谷筋を登るロープウエイーの終着点。山頂までは徒歩で30分程度ですが、山頂まで登る時間や体力のない方は駅のすぐ傍にあるこの獅子岩展望台へ。花崗岩の風化作用で生まれた巨大な岩の上から、弥山山頂に劣らないみごとな眺望が楽しめます。付近一帯は野猿が生息しており、タイミングが合えば猿の群れを見ることができます。鹿は見ましたが・・・。 -
ロープウェーの獅子岩駅から徒歩で弥山まで徒歩。
革靴で登ってきましたが大変でした。杖でもあれば・・・・ -
弥山
島の主峰・弥山は標高535m。 天然記念物に指定されている「瀰山原始林」は、針葉樹林に南方系の植物が混在する森で、ヤマグルマなどの原始的な植物を自然の状態で見ることができる貴重な場所です。標高400m以上の所では、ツガやモミなどの針葉樹とアカガシやウラジロガシなどの常緑広葉樹が混じった混合林が見られます。中腹から麓にかけては、アカマツを主体にシリブカガシ・タイミンタチバナ・ミミズバイなど常緑広葉樹が多い森になっています。そんな多様な植物相をもつ自然の森の美しさ、巨岩奇石が点在する変化に富んだ景観、そして眼下に広がる瀬戸内海の多島美が訪れる人を魅了します。
「宮島の真価は弥山の頂上からの眺めにあり」と名言を残したのは伊藤博文。標高535mの山頂からは息を呑むほど美しい感動のパノラマが広がります。また、1200年前弘法大師空海がこの霊峰弥山を開基したと伝えられ、ゆかりの寺やお堂、不思議な伝説が数多く残っています。 -
帰りは徒歩で大聖院コース:山頂→白糸の滝→大聖院
古くから参詣道として整備され、弥山道とも呼ばれます。コース沿いには滝宮神社や白糸の滝があり、町(丁)石や石仏も多くみられます。 -
あるか遠方に大鳥居が見え、多くの人が鳥居周辺に見ることができました。
-
白糸の滝
-
瀧宮神社
-
瀧不動
-
紅葉の間から大聖院が見えます。
-
-
大聖院
正式な呼び名は多喜山水精寺大聖院。霊峰・弥山の麓にある真言宗御室派の大本山で、明治の神仏分離令までは十二坊の末寺を有し、嚴島神社の別当職として祭祀を司ってきた宮島の総本坊です。寺伝によれば、大同元年(806年)に弘法大師空海が三鬼大権現を勧請し弥山を開基して以来1200年の歴史をもち、弥山山頂の霊火堂や三鬼堂、求聞持堂などの管理にも携わってきました。本堂は鳥羽天皇の勅願道場として創建されたことから、鳥羽天皇の第五皇子である覚性法親王が門跡を務めた京都・仁和寺や歴代皇室との結びつき深く、安土桃山時代には後奈良天皇の御子で仁和寺第二十世任助法親王が法流相伝のために逗留、明治天皇の厳島行幸の際には行在所となっています。今日嚴島神社の年中行事として行われている八月の玉取祭や大晦日の鎮火祭は、任助法親王が京より伝え天正年間に大聖院から始まったもの。また天下統一を果たした豊臣秀吉がここで盛大な歌会を催し、祈不動堂を再建して念持仏の波切不動明王を奉納したことでも知られます -
-
からす天狗
-
-
-
林家住宅(上郷(しょうけい)屋敷)
-
柵守屋敷跡
-
厳島神社
嚴島神社は海を敷地とした大胆で独創的な配置構成、平安時代の寝殿造りの粋を極めた建築美で知られる日本屈指の名社です。廻廊で結ばれた朱塗りの社殿は、潮が満ちてくるとあたかも海に浮かんでいるよう。背後の弥山の緑や瀬戸の海の青とのコントラストはまるで竜宮城を思わせる美しさです。 -
-
-
本殿
繊細かつ華麗な切妻両流造りで、正面には緑青塗りの引き違いの菱形の格子戸がはめられた本殿には、市杵島姫(いちきしまひめ)・湍津姫(たぎつひめ)・田心姫(たごりひめ)の宗像三女神が祭られています。屋根に神社の定番とも言える千木と鰹木を持たず、桧皮葺の屋根に瓦を積んだ化粧棟のスタイルを取り入れた寝殿造りならではの様式が特徴です。現在の本殿は元亀2年(1571年)、毛利元就によって改築されたものです。 -
反橋
かつては重要な祭事の際、勅使がこの橋を渡って本社内に入ったことから別名・勅使橋(ちょくしばし)とも呼ばれました。現在の橋は、弘治3年(1557年)に毛利元就・隆元父子によって再建されたもので、擬宝珠の一つに刻銘が残っています。 -
高舞台
本社祓殿前にある、黒漆塗りの基壇に朱塗りの高欄をめぐらし前後に階段をつけた舞台で、平清盛が大阪・四天王寺から移したという舞楽がここで演じられます。舞楽の舞台としては最小のもの。現在の舞台は天文15年(1546年)、棚守房顕によって作られたもので、当初は組立て式だったものが江戸時代初期に現在のような作り付け構造になったと考えられています。 -
能舞台
国内でも唯一の海に浮かぶ能舞台。現在、重要文化財に指定されている国内5つの能舞台のうちの1つでもあります。厳島での演能は、永禄11年(1568年)の観世太夫の来演がその始まりとされ、慶長10年(1605年)には福島正則が常設の能舞台を寄進。現在の舞台と橋掛及び楽屋が建立されたのは藩主が浅野氏に代わった延宝8年(1680年)のことです。この能舞台は海上にあるため通常は能舞台の床下に置かれる共鳴用の甕(かめ)がなく、足拍子の響きをよくするため舞台の床が一枚の板のようになっているのが特徴。春の桃花祭神能がこの舞台で演じられるほか、茶道表千家と裏千家家元が隔年交互に執り行う献茶祭ではここでお茶が点てられ御神前に献じられます。 -
廻廊
廻廊は幅4m、長さは約275m。床板の間に目透しという隙間があり、高潮の時に下から押しあがってくる海水の圧力を弱め、海水や雨水を海へ流す役目を果たしています。 -
大願寺
-
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったホテル
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?






















































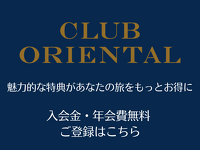







0
45