
2012/10/05 - 2012/10/09
1416位(同エリア2171件中)
![]()
さくらいろさん
- さくらいろさんTOP
- 旅行記272冊
- クチコミ186件
- Q&A回答0件
- 661,083アクセス
- フォロワー67人
道後温泉で贅沢なフレンチを堪能し、賑やかにカラオケで楽しんだ翌日は
高知へ向かいます。
桂浜を散策、高知城を巡り、高知市内へと入りました。
土佐の高知は日本酒の消費量が多いので有名な酒飲み天国!
特に女性が強いようです。
豪快な皿鉢料理の料亭ではお座敷遊びにも興じた私達でした。
- 同行者
- 友人
- 一人あたり費用
- 10万円 - 15万円
- 交通手段
- 観光バス JALグループ
- 旅行の手配内容
- 個別手配
- 利用旅行会社
- 近畿日本ツーリスト
-
「ふなや」さんの朝食です。
とても美味しい朝ごはんでした。
「ふなや」さんは部屋、料理、おもてなし
それぞれに良い印象でした。 -
この日からは貸切の観光バスでまわりました。
18人で1台のバス(大型)にガイドさんも
つきますから、座席はゆったり、好きな場所にも
行けます。
特に女性陣はバス後方のサロンに集まって
話に花を咲かせながらの移動です。
最初に宿の近くの石手寺に行きました。
四国八十八箇所霊場第51番札所です。 -
門には旅の安全を祈念しての大きなわらじが
ありました。 -
こんな可愛いわらじも奉納されていました。
-
石手寺は聖武天皇の728年に創建され、現存の本堂、
仁王門、鐘楼堂などは鎌倉末期の再建とのこと。 -
寺のHPに「子宝石子授け着帯安産 七転八起元気石・・」と
あるように、願いを石に込め、かなったらお礼参りをする
という慣わしがあるようです。
たくさんの石が置いてあります。 -
寺の住職さんが八十八箇所を巡り、そこの砂を袋に入れて
並べてあります。
順番に手で撫でると巡ったのと同じご利益があるという
ので、試してみました。 -
石手寺からは桂浜へと向かいます。
バスの中では女性達のおやつタイム。
前日に大街道近くの「霧の森菓子工房」で
買っておいた「霧の森大福」をいただきました。
テレビで紹介されてから大人気のお菓子らしいです。 -
行列のできる店らしく、生大福は売り切れだったのですが
10個入りの冷凍品はありました。
それを購入して宿の冷蔵庫で保管し、ちょうど食べ頃と
なりました。
抹茶入りのお餅生地の中に、こしあんと生クリームが
入っていて、さらに抹茶がまぶしてあります。
やわらかくて甘すぎず、美味しかったです。 -
桂浜に着きました。
「土佐闘犬センター」の2階で昼食です。
ここは常設闘犬場で、犬の博物館もあり、闘犬試合や
横綱土壌入りも見られます。 -
桂浜での昼食です。
「鰹のたたき定食」
さすがに鰹は美味しかったです。
男性陣は1階のショッピングセンターで日本酒
「酔鯨・秋季限定品・吟麗秋あがり」の一升瓶を購入、
持ち込みをして飲んでいました。
美味しくてあっという間に飲み干したそうです。 -
ショッピングセンターでは、おみやげの買い物も
しました。
私は以前に友人とツアーでここに来たのですが、
その時のバスガイドさんのイチオシが
南国製菓の「塩けんぴ」でした。
美味しかったので、今回も買いました。
やはり好評でした。
闘犬センターではありましたが、残念ながら闘犬は
見ていません。 -
坂本龍馬像の前で記念撮影。
-
龍馬像はこんな感じです。
-
桂浜を散策しました。
天気が良いので綺麗です。
台風の時には大変ですが。 -
おだやかな海に見えますが、潮流が速いため
遊泳は禁止されています。
古くからの月の名所としても知られているそうです。 -
桂浜観光を終え、五台山・竹林寺に向かいました。
四国八十八箇所霊場第31番札所です。 -
聖武天皇が724年に創建したとのこと。
本堂、文殊菩薩などが重要文化財に指定されています。
立派な建物が並んでいました。 -
まるで京都にいるみたいと錯覚するような
雰囲気でした。 -
そこから高知市内に入り、高知城へ行きました。
-
高知城は山内一豊が築城しました。
1603年に本丸が完成。
山内氏は江戸時代ずっと土佐国を治め、明治時代には
伯爵となっています。
現在の本丸は1747年に再建されたものですが、
本丸の建物が完全に残る唯一の城として
知られているそうです。 -
「内助の功」で知られる山内一豊の妻、千代の像。
城内でも一豊よりも高い場所に作ってあります。 -
大河ドラマ「功名が辻」で仲間由紀恵さんが着た
着物。
千代さんは「千代紙」の由来となった人でもある
そうです。 -
こちらは一豊の像。
土佐では、食中毒防止のために鰹を生で食べることを
禁止し、これが「鰹のたたき」の起源とされているとか。 -
城内をボランティアガイドさんと一緒に
回りました。
きれいな庭もあります。
欄間が見事です。
この欄間のデザインは、はりまや橋近くのお菓子屋さんでも
使われています。
現代にも通じる美しさです。 -
高知の町が一望できました。
-
お城を出てからも、のんびりと歩いて
見学しました。 -
高知の中心部、はりまや橋付近にやって来ました。
これは現代のはりまや橋です。
赤いかんざし模様が見えます。 -
こちらは想像復元された「はりまや橋」です。
橋の下に人工水路が作られていて、雰囲気がいいです。
その昔は堀川を隔てて、高知の豪商、播磨屋と櫃屋が
あり、両者の往来のために作られた私設の橋。
よさこい節でも有名で、1998年に今の形に復元したそうです。
がっかり名所の第1位と言われますが、私はそうは
思いませんでした。
(札幌時計台、長崎オランダ坂も、がっかりではなかったです) -
橋の横にあるお菓子屋さん。
「かんざし」というお菓子が有名です。
食べてみました。
ホイル焼きの生地の表面に、かんざしの絵が
あり、ほんのり柚子の香りがしました。 -
高知での宿です。
「西鉄イン高知はりまや橋」
橋のすぐ横にあり、「かんざし」の店も隣です。
高知城で見た欄間のマークもよく分かります。 -
夕食は土佐・老舗料亭「得月楼」へ。
ホテルから歩いて10分くらいでした。
明治3年(1870年)創業で、宮尾登美子作
「陽暉楼」の舞台として知られています。 -
玄関です。
創業からの本館は戦災に遭い、現在地に移転したとの
ことでした。 -
皿鉢料理は土佐の郷土料理です。
直径50cm以上もある九谷焼や有田焼きの大皿に
いろいろな料理が並びます。
これは生ものと呼ぶ刺身です。
説明によると、大皿に並べておけば女性も
一緒に参加できるから、とのことでした。
私達にぴったりです。 -
鰹のたたきも豪快です。
上に生のにんにくがのっているのが、高知らしいです。 -
お寿司もあります。
-
揚げ物や果物まで並んでいるので、お酒を飲まない人でも
楽しめるようになっています。 -
焼き鯖寿司です。
福井あたりの焼き鯖寿司を食べることが多いですが、
こちらは一匹丸ごと、という感じで豪快です。 -
美しく飾られた鯛そうめん。
この鯛そうめんは最後に出されたのですが、
それ以外はずらりとテーブルに並んで
宴会がスタートします。
本当に豪華で、もちろん美味しいものばかりでした。
4,5人で行くよりも人数が多い方が目でも楽しめて
良かったです。 -
飲んだり食べたり、大いに盛り上がった頃に
仲居さんが、お座敷遊びをしましょう、と
声をかけてくれました。
まずはお盆に載せたコマを回し、止まった方向の人が
おかめ、ひょっとこ、天狗の絵(コマに描いてある)と
同じ酒器でお酒を飲む、という遊び。
その時の歌もあります。
「べろべろの神様は、正直な神様よ〜・・」
すっかり歌も覚えました。 -
もうひとつは「菊の花」(花拳)と言って、
人数分の杯を裏返しにして、そのひとつに
菊の花を隠し、順番に開けていくという遊び。
花が入っていたら「当たり」で、それまでに開いた
全部の杯に日本酒が注がれ、開けた人が1人で飲み干す
ということ。 -
ドキドキしながら、順番に開けていきます。
-
そして、当たるとこういうことになります。
お座敷遊びなんて初めてでしたが、大いに
盛り上がりました。
最初はえ〜っと敬遠していたのが嘘のように
特に女性が楽しんだのでした。
あまりに賑やかなので、仲居さんが「ノリの良さでは、
歴代3位に入るほど」と感心し、さらに賑やかさは
「女子高生並み」と言われてしまいました。 -
ついには「べろべろの神様酒器セット(?)」を
買うことになりました。
帰ってからの宴会にも使いたいとのことです。
歌も覚えたし。
本当にノリのいいメンバーです。 -
得月楼には立派なお庭もあります。
お店のパンフレットには「幕末の著名な庭師による」
庭園とありました。 -
本館大広間は昭和25年の建築で、天井は長さ10m、幅75cm、
厚さ1.8cmの魚梁瀬杉の一枚板で、登録有形文化財に
指定されているとのこと。
仲居さんが案内、説明して下さいました。 -
照明も時代を感じさせます。
-
私達が食事をした広間の掛け軸は坂本龍馬の師、河田小龍の
作で、使われている赤い絵の具はジョン万次郎がアメリカから
持ち帰ったものだそうです。
明治来の伝統と新しい感覚でのおもてなしする、とある
得月楼、歴史を感じながら美味しい料理を楽しみました。
2日目はこれで終了。
翌日は金刀比羅宮へ向かいます。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?



















































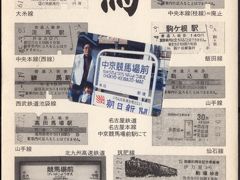











0
48