
2009/03/26 - 2009/03/26
33049位(同エリア44173件中)
![]()
Bachさん
京都の名庭園といわれる100寺院の写真集です。
「京都名庭100選」の一覧リストはコチラをご覧下さい。
→http://shokyoto-kyoto.seesaa.net/
京都の桜の魅力はなんと言っても、歴史ある建物と桜が一体になって楽しめるところで、「桜の歴史は京都の歴史とともにあり」ということを感じさせてくれます。
もともとその昔、嵯峨天皇が「神泉苑」で初めて花見をしたときの花は「梅」で、紫宸殿前庭は「左近の梅、右近の橘」でしたが、平安時代の途中から、中国から持ってきた「梅」ではなく、日本独自の「桜」にして日本文化を形成していこうということで「左近の桜」に変わって、この頃から花と言えば「梅」から「桜」になったようです。
以後は桜が宮廷の行事の主役になり、足利義満は「花の御所」と呼ばれるほど金閣寺などを桜で埋るほどにしました。その後、イベント好きの太閤秀吉が近隣諸国から桜700本を取り寄せ「醍醐の花見」をしたのが花見の頂点で、これが花好きの家康の江戸時代にも盛んになってソメイヨシノを中心に全国に広がっていったそうです。
ちなみに京都の県花は、「枝垂れ桜」となっていて豪華な「しだれ」が目立ちます。うす紅色の優しさと、流れ落ちるようなしなやかさ、風雪に折れにくいシンの強さが、京都人気質に通じるのだろうと勝手に思います。
そういうわけで今年も古の人々に想いを馳せながら桜と庭園の絶妙なコントラストを探したいと思います。
その第1弾は、ちょうど昨日のNHKテレビで紹介されていた、太閤秀吉の「醍醐の花見」です。花冷えの寒さにもかかわらず凄い人出で、早くも春の先取りという感じです。
近くの、春を呼ぶお祭り「はねず踊り」の「随心院」と、鎌倉時代から桜の名所で知られる「毘沙門堂」にも立ち寄りました。
「醍醐寺」は、太閤秀吉が3,000人を招いて「醍醐の花見」を行ったことで有名ですが、境内には700本の桜の銘木があり、霊宝館の大枝垂れ桜と、日本画家の奥村土牛が描いたことから命名された三宝院の「土牛の桜」は見応えがあります。樹齢150年以上の桜が群生しているのは珍しいそうで、質量共にさすが秀吉です。
ここのポイントはもう一つ、老齢の「土牛の桜」を引き継ぐクローン桜が咲いているということです。バイオテクノロジーのサクラが開花するのは世界初だそうで、緑化事業をやっている住友林業が全国の枝垂れ桜を救おうと頑張っているようです。
「三宝院庭園」は、秀吉が「醍醐の花見」に際して自ら基本設計し、完成までに27年間かかったという太閤好みの豪奢な回遊式庭園ですが、残念ながら入場料の高い割りに全面撮影禁止です。(外だけはOKにして欲しいですね)
→http://www.daigoji.or.jp/garan/sanboin_detail.html
鶴亀蓬莱を主題とした庭園で、中央には池、左右背後には築山が築かれ、池の3つの中島を特徴のある橋が架けられ、周囲には多くの石が配されていて、一見しただけでも豪華な気分になります。特に苔生した橋は印象的でした。
少し歩くと、「随心院」です。
「随心院」は、ここで余生を送ったという小野小町ゆかりの寺で、小町姿見の化粧の井戸、文塚などが残っています。
普通のピンクよりも濃い遅咲きの「はねず(薄紅)梅」はまだ残っていて、春を呼ぶと言われる「はねず踊り」は3月29日です。
「小野梅園」を横目に見ながら門をくぐり、小倉百人一首の
「花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」
の歌碑を見て、貴族屋敷のような建物に入ります。
書院前の庭園は、「洛巽(らくせん:都の東南)の苔寺」と呼ばれており、庭一面に青々とした「大杉苔」はこの時期でも綺麗なじゅうたんのようです。梅雨の時期が最も緑が濃く色鮮やかで、この湿気で紅葉も、シャクナゲやツツジも見事に生育するのだそうです。
庭園は池泉鑑賞式庭園で、心字池のまわりのモミジとツツジとコケの絶妙なコントラストがすばらしい。
この静寂なところで、小野小町ばりに写経をしている人もいました。
少し離れて車で近いところに「毘沙門堂」があります。
名前のとおり毘沙門天が祀られていて、鎌倉時代から桜の名所で知られたところです。
特に、寝殿前の樹齢150年の巨木「毘沙門しだれ」は見事で、江戸時代から受け継がれて今5代目だそうです。
門跡寺院の高い寺格と落ち着いた山寺の風情が魅力です。
狩野益信の襖騙絵、円山応挙の鯉の杉戸絵、「天井の龍」など見る角度により目や顔の向きが変わる所謂トリック絵が自慢で、ちゃんと説明してくれました。
庭園の「晩翆園」は、谷川の水を引いて滝を造った江戸初期の回遊式庭園で、心字池に亀石、千鳥石、坐禅石などが配され、20数種のハスや秋の紅葉が見事な名園です。
山裾にあって透明感溢れる深い色合いの翠(みどり)を思わせるところから「晩翆園」と名付けられたそうです。
PR
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「醍醐寺」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「随心院」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
-
「毘沙門堂」
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?














































































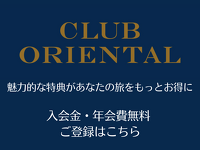








0
69