
2007/09/09 - 2007/09/09
4727位(同エリア5959件中)
![]()
ぬいぬいさん
名古屋城から東側の徳川園にかけて文化のみちと呼ばれているエリアがあります。ここは、江戸時代は武家屋敷が連なっていました。明治から大正時代になると、この地区は企業家たちの屋敷町へと変わっていきます。トヨタの創始者の発明王と言われた兄・佐吉を支えた豊田佐助の旧邸や陶磁器を輸出する貿易商として成功した春田鉄次郎の旧邸などが今も残されており、現在は高級料亭が軒を並べる歴史と文化の香りを漂わせている味わいある町並みとなっています。夏に来た時は早朝の散歩で一回りして、すっかり気に入ってしまい今回の再訪となりました。
- 同行者
- 一人旅
- 交通手段
- JRローカル 徒歩
-
カトリック主税町教会
この礼拝堂は明治37年に建てられたもので名古屋・岐阜地方に初めてカトリックの教えを広めた井上秀斎がテュルパン神父と共に造った教会です。名古屋・岐阜地方のカトリック教伝道の歴史の上で非常に重要な役割を果たしています。 -
隣にある司祭館は昭和5年(1930年)に建てられたもので、礼拝堂と一緒に町並み保存地区の伝統的建造物、都市景観重要建築物に指定されています。現在は礼拝堂の脇に幼稚園が併設されています。
-
鐘木町筋の大森家住宅 大正5年に建てられたもので都市景観重要建築物に指定されています。
-
大森家の隣にある伊藤家 こちらも大正初期に建てられたものです。
-
こちらは鐘木館 大正時代の陶磁器商だった井元為三郎が、大正末から昭和初期にかけて建てた御屋敷です。
-
鐘木館の敷地は江戸時代から続く武家屋敷だったところで、明治維新後武士の去った白壁、主税、鐘木の地に移ってきたのは豪商、旧家や新興財閥の起業家たちで、井元為三郎もその一人で、陶磁器輸出で財をなしこの家を建てたそうです。
-
玄関ポーチの天井を見上げると、青い星型の照明器具が・・・なかなかおしゃれです。
-
2階に登るとステンドグラスの欄間があります。
-
ドアには様々な形の象眼細工が埋め込まれていて絵柄のデザインも唐草模様や鳥の絵が描かれています。
-
1階のリビングの前には部屋の延長で使えるテラスがあります。
-
中庭に面したテラスの向こうには、和館の縁側が見えます。
-
入母屋の屋根の乗った和館の縁側の硝子は建てた当時の手作り硝子がはまっていて微妙なゆがみのある硝子越しの光景はふんわり柔らかなイメージを醸し出します。
-
久しぶりに蚊帳を見ました。私が子供の頃の昭和30年代の夏の季節は、この蚊帳とブタの形の蚊取り線香入れと団扇、硝子の風鈴 夏の風物詩でしたね。
-
この和館には南側の縁側と北側の廊下に面して和室が7部屋もありました。
-
ほとんどが障子で仕切られただけの続き部屋になっていて、人寄せの際には最大で28帖と23条の部屋にするとことができます。
-
子供頃和室の縁側で、夏になると足をぶらぶらさせながらスイカを食べましたよね。
-
そしてやっぱり和風建物にはこの硝子の風鈴が良く似合います。
-
この建物は日本の女優第1号として名をはせた川上貞奴と中部の電力王と呼ばれた福沢桃介が大正9年からともに暮らした家です。もともとは文化のみちの北のはずれの東二葉町建てられていたものを移築したため二葉館と呼ばれています。
-
1階の大広間には和風の絵柄のステンドグラスがはめ込まれています。
-
この家で暮らしていた川上貞奴は、16歳で芸者となり23歳でオッペケペで有名な書生演劇の川上音二郎と結婚。川上一座のアメリカ巡業で女優としてデヴューしました。その後ヨーロッパに渡り明治33年のパリ万博でマダム貞奴の名前は一躍有名になりあのピカソをも魅了させ彼女の絵を描いたそうです。
-
一緒に住んでいたのは福沢桃介。慶応義塾で学び、あの福沢諭吉の次女ふさの婿として実業界にデヴュー。
木曽川水系に多い発電所をはじめとする7箇所の発電所を建設しのちに電力王と呼ばれた富豪でした。 -
2階の各部屋には二人に愛用した調度品がおかれ当時の様子が再現されています。
-
移築される前の東二葉町の敷地は約2000坪あり、その敷地に建つ和洋折衷のこの建物は「二葉御殿」と呼ばれ、政財界人や文化人が集まるサロンになっていたそうです。
-
1階から2階に上がるラセン階段なかなかのものです。
-
丸くせり出した大広間のこのスペースいいですね。
-
赤い瓦葺の屋根が印象的なこの建物平成17年の春にここに移築復元され蘇ったそうです。
-
これは尾張徳川家の菩提寺である建中寺三門。
慶安四年(1651)創建当時の建築物で、総檜造り三間重層門の建築様式です。 -
鐘楼は、天明七年(1787)の再建で、台形の袴腰つきの建築様式、五百貫のの梵鐘がつるされていて梵鐘には林道春(羅山)の銘が刻まれていたため、戦時中の供出を免れ現在まで伝えられているそうです。
-
三門の扉の金色に輝く葵のご紋 まぶしいですね。
-
明王殿(不動堂)これは新しいもので、昭和44年(1969)の再建で、本尊の不動明王は、江戸時代から尾張徳川家戦勝祈願の秘仏として伝えられてきた大変貴重なものだそうです。
-
本堂は建中寺の根本道場で、天明7年(1787)大火の後に再建されたもので、間口15間(27m)奥行14間(25.2m)建坪210坪(700?)の巨大な木造建築で、現在名古屋市内の木造建築物としては最大のものだそうです。
-
主税町長屋門 これは江戸時代の名古屋城下に会ったもので唯一当時の位置のまま残る武家屋敷門です。
-
これは料亭かと思ったらレストランのようです。
-
豊田佐助邸 発明王として有名な豊田佐吉の弟佐助の家は大正12年に建てられた、このタイル貼りの洋館と広い間取りの和館とで構成されています。今日は休館日で中に入れませんでした。
-
春田鉄次郎邸 大正13年に建てられた春田邸は武田五一の設計と言われこの洋館遠くにある和館とで構成されています。
-
旧春田邸も現在はレストランになっています。
-
春田邸の隣にあった春田文化集合住宅
ここは昭和3年から7年にかけ12戸の住宅がコミュニティの核として共用の広場もって建てられた、武田五一の設計による新しい都市のあり方を提示した集合住宅です。
-
文化集合住宅の一角にある明治末期に建てられた陶磁器貿易業の旧大洋商工の社屋
-
この御屋敷も見事な門と塀が連なっています。
-
これは旧豊田家の門
大正7年頃に建てられたもので、豊田佐吉の娘婿の利三郎の家の門です。今は門と塀しか残っていません。 -
武家屋敷風の見事な門と塀の内側の母屋が建っていた場所には立派なマンションが建てられ、エントランスへ通じる門として利用されていました。
-
こちらは櫻井家住宅 明治38年にべ家出身の櫻井善吉氏が自ら設計した洋風の住宅です。
-
旧・料亭樟 都市景観重要建築物に指定されている大正初期の建物
-
この大正浪漫の歴史の香りの漂う屋敷町 文化のみちの名前にふさわしい、なかなかいい雰囲気の町並みでした。
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
名古屋(愛知) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?























































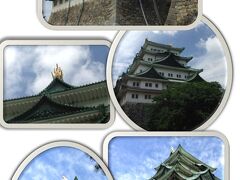









旅行記グループ 愛知旅行記
0
44