
2010/07/16 - 2010/07/16
1037位(同エリア4025件中)
![]()
みにくまさん
祇園祭に行ってきました。
祇園祭は日本3大祭の一つで、八坂神社をはじめ氏子区域一帯で、7月1日の「吉符入」から31日の「疫神社夏越祭」までの1ヶ月間、様々な神事や行事が執り行われます。
そのハイライトである「山鉾巡行(17日)」の前日は「宵山」と呼ばれており、そこかしこに飾り付けられた提灯の光が闇に沈む味わい深い町並みとあいまって、非日常的な風景を醸し出します。
PR
-
祇園祭・宵山
祇園祭に来るのは初めてなのですが、写真の四条通に来てみて、その人の多さに驚きました。
通りはすでに歩行者天国になっているのですが、道は左右に仕切られていて、左側通行をするようになっていました。 -
祇園祭・宵山
大きな道では左側通行になっているのですが、小さな路地では一方通行になっているところも。
とりあえず私は目の前にある提灯を目指して歩いているのですが、なかなか辿りつけません。
少し到着するのが遅かったようです。
本当はもう少し前の夕暮れ時の方が、空が綺麗に赤く染まっていたと思われます。 -
祇園祭・宵山
この付近で貰った団扇やパンフレットを見ながら、どういうコースで歩いたらたくさんの山鉾を見られるか考えていたのですが、結局途中でどこを歩いているか分からなくなってしまうのでした。 -
1(番号は2010年の巡行順、以下同):長刀鉾(なぎなたぼこ)
「くじとらず」の名があるように、山鉾巡行の先頭を受け持つ鉾。
命名は、鉾のてっぺんを飾った三条小鍛冶宗近作の大長刀による。宗近が娘の病気平癒を祈願して八坂神社に奉納したが、鎌倉期にある武人が愛用。しかし何かと不思議が起こり、返納したという。大永2(1522)年、疫病がはやり、神託で長刀鉾町で飾ったところ、疫病は退散した。
創建は、嘉吉元年(1441)説がある。真木は全長20メートル。現在、稚児が乗る唯一の鉾である。 -
1:長刀鉾(なぎなたぼこ)
巡行の順番は毎年くじ引きで決まるそうですが、長刀鉾は必ず1番目になっています。
特に深いことを考えず歩いていて、最初に辿り着いたのが長刀鉾でした。
屋根の上に鉾が乗っているのですが、ものすごく高い位置にあるので、見上げないと見られません。
写真に撮るには、かなり遠くからでないと全体を撮るのは難しいです。 -
1:長刀鉾(なぎなたぼこ)
-
1:長刀鉾(なぎなたぼこ)
良く見ると上にたくさんの人が乗っています。
鉾に乗るのは祭り囃子を演奏する「はやし方」だそうです。
チンチロチンチロと、軽快な音色も聞こえてきて祭の雰囲気を盛り上げています。 -
1:長刀鉾(なぎなたぼこ)
鉾の上部横には通路のようなものが設けられていて、一般の人も見学できるみたいです(有料?)。 -
1:長刀鉾(なぎなたぼこ)
-
1:長刀鉾(なぎなたぼこ)
少し後ろ(どっちが前か分からないが)から見たところ。 -
祇園祭・宵山
本当にたくさんの観光客、何人くらい集まったのでしょうか。
警官・警備員の数ももの凄いです。
彼らの力あって、我々が安心して祭を楽しめるのですから、ありがたいことですね。 -
祇園祭・宵山
通りの両端に、このような提灯が飾られており、目の前にある鉾が「函谷鉾」だということが分かりました。 -
5:函谷鉾(かんこぼこ)
中国古代史話、孟嘗君の故事に基づく。戦国時代、斉の孟嘗君は秦の昭王に招かれ、宰相に重用された。しかし讒言によって咸陽を脱出して、函谷関まで逃げたが、関の門は鶏が鳴かねば開かない。配下が鶏の鳴き声をまねたところ、あたりの鶏が和して刻をつくったので見事通り抜けたという。
真木は22メートル。鉾頭に、三角形の白麻を張り、先頭に三日月が上向きにとりつけられる。 -
5:函谷鉾(かんこぼこ)
読み方は、”かんこぼこ”か”かんこほこ”、どちらでもいいのですが、ゴロがいいので”ぼこ”と書くことにしました。
ただ”鉾”単字の場合は”ほこ”の方がいいでしょう。 -
5:函谷鉾(かんこぼこ)
◎ 夜の撮影に必須の三脚について
三脚が無いと撮影が困難なのは確か。
しかし、この混雑具合では、三脚を立てるのが非常に難しいです。
例えばこの場所、四条通のように広い道なら、何箇所か三脚設置可能場所があって、三脚持参の方の撮影ポイントになったりしていましたが、といってもそういう場所はほんの少ししかなく、そもそも三脚を持って移動するだけでも他の方の迷惑になってしまうありさまでした。
さらに鉾に近づいたところでは、ほぼ三脚仕様は不可能なほど、人が密集していたので、三脚を広げるのは無謀だと思われました。
なので私も三脚を持って行ったのですが、今回は一度も使っていません。 -
5:函谷鉾(かんこぼこ)
月桂冠は、このお祭の大きなスポンサーか。
いろんな鉾の提灯にその名が印刷されていました。 -
5:函谷鉾(かんこぼこ)
この鉾も、上層部分に乗って見学することが可能です。
そのための渡り廊下みたいなのが写真に写っていました。 -
5:函谷鉾(かんこぼこ)
-
祇園祭・宵山
凄い人ですよね。
道路はかなり広いはずなのに、人でぎっしり。
身動きができなくなるくらい混雑した場所もありました。 -
17:月鉾(つきぼこ)
『古事記』によれば、伊弉諾尊が黄泉の国から戻り、禊祓いをされたとき、左眼を洗って天照大神、右眼を洗って月読尊、このあと、鼻を洗って素戔鳴尊を生んだ。月読尊は夜を支配した神だが、水徳の神でもあり、月鉾は、この故事に由来する。
鉾頭に、横40センチ、上下24センチの金色の三日月。真木の中ほどに天王様を飾った天王台の下には籠製の船が真木を貫いてとり付けられる。元治元年の大火にもわずかに真木を失っただけだった。 -
17:月鉾(つきぼこ)
辺りはすっかり暗くなったので、そろそろスピードライトが活躍しています。 -
17:月鉾(つきぼこ)
-
17:月鉾(つきぼこ)
写真に粗さが目立ってきてしまったので、このあたりからISOを1000に固定。
短距離の被写体はスピードライトで対応できますが、遠くのものは撮影できなくなりました。 -
12:郭巨山
山には屋根がないのが普通だが、この山は日覆障子を乗せている。金地彩色法相華文の板絵として他の山にない古い形式を残している。名前の由来は、中国の史話にある貧しくて母と子を養えない郭巨が、思い余って子を山に捨てようしたとき、土の中から金の釜が現れ、母に孝養を尽くした話による。人形は、鍬を持つ郭巨と紅白の牡丹の花を持つ童子の2体。 -
12:郭巨山
あぁ〜そうか!
大型の搭乗可能なものは”鉾”、郭巨山のように小型のものは”山”という名前が付いているのか。
基本的なことも知らないので、一つ一つ勉強です。 -
祇園祭・宵山
次の四条傘鉾の手前で、笛やチンチロ鳴るやつ(名前不明)を使って演奏していました。 -
祇園祭・宵山
最近は人写に挑戦したくてウズウズしていたので、こういうチャンスはとても嬉しいです。
しかも今回は夜ということで、今までに無い難易度、うまく撮れるかな?? -
祇園祭・宵山
-
祇園祭・宵山
やっぱり難しいな・・・。
スピードライトの調整が特に難しくて、強くても弱くてもダメなんですねー。 -
祇園祭・宵山
これが一番綺麗に撮れました。 -
7:四条傘鉾(しじょうかさぼこ)
1987年、実に117年ぶりに巡行に復帰した。
元治の兵火のあとも巡行に加わっていたが、明治5年以降、消滅同然となり道具類も散逸していた。
綾傘同様、壬生六斎の棒振り、囃子での協力が復活に力となった。祇園唐草模様の大傘に錦の垂(さがり)で飾った花傘は応仁いらいの傘鉾の原形を伝える。赤熊(しゃぐま)鬼面 の棒振り、踊り手、囃し方が歩くさまは地味だが、素朴な味わいがある。 -
7:四条傘鉾(しじょうかさぼこ)
-
7:四条傘鉾(しじょうかさぼこ)
-
7:四条傘鉾(しじょうかさぼこ)
◎ 五瓜紋と三頭右巴紋
そうそう、提灯の中に木瓜紋が多くあって、何だろうな〜と思っていたのですが、良く考えたら八坂神社の神文が”五瓜紋”でした。
それに混じって三頭右巴紋も見られますが、こちらはどのような関係なのか分かりません。 -
7:四条傘鉾(しじょうかさぼこ)
-
祇園祭・宵山
四条通りは、5基の山鉾で終わりなので、一旦ここから引き返します。
長刀鉾〜函谷鉾〜月鉾〜郭巨山〜四条傘鉾 -
17:月鉾(つきぼこ)
先ほど見たのですが、また撮影するために立ち止まりました。
もう少し先を見ると、凄い人だかりができています。何かやっているんだろうかと気になるので、近くに行ってみます。 -
17:月鉾(つきぼこ)
この近くにテレビの取材が来ているようです。
凄く強力なライトで照らしているので、この周辺はとても明るくなっていました。 -
17:月鉾(つきぼこ)
明るいライトに照らされた山鉾は、とっても煌びやかです。 -
17:月鉾(つきぼこ)
どこのテレビ局かも分かりませんが、アナウンサーの方を取り囲むように群集ができていたので、なかなか近づくことができませんでした。 -
9:菊水鉾(きくすいぼこ)
謡曲「菊慈童」から着想された鉾。
魏の文帝の勅使が薬水を訪ねて山に入ったところ少年に出会う。聞けば、少年は700年前に、王の枕を誤ってまたいだのが原因で都を追われた。以後、普門品の偈を甘菊の葉に記しておいたところ露が滴り、この水を飲んで不老長生したという。慈童は、この薬水を勅使に献じた。
昭和28年に復興。
鉾頭には天に向いた16菊。
この鉾に限り「菊水」と篆書が掘り出した額がつく。 -
9:菊水鉾(きくすいぼこ)
四条通から、室町通を北上するコースを歩いています。 -
9:菊水鉾(きくすいぼこ)
★ トップ写真 ★
ちょっと狙ってみました。 -
9:菊水鉾(きくすいぼこ)
五瓜紋と三頭右巴紋はここでも共通。
もう一つ、中央に菊水紋がひとつだけありました。 -
9:菊水鉾(きくすいぼこ)
-
祇園祭・宵山
菊水鉾から山伏山に向かう前の交差点。
ここは、前後左右から人が集中してぶつかり合う地点なので、さながら満員電車のような混雑になっており、身動きもままならないくらい。 -
11:山伏山(やまぶしやま)
山に飾る御神体が山伏の姿をしているので、この名前がある。
前(さき)の祭りでは一番北の山。役行者山と同様、当時民間信仰として人気のあった修験道・山伏から着想された。
正面の水引は、雲中の竜、青海波と麒麟を精緻な刺しゅうで描いた中国からもたらされた豪華なもの。見送りも中国・明時代のものとされる。 -
11:山伏山(やまぶしやま)
町家の2階には、写真のような像(山伏?)が。 -
31:鯉山(こいやま)
前掛けや見送りは16世紀のベルギー製のタペストリーで、重要文化財に指定されている。ギリシャの叙事詩に題材をとって人物や風景が描かれており、山鉾きっての貴重なものだ。
人物でなく、魚をテーマにするのは山のなかで唯一。竜門の滝をのぼる鯉は竜になるとの言い伝えで、木製の鯉が勢い良く水しぶきを上げる様は勇壮。 -
31:鯉山(こいやま)
この上に木製の鯉がいるはずなのですが、今はまだ置かれていなかったようです。 -
31:鯉山(こいやま)
鯉山の提灯の左に”御神酒”の文字が見られます。
全ての山鉾にお酒が備えられていることから、祇園祭にとってお酒は非常に重要なアイテムなのでしょう。
ちなみに、御神酒は”おみき”と読みます。 -
28:黒主山(くろぬしやま)
油天神山が梅なら、こちらは桜を松と共に飾り、華やいだ雰囲気をかもす。
謡曲「志賀」のなかで、六歌仙の1人、大友黒主が志賀の桜を眺めるさまをテーマにしている。杖をつき、白髪の髷(まげ)の翁の人形は、いかにも品格がある。
失火で町家(ちょういえ)を失ったのを機に、5階建てビルにし、祭りのときだけ町会所にするのは時代をさきどりしたと話題になった。
山を飾る桜の造花は、家に悪事を入れないお守になる。 -
28:黒主山(くろぬしやま)
-
28:黒主山(くろぬしやま)
-
28:黒主山(くろぬしやま)
-
28:黒主山(くろぬしやま)
-
28:黒主山(くろぬしやま)
-
祇園祭・宵山
この中に2匹の金の鯉を見つけられたら、幸せになるかも?
これ何でしょう?
家の上の方から釣り下げられていました。 -
祇園祭・宵山
-
26:役行者山(えんのぎょうじゃやま)
鈴鹿山と共に山鉾町最北の山。
役行者(えんのぎょうじゃ)は自ら修行するだけでなく、庶民の中に入って医療などにつとめた僧。古くから民衆に人気があった。人形3体はその役行者をまん中に、鬼の顔の一言主神、葛城女神。三者の関係はさだかではないが、者が大峰山と葛城山のあいだに橋を架けようとして、鬼を使ったとの伝説によるらしい。
人形が多いだけ山のサイズも最大級。 -
26:役行者山(えんのぎょうじゃやま)
これだけ五瓜紋と三頭右巴紋があるってことは、三頭右巴紋も八坂神社の神文に違いない。 -
26:役行者山(えんのぎょうじゃやま)
-
29:鈴鹿山(すずかやま)
可愛らしい瞬間に出くわしてしまったので、思わず一枚いただきました(*^_^*) -
29:鈴鹿山(すずかやま)
鈴鹿山は、旧東海道の難所・鈴鹿峠をいう。畿内と東国を結ぶ要衝として、歴史上のエピソードも多い。商人を狙う盗賊が多かったことが、鬼が出る、に転化したようだ。この山の神・鈴鹿明神(瀬織津姫命)の伝説も鬼退治のおはなし。大なぎなたを手に、立て烏帽子の女神の姿がりりしい。 -
29:鈴鹿山(すずかやま)
この写真もちょっとお気に入り。 -
祇園祭・宵山
ここは烏丸通りです。
先ほどの大通り、四条通は街を東西に走る道路ですが、こちらは街の南北方向に通っています。
写真は通りの北側から南方向を見たところで、遠くに京都タワーが確認できます。
歩行者天国となった道路の左右には、延々と屋台が連なり、また観光客もそれを目当てにたくさん集まっているので、四条通と同じくらいの人で賑わっています。
こちらの通りには、鈴鹿山と孟宗山の2つしか山鉾はありません。
とりあえずは、左右の屋台を見つつ、孟宗山のところまで南下してみたいと思います。 -
祇園祭・宵山
各路地にも屋台はありましたが、道が狭かったので、買ったり足を止めたりする人は少なめでしたが、ここは各店とも大繁盛しているようです。
屋台の前にはある程度の道の広さが欲しいです。
どれくらいの広さが適当なのかは、集まる人の数によるので、これくらいって計算するのは難しいですが、人がそこそこスムーズに歩けて、しかも店の前を客の列&見物客が取り囲んでも問題ないくらいがいいようです。
今回のこの通りは、そういう意味でいったら最高の状態だったかもしれません。道の両側にある店にそれぞれ客がたくさん集まっていても、道路は問題なく歩けるくらい確保されていました。
これだと安心して店に並べるし、安心して見物できます。 -
祇園祭・宵山
◎ 肉巻きおにぎり
屋台ではもはや定番となりつつある”肉巻きおにぎり”。
それ自体は珍しくも無いが、この店のキャッチフレーズは”宮崎県で二番目においしい”のだとか。
なぜ2番目なんだろうか。。ちょっと謎ですが、客ウケは良かったようです。 -
祇園祭・宵山
◎ ふるーつあめ -
祇園祭・宵山
◎ ベーコンエッグたいやき
これは今年の新種じゃないかな?
今までに見たことがないかも。 -
祇園祭・宵山
◎ 華美棒
キラキラ光る棒のおもちゃです。
こういうものもかなり人気で、けっこう売れているようでした。
”あなたのまちについに登場!”と書いてあることから、もしかしたら新種かもしれません。 -
祇園祭・宵山
焼物だろうが、冷たいものだろうが、何でもかんでも売れに売れています。
人だかりのできていない店は滅多になく、どこの屋台主も大忙し。 -
祇園祭・宵山
特に客引きをしなくても、次々と客が列を作るので、後はどれだけスムーズに客をさばけるかと、商品の補充をできるかが、売り上げのカギになっています。 -
祇園祭・宵山
◎ ラーメンバーガー
春の段階で、この手のご当地物は多数見ているので、新種ではないですが、どんな食べ物なのかはとても気になっていました。 -
祇園祭・宵山
◎ ラーメンバーガー
焼きそばみたいなお好み焼きみたいな食べ物ですね。
おコゲになったところはカリカリの食感、内側の麺はプルプル、このコンビネーションがなんとも言えないんですわ〜。
美味しいそう〜〜(*^_^*)・・・(想像ですw) -
2:孟宗山(もうそうやま)
中国24孝の1人孟宗は、母親が病気になったため、好物のたけのこを求めて竹林を歩きまわったが、寒の季節で1本もない。疲れて座り込んでしまったとき、たけのこが出、母親は元気を回復した話からきている。
町名が笋(たかんな=たけのこの意味)町というのもこれに由来する。
白綴地に雄渾な筆致で孟宗竹林が描かれた見送りは、竹内栖鳳の筆。極彩 色が多い山鉾のなかで、墨一色が異彩を放っている。 -
2:孟宗山(もうそうやま)
屋台を見てブラブラ歩いているうちに、あっという間に孟宗山まで来ちゃいました。
やっぱ、屋台好きだわ〜(*^_^*)
見てるだけで楽しくなってくる! -
2:孟宗山(もうそうやま)
-
18:占出山(うらでやま)
烏丸通を南下して孟宗山まで行った後は、少しだけ戻って錦小路通を西に進むことにしました(というよりも、西に進んだようだ、と言った方が正しいか。この時点で自分がどこにいて次はどこに行けばいいか、全く分からなくなっています)。 -
18:占出山(うらでやま)
釣り竿を持った人形は、神功皇后の姿をかたどっている。
九州・肥前の川で、鮎を釣って戦勝を占った伝説が由来。
この山には「あいわい山」の別名が明治まで語られていたが、町衆に人気のあった山であったことをうかがわせる。色鮮やかな日本三景を描いた胴掛けが特徴。 -
18:占出山(うらでやま)
扇子や手ぬぐい、お守りなどを売る子供の売り子さん。
社会勉強でしょうか。
みんなで声をあわせて一生懸命売っていました。 -
18:占出山(うらでやま)
-
18:占出山(うらでやま)
-
6:霰天神山(あられてんじんやま)
永正年間、京都が大火にあった際、急に霰が降り、たちまち猛火は鎮火したが、霰とともに小さな天神像が降りてきた。そんな由来から、火よけの神様として祀られたのがおこり。
霊験はあらたかで、多くの山鉾が焼けた天明、元治の大火にもこの山だけは残り、町の誇りになっている。
「雷(らい)よけ火よけのお守は、これより出す…」。宵山に子供たちが歌いながらお守授与の受け付けをする。檜皮葺きの立派な社殿が山に乗る。 -
6:霰天神山(あられてんじんやま)
-
32:南観音山(みなみかんのんやま)
俗に「北観音山の観音様は男だが、南観音山は女性なので、南では宵山の夜更けに翌日の巡行の無事を祈って“あばれ観音"の行をされる」といういい伝えがあり、「あばれ観音」の別名がある。
楊柳観音像と善財童子像を安置する。
楊柳観音は、三十三観音の筆頭とされ、姿を変えて、手に柳を持ち薬師観音と同様に衆生の苦難を救う。この山の楊柳観音は頭から袈裟をつけ趺座(ふざ)する。 -
32:南観音山(みなみかんのんやま)
-
32:南観音山(みなみかんのんやま)
-
32:南観音山(みなみかんのんやま)
-
32:南観音山(みなみかんのんやま)
-
32:南観音山(みなみかんのんやま)
-
32:南観音山(みなみかんのんやま)
”山”なのに、鉾に匹敵するくらいの大きさがあるように感じられます。
上にもたくさんの人が乗っていますが、”山”の中では珍しく搭乗可能な山鉾です。 -
32:南観音山(みなみかんのんやま)
-
祇園祭・宵山
どこの通りも凄い人!
ただでさえ人が多いところに、屋台が出ていてそこでみんなが足をわずかでも止めるもんだから、人の流れが止まりまくる。
とはいえこれも祭の醍醐味の一つ。
こういう混雑も楽しめなければ、祭に来る資格なし? -
祇園祭・宵山
★ かにつり
ついに出た!!
かにつり〜〜〜\(◎o◎)/!
これは初物でしょう、私は初めて見ました。 -
祇園祭・宵山
★ かにつり
割り箸のような棒に、えさを付けたひもを垂らしてカニを釣る。
けっこう難しいのでしょうか、すぐにエサを取られてしまっていました。
でも1人上手な子がいて、バケツにいっぱい、30匹くらい?釣っていました。 -
祇園祭・宵山
とても立派な屋敷の中が見えるようになっていて、小型の山鉾が飾ってありました。
山鉾も立派だが、この屋敷の広さにみなさん唖然としていました。
この近辺ではここだけでなく、たくさんの屋敷が一部見られるようになっていて、祭に関する様々なものが飾ってありました。 -
24:北観音山(きたかんのんやま)
応仁の乱の時代から隣町の南観音山と、1年おきの交代で山を出していたといわれる。隔年にでるというのは例がなく、この両山だけ。
もとはかき山だったが、後に曳き山になった。楊柳観音像と韋駄天立像を安置する。
鉾ではないので真木の代わりに真松を立てる。松は、毎年鳴滝から届けられ、籤で所有を決めている。史料には「左三の枝に尾長鳥あり」とあるが、いまは鳩が留まる。北観音山に、尾長鳥が留まっている。 -
24:北観音山(きたかんのんやま)
-
24:北観音山(きたかんのんやま)
-
27:八幡山(はちまんやま)
八坂さんの祭りに石清水八幡をまつるのは不思議だが、当時それだけ八幡さんが信仰されていたあかしだろう。社殿は江戸時代後期天明年間の作と伝えられる総金箔押しの華麗なもの。前面の鳥居の笠木のうえに、向かい合って八幡さんのシンボルの鳩が2羽、止まっているのが愛らしい。 -
27:八幡山(はちまんやま)
-
27:八幡山(はちまんやま)
全部で32基の山鉾がある中、17基まで回れました。
一日で全部を見ようと思ったら、計画的にルートを決めて進まないと難しいです。
ただ、通りの中には一方通行になっているところもあるし、とにかく凄い人に流されてしまったりで、なかなか思うようにいかないかもしれません。
私は初めて祇園祭の宵山を見たのですが、こんなにたくさんの人がいるとは思いませんでした。
普段は人ごみは苦手なのに、こういう祭の時の人ごみは嫌いじゃないというのはどういうことなんでしょうね。
祭の雰囲気が好きなのかも。
◎ おしまい
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (4)
-
- churros さん 2010/07/19 10:05:33
- !Hola! え!はじめて!
- みにくまさん、おはようございます。
祇園さんは初めてだったんですか、なんか不思議なような、祇園さん
の様な大きなイベントは行っておられると思ってました。
宵山だったんですね、私は巡行に行ってきました、暑くて暑くて全身
水をかぶった様でずぶ濡れ状態でした、カマラのシャッター速度とか
話題になってましたね、私も買ってスグ断念したデジイチを引っ張り
出して試してみました、旅行記を今日アップしてみますね。
流石に祇園さん、人が一杯でシャッターチャンスが少なかったのですが
批評宜しくお願いします。
churros
- みにくまさん からの返信 2010/07/19 10:32:14
- RE: !Hola! え!はじめて!
churros ひらたさん、こんにちは〜。
そうなんですよー。
祇園祭は今回初めてです。
理由は2つ。
1つは祭のような人ごみが苦手だと思っていたこと。
1つは写真撮影に際して、動くもの(人)や夜間の撮影が苦手だったこと。
食わず嫌いみたいなものですね。
行ってみたら楽しくて楽しくて(*^_^*)
撮影技術が以前より向上したのも大きいです。
山鉾巡行も見てきました〜(^O^)/
写真が、巡行だけで1200枚もあったので今整理しているところで、364枚まで減らしたのですが、この後修正作業が・・。
それにしても巡行の時は暑かったですね。
汗だくになりながらの撮影で、最後には頭フラフラでした。
では〜(^O^)/
旅行記楽しみにしています⇒私もがんばらないとw
-
- ku-waさん 2010/07/18 17:40:20
- 私も16日に行きました
- こんにちは。
私も16日に行きました。
友人が仕事疲れで、新町通りの筋だけ行ったのですが、この通りだけで5〜6基見ることができました。
でも人酔いしますね。こんなにたくさんの人出だと。
- みにくまさん からの返信 2010/07/18 19:44:51
- RE: 私も16日に行きました
ku-waさん、こんばんは〜。
16日は凄い人でしたね。
夕方に降っていた雨が、夜になってパッと止んだのが大きいかな。
新町通りだと、地図によれば6基ありますね。
私は船鉾が見られなかったのが残念です。
私も人ごみが苦手だったのですが、祭の人ごみはちょっとちがうみたいで、それほど苦じゃなくなりました。
祭り酔いしてるんですかね〜(^_^;)
では〜(^O^)/
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
みにくまさんの関連旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?




















































































































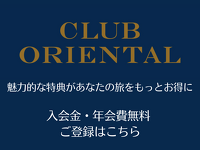









4
103