
2017/08/12 - 2017/08/12
3位(同エリア112件中)
![]()
エンリケさん
この旅行記のスケジュール
もっと見る
閉じる
この旅行記スケジュールを元に
2017年夏休みのオランダ旅行3日目。
オランダの事実上の首都デン・ハーグを後にし、オランダで最も古い街と呼ばれるマーストリヒトへ。
ベルギーから注ぎ込むマース川の両側に広がるこの街は、東西をドイツとベルギーに挟まれた、まさに“ヨーロッパの十字路”とも言える街。
豪華絢爛な装飾が施されたカトリック教会や趣向を凝らした料理など、オランダでありながらどこか他の国にいるような感覚で観光を楽しめた一日となりました。
<旅程表>
2017年
8月10日(木) 成田→台北→
8月11日(金) →アムステルダム→デン・ハーグ
→デルフト→デン・ハーグ
〇8月12日(土) デン・ハーグ→アイントホーフェン
→マーストリヒト
8月13日(日) マーストリヒト→リエージュ→ナミュール
→ディナン→ナミュール→リエージュ
→マーストリヒト
8月14日(月) マーストリヒト→アーヘン→アムステルダム
8月15日(火) アムステルダム→ザーンセ・スカンス
→アムステルダム
8月16日(水) アムステルダム→
8月17日(木) →台北→成田
- 旅行の満足度
- 5.0
- 観光
- 5.0
- ホテル
- 3.0
- グルメ
- 5.0
- 交通
- 5.0
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 15万円 - 20万円
- 交通手段
- 鉄道 高速・路線バス 徒歩
- 航空会社
- チャイナエアライン
- 旅行の手配内容
- 個別手配
-
8月12日(土)
旅行3日目は、オランダの事実上の首都デン・ハーグから、東西をドイツとベルギーに挟まれたオランダ南部の街マーストリヒトへ。
5時50分、鍵を部屋に置いたままホテルをチェックアウトして、デン・ハーグ中央駅に向かいます。 -
この日は早朝からあいにくの雨模様。
そんな中でも、前日訪れたオランダの政治・行政の中心、ビネンホフを別れ際にパチリ。ビネンホフ 城・宮殿
-
ビネンホフの隣にあるプレイン広場から、近代的な高層ビルが林立するデン・ハーグ中央駅方向をパチリ。
オープンテラスの飲食店に囲まれ、前日は深夜まで騒々しかったこの広場も、この時間帯はその騒ぎが嘘であったかのように静まり返っています。 -
6時05分、デン・ハーグ中央駅に到着。
券売機でマーストリヒトまでの乗車券を購入し(25.8ユーロ+紙代1ユーロ+カード使用手数料0.5ユーロ=27.3ユーロ、約3,630円)、駅のホームへ。デンハーグ中央駅 駅
-
デン・ハーグからマーストリヒトまでは直通の電車はなく、まずは途中のアイントホーフェンまで。
ただ、掲示板には“Ends at Tilburg”(ティルブルフ終点)の文字が。
事前に調べた情報では、ティルブルフとアイントホーフェンの間が工事中で、ティフブルフから先は代行バスに乗り換えとのこと。
代行バスとは国内・国外を含め初めての経験ですが、とりあえず電車に乗ってみることにします。 -
6時17分、アイントホーフェン改めティルブルフ行きのインターシティは定刻通り出発。
首都発の電車ですが、この時間帯、車両はこんなふうにガラガラです。 -
車窓からはこんなのどかな風景を眺めつつ・・・。
-
7時20分、終点のティルブルフに到着。
ここで誘導員の案内に従い、駅の外に出て、代行バスに乗り換えです。 -
7時26分、アイントホーフェン駅行きの代行バスはティルブルフ駅を出発。
接続が上手くいって、とりあえずひと安心・・・かな。 -
そしてバスは8時、アイントホーフェン駅に到着。
アイントホーフェンと言えば、世界的な電機メーカー、フィリップス社の本社があることや、エールディヴィジ(サッカーのオランダ1部リーグ)の強豪、PSVアイントホーフェンで有名ですが、観光的にはそれほどでもないようで、駅前の風景はこれと言った特徴もなく寂しい感じです。アイントホーフェン駅 駅
-
ただ、駅の内部はそれなりに大きく、いくつかお店も入っています。
ここで朝食を買って腹ごしらえを・・・。 -
食糧を調達した後はホームに上がり、電車の出発を待ちます。
次に乗るのはこちら、8時31分発マーストリヒト行きインターシティ。
うーん、オランダは先進的なデザインの国と思っていましたが、電車だけはおもちゃみたいな感じだなあ・・・。 -
早速2階建て車両の2階に乗り込んで出発を待ちます。
車内はこんな感じでシンプル。 -
ホーム側の席に座り、先ほど売店で買ってきた朝食を。
購入したのは、トマトとチーズ(Tomaat & Kaas)のパン(3.5ユーロ=約470円)と、Johannisbeereのジュース(2.5ユーロ=約330円)。
食料品の物価は日本よりも高いですね・・・。
ちなみにこのジュース、“beere”と付いてるからビールっぽいのかなと思ったら、ドイツ語でいう“カシス”のことで、普通に甘くて美味しいものでした。 -
アイントホーフェンからはこんな農村の風景を見ながら進み・・・。
-
9時34分、この日の目的地、マーストリヒト駅に到着。
ただ、こちらも天気は雨模様で、駅前は工事中・・・。
重い荷物を持って歩くのがしんどいですが、まずは予約していた宿に向かいます。
(写真は後日撮影)マーストリヒト駅 駅
-
駅を出て、マース川に架かる橋を渡り、こんな石畳の道を歩き続け・・・。
-
1659年から1664年にかけて建てられた、石造りの立派な市庁舎のあるマルクト広場を通り・・・。
マルクト広場 (マーストリヒト) 広場・公園
-
10時、その裏手にあるこの日の宿、“ホテル・ラ・コロンブ”(Hotel La Colombe)に到着。
Booking.comで予約した1泊45ユーロ(約5,990円)、都市税別途3.5ユーロ(約470円)の2つ星の宿で、1階がレストラン&カフェになっていて、騒がしいですが、廉価で観光に便利なところが魅力。
(写真は夕方撮影)ホテル ラ コロンベ ホテル
-
まだチェックイン時間には早すぎたので、荷物だけ預かってもらって観光開始。
ちなみに夕方チェックイン後に撮影した部屋はこんな感じ。
2階の広場側で、外からの声や物音は、朝まで続く感じです。
また、壁が薄いのか、隣の部屋からの声も聞こえ、神経質な方にはお薦めできない宿かもしれません・・・。
わたしは疲れていたので、それほど苦もなく眠れてしまいましたが。 -
この部屋は今回の旅行で唯一、トイレとシャワー付き。
デン・ハーグやアムステルダムのような大都市では高くて手がでませんでしたが、トイレやシャワーはやはり自分の部屋にあった方が落ち着けていいですね。 -
まだ雨が降り続ける中、小路が入り乱れるマーストリヒトの旧市街を南下し、10時30分、“聖母教会”(Basiliek van Onze Lieve Vrouw)へ。
デン・ハーグやデルフトでは見かけなかった、11世紀に建てられたカトリックの教会です。聖母マリア教会 寺院・教会
-
この聖母教会、中世の城と見まがうような堅牢で厳めしい外観。
内部はどんなものかと、左側に付属している建物の入口から入ってみると・・・。 -
入口に向かって待ち構えるようにして立っていたのがこちらの聖母子像。
その前にはたくさんのロウソクが灯され、厳かな雰囲気を醸し出しています。 -
その右側にある通路から教会本堂へ。
こちらも薄暗く、デルフトで見たようなプロテスタントの教会に比べれば権威付けを高めるような装飾が施され、厳かな雰囲気が漂ってきます。 -
こちらの柱には長い年月を経て色褪せてしまった人物像が。
日本人的にはわびさびが効いていて趣が感じられるところです。 -
こちらのピエタ像もプロテスタントの教会では見られないものですね。
・・・そもそもマーストリヒトは、プロテスタントであるオランダのスペインからの独立戦争(1568-1648年)時には南ネーデルラント(現在のベルギー=カトリック圏)に付き、ナポレオン戦争後のオランダ王国成立(1815年)の際にオランダに編入された地域。
オランダのほかのどの地域よりもカトリック色が強い地域なのですね。 -
この聖母教会には無料で入れる本堂のほかに有料の宝物館があり(入館料3ユーロ=約400円)、そちらも見学。
木彫りの聖母子像や銀器など、数は少なめでしたが、この教会に伝わる宝物を興味深く拝見(撮影禁止により写真はありません)。
11時30分、以上で聖母教会の見学を終了。 -
聖母教会の外に出てみると、いつの間にか雨が上がって傘なしで歩ける感じに。
街を歩く人々も増えてきて、いよいよ観光地らしくなってきました。 -
11時50分、聖母教会から南へ向かっててくてく進んでいくと、こんな廃墟然としたところに突き当たります。
これは、マーストリヒト旧市街の南側を流れるイェーカー川(Jeker rivier)に沿って、13世紀から16世紀にかけて造られた城壁。 -
城壁の南側に回ると、こんなとんがり帽子を持った巨大な門が。
1229年建造の通称“地獄の門”(Helpoort)と呼ばれるオランダ最古の門で、この門の先にペスト患者の隔離所があったことから、こんな呼び名がつけられたという・・・。
2020年のコロナ禍に生きる我々にとっては、まさに他人事ではありませんね・・・。地獄門 建造物
-
地獄の門の先は、現在では“5つの頭”(De Vijf Koppen)と呼ばれる出城跡が残るこんな風景。
公園となり、緑がいっぱいの市民の憩いの場所となっています。スタツ公園 広場・公園
-
水際にはこんなカモに似た水鳥たちが。
デン・ハーグのビネンホフ付近でもそうでしたが、オランダでは都市部の自然が上手く保護されているのか、よく水鳥を見ますね。 -
さて、時計を見ると12時20分、もうお昼を回ってしまいました。
次は、こののどかな公園を後にして、マース川の対岸にある“ボンネファンテン博物館”に行ってみたいと思います。 -
12時30分、やってきたのはマース川に架かる人道橋、ホーヘ橋(de Hoge Brug)。
この橋を渡りながら北側を見ると・・・。 -
聖セルファース橋とクルーズ船、そして鉛筆のような尖塔を持つ聖マルティヌス教会(Sint Martinuskerk)の、マーストリヒトを代表する眺望が。
-
三者をズームしてパチリ。
曇っているのが多少残念ではありますが、それでも、マース川の悠々とした流れと、遥か中世からのマーストリヒトの都市としての歴史を感じられる壮大な眺めです。 -
元来た西側の岸の方を見ると、聖母教会や赤い塔を持つ聖ヤンス教会が。
-
南側を見ると、カプセルのようなかたちをした、未来風の建物・・・あれが目指すボンネファンテン博物館。
-
ホーヘ橋を渡り切り、南にあるボンネファンテン博物館への道を進んでいきます。
-
マース川の東岸は新市街になっていて、こんな、足を止めて見入ってしまうような集合住宅が。
オランダデザインかと思って調べてみると、この建物は、スイス人の建築家Aurelio Galfettiによりデザインされた“La Residence”(ラ・レジデンス)という名前の集合住宅とのこと。
さらにこのゆったり感のある広場は“Plein 1992”(1992年広場)といい、EU発足の元となった欧州連合条約(マーストリヒト条約)が1992年にこの地で締結されたことにちなんで名づけられたとのこと。
意識していなかったとはいえ、こんな歴史的名称が付けられたスポットに出会えるとは、発足当時からEUのことをずっと気にかけていただけに、何だか運命のようなものを感じますね。 -
1992年広場からマース側に沿って南下していき、13時、目指していたボンネファンテン博物館(Bonnefantenmuseum)に到着。
棟の一部はカプセルだか宇宙船のような外観をしていて、オランダらしく、非常にユニークです。ボンネファンテン博物館 博物館・美術館・ギャラリー
-
一方で、博物館の入口にはこんな、商店街を思わせるような“OPEN”と書かれたのぼりが。
狙ってるんだか、未来的な外観とのギャップが面白いですね(笑)。 -
さて、入館料12ユーロ(約円)を払ってボンネファンテン博物館に入場。
日本語では“博物館”と呼ばれていますが、実際には、近代絵画や現代美術といった美術品がメインで、博物館を思わせるような考古学的遺物やこの街の歴史などは、わずかしか展示されていません。
ということで、いつもながらの美術鑑賞スタート。
最初はアントワープの画家ビーテル・ブリューゲル(子)(Pieter Brueghel de Jonge、1564-1638年)の、“カルバリ”(キリストが十字架に架けられた丘、Calvary、1605年)。
“農民画家”と呼ばれ、農民たちの素朴な生活を描いたことで有名な同名の画家の息子の作品で、父と同じく、顔が見えない多数の人物が登場する作品となっています。
絵の真ん中あたりに十字架を運ぶイエス・キリストがいるのですが、よく目を凝らさないと分からないですよね。 -
同じくピーテル・ブリューゲル(子)の“ベツレヘムの人口調査”(Census at Bethlehem、1605-10年)。
オリジナルは父ブリューゲルが1566年に描いたもので、ブリュッセルのベルギー王立美術館に所蔵されています。
【ベルギー王立美術館 ピーテル・ブリューゲル(父) ベツレヘムの人口調査(1566年)】
https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-collectie/pieter-i-bruegel-de-volkstelling-te-bethlehem?artist=bruegel-brueghel-pieter-i-1 -
この絵画、主題は、“ベツレヘムの人口調査”とあるように、聖書の中の物語で、イエス・キリストが産まれる直前に行われた、ローマ皇帝アウグストゥスによる人口調査のことを差しますが、実際の絵を見ると、辺り一面雪景色。
これは、作者のブリューゲル(父)が住んでいた16世紀のフランドル地方にある冬の農村で、同地を支配していたスペイン・ハプスブルク家によって人口調査が行われ、人々が税金を取り立てられることになったことに対して、批判を込めて聖書の物語を重ね合わせたもの。
画面の中央下ほどには、ロバに乗った聖母マリアや、それを引く夫ヨセフ(のこぎりを肩にかついでいることから大工と分かる)の姿が見え、確かに聖書の物語をなぞっているのですが、周りには、フランドル風の家屋や、当時の農村で冬に習慣的に行われていた豚の食肉処理の様子が描かれていたりして、まさにブリューゲルが生きていたフランドルの農村の世界が展開されています。 -
続いては、オランダ・ハーレムの画家、ヘンドリック・ホルツィウス(Hendrick Goltzius、1558-1617年)の、“カリストの妊娠を発見するディアナ”(Diana discovers the Pregnancy of Callisto、1599年)。
ホルツィウスは、1590年にイタリア旅行をした際にミケランジェロの作品と出会い、強い衝撃を受けた受けたようで、この絵も、どこかミケランジェロを思わせるような作品となっています。
ちなみにこの絵のストーリーは、古代ローマの詩人オウィディウス(BC43-17/18年)の“変身物語”に出てくる神話で、“狩猟と月の女神”ディアナが、父ゼウスと関係した侍女カリストの妊娠に気付く場面。
この後カリストはアルテミスに追放され、息子アルカスを産むと、ゼウスの正妻ヘラによって熊に変えられます。
やがて成長したアルカスは森の中で熊に変えられたカリストと出会いますが、息子が自分の母に槍を向けるのを見たゼウスは2人を天に上げ、以後、2人は、おおぐま座とこぐま座となって、天を回り続けているという・・・。 -
こちらはアントワープの画家ヤン・ファン・ヘメッセン(Jan van Hemessen、1500-75年頃)の、“人間の堕落”(The Fall of Man、1550-60年)。
エヴァにそそのかされて禁断の果実を手にしようとするアダムを描いたものですが、登場人物2人が中世的なおどろおどろしい様子で描かれていますね。 -
アントワープの画家ヘラルト・セーヘルス(Gerard Seghers、1591-1651年)の、“キリストと悔い改めた罪人”(Christ and the Penitent Sinners、1610-1651年)。
キリストの右側に跪いているのはマグダラのマリア。
ルーベンスが描く聖書の世界のように、登場人物は金髪であったり肉付きがよかったりして、北欧風の風貌をしていますね。 -
アントワープの画家ケルスティアン・デ・クーニンク(Kerstiaen de Keuninck de Jonge、1587-1642年頃)の、“ベテルでのヤコブの夢”(Jacob's Dream at Bethel、1636年)。
アブラハムの孫であり、ユダヤ人の祖でもあるヤコブが、ベテル(イェルサレムの北19kmほどのところにある街)で野宿している最中に夢に出てきた“ヤコブのはしご”がこの絵の主題となっています。
遠目では分かりにくいですが、絵の奥の方に、空に向かって斜めに伸びる階段状のものが見えますね。
この夢が、“自分の子孫が偉大な民族になる”という神との約束となり、ヤコブの子らはイスラエル12部族の祖となっていきます。 -
ここからは時代が少し遡って、ルネサンスの頃のイタリア絵画。
まずこちらは、フィレンツェの画家ドメニコ・ディ・ミケリーノ(Domenico di Michelino、1417-91年)のテンペラ画、“楽園追放”(The Expulsion from Paradise、1450-75年)。
彼はルネサンス初期の画家、フラ・アンジェリコの作風を受け継いだ画家として知られています。 -
フィレンツェの画家ドメニコ・ギルランダイオ(Domenico Ghirlandaio、1449-94年)のテンペラ画、“聖母子”(Madonna and Child、製作年不明)。
レオナルド・ダ・ヴィンチと同世代の彼は、ミケランジェロが最初に師事した画家としても有名であり、イタリア・ルネサンスの歴史に欠かせない画家となっています。 -
シエナの画家サノ・ディ・ピエトロ(Sano di Pietro、1406-1481年)のテンペラ画、“聖母子とアッシジの聖フランチェスコ、シエナの聖ベルナルディーノ”(Madonna and Child with St. Francis of Assisi and St. Bernardine of Siena、1460年)。
ギリシャ正教のイコンのような画風が特徴的で、中世とルネサンスの過渡期という感じの絵ですね。 -
こちらもサノ・ディ・ピエトロの作品、“シエナの聖カタリナ”(St. Catherine of Siena、1444-45年)。
厳格な修道生活を送り、病人や貧者の救済を行ったことで有名なドメニコ会の修道女、シエナのカタリナ(1347-1380年)を描いたもので、その手には純潔の象徴であるユリの花が携えられています。 -
こちらは匿名の画家による“受胎告知”(Anonymous Annunciation、1500-20年頃)。
描かれているのは、“聖母マリアにイエス・キリストの懐胎を告げる大天使ガブリエル”という有名な主題ですが、“受胎告知”というよりは、何やら店のカウンター越しの商談という感じですね(笑)。 -
フェラーラの画家ガロファロことベンヴェヌート・ティシ(Benvenuto Tisi da Garofalo、1476-1559年)の“聖母子”(Madonna and Child、1510-1515年)。
彼と同時代のラファエロ作品に出てくる聖母マリアとよく似た風貌をしていますね。 -
ジェノヴァの画家ニコロ・コルソ(Nicolo Corso、1446-1513年)のテンペラ画、“聖母子と天使たち”(Madonna with Child and Angels、1500年)。
活動地がジェノヴァということもあってか、これまで見てきた画家にはない、独特の作風となっています。 -
ヴェネツィアの画家ロレンツォ・ヴェネツィアーノ(Lorenzo Veneziano、1356-72年)のテンペラ画、“2人の聖者及び寄進者と謙遜の聖母”(Madonna of Humility with two Saints and Donors、製作年不明)。
初期ルネサンスの遠近法が確立されていない時代だからか、聖母マリアの左右にいる人物が異様に小さく描かれてしまっていますね。 -
フィレンツェの画家とされる“シュトラウスのマドンナの画家”(Master of the Strauss Madonna、1368-1415年)による“聖母子”(Madonna and Child、1385-90年)。
こちらもルネサンス初期の作品のため、無表情であったりして、どちらかというと中世の作品に近い印象を受けますね。 -
ルーカス・クラナッハ(子)(Lucas Cranach de Jonge、1515-86年)の“キリストと姦淫の女”(Christ and The Adulteress、1549年)。
ある女が姦淫の罪を犯し、パリサイ派たちは罪を問おうと、その女をイエス・キリストの前に連れてきますが、イエスは逆に、“あなたたちの中で罪を犯したことのない者だけがこの女に石を投げなさい”と聴衆に説き、結果、誰も石を投げることができずにこの女を許したという話。
“ルターの肖像”で有名な同名のドイツの画家クラナッハの息子の作品です。 -
続いては彫刻作品。
マーストリヒトを含むマース地域(Maasgebied、Mosan Region)で発見された、1400年頃のピエタ像。
時代を考えるとなかなかリアルな作品です。 -
こちらは15世紀末頃の英国のアラバスター製の彫刻群。
マース地域のピエタ像と同じく、こちらもなかなかリアルな作品で、この時代は絵画よりも彫刻の方がものを写実的に見せる技術が上だったことをうかがわせます。 -
そんなこんなで近代ルネサンス期の絵画・彫刻部門の鑑賞を終え・・・。
-
こんなアートな空間にある階段を上り、次の部屋へ。
-
上階に待っていたのは現代絵画部門。
こんな奇妙なデザインの部屋があったり・・・。 -
こんな現代アートが展示されていたりします。
ちなみに奥に見える絵画は、ドイツのモニカ・ベア(Monika Baer、1964-)という現代画家の“ヴァンパイア”(Vampire、2007年)という作品。
暗い空間に浮かぶ人の顔が不気味な印象の作品ですね。
15時、以上をもってボンネファンテン博物館での芸術鑑賞を終了。
そこそこじっくり見て2時間の鑑賞時間。
来館者に若者や男性が多かったのが印象的でした。 -
ボンネファンテン博物館からてくてく歩いて引き返し、15時30分、マース川左岸の旧市街に戻ってきました。
写真は旧市街一大きい広場のフライトホフ広場(Vrijthof)。
左側の赤い塔を持つのがプロテスタントの聖ヤンス教会、右側の大きい方がカトリックの聖セルファース教会。
西欧を代表する2つの宗派の教会が仲良く共存する広場でもあります。フライトホフ広場 広場・公園
-
さて、まずは赤い塔を持つ聖ヤンス教会(Sint Janskerk)の方に入ってみます。
聖ヤン教会 (マーストリヒト) 寺院・教会
-
内部に入ると、飾り気のないシンプルな空間の中で、絵画の展覧会が開催されている模様。
この聖ヤンス教会、もともとは隣にあるカトリックの聖セルファース教会の洗礼堂として1200年頃に建てられたもので、1366年に激しい嵐により崩壊。
現在の建物は14世紀から15世紀にかけて造られたものがもととなっており、オランダのスペインからの独立戦争(1568-1648年)中の1632年、オランダ総督のフレデリック・ヘンドリックがマーストリヒトを制圧したことをきっかけに、プロテスタントの教会となります。
(その後、1673年のフランス王ルイ14世のオランダ戦争により、マーストリヒトはフランスの占領下に置かれるなど、1815年のオランダ王国の成立まで、プロテスタントは受難の時代を迎えます。)
【聖ヤンス教会HP】
http://www.stjanskerkmaastricht.nl/ -
次に入場料2.5ユーロ(約330円)を払い、高さ70mの塔を上っていきます。
階段を駆け上り、たどり着いた展望台からの景色は・・・やはり平坦な地平線の眺め。 -
ただ、南の方を見ると、いくらか起伏も。
全体的に平坦なオランダでも、さすがにベルギー、ドイツ国境に近いこの辺りは、起伏のある地形が拝めるようです。 -
時計を見ると16時。
塔を下り、次に向かうのは・・・。 -
聖ヤンス教会のすぐ隣にある教会、聖セルファース教会(Sint Servaas basiliek)。
ただ、観光客は聖ヤンス教会側の入口からは入れず、反対側にぐるりと回りこむ必要があります。 -
反対側に回って、こちらが聖セルファース教会の入口。
ファサードが聖人像でコテコテに装飾された、いかにもカトリックの教会という雰囲気です。
【聖セルファース教会HP】
https://www.sintservaas.nl/#聖セルファース教会 寺院・教会
-
入場料4.5ユーロ(約600円)を支払い入場。
この聖セルファース教会、4世紀のマーストリヒトの司教でこの街の守護聖人ともなった聖セルファースの墓の上に建てられた教会。
最初は木造の小さな教会でしたが、その後、増築が重ねられ、現在の建物の主要な部分は11世紀から15世紀にかけて建造されたと言われています。 -
教会の入口近くにある礼拝堂にはこんな祭壇が。
人々の原罪意識を強めるような、いかにもおどろおどろしい彫刻が飾られています。
これも隣にあるプロテスタント教会に対抗して濃い表現になっているのでしょうか・・・。 -
さて、この聖セルファース教会には宝物殿があります。
この街の守護聖人である聖セルファースにまつわる宝物などが展示されていると言いますが、覗いてみると・・・。 -
いきなり現れたのは、金ピカの聖セルファースの胸像(Borstbeeld van Sint Servaas Koper verguld、edelstenen、1580年)。
目の部分も青い宝石のようなものが使われており、リアルかつ豪勢な代物です。 -
そしてこちらは黄金の聖遺物箱(Schrijn van Sint Servaas(Noodkist)Hout、koper verguld、edelstenen、email、1160年)。
質素で機能的なプロテスタントの教会に比べ、なんと豪勢で権威主義的なことか。 -
こちらは1500年頃のアダムとエヴァの描かれたブロンズの皿。
一見、古代の未開民族がつくった呪術用の器具のようにも見えますね。 -
こちらは1451年製作の銀製のH.Thomasの聖遺物。
中に納められているのは本物の骨でしょうか・・・。 -
以上のほか、地下の古い教会の遺構や聖セルファースの墓(小さな石棺があります)も見た後、教会の本堂へ。
カトリックなだけに、先ほど見た聖ヤンス教会よりも装飾が凝っていて、華やかな印象を受けます。 -
反対側の入口もこんなふうに聖人像によるコテコテの装飾。
いやはや、プロテスタントの教会に慣れると、カトリックの教会が装飾過剰で醜悪なものに見えてきてしまいますね。
16時50分、以上で聖セルファース教会の見学を終了。 -
ここでいったんホテルにチェックインし、17時40分、観光再開。
まだまだ盛り沢山の一日は終わりません(笑)。
次に向かうのは、英ガーディアン紙が発表した“世界で最も美しい本屋”のひとつに選ばれた、“ブックハンデル・ドミニカーネン”(Boekhandel Dominicanen)。
こちらの、ゴシック様式の教会としか思えない建物の中に入ると・・・。 -
壮麗な空間の中に、スチール製の本棚や、積み上げられた本の数々が。
まさに“世界で最も美しい本屋”!ドミニカーネン 専門店
-
側廊の部分も余すところなく本屋として使われています。
-
2階に上がって身廊の部分をパチリ。
黄色を帯びた泥灰岩(マール石)が光の具合によって様々な色に変化し、ゴシック調のアーチと相まって、何とも優雅な空間。
このブックハンデル・ドミニカーネン、もともとの建物は、1294年に建てられたドミニコ会の教会。
その後、18世紀の終わりには、フランス革命の余波を受けて教会は廃止、軍事目的で利用されることになります。
マーストリヒトがオランダ王国領となった1830年以降は、教会は市の所有となり、倉庫や催事場、音楽ホール、時には屠殺場としても使用されることに。
20世紀の終わりには、オランダらしく自転車置き場として使われていたのですが、オランダ人建築家によって2006年に改装、本屋として生まれ変わり、“世界で最も美しい本屋”として、世界中からの観光客を集めるに至っています。 -
18時、この日も一日歩き通しで、そろそろお腹も空いてきました。
この辺りで夕食のお店探し。
しかしこのマーストリヒトの街、マース川沿いの旧市街はコンパクトで趣があって、日本の地方都市では廃れてしまった商店街も活気があり、いつもながらヨーロッパの街づくりには感心させられます。 -
18時30分、聖母教会近くのお店、't Kläöskeがオランダ系の料理があってよさそうだったので、入ってみることに。
店内はこんな落ち着いた空間。
【Tripadviser~'t Kläöske】
https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g188575-d745592-Reviews-T_Klaoske_Food_Drinks-Maastricht_ -
最初に注文したのは、もちろんビール(笑)。
マーストリヒトの地ビール、Brand Beer(2.4ユーロ=約320円)で、安い上にホップの香りが濃厚で最高!
一緒に付いてきたパンは、添えられているチーズがガーリック風味でこれまた美味。 -
そしてこちらがメインのMix Grill(16.5ユーロ=約2,200円)。
やや固い感じもしましたが、うまく味付けされていてこれまた美味。
ただ、案外とボリュームも多く、食べ切るのにけっこうな時間がかかってしまいました・・・。
ケチなオランダ人、外食が少なく料理は不味いと言われますが、ここマーストリヒトは美食の国ベルギーに隣接しているだけあって、料理の味もひと味違うようです。 -
最後にコーヒー(Koffie、2.3ユーロ=約310円)を注文して一息。
締めまで美味しいマーストリヒトの料理でした。
時刻は20時、ここでまた宿に戻って休憩し・・・。 -
辺りが暗くなった21時30分、マーストリヒトの夜景を見に、再び外へ繰り出します。
やってきたのは朝、駅から渡ってきた聖セルファース橋。
まだ少し明るさも残る中ですが、左の方にライトアップされている市庁舎も見えますね。聖セルファース橋 建造物
-
その聖セルファース橋から、南側の人道橋方向をパチリ。
こちらは静かで落ち着いた風景。
次はあの人道橋に行ってみることにします。 -
21時50分、南側の人道橋に到着。
ここから見える景色は・・・聖セルファース橋や両岸に灯る明かりがマース川に映えて、何とも美しいの一言・・・。 -
空はだんだんと暗くなっていき、マース川に映る光も明るさを増していきます。
-
真っ暗になったところでマース川左岸の旧市街に戻って、こちらはフライトホフ広場に面したオープンテラスの店々。
赤い光が灯り、夜遅くまでたいへんな賑わいです。フライトホフ広場 広場・公園
-
22時、こちらもまだ、周囲の店々が賑わう聖母教会。
教会自体は扉が閉められ、鍵がかけられていますが、その奥からは光が。聖母マリア教会 寺院・教会
-
その光の灯る方向を覗き込んでみると、マーストリヒトに来ていちばん最初に見た聖母子像。
教会の扉は閉められても、こうして常に明かりを灯して、人々を見守り続けているのですね。
オランダ、ドイツ、ルクセンブルク、ベルギーの真ん中にあり、カトリックとプロテスタントが共存する街、まさに“ヨーロッパの十字路”として、EU条約締結の地にふさわしい街であったと感じました。
さて、翌日はマーストリヒトの地勢を活かし、ベルギー南部のワロン地方にショートトリップです!
(オランダ旅行4日目~ベルギー・ワロン地方へのショートトリップに続く。)
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
この旅行記へのコメント (2)
-
- 川岸 町子さん 2020/09/14 18:04:40
- 趣ある書店
- エンリケさん、こんにちは(*^▽^*)
デン・ハーグからマーストリヒトまでは早朝にお出掛けで、効率良く行動なさってますね。
久々に陽の長い時季のヨーロッパを列車に揺られてみたいと思いました。
“ベツレヘムの人口調査”こちらは、絵の題名そのものの光景で興味深いです。
一見絵本のようなタッチながら、ありのままの様子の描写ですね。
「世界で最も美しい本屋」、行ってみたいです!!
海外のおしゃれな書店、とても気になります。
海外の書店は、全く異なる用途の建物を上手くリノベーションし、趣のある雰囲気に仕上げていますよね。
ここには暖炉があったんだろうなと思うような、箇所があったり。
書棚の上の方に手を伸ばすためのハシゴがあったり。
私もポルトガルで教会かと思って入ったら、内部は書店だったことがありました。
夜の河沿いの風景は、空の色が深くなるにつれ、川面に映る灯りが鮮やかになり、本当に美しいですね(^^♪
長い一日、お疲れさまでした(*^-^*)
町子
- エンリケさん からの返信 2020/09/15 18:49:13
- 治安の良いマーストリヒトの街
- 川岸 町子さん
こんばんは。マーストリヒト旅行記に早速ご訪問いただきありがとうございます。
> 久々に陽の長い時季のヨーロッパを列車に揺られてみたいと思いました。
やはり陽が長く、遅くまで観光できる夏のヨーロッパは魅力ですよね。
今年はそれを味わえないのが非常に残念です・・・。
> “ベツレヘムの人口調査”こちらは、絵の題名そのものの光景で興味深いです。
> 一見絵本のようなタッチながら、ありのままの様子の描写ですね。
ブリューゲルの作品は登場人物がたくさん描かれていて、一人一人の様子を観察するだけでも楽しいですね。
> 「世界で最も美しい本屋」、行ってみたいです!!
> 海外のおしゃれな書店、とても気になります。
> 海外の書店は、全く異なる用途の建物を上手くリノベーションし、趣のある雰囲気に仕上げていますよね。
> ここには暖炉があったんだろうなと思うような、箇所があったり。
> 書棚の上の方に手を伸ばすためのハシゴがあったり。
> 私もポルトガルで教会かと思って入ったら、内部は書店だったことがありました。
そう、ポルトガルのポルトにも、“世界で最も美しい本屋”に選ばれた“レロ書店”というお店があるのですよね。
ここだけでなく、ポルトにはポートワインを飲みにいつか行ってみたいのですが、コロナ禍も発生してしまい、行ける日はまた遠くなりそうです・・・。
> 夜の河沿いの風景は、空の色が深くなるにつれ、川面に映る灯りが鮮やかになり、本当に美しいですね(^^♪
マーストリヒトは治安も良くて、夜遅くでも人がたくさん街なかにいて賑わっていて、時間があればもっと滞在していたかった街でしたね。
ただ、日本人の旅行者にとってはそんな時間もなく・・・次回は急ぎ足でベルギーのワロン地方の街を見学して回ることになります・・・。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったホテル
-
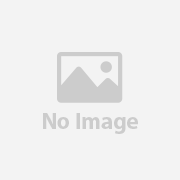
ホテル ラ コロンベ
評価なし
この旅行で行ったスポット
もっと見る
マーストリヒト(オランダ) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?
















































































































































2
99