
2022/09/03 - 2022/09/04
109位(同エリア351件中)
![]()
ハイペリオンさん
- ハイペリオンさんTOP
- 旅行記174冊
- クチコミ91件
- Q&A回答35件
- 480,505アクセス
- フォロワー48人
さて、今回は恒例の日本100名城めぐり
などと書くと、自称4トラのモテ男の旅
行記のパクリになってしまうので、そん
なことは真っ赤なウソで、帰省した際に
地元の歴史的なところを数か所見て回っ
た旅行記である。
実家に帰ったのは、20年ぶりくらいでは
ないかと思う。前に帰ったのは叔母さん
の葬式に出るためだった。
そして、今回は親父が急死したので、法
事の準備のための帰省となった。
もう90を過ぎているし、いつ死んでもお
かしくなかったのだが、あと1~2年は
大丈夫だろうと言われていたので、別に
気にもしていなかった。それが、母親か
ら電話で「お父ちゃん死んだんや」とい
われ、「死んだ!?」と言ったあと、絶
句してしまった。はっきり言って男同士
だし、「尊敬する人は?」と聞かれて、
「父です」と答えるような間柄ではない
ので、絶句したくらいで、それ以上の感
慨はなかった。性格的に全く合わないし、
一つ屋根の下で暮らせるような関係では
なかった。若いころ、よく家庭内暴力に
走らなかったなと思う。
葬式は、コロナということもあり、家族
と親戚一部を呼んで行ったらしい。
しかし、法事くらいは戻ってこいと言わ
れたので、久しぶりに帰ることにした。
- 旅行の満足度
- 5.0
- 観光
- 4.0
- ホテル
- 5.0
- 交通
- 3.0
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 3万円 - 5万円
- 交通手段
- ANAグループ JRローカル
- 旅行の手配内容
- 個別手配
- 利用旅行会社
- 楽天トラベル
-
関西空港から30分弱で東岸和田
駅に着いた。
昔は貧相な田舎駅という雰囲気
だったが、ずいぶん様変わりし
ている。
しかし、駅の見かけは立派だが、
周囲には飲食店がほとんど見当
たらない。
子どもの頃よく通ったショッピ
ングモールもなくなってしまっ
ていた。 -
駅の玄関は、岸和田祭りのだんじ
りの屋根をかたどったもの。
何でもかんでもだんじりにすりゃ
ええっちゅうもんやないぞ。 -
駅近くの唯一のホテル、ホテルルー
トイン東岸和田。
実家は兄夫婦がいるし、実家の布団
で寝ると変な夢を見るので、ホテル
に泊まることにした。
霊感などとは一切無縁の人間だが、
おそらく実家の布団が重いので、そ
れで圧迫されるのではないかと思う。 -
楽天トラベルで航空券と一緒に予約
したので、正確な値段はよくわから
ないが、朝食バイキング付きで5千
円くらい。
シングルルームだからあまり広くな
いが、これで十分。 -
ホテルのバイキングで朝食を済ませ
た。バイキングって人間性が出るよ
なあ。若くてけっこうかわいい女の
子が、どんぶりにから揚げを富士山
のようにてんこ盛り、おまけにオレ
ンジジュースをコップに5杯。どん
な朝めしだよ。
さて、東岸和田駅から天神山町を通
るバスに乗り、天神山三丁目で下車。
バスは1時間に1本しかなかった。
ここは半世紀前に団地と住宅地を建
てるために原野と丘を切り拓いた所
である。
「天神山」という名称がいかにもダ
サく、当時は不評だった。
さらに、団地内には下っ端のヤーさ
んがけっこう住んでいるという噂が
あった。
当時からすでにシノギが厳しかった
のか、ヤクザも団地住まいになって
いたのである。 -
周囲にはこんな感じで、こんもりと
盛り土したような森がある。 -
ぼくの進行方向にも、木々で覆われた
丘がある。
じつはこれらは古墳なのである。 -
ちょっと遠くから見るとこんな感じ。
丘が二つ並んでいて、出来損ないの前方
後円墳のような形をしている。子どもの
頃は前方後円墳だと教えられてきたのだ
が、後の研究では円墳であるとされた。
この古墳を大山大塚遺跡公園と呼ばれ、
一応、岸和田市が管理している。
ということで、古墳の中に分け入って
みよう。ここは皇族の墓ではなく、お
そらく在地の有力者の墓だったので、
勝手に入っても構わないのだ。 -
住宅地の裏手にはゾウ公園という奇妙な
公園というか、ただの広場があった。 -
ゾウのオブジェが置かれているだけの広場
で、遊びに来る子供たちもいないことが、
ぼうぼうの雑草でよくわかる。 -
この階段が古墳の中へ行く道のようだ。
しかし、内部は笹と雑草で覆われ、ほ
とんど獣道状態。
おまけにやぶ蚊の襲来を受け、腕や首
筋を掻きながら歩いた。
「公園」なんだからちゃんと整備しと
けよ。(ゾウ公園もな!) -
ここは、この付近の有力者の墓とさ
れているが、なぜかもう一人葬られ
ている者がいる。
捕鳥部萬(とっとりべのよろず)が
その人物の名前である。
生まれた年は不明、没年は587年と
思われる。
捕鳥部萬は物部守屋に仕える武将で、
100人程度の部下を従えていた。
587年に勃発した、物部守屋と蘇我馬
子、厩戸皇子(うまやどのみこ=聖徳
太子)との戦争、丁未の乱において、
難波にあった守屋の居宅を守っていた
とされている。
この戦争は、教科書には仏教を導入す
るか否かの対立から生じた戦争とされ
ているが、実際には皇位継承戦争である。
穴穂部皇子(あなほべのみこ)を擁立
しようとする物部守屋に対し、それに
反対する蘇我馬子、厩戸皇子らの戦い
である。
物部氏の一族は現在の八尾市あたりを
根拠地としており、この付近の衣摺の
戦に敗れ、守屋含め一族は滅ぼされた。 -
物部一族討滅の報を受けた萬は、夜中
に単独で難波を離れ、奥さんの出身地
のこのあたりに逃げて潜伏した。
この付近を当時は有真香邑(ありまか
むら、またはあまかむら)と呼んでいた。
有真香邑はこのあたりから、貝塚市
の一部までを含む、現在なら一つの
市として成立しそうな広大なエリア
である。
現在でも「有真香」という呼称は使
われている。 -
しかし、蘇我方の残党狩りは執拗で、
数十人からなる追及の部隊がここまで
やって来た。
捕鳥部萬は、たった一人で雑木林の中
でゲリラ戦を行い、蘇我方の兵士を何
人も射殺したという。まるでランボー
である。
しかしさすがに多勢に無勢。最後は木
の上から弓で射かけていたところを討
たれ、斬られた。
当然首は斬られたが、萬が飼っていた
白犬が首を咥えて、威嚇するので、蘇
我兵はそこで引き上げた。 -
その捕鳥部萬の墓が、この古墳の中にあ
るというのだが、場所がさっぱりわから
ない。
しかし、googleマップで「捕鳥部萬 墓」
で検索すれば、たちどころに場所が表示
された。
どうやら、古墳の頂上あたりにありそうだ。 -
雑木林に覆われて薄暗く笹と雑草だらけ
の獣道を蚊に生き血をささげながら登る
と碑のようなものが見えてきた。
どうやら墓もここにあるようだ。 -
硯のような形の頑丈な石に、びっしりと文
字が彫られている。 -
碑名は「捕鳥部萬碑」。
碑文は江戸末から明治時代を生きた公爵、
三条実美という人物によるもの。
文字はほとんど読み取れない。 -
右側に石段があり、その上に墓石があった。
-
これが捕鳥部萬の墓である。
古墳自体は笹と雑草でぼうぼうだが、碑
と墓の周囲はきれいにされていた。
古墳のすぐ近くに、萬の奥さんの子孫と
される方が住んでいて、ずっと墓守をし
ているらしい。
千年以上前から墓守をずっと続けている
なんてすごい話だ。
塚元さんという方らしいのだが、この辺
一帯の土地を持っておられるようで、天
神山に団地と住宅地を造成する際には、
古墳を遺跡公園にすることで承知したら
しい。
中学の同級生に塚元という男がいて、彼
の家はかなり大きかった。あいつのこと
だろうか。でも、チビでいじめられっ子
だった。
ちなみに、萬の首を抱いて守った白犬は
もう一つの丘陵部に「義犬塚」として祀
られている。 -
捕鳥部萬については、調べるといろいろ
な疑問点が出てくる。
物部守屋に仕えていたというが、100人
もの部下を従えて、なぜ難波にいたのか。
戦争は東にある守屋の本拠地で行われて
いたのにである。
彼は殺される間際に次のようなことを叫
んだという。
「私は天皇の盾となって働いてきた。
なのに、それを咎めるとはどういうこと
なのだ。捕らえる、殺すは私の言い分を
聞いてからにしてくれ」。
そこには、主の守屋は全く出て来ない。
天皇に対する忠誠を感じさせる言葉だ
けである。
そして、萬を討ち取ったと飛鳥に報告
すると、「遺体を八つに切り裂き、串
刺しにして8国にばらまけ」との命令
が来た。
物部守屋でさえそんな目に遭わされて
いないのに、死んでそこまでされると
は、朝廷側は萬の存在を恐れていたと
しか思えない。単なる守屋の有力家臣
の一人とは思えないのである。 -
そもそも、武将一人を斬るために100
人近い追っ手を差し向けるとは大げさ
すぎないか? 確かに萬は100人の家
来を召し抱えていた。しかし、単独で
逃亡したことははっきりしている。
100人の家来を持つ武人、大人数で構
成された朝廷側の追っ手、斬られる間
際の言葉。これらのエピソードは、捕
鳥部萬という人物が、現在この周辺で
伝えられているイメージとはずいぶん
異なるものを浮かび上がらせる。 -
古墳を出て村のある方へ歩くと、だん
じり囃しが聞こえてきた。
街道近くの神須屋(こうずや)町のだ
んじりが小屋引き出されていた。
10月の本番に向けて、整備や掃除でも
しているのだろうか。 -
街道を大阪湾方面に下り、府道、通称
小栗街道を大坂方面へ向かった。
ここは、小松里(こまつり)町の交差
点。
関係ないけど我が母校、大阪府立久米
田高等学校はここを左折したところに
ある。
高校野球の予選はだいたい2回戦で負
けるような、何をやらせても中途半端
なヤンキー高校だったが、ダンス部が
今年のだんすこうしえん日本高校ダン
ス部選手権で優勝した。2年連続準優
勝で、3度目の正直で優勝。卒業生か
らすれば、ありえないことである。お
そらく、コーチに優秀な人がいるんだ
ろう。 -
交差点のすぐ近くにあるのが清原和博
(西武→読売→覚せい剤取締法違反)の
生家跡(笑)。
昔ここに「清原電気店」という電気屋が
あったのだが、完全に更地になっている。
学校帰りにここで電池やカセットテープ
を買って帰ったのだが、あの店にあんな
のがいたとはなあ。
清原が西武に入団した際、球団へ納入す
電気製品はすべて清原の親父の店が請け
ることにしたという。おかげで蒸しじゃ
が以上に懐はホクホクだったようだ。
その後一家は芦屋に引っ越したと聞いた。
多分清原は自分に甘い人間のようだから、
クスリは今も時々やっているんじゃない
かと思う。 -
小松里の交差点を右折して、数分行くと、
巨大な溜め池がある。
これが久米田池。一周2.6キロもある池で
ある。
香川県の満濃池に次ぐ大きさである。 -
満濃池が作られたのが701年、この久米田
池は725年。ほぼ同時期である。
聖武天皇が仏僧、行基に掘削を命じ、3年
間の工事を経て完成した。
行基は奈良の大仏造立の実質的責任者だが、
近畿を中心に15の溜め池を作るなど、社会
整備事業も行っている。 -
穴を掘ってそこに水を呼び込んだのではな
く、三方が高くなっている場所で、そこを
川が流れていたので、一角だけ堤を築き、
堰き止める形にしたという。
向こう岸がその堤の部分にあたる。 -
高校生の時、ここをいつも2周走っていた。
40年近く前なので、大阪の片田舎のこの辺
では、ジョギングなどというハイカラ(?)
な文化はなく、街灯のない暗い堤の上を走
っていた。
おかげで冬のマラソン大会では好成績を収
めることができた。 -
久米田池から和泉市方向に自転車を走らせ、
摩湯町というところまでやって来た。
ここには、摩湯山古墳という前方後円墳が
ある。 -
交差点の少し先に周濠とともに古墳が見え
てきた。 -
前方後円墳とはいうものの、上空から見る
とこんな感じ。
造りかけでほったらかしにされような形だ。
細長く伸びる丘陵のしっぽの部分(下の部
分)を切って堀をめぐらせたのだろうとさ
れている。
前方後円墳というと、大阪の百舌鳥古市古
墳群の前方後円墳を想像するが、このよう
ないびつな形のものも多い。 -
周濠の堤のの上を歩いてみた。
この先は道はついていないが、そのまま古
墳の中へつながっている。 -
この辺りは前方後円墳のくぼみのように見
えなくもない。 -
ここが古墳の中への入り口。
現在は立入禁止となっている。
昔は、市内の小学生にとっては遠足コース
だった。
5年生の頃ここまで歩かされたが、往復で
10キロ以上あったと思う。とにかく疲れた
ことだけは覚えている。 -
摩湯山古墳が作られたのは、4世紀末期と
されている。
天皇で言えば、仁賢、武烈両天皇の時代に
あたる。
葬られているのはもちろん皇族ではなく、
地元の有力者である。
しかし、久米田池や天神山の古墳もそう
だが、5世紀ごろに大阪の南部でこれだ
けのものを造る人員を動員していたこと
に驚かされる。
大阪南部は古代にはJR阪和線の手前ま
でが海で、そのあたりに人口は集中して
おり、住宅地を造成しようものなら、弥
生時代から飛鳥時代の住居跡がぼろぼろ
と出てくる。
穴を掘ったら遺跡に当たる状態で、ヘタ
に遺跡に当たったりしたらそこで工事は
中断、不動産屋は頭を抱えるような状況
がしょっちゅうだったのだ。
おそらく、当時としては相当な人口密集
地帯だったのだろう。
そして、飛鳥地方との交流も盛んで、都
周辺で造られた古墳を見た者がいたに違
いない。 -
さて、古墳めぐりのあと、南海岸和田駅
前までやって来た。
この駅も昔と違ってずいぶん様変わりした。 -
駅から海側に伸びる駅前通り商店街。
-
アーケードが高いのは、祭りのとき、こ
こをだんじりが通るため。
日曜の午後だというのに、あまりにも人
通りの少なさに愕然とする。
昔はもっと賑わっていたはずなんだがなあ。 -
よくレコードを買いに来たレコード店
「ヤング」(笑)。
今となってはおじんくささ満点の店名。
レコード店自体が現在では成り立ちに
くい商売で、ほとんどが演歌のCD売
って細々と生きている状態になってし
まった。 -
ここのドル箱はだんじり祭りのDVD
のようだ。 -
商店街を端まで歩き、国道26号線を
渡り、路地を歩いているとこんなも
のを見つけた。
十数年前に放送された、NHKの朝
ドラ「カーネーション」のロケ現場
だったところらしい。
「カーネーション」はファッション
デザイナーのコシノ三姉妹の母、小
篠綾子を描いたドラマである。
三姉妹は五軒家町の生まれというか
ら、おそらくこの付近に違いない。 -
軽自動車1台が通れるかどうかの路地
を行ったところにお寺がある。 -
臨済宗妙心寺派のお寺、本徳寺。
元々は隣の貝塚市にあった海雲寺が戦火
に遭い、ここに移され、本徳寺と名を変
えたものである。
この寺がどうしたかというと、ここには
これが所蔵されているのである。
↓ ↓ ↓ -
昨年はやたらテレビで見かけた、明智光
秀の肖像画である。 -
なぜここにこんなものがあるのかという
と、明智光秀の長男、明智光慶が光秀が
討ち死にした山崎の合戦後出家し、妙心
寺派の僧侶となり、南国梵桂という名で
海雲寺にやって来て、絵師に描かせたと
言われているのだ。
光慶に関しては山崎の合戦で光秀が討ち
死にした日に病死したと言われているが、
ドンピシャのタイミングだけにどうもお
かしいとは言われ続けている。
さらに、実は光秀は落ち延びて、雲海寺
までやって来て、光慶(南国梵桂)の保
護の下、隠棲していたという都市伝説も
ある。
昨年の大河ドラマ「麒麟が来る」のラス
トも長谷川博己が馬に乗って駆けていく
思わせぶりなシーンで終わっていて、光
秀生存説を匂わせるようなだった。 -
本徳寺は個人の住宅と一体化した形になっ
ており、中に入ることはできなかった。 -
焼けた海雲寺を岸和田の五軒屋町に移すこ
とを命じたのが、ここ岸和田城の二代目当
主、岡部行隆である。 -
岸和田市の唯一無二というか、これしかな
いランドマークである。 -
四方を堀に囲まれており、入り口はこの大手
門のみ。 -
入ると三層の本丸が見えた。
-
本丸の正面にははきれいに整備された庭がある。
作庭家の重森三玲という人が昭和28年に作っ
た八陣の庭。
三国志の英雄、諸葛孔明が考案した八卦の陣
をイメージしたものらしい。 -
これが天守閣から見た八陣の庭。
八卦の陣からどうイメージしたのか、さっばり
わからない。
(金網が遠いところに張り巡らされており、思
いっきり手を伸ばして金網をボケさせようとし
たが、これが限度) -
細かい玉砂利には精緻な文様が描かれていた。
-
これが、岸和田城の歴代当主。
確か最後の当主が明治維新後文部大臣に
就任したと聞いた。もうヨボヨボのじい
さんだったらしい。 -
岸和田城を築いたのは楠正成の甥、和田高
家(にぎたたかいえ)と言われているが、
南北朝期は、この辺りはまだ海で、もっと
東側、南海線と阪和線の間あたりだったの
ではないかとされてるが、築城されていた
かどうかは不明。
ここに天守閣を造ったのは羽柴秀吉の叔父、
小出秀政。元は五層だったらしい。 -
これが城下町の風景。今も瓦屋根が多く、
城下町の風情が残っている。 -
東岸和田駅前は飲み屋と言えるものがあ
まりなく、駅構内にある居酒屋、ニュー
タコイチというところに入った。 -
中生にたこわさにモツ煮、枝豆。〆に焼き
そばを食べて2080円。安いもんだ。 -
帰りはANAとの共同運航便、真っ黒なスタ
ーフライヤー。ほぼ満席だった。 -
久しぶりの帰省で、帰ったら改めて見ておこうと
思っていたところを全部回った2日間だった。
こんなことでもないとめったに帰省しないので法
事には感謝。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
この旅行で行ったホテル
岸和田・貝塚(大阪) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?





































































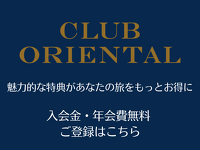








0
61