
2010/09/30 - 2010/09/30
449位(同エリア578件中)
![]()
ムッシュさん
ついに琵琶湖が望める近江路へ!
醒ヶ井宿を立ち、山間の番場宿から琵琶湖を望む磨針峠を越えると、北国街道との分岐点鳥居本宿へ着きます。彦根城も隣接する街道です。
番場宿 第六十二宿(日本橋より464?)
米原港を経て琵琶湖水運に通じる宿として誕生。山間の寒村で、宿の長さは中山道で最短。長谷川伸の小説「瞼の母」の主人公「番場の忠太郎」が番場宿出身の設定で有名になった。
近江中山道では最小規模の宿場。
鳥居本宿 第六十三宿(日本橋より469?)
天候が急変するため、旅人に合羽がよく売れた。また道中丸の赤玉を売る店があり、神教丸、仙教丸など類似の名で売られた。
-
【久礼の一里塚跡】
公園内に大きな自然石の中山道一里塚の跡碑があります、久禮の一里塚跡です、江戸日本橋より数えて117里目(468km)、京三条へ残り19里(76km)です。
江戸時代には、三十六町を一里とし、一里毎道の両側に盛土して塚が築かれていました。川柳に、「くたびれた やつが見付ける 一里塚」
とありますが、旅人は腰を下ろして一息し憩いの場にしたことでしょう。
久禮の一里塚には右側には「とねり木」、左側には「榎」が植えられていました。
平成七年七月 米原町史談会 -
【番場宿石碑】
中山道番場宿碑と中山道分間延絵図番場宿レリーフがあります。
交差点右角のベンチもあるポケットパークに自然石の中山道番場宿碑
天保14年(1843年)の頃、番場宿の宿内家数は178軒、うち本陣1、脇本陣1、問屋6、旅籠10軒、宿内人口は808人で彦根藩領でした。 -
著作権フリー作品「木曽街道六十九次」画像を使用する。
【木曽海道六十九次之内 番場 広重画】
広重は木曽海道六十九次の中で番場としてこの東見付から見た宿内を描いています。
この見付には石垣の上に築いた土塁、そして生垣がしっかり描かれています。
右手の茶屋の屋根は石置きになっています。
左手には馬子が屯しています、醒井宿への帰り馬で、駄賃稼ぎの客拾いです。
見付から番場宿内を見通ししたもの。入口右側の店には「一膳めし」と書かれた提灯と「いせや」の看板が掲げられている。左側中央の茶屋の看板にはヒロの紋に「歌川」と書かれて、歌川広重を暗示している。
番場の名前は、後年、長谷川伸の戯曲「瞼の母」の主人公である「番場の忠太郎」の出身地として知れ渡った。 -
【問屋場碑】
慶長8年(1603年)番場宿本陣を勤める北村源十郎は彦根藩の命によって琵琶湖に米原湊を築き、次いで同16年(1611年)湊と中山道を結ぶ米原道を開削しました、これにより番場宿は9里半街道の終点として大いに賑わいました。問屋場は五軒あった。
宿長は一町十間(約127m)と短く、中山道宿場中最短でした、宿並は下町、仲町、上町の三町で構成されました。 -
次いで右手に中山道番場宿本陣跡標石があります、並びに【明治天皇番場御小休所碑】があり、傍らに「中山道番場宿問屋場跡標石」があります。
北村家が本陣を勤め問屋を兼ねました、建坪百五十六坪で門構え玄関付でした。
本陣を勤めた北村源十郎が米原湊を開発しました。 -
【忠太郎地蔵尊の由来】
昭和三十三年八月三日 文壇の雄長谷川伸先生が南無帰命頂禮 親をたづぬる子には親を 子をたづぬる親には子を めぐり合わせ給えと悲願をこめて建立された地蔵尊。 このお地蔵さまを拝めて 親子の縁はもとより あらゆる縁が完全に結ばれて 家庭円満の楽しみを受ける事ができる それにはお互がいが をがみ合うすなをな心が大切である それをこのお地蔵さまは 合掌せよとお示しになっている 番場史跡顕彰会
蓮華寺の本堂裏手には長谷川伸の「瞼の母」で御馴染みの番場の忠太郎碑があるところだ。元弘3年(1333年)、鎌倉幕府の六波羅探題の北条仲時主従432人が自決した寺である。裏の山腹にその群墓(大小の五輪塔がぎっしりと建っている)が今でも残されている。この年、終に鎌倉幕府が滅亡した -
-
小磨針峠と並行して走る名神高速道路
-
上り坂をグングン進むと、名神高速道路の米原トンネルの上になります、ここが小摺針峠(標高197m)の頂上で、米原市と彦根市の境です。
街道でいうと、中山道と北国街道が分岐する地点。 -
-
-
【望湖堂】
この峠の頂上には茶屋の望湖堂があった処である
当時は、ここから眼下に琵琶湖が見下ろせたという、
今は干拓が進み、湖は遠くなってしまった。今でも遠くに琵琶湖の湖面を望む。昔は埋め立ても無く、湖岸部が相当近くに有ったので、しっかりと琵琶湖が望める地点。
やっと琵琶湖に着いた、京は近いぞ!!これで琵琶湖の見納めじゃ、てな場所でした。
【望湖堂跡】
江戸時代、摺針峠に望湖堂という大きな茶屋が設けられていた。峠を行き交う旅人は、ここで絶景を楽しみながら「するはり餅」に舌鼓を打った。参勤交代の大名や朝鮮通信使の使節、また幕末の和宮降嫁の際も当初に立ち寄っており、茶屋とは言いながらも建物は本陣構えで、「御小休御本陣」を自称するほどであった。その繁栄ぶりは、近隣の鳥居本宿と番場宿の本陣が、寛政七年(1795)八月、奉行宛に連署で、望湖堂に本陣まがいの営業を慎むように訴えていることからも推測される。
この望湖堂は、往時の姿をよく留め、参勤交代や朝鮮通信使の資料なども多数保管していたが、近年の火災で焼失したのが惜しまれる。 -
著作権フリー作品「木曽街道六十九次」画像を使用する
【木曽海道六十九次之内 鳥居本 広重画】
広重は木曽海道六十九次の中で鳥居本としてこの「望湖堂と琵琶湖」を描いています。
往時はここから琵琶湖が一望でき、中山道随一の名勝といわれました。
旅人は茶屋で景色を楽しみ、摺針餅に舌鼓を打ちました、十返舎一九は続膝栗毛の中でこの餅をさとう餅といっています。
木曽路名所図会には「此嶺(みね)の茶店より見下せば眼下に磯崎、筑摩の祠(やしろ)、朝妻の里、長浜、はるかに向ふを見れば、竹生嶋、奥嶋(おきのしま)、多景嶋(たけしま)中略、湖水洋々たる中に行きかふ船見へて風色の美観なり」と著されています、しかし今は干拓により、琵琶湖は遥かに後退しています。
この景勝地には彦根藩が設けた公式接待所望湖堂がありました、参勤の諸大名、朝鮮通信使そして幕末には皇女和宮もここで休息しています、望湖堂の名は朝鮮通信使の一員真狂(しんきょう)の揮毫した書に由来しています。 -
-
-
【おいでやす彦根市】中山道モニュメント
旧道に入ると左手に大きな石柱が三本立っています、正面の石柱にはおいでやす彦根市へと刻まれ、各々の石柱の上には近江商人、旅人、虚無僧の像が乗っています、京方面側にはまたおいでやすと刻まれています。
鳥居本の地名はかつて宿内にあった多賀大社の鳥居に由来しています。
磨針峠を下ると、北国街道(ほっこく、現国道8号線)の追分にでる
北国街道(北陸街道)は、ここから栃の木峠を越え新潟までの全長約520kmの街道である
旧中山道はこの8号線に合流し、再び直ぐ左の細い道に入る
朝鮮人街道や北国街道の分岐、彦根城下に通じる要衝として栄え、大いに賑わい、鳥居本宿の名物赤玉、西瓜、合羽(柿渋の赤)は三赤(さんあか)といわれました。
天保14年(1843年)の頃、鳥居本宿の宿内家数は293軒、うち本陣1、脇本陣2、問屋1、旅籠35軒、宿内人口は1,448人、宿高百十五石で彦根藩領でした。 -
【赤玉教神丸本舗有川家】
十返舎一九に「道中膝栗毛」にも登場する和漢健胃薬”赤玉教神丸(あかだましんきようがん)”を製造販売する有川家(有川製薬株式会社)。
現在の建物は宝暦年間に建てられたもの。皇女和宮、明治天皇も休憩された。
宿並を大きく右に回り込むと右手に万治元年(1658)創業、赤玉神教丸の有川薬局があります。現存する店舗は宝暦年間(1750?60)建造と伝えられる。
多賀大社延命長寿の神の教えによる神教丸は下痢、食あたり、腹痛の妙薬として知られています。
当家は有栖川宮家に出入りが許されたことが縁で二文字を頂戴し、有川と名乗るようになりました。
続膝栗毛の弥次さん喜多さんはここに立ち寄り、狂歌「もろもろの 病の毒を 消すとかや この赤玉の 珊瑚珠(さんごじゅ)の色」とひねっています。
鳥居本の宿場に入り、桝形のところに
赤玉神教丸(あかだましんきょうがん)で有名な有川製薬がある
赤玉神教丸は胃腸薬で下痢、腹痛、食べ過ぎに良く効いたという
今も製造販売している
多賀大社の紳教により調合されたことから神教丸と呼ばれるようになったとか
鳥居本宿の名物はこの赤玉神教丸と鳥居本合羽(かっぱ)の二つであった -
-
【赤玉神教丸本舗】さんです。
「万治元年(1658)創業の赤玉神教丸本舗は、今も昔ながらの製法を伝えています。
有川家の先祖は磯野丹波守に仕え、鵜川氏を名乗っていましたが、有栖川宮家への出入りを許されたことが縁で有川姓を名乗るようになりました。
近江名所図会に描かれたように店頭販売を主とし、中山道を往来する旅人は競って赤玉神教丸を買い求めました。
現在の建物は宝暦年間(1751~1764)に建てられたもので、右手の建物は明治11年(1878)明治天皇北陸巡幸の時に増築され、ご休憩所となりました。
彦根市指定文化財 -
-
【合羽製造所の看板】
看板には、”本家合羽所木綿屋嘉右衛門”と書かれてル。
合羽製造は享保5年(1720年)創業。合羽製造に柿渋をもちいたことにより評判となり、保温性と防水性に富む合羽は雨の多い木曽路に向かう旅人に適した。現在は廃業してるが、看板が健在。
次いで右手に合羽所木綿屋跡があります、本家合羽所木綿屋嘉右衛門という合羽を形取った看板を軒下に吊り下げています。
合羽(かっぱ)は享保五年(1720年)馬場弥五郎が創業したことに始まります、楮(こうぞ)を原料とした和紙に柿渋を塗り込め、防水性を高めた合羽は人気が高く、鳥居本合羽は雨の多い木曽路に向う旅人が雨具として買い求め、文化文政年間(1804~30年) には十五軒の合羽所がありました。
天保三年(1832年)創業の木綿屋は鳥居本宿の一番北に位置する合羽屋で、江戸や伊勢方面に販路を持ち、大名家や寺院、商家を得意先として大八車などに覆いかぶせるシート状の合羽を主に製造していました、合羽に刷り込んださまざまな型紙が当家に現存しています。
大田南畝は壬戌紀行の中で「此駅にまた雨つゝみの合羽ひさぐ家多し」と著しています。
赤い布は、お祭りを表現してる。個性的です。 -
左手が鳥居本宿本陣跡です、標識【旧本陣寺村家】を掲げています。
鳥居本宿の本陣を代々勤めた寺村家は観音寺城六角氏の配下にありましたが、六角氏滅亡後、小野宿の本陣役を勤めました、そして佐和山城落城後、小野宿は廃止され、慶長八年(1603)鳥居本に宿場が移るとともに鳥居本宿本陣役となりました。
鳥居本本宿の本陣を代々務めた寺村家は、観音寺城六角氏の配下にありましたが、六角氏滅亡後、小野宿の本陣役を務めました。佐和山城落城後、小野宿は廃止され、慶長八年(1603)鳥居本に宿場が移るとともに鳥居本宿本陣役となりました。
本陣屋敷は合計二〇一帖もある広い屋敷でしたが、明治になって大名の宿舎に利用した部分は売り払われ、住居部分が、昭和十年頃ヴォーリズの設計による洋館に建て直されました。倉庫に転用された本陣の門が現存しています。
本陣屋敷の建坪は137坪で、合計201畳もある広い屋敷でしたが、明治になって大名の宿舎に利用した部分は売り払われ、住居部分が、昭和十年(1935年)頃ヴォーリズの設計による洋館に建て直されました。 -
【近江鉄道本線の鳥居本駅】
レトロな建築物として歴史の名残を残す。昭和6年開業当時のままの駅舎です。
明治二十九年(1896)に彦根、貴生川間の区間で開業した近江鉄道は、その後、昭和六年に彦根、米原間も開業し、同時に鳥居本駅舎も建設されました。
その後建替えられましたが、今も建設当時の全国の平均的な建築様式をそのまま継承しています。
平成八年にはこの駅舎で百八十四時間におよぶ世界最長コンサートが開催されギネスブックに登録されました。 -
【小町塚】
小野小町に関係してるとも??小野塚があります、地蔵堂には十五世紀後半頃に造立された小野地蔵が安置されています -
ホテルの部屋から琵琶湖を遠望してる。
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?































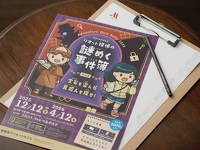





0
25