
2010/06/25 - 2010/06/25
322位(同エリア578件中)
![]()
ムッシュさん
いよいよ近江路へ
【柏原宿(滋賀県) 第六十宿(日本橋より449.1km)】
東西1.4?、近江路最大級の宿場。艾(もぐさ)、薬種産業で賑わい、秀吉の直轄地(太閤蔵入地)、幕府の直轄地の時代もあり享保9年大和郡山藩の飛び地として経済的に豊かな宿場であった。
【醒ヶ井(さめがい)宿 第六十一宿(日本橋より455km)】
三水四石の名所。日本武尊ゆかりの居醒の清水は旅人の休憩の場として有名であった。現在も湧水は絶えることなく、地蔵川へと流れる。
三水四石:清水、十王水、西行水の湧き水と、蟹石、日本武尊の腰かけ石、鞍掛け石、影向石をさす。
*
-
-
-
-
柏原宿の町並み
「伊吹山の麓にして、名産に伊吹もぐさの店多し」(木曽図名所図会)。今も変わらず広重が描いた「伊吹堂亀屋左京」がもぐさを商っている。 -
柏原宿の問屋役庄屋は、映画監督吉村公三郎氏の実家です。
東の庄屋跡です、吉村武右衛門が勤めました、吉村公三郎の祖父が最後の庄屋を勤めました。 -
【柏原宿本陣跡】
南部辰右衛門が勤め年寄を兼ねました。間口は両隣を合せた広さで、屋敷は526坪、建坪は138坪でした、建物は皇女和宮通行に際して、新築されました。
徳川家茂が宿泊したことあり。 -
【福助印伊吹もぐさ本舗】
今も稼動してる。
創業三百数十年。「伊吹堂亀屋佐京商店」は、歌川広重の「木曽街道六十九次・柏原」に店頭の風景が描かれた当時の面影を残し、現在も伊吹山麓特産である”もぐさ”を販売してる。
北に伊吹山がそびえるが、薬草の産地で、良質のヨモギで作った「もぐさ」は伊吹艾として街道の名物であった。
こちらでは、毎年、やいと祭りがあるよ。 -
著作権フリー作品「木曽街道六十九次」画像を使用する
【木曽海道六拾九次之内 酔ヶ井 (広重)】
木曽路名所図会に「此駅は伊吹の麓にして名産伊吹艾(もぐさ)の店多し」と著しています、伊吹山は良質な蓬の葉(よもぎのは)が自生し、これを加工するとお灸(きゅう)に用いる艾(もぐさ)になりました。これは、亀屋佐京の店頭が描かれている。
最盛期には十数軒の伊吹もぐさ屋が亀屋の屋号で軒を連ねていました、亀屋の六代目松浦七兵衛は江戸に出て伊吹もぐさの名声を高めました。
吉原の遊女に「江州柏原伊吹山の麓の亀屋佐京の切りもぐさ」という唄を教え込み、毎夜宴席で歌わせ、伊吹もぐさの宣伝に努めました。
亀屋のシンボル福助人形は働き者の番頭で、店を繁盛させた功労者です、シッカリものの番頭さんと遊び人の旦那、落語の世界ですね!
広重は木曽海道六十九次之内で柏原としてこの亀屋の商い風景を描き、右端に福助人形を配しています。 -
提灯には柏原宿、やいとの里としるされてル。
-
-
【柏原一里塚】
江戸日本橋から数えて115番目。南塚を復元育成中。
柏原宿内の西見附近くに街道を挟んで北塚と南塚があった。(両塚ともに現存しない。)
北塚は、街道沿い北側で、愛宕神社参道の石段東側(現中井町集会所)の場所にあった。
南塚は、街道を横切る接近した二筋の川のため、やむを得ず東側の川岸で街道より奥まった所に築かれた。(現在では、大幅な河川工事が行われてので、この地点から東寄りの河床の位置になる。)
なお、江戸時代刊行の道中記等を見ると、両塚とも三本の榎が描かれている。 -
【自然石道標】
「←東山道横河駅跡 梓/歴史街道 中山道/柏原宿 江戸後期大和郡山領→」と黒御影石の街道並び松(古木)碑「梓 12本 0.1km/ここより/柏原宿 6本 1.3km」があります。
左方は梓、右方は柏原宿 -
【東見付跡で、東枡形です】
この枡形内の左手に中山道醒井宿碑があります。
醒井宿(さめがい)に到着です!
醒井宿は名水の里として名を馳せ、清水が豊富で旅人の良き休憩地として賑わい、ところてんや素麺が名物でした。
宿長は八町二間(約876m)で、宿並は新町、中町、枝折村(しおむら)で構成されました。 -
【居醒(いさめ)の清水】 平成名水百選
古来より醒井には豊富な湧き水が出る場所が、いくつもあり、日本武尊伝説の「
居醒(いさめ)の清水」から湧き出た水は地蔵川となって町を流れている
その川に沿って、かつての宿場作られていた
家に入るには、地蔵川の上に掛けた橋を渡って入るようになっている
地蔵川は生活用水であった
水は透き通り、群生する梅花藻(ばいかも)が流れに揺れている
この海花藻と、水中に群れを成して泳いでいる、小さな針のように細い魚ハリヨは
共に天然記念物に指定されている
夏場には梅の花に似た可憐な白い花を咲かせる -
【醒ヶ井宿本陣跡】
今は料亭”樋口山”が建っています。管内に宿泊した大名の名を大書した関札が陳列されている
地蔵川を渡った奥に日本料理本陣樋口山があります、ここが代々江龍家が勤めた本陣跡です、建坪は百七十八坪で、往時の関札が玄関に掲げられています。
天保十四年(1843年)の頃、醒井宿の宿内家数は138軒、うち本陣1、脇本陣1、問屋7、旅籠11軒、宿内人口は539人で大和郡山藩領でした。 -
地蔵川の「かわと」
清らかな流れは各家庭から水際に直接降りられる「かわと」と呼ばれる階段がある。日常の水仕事に使われる。写真の右中程に階段が見える。 -
地蔵川沿いの街道。
-
中山道醒井(さめがい)宿~
問屋場(右側)と地蔵川(中央)と街道(左側)の構図です -
【醒ヶ井宿問い屋場跡】
本陣の並びが問屋場跡(米原市指定文化財)です、川口家が勤めました。
建物は江戸時代初期の建築で木造平屋建てです、建物は修復され米原市醒井宿資料館として公開されています、醒井宿には七軒の問屋場がありました。 -
【醒ヶ井宿問い屋場跡】
手前の川は、地蔵川。
宿場を通行する幕府の役人や商人に人足や馬を提供し、荷物の積み替えを行っていた。 -
【梅花藻の咲く清流】
地蔵川の川底には梅花藻という水草が生息しており夏場に梅の花に似た可憐な白い花を咲かせる -
あれ? 川の中に人がいるじゃん。
この地蔵川の清水には、絶滅危惧種の小魚”ハリヨ”が、自生梅花藻と共生している。
そんな姿を写真に撮るらしく、水中撮影用のガラス箱にカメラをセットして、チャンスを待ってるところ。
大切に保護して下さいねーー。お願い。 -
きれいなグリーンの水藻は、”梅花藻(ばいかも)”と呼ぶ
しろい可憐な花は、梅の花に大変よく似ていることから”梅花藻”。
透き通った清水からチョコッと顔出してる。こっちを見てね。
自生する水草梅花藻と絶滅危惧種ハリヨが、きれいな水で共生する。
湧水で居醒の清水。醒ヶ井三水の一つ。 -
中山道醒井(さめがい)宿:清流と梅花藻(借用、パンフより)
-
【二つ目の湧水、「十王水」】
「安中期の天台宗の高僧・浄蔵法師が諸国遍歴の途中、この水源を開き、仏縁を結ばれたと伝えられる。もとより浄蔵水と称すべきところを、近くに十王堂があったことから「十王水」と呼ばれるようになったという。」 -
湧水の西行水の源です
【醒井宿三名水の三つ目西行水】
岩の間から清水が湧き出しています。
岩の上に仁安三年(1163年)建立の五輪塔があります、塔には「一煎一期終即今端的雲脚泡」と刻まれています、これが泡子塚です。
西行法師東遊の時、この泉の畔で休憩したところ、茶店の娘が西行に恋をし、西行が旅立った後に飲み残しの茶の泡を飲むと不思議にも懐妊し、男の子を出産しました。 -
【米原市醒ヶ井宿資料館(旧醒ヶ井郵便局)】
大正4(1915)年米国建築家の設計により建築。木造2階建擬洋風建築。
醒井大橋を渡った辺りに高札場がありました、宿並は左に進みますが、居醒橋を渡って進むと右手に旧醒井郵便局があります。
建物は大正四年(1915年)米国のウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計による木造二階建ての擬洋風建物で昭和48年(1973年)まで使用されました(国登録文化財指定)。
今は醒井宿資料館になっています、庄屋と問屋を勤めた江龍宗左衛門家に伝わる古文書等を展示しています。 -
著作権フリー作品「木曽街道六十九次」画像を使用する
【木曽海道六拾九次之内 酔ヶ井 (広重)】
広重は沢山ある宿内の名勝を描かずに、西の外れにある六軒町辺りを東から西に向かって描いている。また、何故か醒ヶ井を酔ヶ井と書いている。
彦根藩との境辺りに六軒の茶屋を作り、六軒町と呼んだ。この浮世絵は、六軒町辺りを進む大名行列の最後尾部を描いている。
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?



































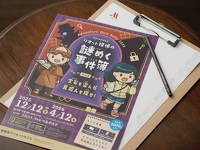





0
28