
2010/01/01 - 2010/01/01
108位(同エリア119件中)
![]()
みなみんさん
2010年1月1日、久しぶりに寒いお正月でしたが帰省の折に郷土史探訪してきました。歴史的にはかなり由緒のある土地のようですが、今回の探訪の旅でもいろいろ勉強になりました。
- 同行者
- 一人旅
- 一人あたり費用
- 1万円未満
- 交通手段
- 自家用車
-
大阪府南河内郡太子町 磯長山叡福寺の中枢とも言える聖徳太子が眠る北古墳です。菊のご紋が神々しいしいです。お正月は参拝客も多く甘酒も振舞われます。しかしここは何度来てもピンと張った空気が清清しいところです。この周辺には推古天皇を始めとする御陵がたくさんあります。日本版王家の谷です。
-
叡福寺から北西に1キロ少々、同じ峰の続きに位置するのが源氏発祥の地壺井の里、通法寺跡です。鎌倉幕府を興した源頼朝の先祖である河内源氏の根拠地です。源の頼信、頼義、義家の三代の墓所と菩提寺である通法寺の跡があります。このお寺は明治の廃仏毀釈で打ち壊されたままになっています。武家の棟梁である源氏の発祥が大阪の片田舎とは今まで知りませんでした。
-
通法寺跡に残る山門。源氏祖郷という看板が掲げられています。
-
この辺りは大阪府下でも歴史のある場所だからでしょうか、歴史街道として整備されており案内板もあります。
-
通法寺から200メートルほど離れた小高い丘の上にある源義家の墓所。八幡太郎義家は武家の棟梁として神格化されています。大昔の大河ドラマで名前は覚えてましたが、奥州の人かと思っておりましたが私と同じ河内の人だった(転勤で全国を転々としているのも同じです。)というのは少々感動です。墓所は小高い丘にさらに高く塚が築かれています。石で囲いがされておりますが、中には大きい木が生えております。
-
義家の墓所になっている塚の下には多くのお墓が一直線になって並んでおります。お墓の字の判読はできませんでした。
-
義家の祖父にあたる頼信の墓所は義家の墓所から100メートルほど離れた丘の上に小さめの塚の上にありました。この辺りは葡萄畑に囲まれており、ビニールハウスに取り囲まれたようになっています。
-
通法寺跡から北方へ500メートルの辺りにある河内源氏の氏神である壺井八幡宮です。ここは源頼義が京都府八幡市にある岩清水八幡宮を勧進して造営しましたが、源氏自体の基盤が東国にシフトしてゆくに伴い源氏の氏神の座も鎌倉の鶴岡八幡宮に移ることとなり、意外とこじんまりとした神社になっています。とは言えお正月は参拝客も途切れずにやって来ておりとんどが焚かれていました。
-
「吹く風をなこその関と思へども道もせに散る山桜かな」の碑です。昔の小学唱歌です。
-
壺井八幡宮のある丘の麓にある湧き水、壺井水です。近年までは飲用水だったそうですが、今では濁って飲めそうにもありません。
-
壺井八幡宮から東北に5キロほど、奈良県との境にある景勝地「どんづる峰」です。まっ白い凝灰岩が露出してます。ここの地層には柘榴石(ガーネット)が含まれていると昔地学の教科書か副読本で学んだ記憶があります。いろいろ探しましたが凝灰岩ばかりでそれらしきものは見当たりませんでした。次回はじっくり探してみようと思います。
-
同じような景色が続きます。それにしても不思議なところです。ここは昔の石切り場だそうで、高松塚古墳の石棺もここの石で出来ているらしいです。
-
どんづる峰から上ノ太子よりに下ってきたあたりに地図では「牡丹洞」という表記があります。この辺りは何度も通っていますがそれらしき洞窟は見たことがありません。で、行って来ました。道路から上方向の近鉄南大阪線に人一人が通れる踏切があります。この踏み切りはこの上のみかん畑に入るためのものだと思われますが、牡丹洞はどうもこの辺りです。結局分かりませんでした。牡丹洞も昔の石切り場の跡地のようでした。
以上、お正月に行くところか、というご批判を承知の上での史跡周りでした。
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?


















![Solitary Journey [1167] 春の旅日記、自由気ままな車旅③~想い出さがして<新沢千塚古墳群>橿原市&<叡福寺>大阪府太子町](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/travelogue_album/10/75/83/240x180_10758365.jpg?updated_at=1365080660)

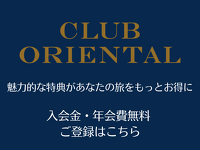








0
13