
1970/05/06 - 1970/05/08
10位(同エリア17件中)
![]()
KAUBEさん
- KAUBEさんTOP
- 旅行記34冊
- クチコミ0件
- Q&A回答0件
- 54,950アクセス
- フォロワー5人
貧乏客船の35日(9)紅海を行く
インド洋を渡り切って、船は仏領ソマリランドのジブチを経て紅海に入った。
このあたりで、もうぼくたちの退屈は半端なものではなくなっていた。ぼくたちはありとあらゆる退屈しのぎを思いついては、大小の騒ぎを繰り返した。
ジブチ5月6日〜5月8日スエズ運河
●紅海の幅
ジブチは小さな港だった。
町というほどの家並も見えず、砂漠を渡ってくる熱風が、木陰一つない港に砂埃を舞い上げる様子を見て、さすがに誰も船の外に出る人はいなかった。
ぼくたちも上甲板からそんな殺伐とした港の風景をしばらく見ていたが、やっぱり食堂に戻って出航を待つことにした。
船はいくらかの荷物を上げ下ろししただけで、その日の午後ジブチを出航し、紅海に入った。
紅海はあんな細長い海だから、ちょうど川下りみたいに両岸の風景が楽しめるかな、などと単純に考えていたが、
両岸の風景が見えたのはジブチを出てすぐ、紅海の入り口のくびれたところだけで、あとは意外に広々とした海の風景が広がった。
「何や、紅海て広いんやな」
北川が言い、曽我部が相槌を打った。
二人ともちょっと不満そうだった。
ぼくも。
何日も海しか見えなかったインド洋の退屈な風景が、つい紅海にへんな期待を持たせたのかもしれない。
ぼくたちは事務所の脇に貼ってある地図を見た。
「うーん、これは250キロから300キロはあるよ」
北川が地図上で紅海の幅を計りながら言った。
「東京・大阪の半分はあるちゅうことや」
「船からの距離はその半分として100キロ以上ある」
「両岸の風景なんか見えへんの当たり前や」
「そういうことや」
思いがけない発見だった。
それでも、両岸にはぼんやりと陸地らしいものが見える。右はサウジアラビア、左はエチオピア、と、ついでに地図で確認した。
エチオピアのほうから強い風が吹いていて、紅海は白波が立っていた。
そして、そのわりには船はほとんど揺れていない。
「そうか、船は海が深いと揺れるんやな」
インド洋では荒れてないのに揺れた。
ここではこんなに波立っているのに揺れない。
ぼくたちは海の深さと船の揺れの関係についてそんな結論を出し、納得した。
甲板に戻ると生暖かい風が激しく吹き付ける中に美恵子さんが海を見ていた。
長い髪の毛が強風でひらひらと舞っている。
晴れいるのに、空は真っ白に曇って、太陽が赤い円盤状に見えた。
砂漠から舞い上がった砂が空を覆っているのだと、美恵子さんが言った。
「さっきピンポンが教えてくれたの」
甲板にもざらざらしたものが積もりはじめている。
髪の毛の中もすでにざらざらしている。
あまりいい気持ちではない。
「ここにこうして立ってると私たちも砂だらけね」
美恵子さんはそう言いながら涼しい顔でそこに立っていた。そしてぼくもそうした。
そんなふうにぼくが美恵子さんと話しはじめると、北川たちはいつもすっといなくなる。
「あはは、気をきかしてるんですよ」
北川はそんなことを言って笑った。
でもそのうち口の中までざらざらしてきて、とうとうぼくたちも食堂に退却した。
風の吹いてくる方向から西日が差して、とても快適とは言いがたい砂漠地帯の船旅が始まっていた。
●退屈しのぎ
何の娯楽施設もない三等船客の退屈はその極に達していた。退屈しのぎはまず内輪の小さなトラブルから始まった。
すでに五十に手が届く年齢と思われる画家のNさんは、かねがね目に余る存在であったぼくたち三人の、とりわけ北川の言動にしきりにクレームをつけ始めた。
下駄履きでディナーの席に出るとは何事か、
国際社会におけるマナーがなっていない、
そもそもきちんとした目的もなく放浪など不真面目きわまる、エトセトラ・エトセトラ。
「言わせとけ」
北川は鼻で笑って取り合わなかった。
「オッサン退屈なんや」
「退屈やったら俺らのアラ拾うより絵でも描いたらええのにな」
「そういうたら、オッサン絵描いとんの見たことないな」
彼は、さぞ端正で、何の面白味もない絵を描くだろうと思った。
一方、京都で会社勤めをしていたという、会社勤めというよりはずっとケバい、風俗商売風の二人の女は、結局何のためにヨーロッパに行くのかよくわからず、あれは売春旅行だと噂されていた。
そこへ、甲板の隅で船員といちゃついていたとか、パーサーの部屋から出てくるのを見たとか、まあうなずけなくもないような噂が流れた。
そしてそのことで、ローマに美術の研究に行くというYさんが「私たち日本女性に恥じをかかせた」と、二人に食ってかかり、救いがたいゆがみ合へと発展した。
「知らん顔しとこな」「ウン、それに限るよ」
その件も完全に無視した。
喧嘩といえば、ボンベイからたくさん乗ってきたインド人乗客もよく食事の席で喧嘩をした。
食事を中断して取っ組み合いの乱闘を演じたりするのを見ていると、まだわが日本チームのは、一応「国際社会」を意識してか、いくら議論が白熱してもアクションにまでは及ばないのがせめて救いだった。
「この退屈がいかんのやな」
「なーんもすることないし、目に入るもんいうたらこの狭い社会の他人の行動やから」
その日も、そんなふうに退屈をもてあまし、
部屋に戻って昼寝でもしようや、
と三人で薄暗い階段を下りてきたのだった。
「なあ、この下はどうなってるんやろか?」
廊下の途中に一箇所、マンホールのふたのようなものがある。北川はそう言いながらもうそのふたに手をかけていた。
「わあ!」
階段が現れた。その下に結構広い空間が見える。
当然のようにぼくたちはその狭い階段を下りた。
かすかにリズムを刻んでいたエンジン音がにわかに大きくなった。
階段を下りきったところは細い廊下になっていて、そこを音のするほうに少し歩くと、音はどんどん大きくなった。
「エンジン室や」
「おう、ダイナミックぅ!」
そんな声はもう聞こえなかった。
ガンガンとものすごい音を立てて無数のピストンが上下動を繰り返している。
ぼくたちは思わず耳をふさいでそこを離れた。
廊下をさらに進むとエンジン音は遠ざかり、その代わりに香ばしい匂いがしてきた。
「パンの匂いや」
廊下の左手に大きなパン工場があった。
そこは廊下との間がガラスで仕切られていて、中がよく見える。
「あのパンはここで焼いてたんやな」
「そうか、そういうことやったんか」
毎日食堂で出されるパンはきっちり三日周期で鮮度が変わる。
不思議といえば不思議だが、そのことを深く考えたことはなかった。
ついでに言うと、あのクソミソの残飯ディナーだが、パンだけはうまかった。
食べる楽しみを奪われたぼくたちに、唯一これだけは救いだった。
「ここで三日ごとに焼いてたんや」
「いや、毎日焼いてるんや。パン職人が三日に一回しか働かへんわけないやろ。一、二等のは毎日焼いてるんや」
「違う。一等は毎日、二等は一日おき、三等は三日ごとや」
「どうでもええわな、そんなこと」
「ははは」
ぼくたちはそのパン工場の様子をしばらく見学していた。
電灯がこうこうとパン職人たちの手元を照らしていて、ほの暗い廊下のことは見えないらしく、職人たちはぼくたちに気付くことなく、黙々と働いていた。
ぼくたちはさらにへさきのほうに進んだ。
やがて廊下は行き止まりになっていたが、
ちょうど「上がっておいで」と言わんばかりにそこに梯子がかかっていた。
当然のようにそれを上がって天井の鉄板を押し開けると小汚い空間に出た。
そこは明らかに船員たちの空間と思われ、ここで船員に見つからないほうがよいことはわりとはっきりしていた。
ぼくたちはその上につながる梯子を急いで上がってまた天井板を押し上げると、いきなり明るい日差しの下に出た。
あろうことか、そこは一等のプールサイドだった。
床の下からヌウと現れた、いやに平たい身なりの三人に、プールサイドでくつろいでいた一等船客はいっせいにぼくたちを見た。老人ばかりだった。
「どこから来た!」
白服がすっ飛んできた。
「サードクラス!」
北川が大いばりで答えた。
白服はあきれた顔で、ついて来い、とあごをしゃくった。
ぼくたちは一等ロビーの脇を抜けて階段を下り、二等船室の並ぶ中廊下からさらに階段を下りて、三等との境の鉄の扉の前に立った。
「もう来るんじゃない。今度来たら…」
言いながら白服は鉄の扉を開けた。
「今度来たら、あんたたち四等だぞ!」
ちなみにこの船には、船底の大部屋に簡易ベッドを並べただけの、四等というクラスがほんとうにあったのだと聞いている。だがさすがにあまりひどいので最近廃止されたいうことだった。
白服はだいぶ頭にきてるな、ということはよくわかった。
船は紅海を北上してスエズ運河に近づいていた。
退屈しきった三等船客も、ようやく目指すヨーロッパがもうそんなに遠くないことを意識しはじめていた。
●スエズ運河
紅海に入って二日目の夕方、船は今度こそ細くて両岸の風景のよく見えるスエズ湾に入った。
そこで船はいったん錨を下ろし、運河の入口にスタンバイすることになっている。
運河はごく細い人工の水路だから、船は厳密な交通整理のもと、整然と通行させられる。
夜になると順番待ちの船がどんどん増えて、右にも左にも船の灯がたくさん並んだ。
夜が明けても船はまだ停まったままだった。
運河の真ん中で事故を起こした船があるので、停泊時間が少し延びるのだそうだと、北川がピンポンから聞いた情報を日本人社会に伝えた。
エジプト商人が一人、小舟を船腹に乗りつけて甲板に店を出した。
そうでなくてももう退屈のきわみに達していた乗客たちは、いっせいに店を取り囲んだ。
しかし商品はちゃちな細工物のアクセサリーや小物ばかりで、誰も買おうとはせず、ただ取り巻いて冷やかすだけだった。
だが、ここに来てまた停まってしまったカンボジュ号の上甲板では、もうひと騒動起きていた。
甲板から池のように静かな水面を眺めているうちに、ぼくはふと次の暇つぶしを思いついた。
「なあ、この海に魚いるんかなあ」
「そりゃいるでしょう」
「釣れへんかなあ」
「釣れるかもしれんけど、でも道具ないし」
ピンポンに言ってみたらニヤリと笑って、でも思いがけず釣り針が出てきた。
ただ、糸が足りない。なにしろ一万五千トンだ。海面ははるかかなた。
仕方ないから、持っていたタコ糸を手元のほうにつなぎ足して何とか間に合わせた。
針の先にはフランスパンのかけらをくっつけた。
釣りの経験はない。こんなことで何かが釣れるとは全然思ってないが、だからやめとこうとあきらめることは、極限に達していたぼくたちの退屈度が許さなかった。
上甲板に腰を下ろして、糸をはるか下の海面に垂らし、釣りをしているつもりになった。
半裸にゴムぞうりのドイツ人のグループが通りかかって、何が釣れるんだと聞いた。
「マグロ」
わざと大真面目な顔でそう言ってやったら裸の腹を叩いてげらげら笑った。
そのドイツ人たちが次の騒動を起こしてくれたおかげで、ぼくはこのばかばかしいマグロ漁を間もなく切り上げることが出来た。
釣り糸を垂れている海面にいきなり波しぶきが立った。
何だ。
身を乗り出して海面をうかがうと、海面に浮き沈みする人影が見えた。
「何事だ!」
騒ぎはすぐにパーサーに伝わり、また白服がすっ飛んできた。
コロンボの港での北川の「事件」のときと同じように、顔面が硬直している。
「あのドイツ野郎に縄梯子を下ろしてやれ」
甲板はいつの間にか観客席になっていて、あのときと同じようににぎやかにはやし立てる。
ここから海に飛び込んだら10ドル、で賭けをしたのだそうだ。
そしたらあいつが、つまり今水面でもがいているやつが「よし、俺が」なんていきなり飛び込んだらしい。
彼は、あのときの北川と同じように縄梯子を揺らしながら上がりきると、観客に向かって高々とVサインを出した。パーサーは大げさに両手を広げ、フランスなまりの英語で聞こえよがしにぼやいた。
「何かあるといつもドイツ人か日本人だ。まったく」
それから船はまだ一昼夜停泊して、次の日の朝ようやく動き出した。
スエズ運河は狭い水路で、両岸の白っぽい建物や、砂ぼこりを上げて走り去る車、岸辺で船の往来を眺める人たち、といった風物がよく見えた。
運河を抜けたところで船はポートサイドに寄港したが、乗客の下船は中止で、積荷を忙しく上げ下ろしするとすぐに出航した。
本来ここには一昼夜停泊する予定で、ピラミッド見学のオプショナルツアーも組まれていたが、運河の通過に時間を食いすぎたため、そんな予定もみんなキャンセルになった。
「いよいよ来ましたねー」
「地中海やなあ」
「うん、ヨーロッパが匂ってくる」
ヨーロッパに遠大な夢を描き続けてここまでやってきたぼくたちには、地中海の名はそれだけで感動的な響きを持っていた。
翌朝早く、船はイタリアの最南端、シチリア島の島影を右手に見て西に向かっていた。
「シシリー」
ぼくの後ろで声がして、アメリカ人のスーザンがいつもの、ボンレスハムの太もも丸出しの短パン姿で立っていた。
「イエス、シシリー」
そして、ぼくもスーザンもそれ以上は何も言わず、初めて見るヨーロッパの島影を追った。
明朝はバルセロナ。
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?












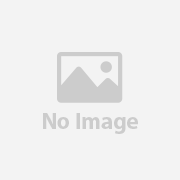





0
0