
2022/04/20 - 2022/04/20
2位(同エリア471件中)
![]()
montsaintmichelさん
- montsaintmichelさんTOP
- 旅行記392冊
- クチコミ0件
- Q&A回答0件
- 3,390,473アクセス
- フォロワー169人
「日本の三大名藤」をご存じでしょうか?「牛島の藤」(埼玉県春日部市)、「春日野の藤」(奈良春日大社)までは容易いかもしれませんが、もうひとつは大阪市福島区にある「野田の藤」です。
学問の神様 菅原道真が太宰府へ左遷される際、河内道明寺を経て、福島玉川の地から舟で九州へ向かったと伝えます。この地に立ち寄った際、改名されたのが地名「福島」です。かつて大阪に数多の島々があった頃、現在の福島は細った島で「鹿飢島(餓鬼島)」と呼ばれていました。その島に道真が立ち寄った折、里人の徳次郎が旅情を慰めたのをいたく喜び、その地名では不憫だろうと反対の意味の「福島」と名付けたと伝わります。
両脇を淀川と堂島川に挟まれた野田・福島エリアを巡ると、『平家物語』にも記された「逆櫓戦略論争の地」や本願寺と織田信長の主戦場だった野田城址、大坂冬の陣の前哨戦「野田福島の合戦」など、数々の歴史を彩った舞台に遭遇します。その一方、かの秀吉も愛でたという「野田藤の名所」が日常のあわただしさを癒してくれます。黙して語らぬ野田藤が見つめ続けてきた「野田福島の歴史絵巻」を紐解いてみることにしました。
- 旅行の満足度
- 5.0
- 同行者
- カップル・夫婦
- 交通手段
- 私鉄
-
阪神電鉄 普通電車5700系
「のだふじ巡り2022」のアプローチは阪神電鉄「野田駅」からスタートです。
アクセスには阪神電車を利用いたしました。
普通用車両としては20年振りのフルモデルチェンジ車両として2015年に颯爽とデビューしました。1959年から製造されていた「5201形」の後継車両です。従来の高加減速性能を継承しつつ、最新技術を導入したステンレス車体に普通車両伝統の「カインドブルー」を配色しています。愛称は「ジェット・シルバー5700」。2016年には鉄道友の会より「ブルーリボン賞(第59回)」を阪神電鉄の車両として初受賞しています。
これから向かう「藤見」にはうってつけのボディーカラーに期待が膨らみます。 -
阪神電鉄 野田駅
停車中の車両は急行9000系で、阪神・淡路大震災の震災復旧車両として導入されたステンレス車体の急行用車両です。車体は「ジェットシルバー」以来となるステンレスを採用しており、「ビバーチェオレンジ色」のラインが特徴です。
左端手前のビルが阪神電鉄本社が入居している阪神星光ビルです。その後方が1999年に竣工した阪神野田センタービル(19階建、地上高88m)です。 -
「のだふじ巡り2022」マップ
マップは大阪市HPから入手できます。また、野田駅でも入手できます。
尚、「のだふじ巡り」は福島区内の藤棚を巡るイベント(4月9日~4月23日)ですので、場所により開花状況が異なります。事前に開花状況をhttps://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/page/0000194121.htmlでチェックされると良いかもしれません。
このマップは次のサイトから引用させていただきました。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushima/cmsfiles/contents/0000562/562967/ura.pdf -
③海老江東公園
野田駅を出て、まず駅周辺の北方面を攻略します。
③は便宜を図るためマップにある番号を引用しています。
イオン野田阪神店の北隣に2016年にできた比較的新しい公園です。その一画に立派な藤棚があります。
因みに、イオンの南側にも藤棚がありますが、タイミングが遅かったのか、すでに房が切り落されていました。藤は、房の上の方が散り始めるタイミングで房をカットするそうです。そうすることで来年も綺麗に花が咲くそうです。花が終わってそのままにしておくと、実を付けようとして木に負担がかかるので切り落とすようです。 -
③海老江東公園
2016年にできた公園との情報を得ていたため正直なところ藤には期待していませんでしたが、意外にも立派な房が沢山垂れていて吃驚です。
公園には誰もおらず、意外と穴場なのかもしれません。 -
③海老江東公園
風と戯れて藤波となる薄紫色の房を見つめていると時間が止まったような気持ちになります。
癒し効果抜群です! -
阪神野田センタービル
阪神電鉄本社(手前のビル)に隣接する高層オフィスビルです。
アイテック阪急阪神本社や中央電設本社、ケーブルテレビ局のベイ・コミュニケーションズ(Baycom)本社などグループ企業が多く入居しています。 -
27:阪神野田駅前広場
野田駅の南側に藤棚があります。
阪神電車と藤のツーショットを撮りたかったのですが、なかなか良い場所が見つかりませんでした。
時間的な制約もあり、旅行記の表紙に掲載した写真がベスト・ツーショットです。 -
27:阪神野田駅前広場
間近で見ると鮮やかな紫色の花が咲き誇り圧巻です。
「野田の藤」の起源は鎌倉時代まで遡り、南北朝時代には南朝方(後醍醐天皇から4代、建武政権)が誇る「吉野の桜」(関西桜の名所)に対抗し、「野田の藤」は北朝方(光厳天皇から5代、室町幕府側)の誇りとされたほどです。
樹木の歴史を鎌倉時代から現在に至るまで文献で辿ることができる事例は珍しく、「野田の藤」はさながら「大阪の植物文化の象徴」と言えます。 -
21:野田新橋筋商店街
阪神野田駅からJR野田駅へと繋がるウナギの寝床を彷彿とさせる細長い商店街で、1~6番街まであります。アーケードを抜けた先はJR大阪環状線の高架下です。
こちらは「野田藤ポイント」がもらえる商店街として地元では人気のようです。
また、年に数回「100縁笑店街」を開催しています。78店舗が様々な100円商品を提供する他、500円、1000円などでお買い得商品を販売する「ポッキリ商品市」を同時開催するイベントです。各店が選り抜きの100円商品を用意することにより商店街全体をひとつの100円ショップに見立てる商店街活性化事業のひとつで、平成16年に山形県新庄市の新庄南本町商店街でスタートし、これまでに全国100を超える市町村で実施されているそうです。
商店街も生き残りをかけて様々な企画を考案してチャレンジしているのが窺えます。 -
21:野田新橋筋商店街5番街
マップにある商店街の5番街エリアに秘密の「藤の名所」があるのかと思いきや、苗木の販売所のことのようです。
「まちの電気屋 きょうりつ」前の特設販売所で1鉢1800円で「のだふじ苗木」が販売されていたようですが、訪れた時には完売しておりました。
写真は商店街の奥にある花屋「花翔」で見かけた「のだふじ苗」です。値段はともかく、普通に花屋さんでも売られているようです。 -
⑬春日神社
福島区玉川2丁目の閑静な住宅地の道路に面した一角にひっそりと佇んでいます。現在の春日神社は小さな祠があるだけですが、かつては広い境内を誇ったそうです。野田・玉川界隈は藤の一種である「野田藤発祥の地」とされます。その昔、この地は難波の西端に当り、大阪湾に伸びた砂州(野田州)の湿地帯であり、野田郷と呼ばれる難波八十島が浮かんでいました。そこに洪水などで上流から土砂と共に藤の木が漂着して根付いたのが野田藤です。松の木に絡まって自生し、雲のように一面に広がる雄大な景色を誇ったようです。
野田藤の起源は鎌倉時代初期(13世紀)とされます。 -
⑬春日神社
近年は神社の所在すら知る人も少なくなったと言われるほどですが、室町時代から藤の名所として知られていたことから「藤之宮」とも呼ばれ、江戸時代には藤の名所として浪速名所のひとつに数えられました。幟にも「藤之宮」の文字が躍っています。尚、「玉川」の地名の由来は、神社の横を玉川という名の清流が流れていたことに因みます。
江戸時代に刊行された『摂津名所図会』には、春日神社は「野田村林中にあり。当所、藤によりて藤原の祖神を祭るならんか」とあります。また、『藤伝記』では藤原氏の分流である藤原藤足がこの地に移り住み、祖神である春日明神を奈良 春日大社から勧請したことが創始ともあります。春日大社も藤の名所ですから、藤原氏の末裔が野田藤が咲き乱れる玉川に春日明神を勧請するのは理に適ったことと思えます。
その後、野田村の庄屋であった藤家の氏神として祀られ、主祭神に天児屋根命、相殿に天照皇大神と宇賀御魂神を祀っています。 -
⑬春日神社
周囲を藤棚が取り囲むように小さな祠があります。
野田藤の最初の危機は戦国時代の1533(天文2)年のことでした。本願寺10世 証如が野田で佐々木(六角)定頼の兵に襲われ、門徒21人が討死した「本願寺騒動」で春日社が焼失した時です。しかし、僅かに芽を出した藤のひこばえを再生させ、『摂津名所図会』によると江戸時代には茶店などで賑わうほどに復興しています。その後、明治時代以降の急激な都市化によりかつての賑わいは昔語りとなり、僅かに残された藤棚も太平洋戦争の空襲で殆んど焼失し、1950(昭和25)年のジェーン台風の大阪直撃や公害問題、阪神高速3号神戸線開通などでこの地の野田藤は壊滅状態になりました。
現在に至る復興のはじまりは、1970年代に大阪福島ライオンズクラブの働きかけにより住民らが復興活動を始めたことでした。往時第3副会長だった藤田正躬氏は阪神高速道路建設に伴う立ち退きで庭がなくなる藤家を訪ね、残っていた2本の野田藤の枝を挿木用にもらったそうです。藤を植え、棚を整備して約60カ所・140棚にまで増やし、野田は再び藤の名所へと蘇りつつあります。 -
⑬春日神社
境内には牧野富太郎博士による「ノダフジ」命名のきっかけとなった、「野田の藤跡碑」があります。富太郎は藤家の庭の藤を調べて「ヤマフジ」とは別種であることを発見し、野田の地名を取って名付けたそうです。現在、日本に自生する藤はノダフジとヤマフジの2種ですが、それ以前は別種として分けていなかったようです。「ノダフジ」は花は小型ですが花穂が長いのが特徴です。中には九尺藤と言われるものもあり、春日大社にある「砂ずりの藤」も同じ仲間です。 -
⑬春日神社
平安時代末期~鎌倉時代前期にかけての公卿・歌人である西園寺公経はこの付近を領地としていた時に「野田藤」を詠んでいます。
「難波かた 野田の細江を 見渡せば 藤波かゝる 花の浮き橋」
一説には往時の太政大臣であった西園寺公経が祖神を祀る当社を創建したとも伝わります。ただし、この説は時代が合いません。また、往時の太政大臣は西園寺家の出身ではあるものの、今出川兼季でした。
室町時代の1364(貞治3)年に2代将軍 足利義詮が住吉詣の帰途にこの地で藤を鑑賞し、「野田の玉河と云所あり、このほとりに藤の花咲き乱れたり」と記し、次の歌を詠みました。
「むらさきの 雲とやいはむ 藤の花 野にも山にも はいぞかかれる」と石碑に刻まれています。
また、「いにしえの ゆかりを今も 紫のふし浪かかる 野田の玉川」とも詠みました。
更に、1594(文禄3)年には、豊臣秀吉も千利休や曽呂利新左衛門をお供に藤見に訪れて茶会を開き、「吉野の桜、野田の藤、高尾の紅葉」と童歌にも歌われるほどの名所となりました。この時に休息した茶店「藤亭」で藤の木の根を切って額を作り、そこに落語家の始祖とも言われる秀吉のお伽衆だった曽呂利新左衛門が「藤庵」と揮毫した額は今でも藤家の家宝です。
江戸時代には全国的な知名度を誇るほどになり、1700年代には上方へ来た商人や武士は土産として野田藤を持ち帰り、宇和島 「天赦園」や福岡県「中山の大藤」などの名所を生んでいます。
今でも「野田の藤」は「牛島の藤」(埼玉県春日部市)や「春日野の藤」(奈良春日大社)と並び「日本の三大名藤」のひとつに数えられています。知名度は低いのですが…。 -
⑬春日神社
残念ながら、藤の房は切り落とされた後でした。
春日神社境内にも戦前まで藤の古木があったそうですが、空襲で焼失したそうです。現在ある藤は宇和島市にある国指定名勝「天赦園(日本庭園)」から2000年に里帰りしたものの1株です。これは宇和島5代藩主 伊達村候(むらとき)が、参勤交代の途上大坂を通過した際、野田藤の苗木を宇和島に持ち帰り、国元の邸内で育て上げたものの子孫に当たります。 -
白藤大神
春日神社の境外末社と思われ、かつては野田藤に所縁のある藤家の邸内社だったのでしょう。
祠に向かって左手に古井戸があります。
足利義詮がこの地に遊びに来た時に「野田の玉川」を詠んでおり、その川の名残がこの古井戸だそうです。 -
影藤大神
高速道路の高架下の一般道「新なにわ筋」南行きの歩道沿いに遠慮がちに鎮座しています。赤い鳥居が立ち、その奥に小さな祠があるだけの、とても手狭な境内です。
ここも野田藤に所縁のある藤家の邸内社でした。
春日神社が大きな神社であった頃の名残のひとつです。 -
影藤大神
激しい空襲にも焼けず奇跡的に今日まで残り、焼け野原から復興して着々と発展し続ける野田の町並みをじっと見守っているかのようです。
「野田の影藤」は藤の花が民家の障子に影を投影する様子を言うそうです。
随筆『在京在阪中日記』(1866年)には「野田の藤と申て、かげふじ名高き物也」とあります。藤にはそんな風流な愛で方もあったのですね! -
⑭玉川南公園
春日神社の西隣にある小公園です。
小さいながらも花壇はしっかりメンテされています。
ここには野田藤では希少な存在となる「白藤」の藤棚があります。
白藤神社の近隣にあるという所縁があるのかもしれません。 -
⑭玉川南公園
江戸時代の庶民の藤見物の様子が絵双紙『花の下影』に描かれています。
酒に酔った町人が川柳を短冊に書き、それを高々と掲げて自己陶酔しています。要するに「花より団子」で藤を愉しんでいたようです。横に置かれた重箱の中身は「藤菜飯田楽」だそうです。これは明治時代に至るまで野田の名物でした。
つまり、現在の「お花(桜)見」に近いものだったようです。 -
⑭玉川南公園
白藤は香りも強く、近づくだけで甘い香りに包まれます。
シロバナフジ(白藤)にはヤマフジの品種もありますが、つるが上から見て右巻きですので野田藤の品種のようです。 -
⑭玉川南公園
上部にある大きな花弁は「旗弁」と呼ばれます。
白色の藤の花言葉は「可憐」「歓迎」「恋に酔う」です。
白藤は古い時代から歌にも詠まれた優雅な花でもあります。
因みに、紫色の藤の花言葉は「君の愛に酔う」です。
花が房のように連なって咲く姿から、徐々に愛が深まっていく様子を表しています。 -
⑰玉川西公園
静かな住宅街の一画にある小公園です。
ここにも立派な藤棚があります。
こうした児童公園に藤棚を植樹するのは、スペースの関係でやむを得ないことなのかもしれません。しかし、藤=クマ蜂というイメージが払拭できず、子どもたちが蜂に刺されないか心配でもあります。 -
⑰玉川西公園
藤はマメ科フジ属の落葉蔓性植物です。別名「雪中花」とも呼ばれます。
自ら大木にはなりませんが、大木に寄り添って大きくなります。また、生命力が強く、先端を切っても別の場所から芽が伸びるそうです。
更には長寿の木でもあります。例えば、山崎の大歳神社の千年藤は樹齢1000年、春日部市の牛島の大藤は樹齢1200年です。藤には年輪がないため樹齢は判断し難いのですが、これらの藤には、誰が何時植えたという、植えた時の記録が残されているため正確な樹齢が分かるそうです。 -
⑯玉川コミュニテ ィセンター
自治区の集会所と思われます。
柵があるため中には入れず、外から眺めるだけです。 -
⑯玉川コミュニテ ィセンター
ここには「二十一人 討死之碑」があります。本願寺第10世 證如上人を守るために討ち死に した門徒宗21人の碑です。玉川地区には4基の同様の碑があり、この石碑は1940(昭和15)年に西野田青年団が生涯橋の西側 に建てたものを現在の位置に移設したものです。
下福島中学校のプール建設のため1977(昭和52)年に現在地へ移されました。 -
⑯玉川コミュニテ ィセンター
1533(天文2)年8月9日、当地を訪れた證如上人は、近江の佐々木(六角)定頼と法華宗徒に襲撃されました。この時、本願寺第8世 蓮如上人の教化を受けていた野田・福島の一向宗門徒の百姓たちが證如上人を守護せんとして鋤・鍬・鎌などで果敢に戦いました。そのおかげで證如上人は小船に乗って無事泉州方面へ逃れましたが、この戦いで信徒21人が犠牲になりました。時に證如上人は17歳でした。 -
居原山 円満寺 (西本願寺末寺)
1533(天文2)年、證如上人を守るために殉教死した21人 の菩提を弔うため、久左衛門が證如上人より教圓という名を授けられ、1534年に一宇の坊舎を建立しました。これが摂州野田円満寺のはじまりです。創建時は摂津国下仲嶋野田村惣道場と称していました。境内には證如が与えた感謝の書状と供養碑があります。
信仰のために命までも捧げた野田村の人々。命を捧げてまでも守り通したいものがはたして自分にはあるのか?圓満寺の縁起を記しながら改めて深く考えさせられました。 -
清浄山 極楽寺
真宗大谷派(東本願寺)の野田御坊です。
本願寺第10世 證如上人襲撃事件で命を落とした村人の菩提を弔うため、教如上人の御代に門徒衆の墓所に一宇を建立したのが極楽寺です。
江戸初期には、大坂・南御 堂(難波別院)の掛所となり、その後、野田御坊として今日に至ります。
境内には「21人討死の墓」がありますが、現在は浄土真宗東本願寺派の末寺で菩提寺ということで一般人は立ち入れません。本尊は阿弥陀如来です。 -
清浄山 極楽寺 野田城跡伝承地
山門の右側に「野田城跡」の石碑が立っています。
1531(享禄4)年の頃、三好元長と細川晴元が対立し、三好方の浦上掃部の軍勢が野田・福島に陣取った際に砦を築いたのが野田城の起源とされます。
1570(元亀元)年に三好三人衆と織田信長が対立すると、打倒信長を目指す石山本願寺が呼応して三好勢と共に籠城しました。こうして石山合戦が始まり、1576(天正4)年に明智光秀・荒木村重の猛攻により落城しました。
現在、野田城の遺構は全く残っていませんが「城之内」「弓場」という地名が明治時代初期まで残されていたことから、玉川付近にあったと推察されています。 -
清浄山 極楽寺
寺院の築地塀の外側には「討死」という文字を刻んだ物騒な石燈籠があります。
これも本願寺第10世 證如上人襲撃事件の遺産のひとつです。
1532年、江洲観音寺の城主 佐々木定頼は念仏宗門の本願寺の繁栄を妬んで法華宗徒を集め、3千人の軍兵で山科本願寺を不意打ちしました。その際、證如上人は石山本願寺へ逃げるため三島江(現 高槻市)へ向かいました。それを知った野田の一向宗徒600人余りは、舟で證如上人を野田御堂に迎え、身命を捨てて上人を護りました。その後、無事に石山御坊へ入られました。その翌年、上人は僅かな家臣をお供に要地として知られた野田福島を見聞されました。それが敵に知られ、野田の芦の原っぱに潜む伏兵に襲われました。これが證如上人襲撃事件の全貌です。 -
⑮野田恵比須神
社伝によれば、113(永久元)年、当地開発の際に恵比須神を勧請したのが起源とされます。神社に保存されている御影石の建石 には「永久三乙未年三月」と刻まれています。往時この周辺は「難波八十島」と呼ばれる淀 川の河口部に当り、漁業の神として恵比須神が信仰される地域でした。そのことから、野田・福島の漁民の守り神として信仰されていたと考えられています。 -
⑮野田恵比須神
野田恵比須神社の存在が漁業が盛んであったことを偲ばせますが、大阪がまだ海で島が沢山あった頃、大量の土砂と共にヤマフジが島に漂着して根付いたものが「野田藤」と呼ばれ、全国に広まりました。室町時代から明治時代までは「吉野の桜か野田の藤」と称されたほどでした。 -
⑮野田恵比須神
ご祭神は
事代主大神
(託宣を司る神。釣り好きの為、海と関係の深いえびすと同一視される。)
天照皇大神
(日本人の総氏神)
八幡大神
(応神天皇。武運の神。) -
⑮野田恵比須神
本殿の裏側、石鳥居の近くに立派な藤棚があります。僅か2株の藤が数多の房を垂れていますが、これには長い歴史が担われています。
かつての境内は巨樹が鬱蒼と生い茂り、森林を彷彿とさせるスケールがあったそうです。この巨樹に野田藤が絡みつき、藤色に染まった雲のような景観はは野田藤・玉川藤と称され、その名遠近に聞え、難波名所のひとつとして来遊した人々が多かった様子が絵巻より偲ばれます。 -
⑮野田恵比須神
戦国時代にこの周辺に野田城という城郭が築かれ、この社も城郭の一部に取り込まれたと考えられています。また、安土桃山時代には織田信長と三好三人衆との間で野田城・福島城の戦いが繰り広げられ戦乱の地と化しました。そのような中、野田城の守護神の他、武士たちの信仰の対象ともなりました。
元亀年間(1570~72年)に三好山城守入道笑岩が当地に築城してからは城内守護神として尊崇されたようです。社に記録がないのは、この地は度々水害に遭い、また、しばしば兵乱の巷となったからと思われます。 -
⑮野田恵比須神
藤の全般的な花言葉は「優しさ」「歓迎」「決して離れない」「恋に酔う」「忠実な」です。
藤の花が女性を象徴するように、花言葉にも女性的な意味合いが多く含まれます。
藤の花姿が、深く頭を垂れ、美しい姿で相手をもてなそうという気持ちを連想させることに因みます。 -
⑮野田恵比須神
「決して離れない」という花言葉には深い意味が込められています。
日本では古来「藤を女性」「松を男性」に喩え、藤と松を間近に植える習慣があったそうです。
藤の花姿は振袖姿の艶やかな女性をイメージさせます。そしてその藤が男性である松の木に巻き付く姿が、「一度捕まえたら二度と離さない」と言う恐ろしいほどの執着心を連想させます。 -
⑮野田恵比須神
現在の「野田藤」からかつて称賛されていた頃の花姿を想像するのは難儀ですが、敢えて喩えるなら、世界一美しい藤とも称される「あしかがフラワーパークにある迫間の藤」ではないでしょうか?
樹齢約140年、幹周3.6mもの大藤で、足利市の天然記念物にも指定されています。
因みに、「迫間の藤」のルーツが「野田の長藤」です。野田藤の子孫が姿を変え、遠く足利の地で、先祖の名を汚すことなく美しい花姿を今に伝えています。 -
⑮野田恵比須神
藤は、縁起が良い木でもあり、悪い木でもあります。
寿命が長く、藤という言葉の響きが「不死」に近いため、縁起が良いと言われます。一方では逆に「不治の病」を連想させてしまうこともあり、病気の方へ贈るには適さないとされます。 -
⑫玉川ひばりこども園
社会福祉法人 麦の穂が運営する幼保連携型認定こども園です。
ここの園庭内に藤棚があります。 -
⑫玉川ひばりこども園
周囲は鉄柵で囲まれているため、ここではコンデジが重宝します。
ここに通園している子どもたちはこんな藤の房を見ながらすくすくと育っていくのですね!
子ども園ですので長居すると怪しまれます。
ご注意を! -
⑫玉川ひばりこども園
「藤」の名の由来には諸説あります。長く垂れ下がる花の姿を「フキチリ(吹き散り)」や「フサタリハナ(房垂花)」と呼び、それらが転訛して「フジ」になったとする説。
また、ツルが鞭(ムチ・ブチ)の材料になることから「ムチ・ブチ」が「フジ」に転訛したとする説などです。 -
⑫玉川ひばりこども園
藤棚だけでなくステンドグラスも見所です。 -
⑫玉川ひばりこども園
ステンドグラスを嵌め込んだ円窓がアクセントになっています。 -
モッコウバラ
背丈のあるモッコウバラです。
バラ科バラ属の常緑性蔓植物で、中国原産です。
和名の由来はインド原産のキク科の「木香」に芳香が似ることに因みます。開花期は4~5月で、バラの中ではいち早く開花する早咲き種です。小輪で可愛い黄色いモッコウバラは、旧姓秋篠宮 眞子内親王のお印の花となったことでも注目されました。小室眞子さんが30年間過ごされたお住まいを後にする際、妹の佳子さまと抱き合われた感動的なシーンでは、眞子さんの手にモッコウバラのブーケがありました。
一般的な花言葉は「純潔」「あなたにふさわしい人」「初恋」「幼いころの幸せな時間」「素朴な美」です。黄色い花の花言葉には珍しく、ネガティブな意味はありません。
「あなたにふさわしい人」は、アーチや支柱などに寄り添って伸びていくつる性のバラの特徴に由来した言葉です。愛おしく恋を育んでいく姿を連想せずにはいられません。
「素朴な美」は、他のバラのように華美過ぎず、どこか懐かしい美しさを感じさせることに由来します。この花言葉には、人の心を掴むようなメッセージが込められているのかもしれません。 -
ベニバナトキワマンサク(紅花常磐万作)
マンサク科トキワマンサク属に唯一分類される常緑樹です。春先に枝先に糸のような花をいっせいに咲かせます。
マンサク科の代表品種のマンサクは落葉性ですが、こちらは常緑性のため「常磐万作(トキワマンサク)」と名付けられました。
マンサクの名は、春一番に咲く「まず咲く」という言葉が転訛したものとされます。また、沢山の花を付けることから、作物の豊年満作を占う植物として古くから親しまれてきました。それ故、豊年満作を祈願して名付けられたとも言われます。
トキワマンサクとして園芸用に流通しているのは、「ベニバナトキワマンサク」という変種です。1972年に中国で発見され、濃いピンク色の花を咲かせることから名付けられました。葉は、新芽の時は赤紫色ですが、生長と共に緑色になる「緑葉」と、紅色が濃くなる「銅葉」のタイプがあります。
花言葉は「私から愛したい」「霊感」「おまじない」です。
「私から愛したい」は濃いピンク色の花はハートの色など恋愛を象徴することに因みます。
「霊感」「おまじない」といったスピリチュアルな花言葉は、同属に分類されるマンサクと同じものです。米国先住民がマンサクの枝を使って占いをしていたことや、東北地方にマンサクの花の咲き具合から農作物のでき高を占っていたことに因みます。 -
シャクナゲ(石楠花)
少し季節を先取りしている感もありますが、青紅葉とのコラボです。
ツツジ科ツツジ属 無鱗片シャクナゲ亜属、無鱗片シャクナゲ節の総称です。
可憐な花を房状に咲かせる姿は見応えがあり、「花木の女王」や「花の王」とも称されます。
シャクナゲが一般的に普及したのは江戸時代以降と言われています。園芸好きの日本人が何故手を出さなかったのでしょうか?その理由は高山植物であったからです。高い山の岩場などに張り付くように咲くシャクナゲは採取が困難であり、「高嶺の花」の由来になったほどです。また日本には古くから山岳信仰があり、山岳の岩場に不似合いな豪華な花は山の精霊の化身とされてきたからです。
花言葉は「警戒』」「危険」「威厳」「荘厳」です。
「危険」「警戒」はシャクナゲが生息する環境に因みます。元々ヒマラヤの高山地帯に生える植物であり、採りに行くのが難儀だったことに由来します。
「威厳」「荘厳」は、高山の奥地に咲いている様子に因みます。 -
福島区の住居表示プレートは野田藤の色に因んだ「藤色」になっています。
-
⑪ユニライフ福島
1979年に竣工した、地上15階建、総戸数492戸の大型マンションです。
その北西の一画に藤棚があります。
花壇に植えられたマリーゴールドもとてもきれいでした。 -
⑪ユニライフ福島
マンション敷地内ですが、一般の方も入れます。
鈴なりに咲く薄紫色の花がとても艶やかでエレガントです!
周りの景観は都市公園にある藤棚の雰囲気を醸しています。 -
⑪ユニライフ福島
ベランダの洗濯物と野田藤のコラボも希少価値あり!
野田藤の説明が書かれた看板もあります。
「此の地は下福島の西北にあり
紫藤多く林中の古松にまとひいて風流也
花盛の頃は、近遠の稚俗ここに来つて幽艶を賞す
樹下に春日の祠 又傍に藤の庵といへるあり
豊太閤御遊覧の古跡といふ」 -
⑪ユニライフ福島
大挙して藤見に来られたら、マンションの住人さんはさぞ迷惑でしょうね! -
⑧下福島公園
右手は大阪市立公共スポーツ施設のひとつの下福島プールです。
子どもスイミング教室などもありますが、運営はコナミスポーツクラブに委託されています。
ガラスへの銀杏の緑葉の映り込みがきれいです! -
⑧下福島公園
紅葉の季節を想像すると胸が高鳴ります。 -
⑧下福島公園
背丈のあるソテツです。
この公園には場違いな気がしますが、1990年開催の「大阪花博」のおさがりでしょうか?
裸子植物ソテツ科ソテツ属の常緑低木です。原産国は日本やインドネシアなどです。6~7月にドーム状に膨らんだ白や黄色の花を付けます。
学名の「Cycas(シカス)」は、「ヤシに似た植物」という意味です。和名「ソテツ」は、木が弱った時、株元へ鉄を打ち込むと元気が戻ったことから「蘇鉄(鉄で蘇生する)」と名付けられました。
花言葉は「雄々しい」です。
自生するソテツは海岸沿いの岩場に多く、巨大なソテツの木が風になびく姿が勇ましさと力強さを感じさせることに因みます。 -
⑧下福島公園
堂島川の畔、堂島大橋北詰に位置します。かつての大日本紡績株式会社(現ユニチ カ株式会社)の主力工場であった福島工場跡地に大阪厚生年金病院などと共に1942年に造営された歴史ある公園です。福島区内では福島公園 に次ぐ古い公園でもあり、面積は区内最大規模(約3.8ha)を誇ります。
現在では高層マンションなどに囲まれており、住民の中庭風の都市公園です。スポーツ施設や遊具など区民に親しまれている公園ですが、中央を大きく野球グラウンドが占めているため開放感に満ちています。随所に設けられた藤棚では紫色の房を伸ばした「野田藤」が見られます。また、純白の野田藤も見られます。 -
⑧下福島公園
公園の南端に聳える大藤の木です。
スケール感を伝えるため人を入れてみました。 -
⑧下福島公園
見上げれば滝のように藤の花が降り注ぎます。 -
⑧下福島公園
野田藤は、つるが上から見て右巻きで、通常50~70cm程度の長い花房を付けるのが特徴です。なかには最長1.8mになるものもあるそうです。
隣の銀杏の木に巻き付く野田藤の雄姿です。まるで銀杏の枝に藤の花が咲いているかのような奇妙奇天烈な状態になっています。
因みに、藤と葛(クズ)が絡み合ってどうにもならない様を「葛藤」と言います。藤の蔓は丈夫で簡単には切れないことで知られており、昔から漁網や山登りのための臨時のロープに使われてきました。 -
⑧下福島公園
「大木に寄り添って大きくなる」とはこういうことなのでしょう。途中から隣の銀杏の木に絡み付いています。
木に絡まった藤は大蛇が巻き付いたような姿で成長し、やがて絡まった木を絞め殺し、絡み付かれた木は枯れます。しかも、枯れ木と同時に地面に倒れた藤は次の狙いを定めて這い上がります。藤は枝を隣の木、そのまた隣の枝へと広げ、しぶとく生き続けます。
かつて、藤原氏は天皇家に絡み付いて一時は天皇家の一部のような存在になりましたが、天皇家を枯らすことなく温存する戦略を採りました。
ここまで辿ってきた名所の藤棚は小ぢんまりした印象でしたが、下福島公園の藤棚はスケールが違います。そして、藤棚がいくつもあります。まさに藤の一大名所と言えます。
下福島公園の詳細レポは青嵐薫風 摂津福島 野田藤絵巻(後編)でお届けします。
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
montsaintmichelさんの関連旅行記
新大阪駅周辺・十三(大阪) の旅行記
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?








































































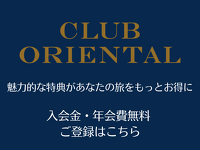







0
63