
2003/01 - 2004/12
4367位(同エリア6094件中)
![]()
KAKUさん
■以前何度か行っている中で、撮影してきたものの中から選びました。車窓や休憩地のわきに珍しい木「原生植物」や「飛べない鳥」やユニークな鳥など、そういったものをピックアップしました。おそらく行ったことがある方はこれらをどこかで見かけられたと思います。また、これから行く方も一度は目にすることと思います。■この表紙の写真はテカポ湖とルピナス。ルピナスは残念ながら外来種で、ニュージーランドにとっては原生種を脅かすということで、喜ばれていない。でも観光客にとっては実は楽しみの一つ。11月下旬から12月終わり頃までに運がよければこのように群生して見られる。
-
◆キャベッジ・ツリー ■当時、根の部分はマオリ人の伝統的なハンギ料理に使われていた。葉の付け根辺りはマオリ人や開拓者に野菜として食べられていた。葉のゆで汁は赤痢に効く薬として飲まれていたということ。この幹は燃えにくい為、開拓者たちは煙突に利用していたらしい。名前の由来は味がキャベツに似ているからという説がある。■よく見かけるエリア ほぼ南島全般と北島でも見られる。観光中では主な場所として、クライストチャーチの郊外やクイーンズタウンからミルフォードサウンドに行く途中などの道端、テ・アナウの町などでも見かけられる。
-
◆キャベッジ・ツリー その2
-
◆ニュージーランド・フラッグス ■葉は細長く、硬くて丈夫。マオリ人はこれを栽培し、葉を石で削ぎ、繊維をくるっと束ねて編んで、服(腰周りにつける)や魚釣り用の網をつくった。ロトルアのファカレワレワでツアーで行くと作り方を見せてくれる。茎と花が黒いのが特徴。これは伝統的に女性の仕事。
-
◆ニュージーランド・フラッグス その2
-
◆タソック ■これは中が緑なので、スノータソック。ニュージーランドの荒野や高地でよくみかける。イネ科の植物。葉は硬く、家畜も食べないので、開拓者たちはこれを刈り取ってきたが、近年、この植物は大気を清浄化する働きがあることがわかり、増やそうと努めている。全体的に赤いのはレッドタソック。これは飛べない鳥の「タカヘ」が食べると以前聞いたことがある。レッドタソックの方は南島のミルフォードサウンドに行く途中で群生地を通る。■スノータソックの方は南島では郊外の丘や山を越える時などその周囲でも見られる。Omarama〜Cromwellで群生地を通る。
-
◆レッド・タソック その1
-
◆レッド・タソック その2
-
◆トイトイ ■ススキの仲間。マオリ人は根に近い部分を食べていた。茎の部分は腎臓病に効くとされていて、そのままかじっていたらしい。ここはクィーンタウンのスカイ・レストランの外。ゴンドラを降りたら、外に出れば見ることができます。
-
◆スイート・ブライアン・ローズの実 ■花は春に咲き、うすいピンク色。実は秋になる。外来種で、昔、ニュージーランドのゴールド・ラッシュ時代にたくさんの中国人労働者がこの地にきた時、ビタミンをとるためにジャムにしていたという。プカキ湖からマウントクックに向かう道の両端に多く見られる。
-
◆スイート・ブライアン・ローズの実 その2
-
◆スイート・ブライアン・ローズの花
-
◆ゴールデンウィロウ ■ヤナギ科。春先、葉がつく前の方がはっきりとわかる。幹が黄色をしていて、まるで秋の黄葉のような感じを受ける。枝が茶色のはクラックウィロウ。クライストチャーチからオマラマに行く途中の湖や川の付近でみかける。
-
◆南洋杉 ■スギ科。茎の同じ位置から正確に6本枝が生える。まるで造花のようにみえる。主に亜熱帯地方でみられる。ニュージーランドでは、北島で見かけることができる。オークランド近辺では、家の庭にたくさん植えられている。この木、オスとメスが仲が悪く、お互いがそばにいると死んでしまうらしい。この写真はメス。オスは枝にモップのように葉がつくという。
-
◆ルピナスの群生 ■ルピナス。英語ではルピーと発音する。もともとはイギリス人が庭用に持ってきた植物だったのだが、繁殖力が強く、自生している植物を脅かすため、現地では雑草扱いされている。11月下旬頃から徐々に咲き始め12月下旬頃まで見ることができる。茎が複数出ていて黄色く咲くツリールピーという種類もある。
-
◆ツリールピーの群生 ■この場所は、クライストチャーチから列車で南島最北端のPictonまで、列車を使って走ったときに撮影。Kaikouraの前後でこのように群生するところがいたるところで見かけられた。これだけ広がるとやはり、原生種に危機感を感じてしまう。
-
◆マウントクック・リリー■2004年の11月16日に撮影したもの。lilyとはいうが実はキンポウゲ科。葉の形がスイレン(英語ではウォーターリリーということから)に似ているのでリリーと呼ばれている。キンポウケ科の中で花の大きさは世界で最も大きい種類のなので正式には「ジャイアント・バターカップ」というそうです。
-
◆マウントクック・リリー その2
-
◆ソフト・トゥリー・ファーン(Katote) ■ニュージーランドのシダ類の中でも大きな種類。8mぐらいまで成長する。この場所はキャズムといって、ミルフォードサウンドまで車で行くと到着の15〜20分手前のところ。この森は恐竜時代の頃から様相はほぼ変わっていないらしい。
-
◆ランス・ウッド(幼年期) ■この木の葉は成長するにしたがって、葉が短く丸くなっていく。最初の頃はこのように葉は長くとげがはえている。これは葉を(飛べない鳥たちから)食べられないようにするため。
-
◆成年木に近づいたランス・ウッド ■<右の木>上のほうの葉が短くてもう棘がない。
-
◆ボブ・パイン(沼松)の群生 ■南緯39度より南にある。とても珍しい植物。寒いところで育つが成長がゆっくりで、この写真ぐらいの大きさでも樹齢は100年は過ぎている。この木の仲間は世界でも3ヶ所でしか見られないということ。この場所は、クィーンズタウンからファイブ・リバーズを過ぎ、そこからテ・アナウに行く途中で見ることができる。
この旅行記のタグ
利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。
コメントを投稿する前に
十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?
サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。
旅の計画・記録
マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?
ニュージーランド の人気ホテル
ニュージーランドで使うWi-Fiはレンタルしましたか?

フォートラベル GLOBAL WiFiなら
ニュージーランド最安
418円/日~
- 空港で受取・返却可能
- お得なポイントがたまる


























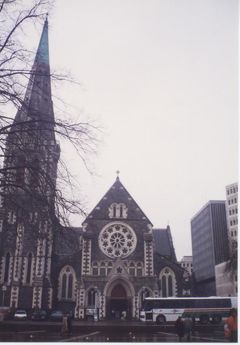







0
21